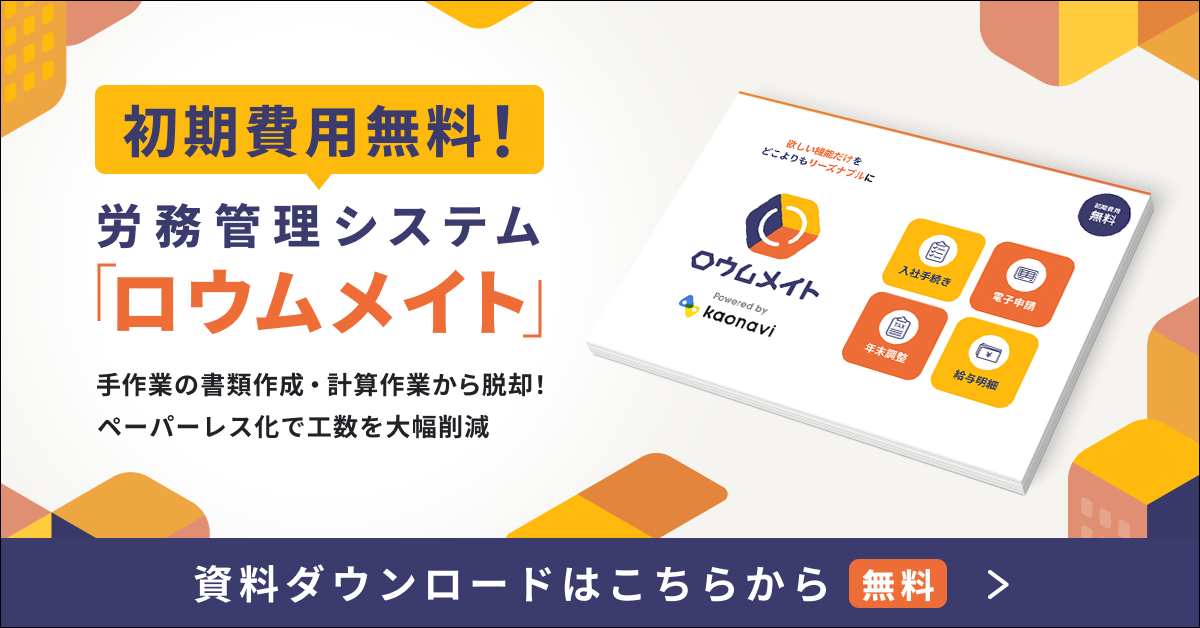「労働組合」は、組合員の安定した雇用や労働条件の改善を会社に求めるために活動する社内組織です。ここでは、労働組合に関わる「労働組合法」や労働組合のメリットなどについて解説します。
目次
1.労働組合法とは?
「労働組合法」とは、労働者が労働組合を組織し、使用者と対等な交渉ができるよう関係性を定める法律のこと。労働者を守る法律のひとつで、「労働基準法」や「労働関係調整法」と合わせて「労働三法」と呼ばれます。
労働者と会社が協力して職場の問題を解決し、より良い職場と労働条件を実現していくための法律です。
憲法28条の概要
日本国憲法第28条では、労働者の権利として「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」という3つの労働基本権を認めています。社会的関係上、使用者である会社に対する労働者の立場は弱いもの。
そのため働く環境に問題や不満がある際、労働者が声をあげやすいよう、法律によって保護しているのです。会社は労働基本権を尊重する必要があり、労働組合の組織や加入、労働組合からの交渉要請、ストライキ権の行使を正当な理由なく拒否できません。
団結権
「団結権」とは、労働条件の問題解決や安定維持のために労働組合を組織したり、組合に参加したりできる権利のこと。目的は労働者全体の意志を反映した団体や労働組合をつくり、会社と対等な立場で団体交渉できるようにすることです。
正当な理由なく、公権力や会社は労働組合内部に関与できません。なお日本の公務員の団体権を含めた労働基本権は、制約がされているという現状もあります。
団体交渉権
「団体交渉権」とは、労働者団体がその代表者を通じて、使用者と労働条件や労使関係上の取り決めなどを交渉する権利のこと。話し合いで決まったことは、文書などで約束として取り交わせます。
使用者は労働組合からの交渉要請に応じる義務があり、不当な拒否はできません。労働組合を通じて労使で締結した「労働協約」は非常に効力が強いものとなっています。会社の就業規則や労働規約が労働協約と異なる場合、労働協約が適用されるでしょう。
団体行動権
「団体行動権」とは、粘り強く交渉を続けたにもかかわらず現状打開が困難な場合、労働を放棄して団体で抗議できる権利のこと。この権利によって、労使の交渉が決裂したり交渉進展が見込めなかったりした際、ストライキといった争議行為を実力行使できます。
ビラの配布、演説や集会の開催なども組合活動権で認められている行為です。ただし争議行為は使用者(雇用者)の操業の自由を奪うため、適切な手順を追って慎重に行わなければなりません。
正当性を欠く場合は不法行為となり、使用者は労働者に対して損害賠償できます。

2.労働者を守る法律
労働者を守る「労働三法」は、労働者保護を目的とした基本的法律の総称です。ここでは「労働三法」に含まれる3つについて見ていきます。
- 労働基準法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
①労働基準法
「労働基準法」とは、労働条件の最低基準を定めた法律のこと。すべての労働者に人としての最低限度の生活を保障するための法律で、網羅する範囲は多岐にわたります。
記載されている基準は、「労働時間と休日規定、賃金の支払い規則」「怪我や病気を抱える人や妊産婦への特別措置」「職場の安全確保や衛生管理義務」などです。
使用者は労働基準法に従い、労働者の利益と権利を守る必要があります。そのためには社内制度や就業規則を整備し、労働基準法にもとづいた雇用契約を結ばなければなりません。
②労働組合法
「労働組合法」とは、労働者が労働組合をつくり、会社と対等な立場で話し合いできる権利を保障する法律のこと。目的は社会的関係上、労働者が会社に言いにくい困りごとや改善要求を吸い上げ、労働組合として改善を働きかけていくことです。
使用者にとっても、労働組合を通じた労働者の意見回収は効率が良く、それに伴う職場改善や労働者の協力を実現しやすいという利点があります。労使紛争を未然に防ぐ非常に重要な法律といえるでしょう。
③労働関係調整法
「労働関係調整法」とは、労使紛争で当事者同士の解決が難航する際、労働委員会が関与するための手続きを定めている法律のこと。
労使間で話し合いを続けても歩み寄りが見られず、いずれかが実力行使をして操業に支障が出ている場合、長期化すると双方に大きく不利益が生じるでしょう。
こうしたとき労働関係調整法にもとづいて、公平な第三者機関である労働委員会が間に立って調整できます。労働委員会が行う調整活動には、「斡旋・調停・仲裁」の3つがあり、必要に応じて事実調査や解決に向けた措置を勧告する場合もあるのです。

3.労働組合法の概要
「労働組合法」は、労働法の基本となる労働三法のひとつ。労働者が労働組合を結成したり、参加したりすることを認める法律となっています。労働者の総意として会社に対する改善要請を交渉する権利を守っているのです。
労働組合とは?
「労働組合」とは、労働者が主体的かつ自主的に組織する団体のこと。労働者が団結して、賃金や労働時間、職場環境などの労働条件の改善を求めるために結成します。この労働組合の活動や機能を法的に認めているのが労働組合法です。
労働組合は労働者が複数人集まると結成でき、行政への届け出や認可は不要となります。日本では、企業ごとに組織される企業内労働組合がほとんどでしょう。
ほかの労働組合として、同業の組合がいくつか集まる「産業別労働組合」や業種を超えて結成される「日本労働組合総連合会」などもあります。
ユニオンという言葉
「ユニオン」は労働者であれば雇用形態に関係なく個人加入でき、一定地域にて結成される労働組合で、「合同労働組合」とも呼ばれます。主に参加しているのは中小企業の労働者や企業の管理職。
その背景には、「日本の中小企業における企業内労働組合の組織率が0.9%以下と非常に低い点」「人事や管理職など使用者側の利益代表は労働組合に参加できない傾向にある点」が関連しているでしょう。
このような労働者が労働問題に直面した場合、問題解決のため社外の合同労働組合やユニオンに加入するケースが多いようです。
春闘とは?
「春闘」とは、新年度に向けた労働条件を、労働組合が使用者へ要求や交渉を行う一連の運動のこと。正式名称は「春季生活闘争」といいます。労働条件の要望は例年2月に労働組合から使用者へ提出され、使用者の返答は3月頃です。
争点は主に賃金や一時金についてで、「時短勤務やテレワーク導入など育児や介護と両立して働きやすい制度の整備」「ハラスメント対策」など、労働のあらゆる面が対象となります。
短時間や有期雇用の労働者、障がい者や外国人労働者が焦点になる場合も多く、内容は年々多様化している傾向にあるようです。

4.労働組合法に反する行為
労働組合法では、使用者が正当な理由なく労働組合やその加入者に不利益を与えることを禁止しています。使用者から不当労働行為を受けた場合、損害賠償や慰謝料の請求、労働委員会に対して救済を申し立てられるのです。
定められている主な違反行為
労働組合法が使用者に禁じる主な行為は、以下の4つです。
- 労働組合員である点を理由に、労働者を不当に扱う
- 団体交渉を正当な理由なく拒否する
- 労働組合の運営に不適切な介入をする
- 使用者の違反行為を労働委員会に申し立てた事実をもって、労働者に不利益を与える
上記のような不当労働行為が行われた場合、労働者は労働委員会に救済申立をしたうえで、使用者へ救済命令を出せます。
①労働組合員である点を理由に、労働者を不当に扱う
使用者は、労働組合との関係を理由に労働者の雇用や労働条件に不利益を与えてはいけません。そのため労働組合の結成や加入、正当な活動による解雇やハラスメント、不当な配置転換、賃金や昇進に関する冷遇などが禁じられています。
また労働者が労働組合から脱退する、あるいは加入しないことを雇用条件にする「黄犬契約」も結んではなりません。
②団体交渉を正当な理由なく拒否する
使用者は、労働組合から申し入れのあった団体交渉を正当な理由なく拒めません。使用者は、労働にかかわる問題について労働組合と誠実に団体交渉を行う義務があります。
形式的に交渉に応じても、誠実に話し合わなかったり、使用者の一方的な都合で話し合いを打ち切ったりすると、団体交渉の拒否とみなされるでしょう。
③労働組合の運営に不適切な介入をする
使用者が労働組合の運営や統制について、以下のような不適切な介入を行うのは禁止されています。
- 労働者に、労働組合に加入しているかを問いただす
- 労働組合に対して経費を援助する
- 組合員の資格について口出しをする
- 労働者に労働組合からの脱退や非加入を説得する
- 労働組合について批判・非難・誹謗する
このように労働組合の団結や統率を弱める言動は労働組合法違反にあたるのです。
④使用者の違反行為を労働委員会に申し立てした事実をもって、労働者に不利益を与える
使用者は、「不当労働行為の証拠提出や証言をした」「労働委員会に救済申立をした」点を理由に、労働者を解雇したり不当に扱ったりしてはいけません。不当労働行為はれっきとした違法行為で、不当労働行為からなされた人事決定は法的効力を持たないのです。
労働委員会が使用者の違反事実を認めた場合、労働者に救済命令が出され、使用者には違反行為を改善する義務が生じます。
違反者に対する罰則は?
使用者の不当労働行為は、労働組合法の違反にあたるものの刑事責任は問われません。その代わり民法上の権利侵害として不当な人事決定の無効化、損害賠償や慰謝料の請求などを行う余地があります。
労働組合が出した救済命令に反した場合、裁判へ持ちこまれるケースも少なくありません。裁判所が労働組合の救済命令を支持した場合、使用者の命令不履行に対して労働組合法違反とみなされて刑事責任が生じる可能性も高くなるのです。

5.労働組合に入るメリット
労働組合に加入するメリットは何でしょうか。下記3つについて解説します。
- 組合員に対する不当行為を抑える
- 組合員は団体交渉ができる
- 雇う側にもメリットがある
①組合員に対する不当行為を抑える
労働組合は、組合員が主体となって自分たちの権利と利益を守るためにあります。組合として会社への不満や改善要求や意見をまとめて会社と同等の立場で伝えるため、労働者の意見が会社に届きやすくなるのです。
労働組合法によって会社は話し合いに応じる義務があり、組合員は正当な順序を追ったうえでの実力行使も認められています。つまり労働組合は、職場に悩みを持つ組合員にとって心強い存在なのです。
②組合員は団体交渉ができる
労働者個人では交渉が難しいようなとき、労働組合法の団体交渉権を行使できます。会社対個人では直接言いにくい労働問題も、組合が代表すれば交渉しやすくなるもの。
使用者は組合からの交渉申し込みを正当な理由なく拒否できません。組合として団結して話し合いにのぞんだ結果、要求がスムーズにとおるケースもあるのです。
③雇う側にもメリットがある
労働組合の存在は、組合員だけでなく使用者にもメリットをもたらします。労働者が抱える不満や苦情などを効率よく吸い上げて、労働条件や職場の改善に活用できるのです。
働きやすい職場づくりは、労働者のモチベーションや成果の向上、ひいては業績アップにもつながるでしょう。
コンプライアンス強化や個別労使紛争の未然防止のためにも、職場で起きている問題のいち早い把握は重要なものです。労働組合と使用者は適度な距離感を保ちながら相互協力する姿勢が求められます。

6.労働組合に入るデメリット
労働組合に入るデメリットは何でしょうか。ここでは下記2つについて解説します。
- 組合費が高い場合も
- 仕事の成果や労働時間に見合わない対価
①組合費が高い場合も
労働組合は労働者が自主的に加入する団体で、会社からの金銭援助は禁じられています。そのため組合費は、自己負担になるのです。労働組合の組合費は月々の給与から天引きされる場合が多く、金銭的な負担を感じる人も少なくはないでしょう。
労働組合の運営も組織によって違いがあり、組合費が高額に設定されているケースもあるようです。加入を検討する際は、収入と支出のバランスを見て、無理なく継続できるようにしましょう。
あまりに自社の組合費が高額な場合は、社外の合同労働組合やユニオンを探すのも1つの方法です。
②仕事の成果や労働時間に見合わない対価
給与から「組合費」を支払って参加する労働組合は、組合員の自主運営であるため活動や運営方針は組織によりさまざまです。なかには労働組合が実質機能しておらず、労使間の課題解決がなかなか進まないケースも少なくありません。
そうなると現状の仕事の成果や労働時間と組合費を払って組合に入るメリットが見合わなくなります。活動内容や実情をできるだけ調べたうえで、加入する労働組合を検討するほうが安心かもしれません。