管理部門は、企業の経営活動を支える重要なポジションです。主な部門には人事や総務、財務や法務などがあり、一つひとつの部門が円滑な組織運営に欠かせません。
今回は管理部門について、その種類や役割、具体的な仕事内容や求められるスキルなどを詳しくご紹介します。
目次
1.管理部門とは?
管理部門とは、営業やマーケティングなど、売上に直接影響する部署や経理をサポートする部門です。顧客や売上に直接かかわらないため、裏方の部門として「間接部門」や「バックオフィス」とも呼ばれます。近年、企業によってはコーポレート部門と呼ぶこともあります。
2.管理部門の種類と仕事内容
下記は、管理部門に該当する代表的な職種です。
- 人事
- 経理
- 財務
- 総務
- 労務
- 法務
- 経営企画
- 情報システム
- 内部監査
- 広報・IR
企業規模によって職種が異なる場合もあります。ここでは、管理部門の主な種類と各職種の仕事内容をご紹介します。
①人事
人事は、経営における「人材」を管理する部門です。人事の主な仕事内容は、以下のとおりです。
- 人材採用
- 人材育成
- 人材配置
- 人事評価
- 人事戦略制度の管理・企画
- 労務管理
人事の役割は、人材を確保・育成・配置して利益や組織を拡大することです。近年は人的資本経営が重視されていることもあり、人材を管理する人事部の役割はますます重要になっています。
企業規模によって人事の役割や業務範囲は異なるものの、経営と連動して戦略を立案する上流から労務管理といった下流まで幅広い業務を担当します。

人事の仕事とは? 役割と仕事内容、必要なスキルをわかりやすく
人事とは、企業目標の達成に向け、人的資源を確保し有効活用するための業務です。ここでは、人事について解説します。
1.人事とは?
人事とは、企業の目標達成に向けて「人材を確保する・活用する」ため仕組み...
②経理
経理は、企業の「お金」を管理する部門であり、日々の事業活動で「すでに使ったお金」が管理対象です。
- 日々の取引の記録
- 請求書や領収書の処理
- 月次の締め作業、記帳作業
- 決算書の作成
- 年末調整
- 給与、保険、税金の計算
経理は、現状のお金の流れを把握・管理する仕事です。日々のお金の流れを可視化することは、適切な経営判断を行うことにつながります。
③財務
財務は、経理と同じく企業の「お金」を管理する部門です。財務が管理するのは「これから使うお金」であり、将来を見越して必要だと思われるお金を計画したり、調達したりして今後に備えます。
- 財務戦略の検討・立案
- 予算編成・管理
- 資金調達
- 余剰資金や資産の運用
- 監査対応
財務は現場よりも経営寄りの管理部門です。経理部よりも専門性が高く、お金や法律に関する幅広い知識やスキルが必要です。
④総務
総務は、企業運営に必要な業務全般を扱う部門です。ほかの部門に属さない業務全般に対応する部門ともいえ、円滑な企業運営に欠かせない存在です。
- 備品の発注・管理
- 施設管理
- 社内行事の企画・運営
- 契約管理
- 来客・電話・メール対応
- 防災・セキュリティ管理
他の部門に属さない業務を担当することからも、企業によって役割や仕事内容は大きく変わります。管理部門の中でもサポートの役割が強く、会社全体の状況を俯瞰できる立場にあります。
⑤労務
人事と同様に「人」を管理する部門です。労務は従業員の労働環境の管理に特化しており、従業員を間接的にサポートする役割を持ちます。
- 給与計算
- 勤怠管理
- 社会保険手続き
- 福利厚生の管理
- 安全衛生管理
- 就業規則の作成
- 労使関係の管理
労務の仕事は事務処理や管理業務が中心です。企業規模によっては、人事が労務を兼任する場合もあります。
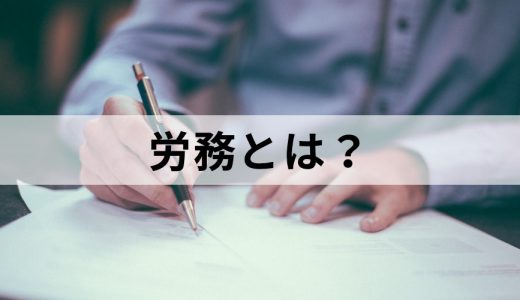
労務とは? 仕事内容や人事との違い、向いている人を簡単に
労務とは、企業が持つ資産である「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち、「ヒト」に関連する業務のことです。
本記事では、労務と人事の違いや、労務の役割・仕事内容・やりがい、労務に向いている人の特徴などを解説し...
⑥法務
法務は、法律面から経営をサポートする部門です。経営や事業活動にはさまざまな法律が関係してくるため、法律を遵守した運営が行えるよう管理・サポートします。
- 契約書の作成・チェック
- 法律相談の対応
- コンプライアンス推進
- 社内規程の整備
- 法改正への対応
- 訴訟対応
- 知的財産権の管理
- 債権の管理・回収対応
- 法令調査
法務には、大きく以下3つの役割があります。
- 臨床法務:トラブル発生時の法務対応
- 予防法務:トラブルの予防対策の法務対応
- 戦略法務:経営戦略を踏まえた攻めの法務
法律に関する部門であることから、管理部門のなかでも専門性が高い点が特徴です。
⑦経営企画
経営企画は、企業の成長や目標達成を実現するため、経営計画の立案・実行・管理を担う部門です。経営陣のサポートや事業部をまとめる政治的な役割も持ちます。
- 経営戦略の立案
- 経営戦略の実行・管理
- 新規事業の企画
- コンプライアンス対応
- ステークホルダーとの交渉・調整
経営陣のサポートと経営陣の決定を現場に落とし込む役割を持つことから、組織内では仲介役的なポジションとなります。ビジネスの全体像を把握し、経営戦略の策定・実行と経営の実務を担当する重要な部門です。
⑧情報システム
情報システムは、社内のインフラの構築・運用・保守を担当する部門で、略して「情シス」とも呼ばれます。近年はIT化も進んでおり、企業運営においてネットワークやシステムの存在が欠かせないことから、情報システム部門の必要性も高まっています。
- 社内システムの開発・管理
- IT機器の運用・管理
- ヘルプデスク業務
- セキュリティ対策
情報システムの役割は、大きく以下2つです。
- 業務部門が利益を生み出せるような情報システムを実現
- 情報システムの抱える課題の解決
ヘルプデスクのような定型業務の割合が多くなりがちですが、本来は社内の情報システムを有効活用し、社内の課題解決や利益創出につなげる役目を持ちます。
⑨内部監査
内部監査は、経営の健全性や適正性を管理する部門です。企業内の独立した部門として、健全な経営が行われているかを監査し、不祥事の防止や業務効率のチェックなどを行います。
- 予備調査
- 監査計画の策定
- 企業内監査の実施
- 調査調書の作成
- 監査報告
- 改善の提案
監査が適切に行われていると、社外に対して経営の健全性や透明性が証明しやすくなります。企業の発展に重要な部門であり、近年内部監査を導入する企業が増えています。
⑩広報・IR
広報・IRは、ステークホルダーに対して経営に関する情報を発信する部門です。広報は消費者や取引先に向けて企業の方針や新商品・サービスについて発信し、IRは株主や投資家に向けて財務状況に関する情報を発信する役割を持ちます。
企業文化やイメージの醸成に大きく影響する部門といえるでしょう。
- プレスリリースの作成・配信
- 取材対応
- WebサイトやSNSなどでの情報発信
- 株主総会の運営
- 有価証券報告書の作成
- IRサイトでの情報発信
- 事業活動の報告
- 社内報の作成
広報は情報発信により、企業間や社会との良好な関係を構築することが目的です。IRも広報と同じように情報発信によって、利害関係にあるステークホルダーとの良好なコミュニケーションを促進することを目的としています。
3.管理部門の役割
管理部門はさまざまな職種に分かれていますが、その役割には共通する部分もあります。しかし、企業規模や成長段階によっても管理部門全体の役割が異なります。
管理部門全体に共通する役割をふまえ、企業規模や成長段階ごとの管理部門の役割をみていきます。
共通する管理部門の役割
管理部門に共通する役割には、下記が挙げられます。
- 直接部門の支援
- 経営資源の管理・活用
- 円滑な企業活動の推進
- 組織の生産性向上
直接部門の支援
管理部門は企業の基盤を支える存在であり、それは直接部門の支援に直結しています。直接部門の役割は、最前線に立って顧客と直接関わり、利益を創出すること。
一方、直接部門が利益創出に集中するため、直接部門に必要なリソースを確保したり、労働環境を整えたりすることが管理部門の役割となります。直接部門を支援することで間接的に利益創出に貢献していることから、安定した企業経営のために管理部門は欠かせない存在です。
経営資源の管理・活用
企業活動や業務をスムーズに進めるためには、人材や資金の確保が必要です。ヒトやカネ、モノといった経営資源を確保・管理・活用することも管理部門の役割の一つ。
ヒトを管理する人事や労務、カネを管理する経理や財務といったように、経営資源の内容によって部門が分かれています。管理対象ごとに部門をわけることで、各経営資源の管理に特化でき、業務の質が向上します。
円滑な企業活動の推進
管理部門が企業活動の基盤を構築・整備することで、企業活動がスムーズに進められます。必要な経営資源が確保・活用できておらず、労働環境も整備されていない状態では、企業活動全体に支障が生じてしまいます。
直接部門が快適に働けることが企業の利益創出・拡大につながり、管理部門はそこに間接的に貢献しています。
組織の生産性向上
管理部門の存在は、組織の生産性にも大きく影響するもの。管理部門が経営資源を適切に管理・分配することで、直接部門に必要なリソースが行き渡り、生産性が高まります。
たとえば、人事であれば不足する人材を確保・育成し、適材適所に配置することで従業員が能力を発揮でき、効率的に利益を創出できるようになります。組織全体の成長を促すためには生産性を高めることが欠かせず、管理部門がその役割を担っているのです。
企業規模・成長段階別にみた管理部門の役割
管理部門の役割は、企業が成長する過程で変化していくものでもあります。あわせて、成長段階や企業規模に応じた管理部門の役割もみていきましょう。
創業期
創業期の管理部門は、組織全体を管理する役割を持ちます。創業期は従業員数も少なく、社長や経営層が企業全体の状況を把握できる状態です。
人材管理も比較的行いやすく、社長が直々に管理部門の役割を担ったり、専任者が一人で担当したりするケースが多いでしょう。
一方で、資金面で十分な人材を確保する余裕がないことで、そうした体制になっている場合もあります。
成長期
成長期は従業員が徐々に増え、創業期のような単独の管理が難しくなってくる段階であることから管理部門の重要性が高まります。管理する経営資源も増えるため、人事、経理、法務など専任者を配置して管理体制を整備します。
各管理部門が経営層や現場と連動し、必要な経営資源を管理・分配したり、経営戦略や経営目標の実現に向けて直接部門の支援に力を入れたりすることが求められます。
くわえて、コスト削減を図りつつ、いかに管理部門を充実させて経営全体を効率化させるかがポイントです。
上場企業
上場企業の管理部門は直接部門をサポートし、その役割・効果を最大化させる役割を持ちます。上場企業になると企業の社会的責任も大きくなり、コンプライアンスのリスクも高まることから、管理部門に求められる役割が高度かつ専門的になっていきます。
とくに、コーポレートガバナンスや内部統制の強化が重要視されるため、財務や法務といったステークホルダーとも関わる管理部門の役割が一層重要になります。管理部門は経営層と連動し、ビジネス視点をもって管理していくことが必要です。
4.管理部門の課題と解決方法
管理部門は業務の特性上、以下のような課題が発生しやすいでしょう。
- 人手が不足しやすい
- 業務が属人化しやすい
- 業務削減の対象になりやすい
- 目標設定が難しい
- 定量的な評価が難しい
ここでは、管理部門の課題とその解決方法をみていきます。
①人手が不足しやすい
管理部門は業務量が多いため、人手不足に陥りやすいです。それゆえ、人事が労務を兼任するなど、一人あたりの業務量が多くなってしまうことも多いでしょう。管理部門の人手が不足する結果、直接部門にも影響が出てしまう場合もあります。
また、管理部門の種類によっては高度な専門知識やスキルが必要であるため、求める人材の確保が難しい点も人手不足の原因です。
- 採用の強化
- 外部リソースの活用
- 業務フローの見直し
- ITツール・システムの活用
②業務が属人化しやすい
管理業務はプロセスやフローが可視化しにくく、業務自体が属人化しやすい傾向にあります。ヒト対ヒトの業務が多く、担当者の経験やコミュニケーション力に依存しやすいことも原因です。
また、人手不足によりマニュアルを整備できなかったり、十分な教育体制が確保できなかったりすることも原因といえるでしょう。業務が属人化すると担当者の変更や離職、休暇などによって穴が空くと不都合が起こりやすくなります。
- 業務プロセスの可視化・標準化
- 業務マニュアルの作成・共有
- 業務の権限移譲
- 業務ローテーションによる人材育成
③業務削減の対象になりやすい
管理部門の業務は直接利益につながるわけではないことから、人件費削減の対象になりやすい傾向にあります。業務削減により、人手不足や従業員のモチベーション低下といった副次的な課題も発生してしまうでしょう。
管理部門に支障が出てしまうと結果として直接部門に影響が出て、利益につながらなくなる恐れもあります。
しかし、業務削減については経営層の決定に依存することからも解決が難しい課題です。業務削減を実施する際は、以下ポイントに注意することが解決につながります。
- 業務削減にあたって、対象となる業務の優先順位を明確にする
- 管理部門の業務量や社内への影響を把握する
- 定量的な効果測定を行い、業務削減の効果を検証して次のアクションに生かす
④目標設定が難しい
管理部門は成果を明確な数値で測れないため、定量的な評価が難しく、目標設定も定性的になりやすい点が課題です。また、管理業務は中長期的な視点で業務に取り組むことも多く、短期での目標達成が難しいことも目標設定を難しくしています。
管理部門の役割は企業の基盤作りであるため、企業全体の目標と連動させることがポイントです。
- 企業目標にもとづいて個人目標を設定する
- 具体性を重視した目標を設定する
- 中長期的な目標を立てる
⑤定量的な評価が難しい
目標の設定が難しいことに関連し、定量的な評価が難しい点も課題の一つ。業務の効果が即時にわかったり、数値で明確に成績が出たりするわけではないため、個人の実績との紐付けが難しいことも原因です。
明確な評価基準の設定が難しく、昇格・降格の基準も不明瞭になりやすいでしょう。評価は従業員のモチベーションに影響するものであり、適切な評価ができないと管理部門の生産性低下を招く恐れがあります。
- 定性評価もくわえ、評価に必要なデータを収集する
- 定性評価を定量評価に分解する
- 定量評価に用いられる具体的な評価指標を設定する
5.管理部門の目標設定方法
目標設定は評価にも大きく影響するものであり、管理部門の課題の中でも解決の優先度が高いものです。従業員のモチベーションと生産性を高めるためにも、適切な目標設定を行うことが重要です。
ここでは、管理部門の目標設定方法のポイントをお伝えします。
企業の目標と連動させて設定する
管理部門は企業運営に影響する部門であることからも、企業の目標と連動させることがポイントです。経営理念や中期経営計画などを参考に、目標を設定してみましょう。
連動させることで個々の目標達成が企業目標の達成につながっていることが意識でき、モチベーション向上にも期待できます。また、企業の目標達成のKPIや進捗と照らし合わせることで、評価しやすくなります。
個人の能力に合わせて設定する
従業員の能力には個人差があるため、個々にカスタマイズした目標を設定することもポイントです。部門ごとの目標をふまえ、個々のキャリア志向や強み・弱みの補強など、目指す姿をゴールとして目標を考えると良いでしょう。
役割に応じて設定する
管理部門といっても、部門によって業務の難易度や役割はさまざまです。部門ごとの役割に応じた目標を設定することで、目指すべき方向性も明確になります。
そのためにも、部門ごとに従業員が目指すべき姿や求める役割を明確にしておくことがポイント。部門内のハイパフォーマーを分析し、そこを基準とするのも一つの方法です。
数値目標を設定する
目標として取り組みやすいのは、やはり数値化できる定量的な内容です。管理部門は数値目標の設定が難しいだけであって、全く設定できないわけではありません。結果を数値化しやすい業務を探し、そこに合わせて目標を設定するのも一つの方法です。
ただし、数値目標の設定が目的にならないよう、企業や部門の目標との連動性も考慮する必要があります。たとえば、総務であれば経費の削減率、人事であれば採用計画の達成度などを数値目標として設定できるでしょう。
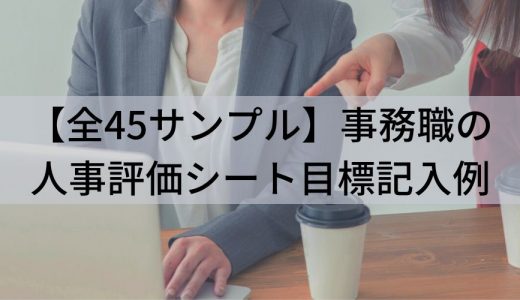
【全45サンプル】事務職の人事評価シート目標一覧と例文
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...
6.管理部門のやりがい
管理部門は裏方での活動となるものの、さまざまなやりがいが感じられる仕事です。管理部門のやりがいを詳しくみていきましょう。
企業の成長に貢献できる
管理部門は経営層との距離も近く、部門によっては経営者目線での業務対応が求められる立場です。経営の意思決定や課題解決に携われるポジションであることからも、自分の仕事が企業の成長に貢献できていることが実感しやすいでしょう。
経営層と現場の中間に位置するため、ほかにはない視点から企業の課題に気づける点で唯一無二の存在といえます。
多方面から頼られ、感謝される
社外とのかかわりが少ないため感謝される機会が少ないと思われやすいものの、社内で多くの人とかかわる仕事です。
経営陣や従業員の依頼に対応することも多く、頼られたり感謝されたりする機会も多くあります。個人を評価して頼られることも多いため、満足感ややりがいが感じやすいでしょう。
専門的なスキルが習得できる
部門によって業務内容はさまざまであるものの、共通して専門性の高い知識やスキルが必要です。とくに、経理や財務、法務や労務は高度な専門性が求められます。
業務を通して専門性が磨かれたり、知識やスキルが身についたりすることで自分の成長や成果を実感しやすい点でやりがいが感じられます。
7.管理部門の仕事に向いている人の特徴
仕事は向き不向きがあり、それは管理部門にもいえることです。ここでは、管理部門に向いている人の特徴をみていきます。
責任感がある
経営資源を扱う管理部門は、ミスが経営に影響をおよぼしやすいことからも責任が大きい仕事です。とくに、経理や財務、法務のような法律・法令に関わる仕事はその責任も重大でしょう。そのため、小さな仕事でも責任感を持って遂行できる人は管理部門に向いています。
忍耐力がある
管理部門は事務作業も多く、社外に出て活発に動く仕事ではありません。良くも悪くも環境の変化が少なく、同じ環境で同じ作業にコツコツと取り組むことも多いです。
また、中長期的に遂行する業務もあり、最後までやり遂げるには粘り強さや忍耐力が必要です。同じ作業やすぐに成果がでない仕事を最後までやり抜くためにも、忍耐力のある人は管理部門への適性があるでしょう。
人とかかわることが好き
管理部門は社内のさまざまな人と関わる機会が多く、部門を超えて横断的に業務に取り組むこともあります。多方面との連携や調整も必要となるため、良好な人間関係を構築することが大切です。
人とかかわることが好きな人やコミュニケーションを取るのが得意という人は、管理部門に向いているでしょう。
サポートすることにやりがいを感じられる
管理部門は部門ごとの役割をもって、直接部門や経営をサポートします。表立った仕事ではないものの、管理部門の存在が企業の大きな支えとなっています。裏方に周りサポートすることが好きな人、それにやりがいを感じられる人は管理業務に向いています。
8.管理部門に求められるスキル
あわせて、管理部門に求められるスキルについてもご紹介します。
コミュニケーションスキル
ここでいうコミュニケーションスキルは単に話すスキルだけでなく、傾聴力や相手の意図を汲み取る力も含まれます。社内のさまざまな部門とかかわり、交渉や調整、連携を図るポジションであることから管理部門にはコミュニケーションスキルが必要です。
周囲と良好な人間関係を構築してこそ、円滑に業務が遂行できるようになります。
PCスキル
管理部門は資料作成やデータ入力といった事務作業が多く、PCスキルがないと業務がスムーズに進められません。そのため、ExcelやWordなどのツールや基本操操作のスキルを身につけておくことは必須です。
企業によってはさまざまなシステムを導入している場合もあるため、新しいシステムやツールに苦手意識を持たないことも大切です。
タスク管理スキル
タスクの優先順位を明確にし、計画的に進めるスキルも必要です。管理部門は納期がある仕事も多く、マルチタスクになりやすい点でタスク管理能力が欠かせません。
突発的に業務が発生することも多いため、スケジュールや優先度をふまえて臨機応変に対応する力も求められます。
各部門の専門知識
特に、経理や財務、労務、法務は高度な専門知識やスキルが求められます。そもそも知識やスキルがないと、業務に対応できないといったこともあるでしょう。
人事や労務など、その他部門も業務の担当範囲や求められるレベルに応じた専門知識が必要です。あわせて、学ぶ姿勢や向上心も大切です。
9.管理部門のキャリアパス
管理部門は業務の専門性が高い点でキャリアパスに悩みやすい傾向にあります。ここでは、管理部門の主なキャリアパスをご紹介します。
スペシャリストを目指す
担当部門の知識やスキルを磨き、スペシャリストを目指すのもキャリアパスの一つです。企業によっては、特定分野の知識や能力を評価することで、管理職と同等に評価される専門職制度を導入しています。
管理部門は専門性の高さから採用が難しい傾向にあるため、スペシャリストを目指すことで市場価値も高まります。
管理職を目指す
一般的なキャリアパスが、管理部門のなかでも上の立場となる部長や課長といった管理職を目指すことです。管理職になると課せられる責任が重くなり、マネジメントまで対応するようになります。職種のスキルだけでなく、リーダーとしてのスキルも必要になってきます。
管理職になるとより経営層に近い視点で管理業務に取り組むことになり、次に紹介するCOOやCFOへのキャリアパスも開かれやすくなるでしょう。
COOやCFOを目指す
経営陣に含まれるポストとなる、COO(最高執行責任者)やCFO(最高財務責任者)を目指すキャリアパスもあります。COOは経営企画、CFOは財務からのキャリアアップとして目指せるポストです。
これまでの管理経験を活かし、企業経営により深く携わっていきたい場合におすすめのキャリアパスです。社内でキャリアアップするほか、他社からの引き抜きや会社設立時に就任するなどルートは複数あります。
独立を目指す
経理・財務や法務といった、高度な専門性が求められる管理部門で経験を積んだ場合は、独立もキャリアパスの一つです。
たとえば、経理・財務であれば税理士や公認会計士、法務であれば弁護士、総務・労務では社会保険労務士などの資格を取得することで独立を目指せます。
実践で身につけた知識やスキルがあるため、未経験で一から勉強するよりも効率的な資格取得が可能となります。
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

