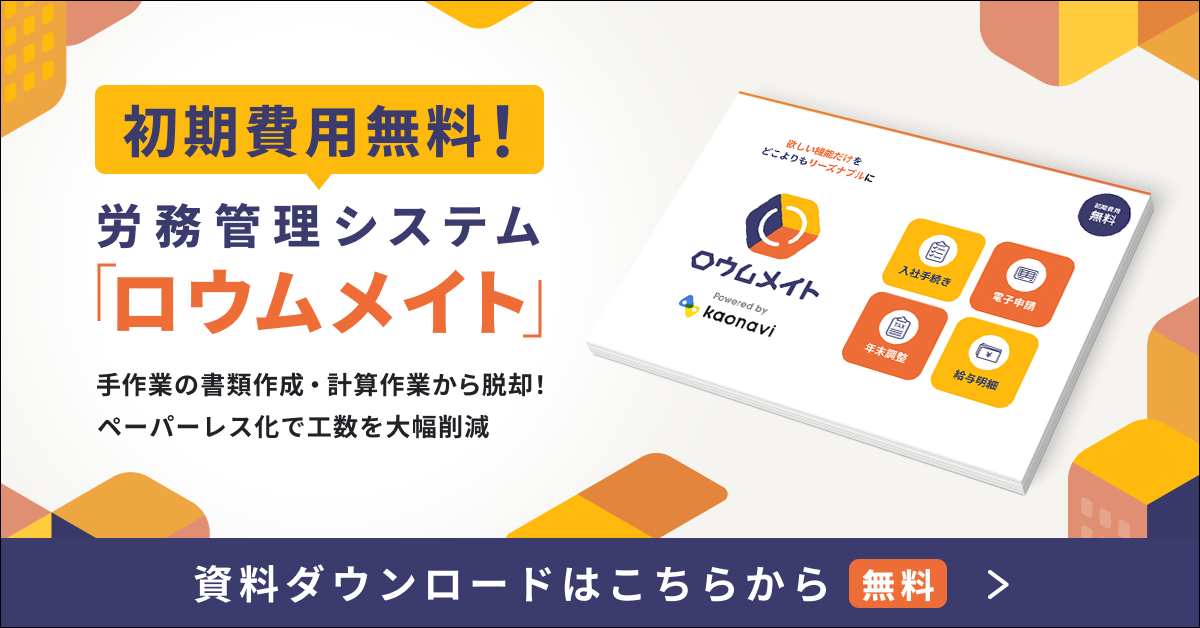新たに人事労務担当者になり、雇用保険の手続きに不安を感じていませんか。雇用保険の資格取得手続きは、新入社員の入社時に必ず行う重要業務ですが、事業主が法的義務を怠ると罰則の対象となる可能性があります。
特に初めて担当する方にとって、雇用保険の被保険者区分の選択や必要書類の準備、正確な記入方法など、戸惑う点が多いのが現実です。本記事では、雇用保険資格取得手続きの基本から応用まで、人事労務担当者が押さえるべきポイントを分かりやすく解説します。
雇用保険資格取得手続きの基本と提出期限

雇用保険資格取得手続きにおける基本条件や提出期限、被保険者区分などについて理解することが、適切な手続きを進める上で役に立ちます。ここでは「31日以上の雇用見込み」と「週20時間以上の労働時間」という加入条件や、被保険者区分の選択方法、提出期限や遅延リスクについて具体的に解説します。
これらの知識をしっかり押さえておくと、手続きのミスを防ぐことができ、スムーズな申請が可能となります。
雇用保険の加入対象となる条件と適用範囲
雇用保険は労働者の生活安定と再就職支援を目的とした重要な制度です。
雇用保険の加入対象となる条件は主にふたつあります。ひとつ目は「31日以上の雇用見込みがあること」です。具体的には、期間の定めのない雇用契約、31日以上の雇用期間が明示されている契約、または更新規定があり31日未満での雇止め明示がない場合などが該当します。
ふたつ目の条件は「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」です。これは契約上の労働時間であり、一時的に20時間以上働いた場合でも、契約上20時間未満であれば対象外となります。
注意すべき点として、雇用形態(正社員・パート・アルバイトなど)は関係なく、条件を満たせば必ず加入しなければなりません。また、学生は原則として加入対象外ですが、卒業見込みで就職が内定している場合や夜間・通信制の学生は例外的に加入できます。
加入手続きは、従業員を雇用した月の翌月10日までに事業所管轄のハローワークで行う必要があります。
| 加入条件 | 詳細 |
| 雇用期間 | 31日以上の雇用見込みがあること |
| 労働時間 | 週20時間以上の所定労働時間があること |
| 雇用形態 | 正社員・パート・アルバイト等の雇用形態は問わない |
| 学生の扱い | 原則対象外(卒業見込みや夜間・通信制は例外) |
被保険者資格取得届の提出期限と遅延のリスク
雇用保険被保険者資格取得届の提出期限を守ることは非常に重要です。提出が遅れると、さまざまなリスクが発生します。
まず、期限を過ぎると添付書類が必要になります。通常は添付書類は不要ですが、遅延すると雇用契約書や賃金台帳のコピーなどの提出を求められます。特に雇用から6か月以上経過すると遅延理由書も必要となり、手続きの負担が大きく増えます。
また、手続き遅延によって、労働者が失業した際に受けられる基本手当(失業給付)の給付日数に影響する可能性があります。被保険者であった期間が正確に記録されないと、労働者に不利益が生じます。
近年はマイナポータルで雇用保険の加入状況を従業員自身が確認できるようになりました。適正な雇用保険手続きは、企業の信頼にも関わる重要な責務といえるでしょう。
被保険者区分の正しい選び方(一般・高年齢・短期雇用特例・日雇)
雇用保険の被保険者は主に4種類に分類されます。
まず「一般被保険者」は65歳未満の労働者で、高年齢被保険者や特例被保険者に該当しない方です。「高年齢被保険者」は65歳以上の方で、短期雇用特例被保険者等に該当しない労働者です。
「短期雇用特例被保険者」は季節的に雇用される方で、4か月以内の雇用期間や週30時間未満の労働時間に該当しない場合に適用されます。
さらに「日雇労働被保険者」は日々雇用される方や30日以内の期間を定めて雇用される方です。
被保険者区分を選ぶ際に重要なのは、雇用期間と労働時間です。パートやアルバイトでも、週20時間以上働き、31日以上の雇用見込みがあれば被保険者となります。ただし、学生は原則として適用除外です。被保険者区分によって失業時の給付内容が異なるため、正確な区分選択が重要です。
雇用保険資格取得届の正しい記入方法と記入例

雇用保険被保険者資格取得届の記入には細かい注意点がいくつもありますが、項目ごとに押さえるべきポイントを理解すれば確実に手続きを完了できます。
ここでは、資格取得届の各項目の正確な記入方法から、職種・雇用形態・賃金の記入例、そして資格取得日の正しい設定方法まで、実務で特に重要となる部分を解説します。雇用保険の適用に関わる重要な手続きですので、以下の記入方法をしっかり押さえて、ミスのない申請を心がけましょう。
資格取得届の各項目の正確な記入方法とポイント
雇用保険被保険者資格取得届の記入は、一見複雑に思えますが、項目ごとに正確に記入すれば難しくありません。まず個人番号(マイナンバー)欄には、本人確認を行った上で正確に12桁を記入します。被保険者番号は、過去に雇用保険に加入していた場合に記入し、初めての加入なら空欄にします。
取得区分は、初めて加入する場合や離職から7年以上経過している場合は「1」(新規)、すでに被保険者番号を持っている場合は「2」(再取得)を選びます。被保険者氏名は姓と名の間に1マス空けてカタカナで記入し、氏名変更がある場合は変更後の氏名欄に現在の氏名を記載します。
賃金欄には支払形態(月給・日給・時給など)を選択し、毎月決まって支払われる額を千円単位で記入します。資格取得年月日は、試用期間があっても雇用関係が始まった最初の日を記入することが重要です。
雇用形態や職種などほかの項目も、該当する番号を選んで正確に記入しましょう。OCR(光学式文字読取装置)で読み取られるため、明確な記入が求められます。記入ミスがあれば雇用保険の適用に影響するため、慎重に確認しましょう。
職種・雇用形態・賃金の正しい記入例と間違いやすいポイント
職種欄の記入は雇用保険資格取得届の中でも特に注意が必要です。職種区分によっては保険料などに違いが生じることがあるためです。
職種は全部で11種類に分類されており、該当する職種を2桁の数字で記入します。例えば、事務的職業は「03」、専門的・技術的職業は「02」となります。一桁の職種コードには先頭に0を付けることを忘れないようにしましょう。
雇用形態欄では、正社員・パート・アルバイトなど該当する番号を選択します。特に有期雇用の場合は契約期間を正確に記入することが重要です。
賃金欄は毎月の固定給を千円単位で記入します。月給や日給など支払形態を選択、通勤手当は含みますが、残業代や賞与は含みません。
| 項目 | 記入例 | 注意点 |
| 職種 | 03(事務的職業) | 一桁の場合は先頭に0を付ける |
| 雇用形態 | 1(常用フルタイム) | 有期雇用は契約期間を明記 |
| 賃金 | 210(月給21万円の場合) | 千円単位で記入、小数点不要 |
資格取得日の正しい設定と確認方法
雇用保険の資格取得日は、試用期間の有無に関わらず労働者との雇用関係が始まった初日を設定します。雇用保険被保険者資格取得届の11欄には、この雇入れ初日(試用期間や研修期間を含む)を正確に入力することが重要です。
資格取得日の入力ミスは、後日の失業給付申請などに影響する可能性があるため、慎重に確認しましょう。申請時には資格取得日を証明できる賃金台帳や労働者名簿などの書類を準備しておくと安心です。
| 項目 | 内容 |
| 資格取得日の定義 | 雇用関係開始初日(試用期間含む) |
| 届出書11欄の記入内容 | 試用期間・研修期間を含む雇入れ初日 |
| 準備書類 | 賃金台帳、労働者名簿など |
雇用保険手続きに必要な添付書類と提出方法

雇用保険の手続きに必要な書類と提出方法について解説します。雇用保険資格取得届を提出する際、基本的には添付書類は不要となっていますが、特定の状況では書類の提出が求められることがあります。
また、申請方法には便利な電子申請と従来の窓口申請のふたつの選択肢があり、それぞれ特徴や手順が異なります。さらに、外国人労働者の雇用保険加入手続きには日本人従業員とは異なる特有の注意点があります。これらの知識を正しく理解することで、雇用保険の資格取得手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
雇用保険資格取得届に必要な添付書類一覧
雇用保険資格取得届の手続きに必要な添付書類は、平成22年4月1日以降、基本的に不要となりました。ただし、特定の状況では書類提出が求められることがあります。
以下に該当する場合は、書類の添付が必要です。
- 事業主が初めて被保険者資格取得届を提出する場合
- 提出期限(入社月の翌月10日)を過ぎた場合
- 過去3年以内に不正受給があった場合
- 労働保険料の納付状況が不適切な場合
- ハローワークが確認の必要があると判断した場合
- 事業主と同居の親族や役員についての届出の場合
求められる書類としては、労働者名簿、出勤簿やタイムカード、雇用契約書のコピー、賃金台帳などが一般的です。社会保険労務士や労働保険事務組合を通じて提出する場合は、原則添付書類不要です。円滑な手続きのために、事前にハローワークで必要書類を確認しておくことをおすすめします。
電子申請と窓口申請の手順と違い
雇用保険の手続きは、電子申請と窓口申請のふたつの方法で行うことができます。電子申請は「e-Gov(イーガブ)」というサイトを通じて、24時間365日いつでもオンラインで手続きができる便利なシステムです。従来の窓口申請ではハローワークの開庁時間に合わせて出向く必要がありましたが、電子申請の場合は自宅やオフィスのインターネット環境があれば申請可能で、時間を気にする必要がありません。
電子申請を利用するには、事前に電子証明書の取得が必要です。申請後、電子公文書として雇用保険被保険者証などが電子データで交付され、e-Govからダウンロードできます。紙の交付物が必要な場合は、電子公文書を印刷して使用します。従業員が離職した場合の離職票は、電子申請の場合もA4サイズで印刷して本人に渡すことになります。
外国人労働者の雇用保険加入手続きの特徴と注意点
外国人労働者も雇用保険の適用対象です。国籍を問わず労働関係法令と社会保険関係法令が適用されるため、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合は、速やかに雇用保険の加入手続きを行う必要があります。
ただ、雇用保険被保険者資格取得届を記入する際に注意が必要です。通常の記入項目に加え、備考欄に外国人特有の情報として「国籍・地域」「在留資格」「在留期間」「資格外活動許可の有無」を記入しなければなりません。これらの情報は旅券または在留カードを確認した上で正確に記載してください。
また、雇用対策法により外国人の雇入れ時と離職時には、氏名や在留資格などをハローワークに届け出る義務があります。この届出は雇用保険の加入手続きと同時に行うことができるため、効率的に進めましょう。
なお、被保険者氏名欄には外国人の氏名をローマ字または漢字で記入してください。不明点がある場合は早めに管轄のハローワークに問い合わせることをおすすめします。
雇用保険資格取得手続きのトラブル防止と確認方法
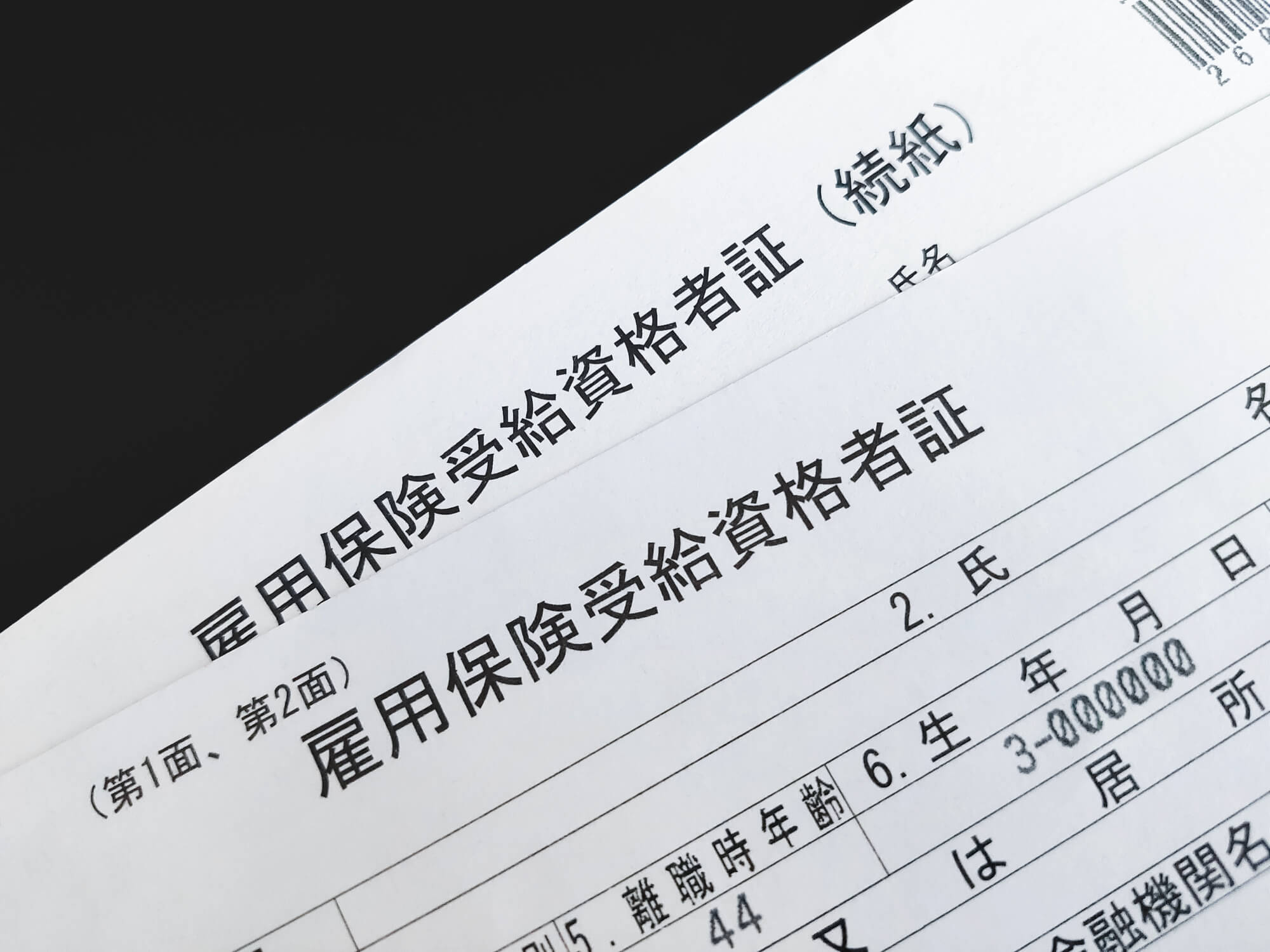
雇用保険の手続きにおいては、よくあるミスや確認方法を把握しておくことが重要です。特に新入社員の加入手続きを行う担当者は、手続きミスによる差し戻しや遅延のリスクを避けるための対処法と、手続き完了後の確認方法を知っておく必要があります。
氏名の漢字間違いや資格取得日の設定ミスなどの典型的なトラブルを防ぐための具体的な対策と、マイナポータルや被保険者証による確認方法を理解しておくことで、雇用保険資格取得の手続きをスムーズに進められるでしょう。ここでは、手続きの過程でよく発生する問題点とその解決策、そして手続き完了後の確認方法について解説します。
よくある手続きミスとその対処法
雇用保険の手続きでよく見られるミスには、氏名の誤記や基礎年金番号・雇用保険番号の入力ミスがあります。特に「小嶋」と「小島」のような漢字の違いや、異体字の存在する文字は注意が必要です。これらのミスが発生すると、申請が差し戻されて保険証の発行が遅れたり、間違った情報のまま保険証が発行されて後で訂正が必要になったりします。
対処法としては、メモや伝聞情報に頼らず、新入社員から年金手帳のコピーや雇用保険被保険者証のコピー、住民票などの原本資料を直接提出してもらい、一次情報に基づいて申請書類を作成することが重要です。また、電子申請を行う際は常用の字体でない漢字(例:「﨑」など)がエラーになる場合があるため、氏名欄には常用字体で記入し、備考欄に詳細を記載するか、別紙で補足情報をPDFで添付するとよいでしょう。
ミスを防ぐには複数人によるダブルチェック体制を整えることも効果的です。
手続き完了後の被保険者資格の確認方法
雇用保険資格取得手続きが完了したら、適切に処理されたかを確認することが重要です。確認方法は主に3つあります。
まず「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」を利用する方法です。この場合、ハローワークの窓口や郵送で申請が可能で、本人確認書類を提示すれば資格取得状況を確認できます。
次にマイナポータルを利用した確認方法です。従業員がマイナンバーカードを持っていれば、オンラインで簡単に雇用保険の加入状況や資格取得日を確認できます。ただし、事前にハローワークにマイナンバーを届け出る必要があります。
最後に「雇用保険被保険者証」と「雇用保険被保険者確認通知書」で確認する方法です。手続き完了後、事業所には事業主通知用が、従業員本人には被保険者証が発行されます。
まとめ

雇用保険の資格取得手続きは、31日以上の雇用契約かつ週20時間以上働く従業員が対象となります。手続きには被保険者資格取得届の正確な記入と適切な添付書類が必要です。書類作成時は被保険者区分の確認や職種コードの正確な記入が重要となります。また、手続き完了後は従業員自身がマイナポータルで加入状況を確認できます。適切な期限内に手続きを行い、トラブルを未然に防ぎましょう。
雇用保険の資格取得手続きは、提出期限や記入ミスなどに気を配る必要があり、人事労務担当者の大きな負担となっています。被保険者区分の選択や職種コードの記入、外国人労働者の特殊な記載事項など、注意点は多岐にわたります。
このような煩雑な労務業務は、労務管理システム「ロウムメイト」で効率化できます。雇用保険の電子申請機能が搭載されており、手続きにかかる工数を削減することができます。また、月額定額制で導入しやすく、必要な機能だけを選べる点もおすすめです。ぜひ無料デモをお試しください。