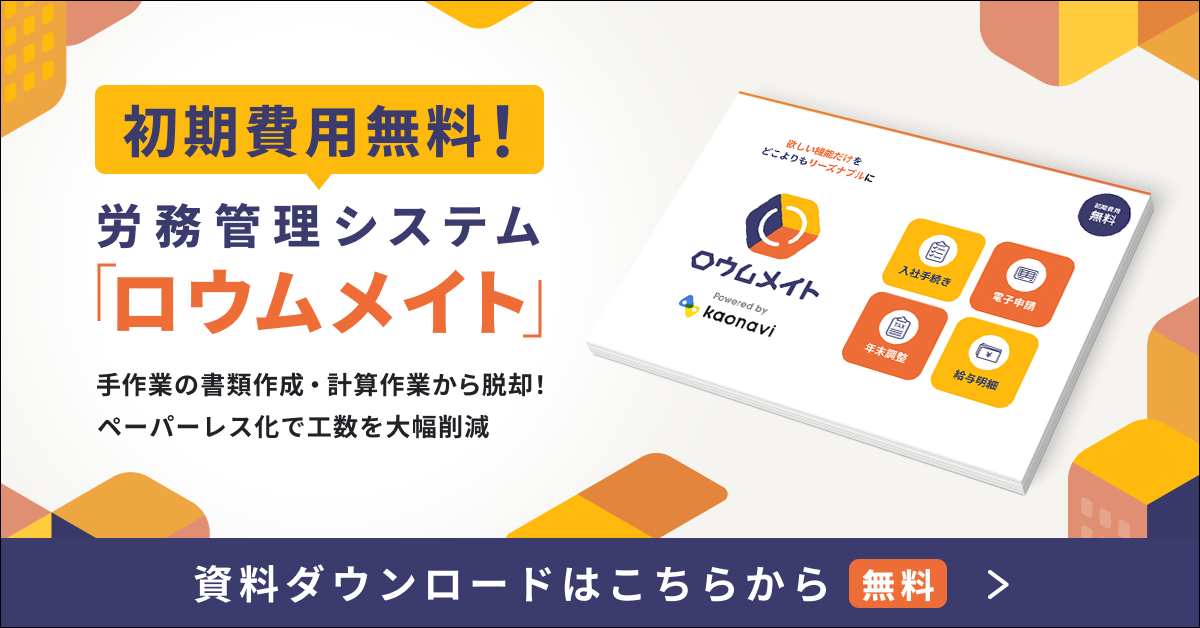年俸制は、給与額を年単位で決める賃金制度です。成果主義の評価制度と相性が良いほか、経営計画を立てやすい、従業員のモチベーションを高めやすいなどのメリットがあり、一部の企業では、年俸制を導入している場合もあります。
この記事では、年俸制について、制度の基本情報や月給制の違い、企業・従業員へのメリット・デメリット、などを詳しく解説します。
目次
1.年俸制とは?
年俸制とは、年単位で給与額が決定する賃金制度のことです。従業員の成果や業績を評価基準として、給与額を決定します。基準をふまえて決定した給与額を労使間で協議し、合意を得たら翌年の給与額が確定する仕組みです。
給与額の決定基準が成果や業績であるため、実力主義や成果主義とともに採用されることが多い賃金制度です。また、1年分の給与総額が事前に把握できるため、経営計画を策定しやすい点でも採用されています。
年俸制の導入率
少し古いデータとなりますが、厚生労働省が出した「平成24年就労条件総合調査結果の概況」によると、年俸制を導入している企業の割合は13.3%です。企業規模が大きくなるほど年俸制を導入している割合も高くなっています。
| 年俸制を導入している企業 | 年俸制を導入していない企業 | |
| 1,000人以上 | 32.6 | 67.4 |
| 300〜900人 | 24.5 | 75.5 |
| 100〜299人 | 18.4 | 81.6 |
| 30〜99人 | 10.4 | 89.6 |
出典:厚生労働省「平成24年就労条件総合調査結果の概況」
また、産業別では、下記の3業種が年俸制の導入割合が高いです。
- 情報通信業
- 学術研究/専門・技術サービス業
- 金融業・保険業
グローバル化や年功序列の賃金体系の衰退に伴い、近年、年俸制を導入する企業が増加傾向にあると考えられます。
2.年俸制と月給制の違い
年俸制と月給制は、以下2つの点に違いがあります。
- 年間の給与額の変動有無
- 給与額が決まる要素
①年間の給与額の変動有無
年俸制と月給制の大きな違いは、年間の給与額の変動有無です。基本的に、年俸制はあらかじめ決まっている1年の給与額を12等分して毎月支払うため、一定額が毎月支払われます。
月給制は固定の基本給があるものの、給与額は月単位で決まるため、業績不振によっては、年の途中で収入が変動する可能性もあります。そのため、月給制では年間の給与額の見通しが立ちません。
②給与額が決まる要素
月給制では年齢や勤続年数を考慮して毎月の基本給や諸手当が決まったり、業績によってボーナスが増減したりします。
一方、年俸制は成果主義型の賃金体系です。年齢や勤続年数といった属性ではなく、基本的に成果や業績の評価によって給与額が決まります。年齢や勤続年数に関係なく、評価が良ければ給与は上がりますが、評価が下がると給与も減る仕組みです。
3.年俸額の決まり方
年俸額は、基本的に前年度の評価や企業独自の賃金規定のルールや計算式にもとづいて決まります。なお、具体的な年俸額の決め方は企業によって異なります。企業側で算出した年俸額を従業員に提出し、合意が得られた場合に確定し、次年度の給与に反映される仕組みです。
企業によっては、労使間で合意を得ずに決定する場合もあるでしょう。ただし、評価基準や不服申立て続きなどの規定が就業規則に明示されており、公正性が保たれている場合に限ります。
4.年俸の支払われ方
決定した1年間の給与額は、分割して毎月支払われます。支払い形式としては月給制と同じで、単純に12等分するケースが一般的です。
等分して毎月支払いが必要なのは、労働基準法第24条によって「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定めがあるためです。
支払日は一定の期日を定めていれば、企業で自由に決めて問題ありません。年俸制と月給制の両方を採用している企業は、月給制の従業員の給与支払日に合わせるケースが多いでしょう。
5.年俸制での残業代は支払われる?
年俸制であっても残業代は支払われます。なぜなら、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた分の賃金は、企業に支払い義務があるからです。
ただし、みなし労働時間制を導入している場合、一定の労働時間の範囲の残業代は支払われません。というのも、残業代はすでに年俸額に含まれているためです。
一方、一定の労働時間の範囲を超えた場合は残業代は支払われ、みなし労働に含まない休日出勤や深夜労働を行う場合には割増賃金が適用されます。

残業代とは? 種類と仕組み、割増率、計算方法をわかりやすく
8時間以上の仕事をすると残業代が支払われると思っていませんか。残業の種類、計算方法、トラブルなど残業代について詳しく説明します。
1.残業代とは?
残業代とは、労働基準法で定められた法定労働時間を超...
6.年俸制に賞与(ボーナス)はない?
賃金制度に関係なく、賞与を支払うかは企業の任意です。賞与がある場合、賞与の扱いは企業によって異なり、一般的には以下2通りとなります。
- 年俸額に賞与を含める
- 年俸額とは別で賞与を支払う
①年俸額を賞与に含めるケース
年俸額に賞与を含める場合、算出した年俸額に賞与を加えた金額が最終的な年俸額となります。年俸額を14〜16等分して12回分を毎月支払い、残りの2〜4回分を夏や冬に賞与として支払う形式が一般的です。
賞与として支払われるものの、事前に年俸額に含まれるため労働基準法上の賞与として扱われません。
②年俸額とは別で賞与を支払うケース
年俸額と別で賞与を支払う場合、年俸額の決定時に賞与額は決めません。そのため、年俸額に賞与が上乗せされて最終的な年収が決定します。この場合、賞与はその時の業績などに応じて自由に変更可能です。

賞与(ボーナス)とは? 支給時期や平均、手取りの計算方法を解説
賞与(ボーナス)とは、毎月の給与とは別に、企業が従業員に対して支給する特別な報酬のこと。支給額や回数、支給時期などは企業の判断に委ねられているため、各社で賞与の条件が異なる場合があります。
この記事で...
7.年俸制のメリット
近年、グローバル化により年俸制を採用する企業も少しずつ増えつつあります。年俸制を導入するメリットを企業側・従業員側双方の視点からみていきましょう。
企業側
年俸制を採用する企業のメリットには、下記4つが挙げられます。
- 給与計算の手間が減る
- 経営計画を立てやすい
- 従業員のモチベーションを上げやすい
- 優秀人材の採用につながりやすい
①給与計算の手間が減る
あらかじめ決定している年俸額を12等分した額を毎月支払うため、計算が必要なのは残業代のみとなり、給与計算の手間が減る点はメリットです。
給与計算を担当する人事労務や経理はそのほかにも多くの業務を抱えているため、毎月の給与計算にかかる工数が削減されることで他の業務に集中でき、業務全体の効率化にも期待できるでしょう。ただし、年俸額を決定する時期は一時的に業務負担が増えてしまう点に注意が必要です。
②経営計画を立てやすい
次年度の人件費の総額をあらかじめ把握できるため、経営計画を立てやすいというメリットがあります。経営計画では予算計画や予算編成も行いますが、その中でも人件費は経営にかかるコストの中でも額が大きく、重要度が高いものです。
あらかじめ把握できることで、中長期的な目線でより実態に即した経営計画が立てやすくなります。
③従業員のモチベーションを上げやすい
年俸制は成果主義と連動する賃金体系であることから、従業員が成果を出すだけ給与に反映されます。年齢や勤続年数といった努力では変えられない要素が影響しないため、成果を出すためにモチベーションを高めて業務に取り組めるようになるでしょう。
自分の成果が給与として目にみえる形で表れることで、モチベーションアップにつながります。
④優秀人材の採用につながりやすい
労働人口が減少している現代では、優秀人材の確保はより難しいもの。年功序列の賃金体系では、とくに若い優秀人材の確保にはつながりにくいでしょう。
年俸制なら実力や成果が評価基準となるため、高い給与を目指しやすいことから優秀人材が採用しやすくなる可能性があります。給与条件がすべてではないものの、実力や成果に値する給与がもらえるかは重要なポイントです。
従業員側
一方、従業員側は以下のようなメリットに期待できます。
- 成果次第で年収アップが狙いやすい
- 年間の収入が安定する
- 収入の見通しが立てやすい
①成果次第で年収アップが狙いやすい
年齢に関係なく、実力や成果次第で年収アップを狙いやすい点は年俸制ならではの特長です。成果を出した分だけ給与に反映されるため、仕事にもモチベーション高く取り組めるようになるでしょう。
第二新卒や未経験からの転職であっても、成果が出せれば短期間で年収アップが目指せる点は大きなメリットです。
②年間の収入が安定する
成果が出せなかったり、業績が悪くなったりしても、あらかじめ決まった年俸額が減ることはありません。そのため、年間を通して安定した収入が得られます。
月給制の場合、業績の悪化により急に給与が減る可能性も0ではありません。業績悪化によって年俸額が減る可能性があっても次年度からであるため、それまでの間に計画的に行動できるでしょう。
③収入の見通しが立てやすい
上記に関連し、収入の見通しが立てやすくなるといったメリットもあります。1年間の収入が年度始めの時点でわかっているため、住宅や車の購入などのローン返済の計画が立てやすくなります。
また、急な給与の減額もないため、年間を通して生活を安定させられる点もメリットです。
8.年俸制のデメリット
一方で、年俸制にはデメリットもあります。導入を検討している場合はデメリットも理解した上で、年俸制が自社の企業風土に合っているかを確認することが大切です。
企業側
年俸制の導入による企業側のデメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 経営状況の悪化に柔軟に対応できない
- 長期的な目標達成に取り組みにくくなる
- 従業員のモチベーション低下やトラブルを招くこともある
①経営状況の悪化に柔軟に対応できない
あらかじめ年間の人件費が確定していることは経営計画が立てやすい反面、業績悪化などによって経営状況が変わった場合に柔軟に対応できない点はデメリットです。
年俸制ではすでに決まった年俸額を年の途中で変更できないため、業績が悪化してもあらかじめ決定した額を支給し続ける義務があります。そのため、年俸額を決定する際はある程度の収支予測を立てておくことが大切です。
②長期的な目標達成に取り組みにくくなる
成果主義の風潮が強まり、従業員は成果を上げることへのプレッシャーがかかってしまうかもしれません。また、目先の成果を重視してしまうことで、中長期的な目線から目標達成に取り組むのが難しくなる恐れもあるでしょう。
短期的な目標達成に偏らないよう、目標ともうまく連動させた評価制度の整備が必要です。
③従業員のモチベーション低下やトラブルを招くこともある
評価制度が不透明だったり、公正でないと認識されてしまったりすると、従業員の不満や不信感が募ってしまいます。そのため、従業員が決定した年俸額に納得できるよう、明確な評価制度の整備・運用が不可欠です。公正かつ明確な評価制度を整備し、業員が納得できるよう運用しましょう。
従業員側
一方、従業員側には以下のようなデメリットがあります。
- 成果がすぐに給与に反映されない
- 減額する可能性もある
- プレッシャーやストレスを感じてしまう恐れがある
①成果がすぐに給与に反映されない
年の途中で成果を上げても、給与に反映されるのは翌年です。将来的に給与が上がることがわかっていても、その間でモチベーションが下がってしまう人が出てくる可能性があるでしょう。モチベーションを維持するためにも、年俸額を算出する計算式を明らかにする、公正な評価が行われる環境であることが大切です。
②減額する可能性もある
成果が出せなければ、翌年は今よりも給与が下がる可能性があります。また、下がった年に成果を出せても、それが反映されるのは翌年です。成果が出せない年が続くと年々給与も下がってしまうため、モチベーションを挽回するのが難しくなる恐れもあります。
③プレッシャーやストレスを感じてしまう恐れがある
給与が上がったからと、翌年以降も同じかそれ以上になるとは限りません。それゆえ、成果を出し続けることにプレッシャーやストレスを感じてしまう可能性があるでしょう。
そうならないためにも、成果を出すことだけを重視するような評価制度にしない、従業員のストレスマネジメントを行うことが大切です。
9.年俸制の注意点
あわせて、年俸制を導入する際の注意点についても押さえておきましょう。
導入時は就業規則の改定が必要になる
年俸制を新たに導入する場合、賃金の決まり方などが変わるため就業規則の変更が必要です。就業規則の変更は、所轄の労働基準監督署へ届出を行います。
くわえて、評価制度の整備も必要になってきます。年俸制を新規で導入する場合、その手間もかかるため導入時期を決めたら計画的に準備しましょう。
年俸に賞与を含む場合は金額を変更できない
年俸額に賞与を含む場合、労働基準法上「賞与」ではなく「毎月支払う賃金」とみなされます。そのため、一般的な賞与のようにその時の業績や評価に応じて賞与額を変更することは認められません。
また、業績悪化などを理由に賞与を支払わないということも不可能です。あらかじめ賞与額を含めることがリスクになる場合は、年俸額と別にすることでその時の状況によって支払い有無や金額の変更が可能となります。
年の途中で退職すると全額は支給されない
年の途中で退職、または解雇された場合、基本的には働いていない期間の給与は受け取れません。たとえば、年俸600万円を12等分で支払うケースでは、10月で退職した場合、11月〜翌年3月分の250万円は支払われないということです。
賞与が含まれている場合、在籍していた期間分の賞与は受け取れます。ただし、それも規定によるため、就業規則や雇用契約書、賃金規程などを確認しておきましょう。
欠勤分は給与から減額される場合がある
遅刻や早退、欠勤した場合、その分の賃金を減額することが可能です。欠勤分をどう扱うかは企業によって異なるため、就業規則や賃金規程を確認しておくとよいでしょう。