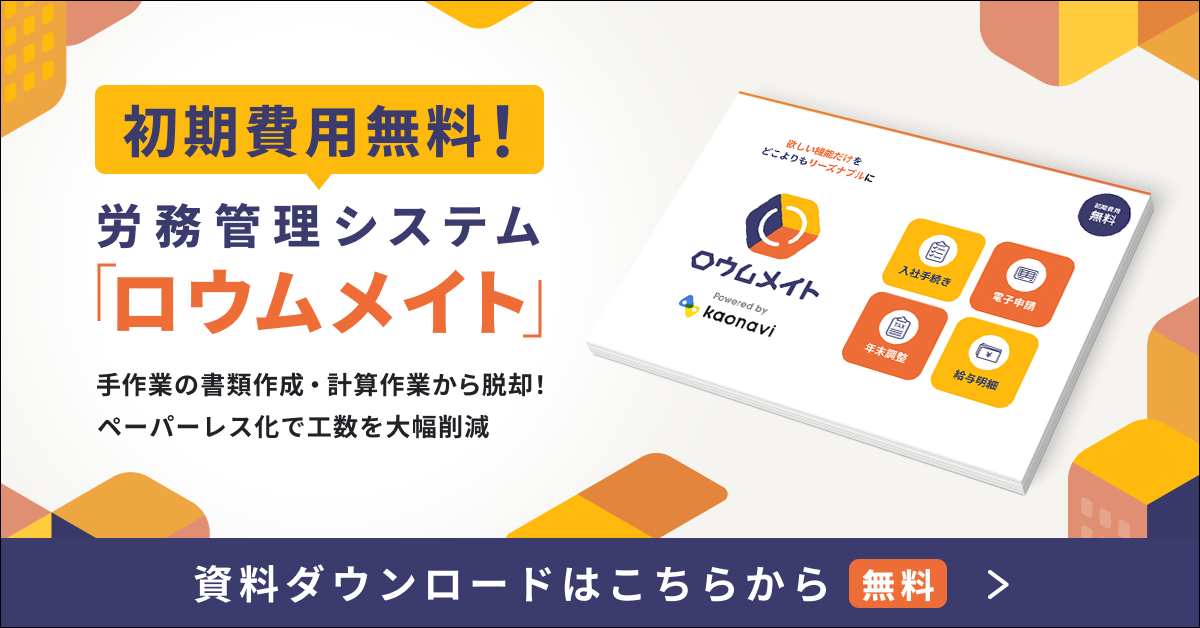バックオフィス業務は、総務や人事を始めとした社内で顧客と直接的な関わりを持たない業務のことです。今回は、会社の下支えにおいて重要な役割を担うバックオフィス業務について解説します。
目次
1.バックオフィス業務とは?
バックオフィス業務とは、顧客との直接的なかかわりを持たず、主に社内で完結する業務のこと。人事や経理、法務や総務などデスクワーク全般が該当します。一方、バックオフィス業務と対照であるフロントオフィス業務は、顧客や取引先と直接コンタクトを取る業務を指し、営業やカスタマーサポート、マーケティングが該当します。
バックオフィス業務は、直接的な収益を生み出すわけではないものの、人材採用や給与査定など、企業運営を支えるうえで不可欠な存在です。
社内にバックオフィス業務を専門に扱う部署があると営業やマーケティングなど、フロントオフィスも本来の業務に注力できます。バックオフィス業務は、企業を効率的に運営するのに欠かせない存在です。
対義語はフロントオフィス
フロントオフィス業務は、多様な顧客ニーズへ柔軟に対応する役割を担います。企業への問い合わせやクレームは、業種や商品ごとで都度異なるため、個別の顧客に合わせて適切に応対するスキルが欠かせません。
フロントオフィス業務の遂行には「コミュニケーション」「プレゼンテーション」の能力が必要で、商談相手や見込み客のニーズを素早く理解し、即座に適切な対応を取る姿勢が求められます。顧客と直接取引を行うため、自社製品・サービスへの深い理解と相手へわかりやすく説明するスキルが取引の成否を左右します。
また、営業に限っては上記スキルのほか、交渉能力や提案能力も同様に必要です。
2.バックオフィス業務の重要性
企業活動においては、相手と直接やり取りするフロントオフィス業務が最も重要ととらえられがちであるものの、企業運営ではバックオフィス業務も欠かせない存在です。バックオフィスは「ヒト・モノ・カネ・情報」といった企業の経営資源を、管理・最適化する役割を担っています。言い換えれば、経営に一番近い存在ともいえるでしょう。
バックオフィスの強化は、経営資源の最大活用や業務改善、生産性向上や精度の高い経営判断につながります。フロントオフィスが会社のリソースを使って効率よく仕事を遂行するには、バックオフィスの運営能力が欠かせないのです。
近年では、健康的な企業運営の土台を作る「戦略総務」「バックオフィスDX」といった取り組みが注目を浴び、バックオフィスの重要性に企業が注力し始めています。
3.バックオフィスの業務一覧
ここからは、バックオフィス業務を担う主な部門と、業務内容に焦点を当てて解説します。バックオフィスの存在は、企業運営において不可欠であり業務の円滑な遂行において重要な役割を担います。
総務
総務職は、企業内で他の部門が取り扱わない、さまざまな管理業務や他部門の支援を担います。具体的な業務例は、以下のとおりです。
- 資産管理
- 設備管理
- 社内イベントの企画
- コンプライアンス規定
総務の業務範囲は企業の状況に応じて異なり、広範囲に渡ります。
一般事務
一般事務とは、経営上で発生する庶務を担う部門です。主な業務内容は、以下が挙げられます。
- 文書作成
- ファイリング
- データ入力
- 議事録作成
- 送付物整理
- 請求書処理
- 備品管理
一般事務が担う業務内容は企業のセグメントによって異なり、非常に多様なのが特徴です。ほとんどがデスクワークのため人との接触はわずかであるものの、場合によっては電話応対や来客対応を兼任することもあります。一般事務は会社の円滑な運営を支える要職であり、組織内のあらゆる業務のサポートを果たす存在です。
経理
経理部門は、企業の財務活動、いわゆる「カネ」の動きを管理し、取引先との請求書や支払いなどの金銭取引を監督する部門です。主な経理業務としては、以下が挙げられます。
- 売上や支出の記録
- 帳簿の管理
- 税務申告
- 予算立案
- 財務報告
経理部門は、企業の財政健全性を確保し納税を始めとした法的要件に適合させるのも役割のひとつです。また、経理データを基にした分析や財務戦略を策定し、資本の最適化を以て経済的な成功に繋げる部門でもあります。
財務
財務は、主に資金調達やM&A、予算管理を担当し企業の資本を運用・管理する部門です。企業活動における融資交渉やステークホルダーとの協議を担い、資金管理の知識だけでなく、金銭面での交渉力や提案力が求められます。中小企業では人材不足の問題から経理と財務を兼任することがあり、これにより個人の業務負担が増える課題も存在します。
人事
人事業務は、経営資源のひとつ「ヒト」の確保や育成を担う部門です。主な業務内容は以下が挙げられます。
- 採用活動
- 社員の教育
- 人材の配置
- 人事評価
- 社員の相談窓口
人事担当者には求職者の性格やスキルを適切に評価し、採用の可否や配属部署を決定する洞察力が求められます。また、エントリーの母体数形成や、自社にマッチングした人材からの応募を目的とした採用戦略の策定も人事の役割です。企業によっては労務管理が業務に含まれることもあります。
広報
広報は、企業認知度の向上やステークホルダーとの良好な関係の構築など、社内外へ自社の情報を共有する広報活動を担う部門です。社外へは公式SNSやオウンドメディアを通したプレスリリースやイベント、社内へは社内専用のSNSアカウントやポータルサイトを用いて自社製品やサービス、企業理念や経営に関する情報を発信します。
広報部門は自社の存在を能動的にアピールする役割を担うため、自社の名前や製品をブランド化するうえで欠かせない存在です。
労務
労務は、従業員の公的扶助や権益を守り、快適な労働環境を整える部門です。具体的な業務内容としては以下が挙げられます。
- 給与計算
- 社会保険手続き
- 交通費管理
- 勤怠管理
- 安全衛生管理
- 就業規則の改訂
労務部門では、労働上で発生するさまざま問題に対し、社内の規則や法律、コンプライアンスに基づいた適切な対処が求められます。従業員とのコミュニケーションを通じて対人関係を構築し、個人の生産性やモチベーションを向上させるのも業務の一環です。
また、法律を遵守した企業規則の適用・改訂にも貢献し、従業員と企業の双方の権益を保護しなければなりません。
法務
法務は、コンプライアンス・訴訟対応・契約書の法的チェックなど、法律に関連する業務を担う部門です。近年では、世間の企業に対するコンプライアンスの高まりから、法務部門の対処が重要視されています。
法務では、法令や契約に基づく企業活動の適合性を確認し、健全な発展を支える能力が求められます。法務は高度な専門知識が求められることから、専任の人材を自社で雇わずに法律事務所を始めとした外部へ委託するところも少なくありません。
物流業務
物流は、自社製品の梱包から配送までを担当する部門です。具体的な業務内容として以下が挙げられます。
- 商品の積み下ろし
- 仕分け
- 検品
- 倉庫管理
- 出荷準備
- 配送手続き
- 流通加工
- 包装
物流業務では、物流に関わる配送プロセスを適切に管理して、スムーズに業務を遂行する能力が必要です。近年はインターネットを用いた通販が主流になりつつあり、物流の需要は増加の一途を辿っています。標準化しやすい業務なため、外部委託している企業も少なくありません。
経営企画
経営企画は、企業運営における事業戦略の中核を担う部門です。主な業務内容として以下が挙げられます。
- 経営目標の達成に向けた戦略や実行計画を策定
- 中期計画や年次予算の設定
- プロジェクトの進捗管理
- 経営陣への情報提供
- 新規事業計画の立案
- 事業継続計画の策定
企業が継続的に成長するには、変化する社会情勢や経済環境に目を配り、絶えず適応し続けなければなりません。経営企画部門は事業の中核に位置することで、経営陣の指針を示す役割を果たします。
情報システム
情報システムは、業務で用いるデータベースやシステムを管理し、社内ネットワークの構築と保守・運営を担当する部門です。現代の企業活動においてインターネットやIT技術の活用は不可欠で、情報システム部門は企業のIT戦略の策定やセキュリティ対策において重要な役割を果たしています。
4.バックオフィス業務の課題
バックオフィス業務は多くの人員が携わるため、人間関係や業務上の不満など、悩みが尽きることはありません。ここからは、多くの企業がバックオフィス業務において抱える課題を解説します。
属人化しやすい
バックオフィス業務は専門の資格やスキルを求められることが多く、業務が属人化しやすい傾向にあります。そのため、ノウハウを持っている人員の退職や異動が発生すれば、業務負担の増加や業務マニュアルの作成・引継ぎに対応できない事態が起きかねません。
バックオフィス業務を個人のスキルに依存すると、業務改善はおろか、ミスや不正のリスクが高い状態に陥ります。
慢性的な人材不足
バックオフィスはフロントオフィスに比べ専門性が高いため、人手不足に陥りやすい傾向にあります。そもそもバックオフィス業務は個人の業務負担が大きいことがあり、業務内容も直接的な収益を生み出すものではありません。
そのため、バックオフィス業務をやりたいと思う人材が市場に少なく、また経営層もバックオフィスの重要性を理解していない背景から、新たな人材の採用や業務の外部委託に予算を割けないのが現状です。
とくに専門的な知識やスキルが必要な経理・財務・法務では、予算があっても適切な人材を確保するのが難しいとされています。
進まないデジタル化
バックオフィス業務は業務の効率化や省人化を目的としたデジタル化が遅れており、未だに業務マニュアルや稟議書、勤怠管理に紙を用いたアナログな手法を採用している企業が多く存在します。
アナログ業務は同時作業の制約・紙文書の管理費用・稟議承認の遅延などデメリットも少なくありません。また、必然的にオフィスでの勤務が必要なため、リモートワークやテレワークの実施に至れないのも問題です。デジタル化に遅れたバックオフィス業務の改善は業務効率の向上と働き方改革の促進につながります。
増加する業務負荷
中小企業では、経理と財務、人事と労務など複数の役割をひとつの部署が担うケースは珍しくありません。そのため社員1人がカバーする業務の範囲が幅広くなり、業務負担が増加する事態に陥ります。
また、営業やマーケティングなどフロントオフィスにリソースの大半が割り当てられ、バックオフィスへのリソースが不足するといったケースも見られます。
フロントオフィスのサポート業務もバックオフィスが処理することが一般的なため、フロントオフィスにリソースが割かれるほどバックオフィスの負荷は増加の一途を辿るのです。
業務増加に伴うミスの多発
バックオフィス部門は稟議書や契約書など幅広い文書を扱うものの、紙ベースの文書管理は手間が多く、ヒューマンエラーを招くリスクがあります。
また、手書き文書は効率面も悪いため仕事に追われやすく、結果としてさらなるミスやエラーを引き起こすかもしれません。この問題を解決するには、文書のペーパーレス化や自動化ツールの導入が有効です。
デジタル技術を導入すれば文書の管理・データ入力・業務プロセスなど諸々の業務が効率的に処理でき、個人の負担軽減と企業全体の生産性向上につながります。
進まないテレワーク導入
業務で紙の文書を多用するうちは、出社の必要性からテレワークの実施に至れません。これはテレワークが流行したコロナ禍以降も多くの企業が抱えている問題です。テレワークの導入には文書のペーパーレス化が不可欠なため、紙媒体を業務に用いている間は進展が難しいとされています。
5.バックオフィス効率化の手段一覧
バックオフィス業務を効率化するには、業務のデジタル化やアウトソーシングサービスの利用など、さまざまな手法が存在します。ただし、効率化できればどんな手段でもいいわけではありません。
たとえば、アウトソーシングは専門知識を持たない社員でも効率的に業務を遂行できるものの、社外秘の情報も取り扱うためサービスを提供している企業との機密保持契約が必要です。
また、デジタルツールの導入に際して社員の一部から反発意見が発生することも考えられるため、事前の意識調査や新システムの研修を行うなど計画的に進めなければなりません。
ここからは、バックオフィス業務を効率化させる手段について解説します。
RPA
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)とは、コンピュータソフトウェアを用いて定型業務を自動化することで、人の手で行う業務の省略化とヒューマンエラーの防止が期待できる技術です。RPAは繰り返し行われるデータ入力やシステム間の連携など定型業務に適しており、事前の設定だけで業務を自動で実行してくれます。
その代わり、RPAは単純業務を自動化する特性上、非定型業務や目視による判断が必要なタスクには使えません。ただ、AIの進化によりRPAの性能は年々向上しており、数年前と比べ現在のRPAではカバーできる業務範囲が拡大しています。RPAの導入を検討する際には、業務の特性に合わせて適切なソフトウェアを選択しましょう。
アウトソーシング
バックオフィスは業務のほとんどがマニュアルで標準化されており、外部へのアウトソーシングで容易に代用できます。
たとえば、経理業務を税理士、法務を法律事務所に委託すると社内の専門スタッフの配置が不要です。これにより、煩雑な業務から解放されて社員はよりコアな業務に集中できます。また、委託先が持つスキルやノウハウを活用したり、専門家へ相談したりすることも可能です。
チャットボット
チャットボットとは、AI技術を活用した自動会話プログラムの一種です。バックオフィス業務においては、カスタマーサポートや社内問い合わせの自動応答システムに利用されます。
社内向けチャットボットの導入は他部署からの問い合わせをほとんど自動化でき、度重なる連絡業務による負担を軽減したり、業務の属人化を解消したりするメリットがあります。
経費精算ツール
経費精算業務の効率化には、Excelと連携したツールの導入が役立ちます。このツールは、経理作業における計算を効率化するだけでなく、クレジットカードとの連携による立替精算書の自動生成やWeb上で申請手続きの簡略化など、多様な機能が特徴です。
交通系ICカードや乗換案内アプリとも連携でき、勘定科目ごとの経費精算業務もスムーズに行えます。仕分け業務や経費精算が煩雑化している場合は、ツールの導入で負担を軽減し、効率的に経費の管理ができます。
基幹系システム
基幹系システムとは、企業の主要なデータを統合し一元管理化する中枢システムです。たとえば、販売管理・生産管理・在庫管理・財務管理・人事給与などバックオフィス業務で用いられるデータは、基幹系システムを用いればすべてをひとつのシステムに集約して管理できます。
その代わり、基幹システムがダウンすると企業の経営活動がストップするリスクがあるため、強力なセキュリティ対策や定期的なバックアップも同時に必要です。
ERP
ERPは「基幹システム」の一種で、企業の基幹業務と情報を効率的に一元管理できるプラットフォームです。業務データの一元管理化は「案件管理や勤怠管理を同じシステムで行える」「請求書作成時の手間や二重入力が不要になる」などさまざまな利点があります。
情報管理系システム
情報管理系システムとは、ビジネスチャットツール・スケジュール管理ツール・オンラインストレージ・顧客管理システムなど、社内の情報共有を可視化・効率化するツールやサービスのこと。
導入すると情報の散逸を防ぎ、必要な情報に誰でもすぐアクセスできる共有コミュニティを構築できます。組織の連携強化やタスクの明確化に役立つ手法です。
ペーパーレス化
ペーパーレス化は紙媒体のアナログ業務をデジタル化する一連の取り組みです。テレワークやリモートワークなど遠方で働く労働スタイルを促進するためには、ペーパーレス化による書類業務のオンライン化が欠かせません。
以前は契約書、請求書など一部の業務には紙の文書を用いなければなりませんでした。しかし、2021年のデジタル改革法制定により、デジタル手続きが合法化されました。
ペーパーレス化の実現は遠隔地での契約を容易にし、押印や書類のためにオフィスへ出勤する行為が不要なため、テレワークの推進に大きく貢献します。また、紙の不使用による印刷コストの削減や重要書類の紛失リスクを低減する効果も期待できます。
クラウドサービス
予算の問題で外部委託ができない場合、手軽かつ効果的な方法としてクラウドサービス・ツールの活用が挙げられます。近年企業のDX推進が流行している背景から、バックオフィスの改革・効率化をサポートする多彩なクラウドサービスが提供されています。
導入に大規模な設備投資が必要ないことから、中小企業を始めとしてクラウドサービスを利用しているところも少なくありません。サービスやツールを適切に導入・活用することで、業務の合理化と生産性向上が期待できます。
クラウドサービスはタスクの自動化やデータの共有、部署間のスピーディーな連携を可能にし、組織の競争力を強化するのに役立ちます。外部委託と比べてコストが抑えられ柔軟性も高いため、バックオフィス業務の最適な効率化手段として有効です。