一億総活躍社会では、障害のあるなしを問わずすべての人が自らの能力を発揮して就労する機会を持つことを目標としています。そのためには、企業も障害者雇用に積極的になる必要があるでしょう。
ここでは、企業が障害者を採用、雇用するときのために必要な、
- 障害者雇用とは何か
- 障害の種類や条件
- 紹介者雇用の義務や罰金
- 障害者雇用の手続き
- 障害者の社内の受け入れ準備
といった情報についてまとめいます。
目次
1.障害者雇用とは?

障害者雇用とは、障害のある人・障害のない人の双方が、同じように能力・適性に応じた雇用の場に就けるようにするため、自治体や事業主が中心となって障害のある人を積極的に雇用すること。
働き方改革の中で一億総活躍社会を目指しているように、障害者雇用の推進は、障害のあるなしに関わらず誰もが地域での経済的な自立に大きく貢献するものと考えられています。
障害者の定義
障害者雇用の中の「障害者」という言葉には定義があります。障害者基本法の中で「障害者」は、「身体障害、知的障害、または精神障害があるため長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」と定義されているのです。
障害者雇用枠
障害のある人が就労の機会を得るためのひとつの方法に、障害者雇用枠があります。障害者雇用枠とは、障害者手帳を持っている障害者を対象として、一般雇用とは異なる採用基準により企業や公的機関などに就職することができる雇用枠のこと。
障害者雇用枠での就職を目指す場合、障害者雇用枠での採用を行っているのか否かを確認する必要があります。

2.障害の種類とは?
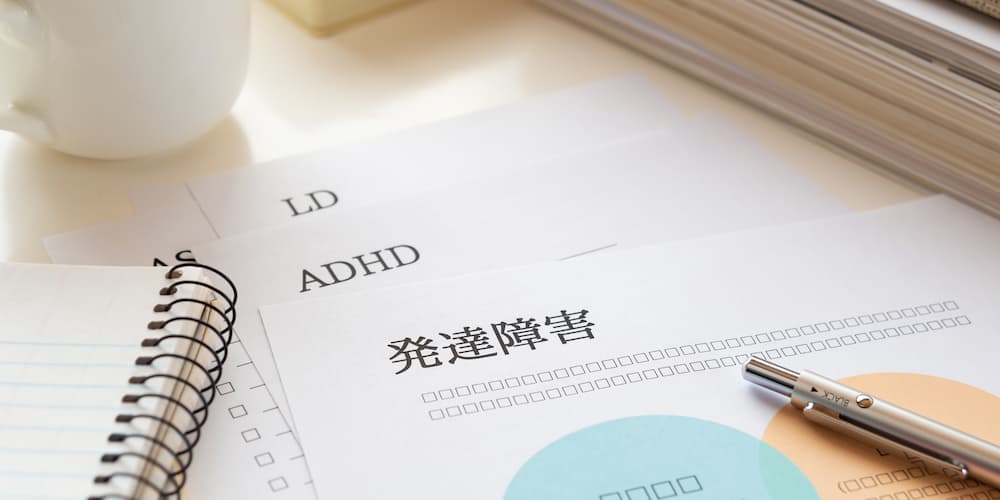
障害といっても、さまざまな種類の障害があります。障害に関しての理解が進まず、支援の手を差し伸べるのが遅れていたのが、発達障害です。
しかし2005年、発達障害者支援法が施行されたことで、長年、その障害の存在に気付くことや対応が不十分であった
- 自閉症
- アスペルガー症候群
- LD(学習障害)
- ADHD(注意欠陥多動性障害)
などを、「発達障害」という名で定義することになりました。
さらに、これら発達障害の特性やライフステージに応じて、国や自治体、国民が支援を行うことが責務として定められました。
障害者雇用枠を考えた場合、現在、支援が責務となっている障害の種類の把握は重要でしょう。そこで、障害と認められているものについて説明します。
- 精神障害
- 発達障害
- 知的障害
- 身体障害
①精神障害
精神障害とは、精神疾患のために精神機能に障害が生じること。原因はさまざまですが、脳の気質的変化や機能的障害が起こることで、意識や知能、記憶、感情、思考、行動といったさまざまな部分の精神機能に障害が生じるのです。
精神障害と認定されるのは、
- 精神が正常に働かない
- 行動の異常が出現する
などの特徴が確認できた場合になります。
具体例
精神障害の具体例は、
- 気分障害(うつ病、躁うつ病)
- 統合失調症
- 双極性障害
- アルコールや薬物依存症
- てんかん
- パニック障害
- 高次脳機能障害
など。
雇用上の留意点
精神障害のある精神障害者を雇用する際、雇用上の配慮が必要なケースが多くあります。実際、精神障害者を雇用している事業所の52.4%が何らかの配慮をしているという調査結果もあるほどです。
調査によれば雇用上の配慮の上位は、
- 「配置転換等人事管理面についての配慮」(54.2%)
- 「通院・服薬管理等医療上の配慮」(46.3%)
- 「短時間勤務等勤務時間の配慮」(38.6%)
で、採用後、従業員が精神障害者となった場合に、当該従業員を雇用している事業所の59.5%が配慮を行っているという結果も出ています。
雇用上の配慮の上位には、
- 「職場復帰準備期間中の雇用継続」(72.9%)
- 「配置転換等人事、管理面についての配慮」(69.9%)
が挙げられています。
②発達障害
発達障害とは、脳の発達が生まれつき異なるために起こる障害のこと。先天的な脳の機能障害によって、幼児の段階から症状が現れるのです。
- 乳幼児期の発達の遅れ
- 知的障害
などがあり、通常の育児では対応が難しくなるケースもあります。発達障害は個人差が非常に大きい障害です。
- 複数の発達障害を伴う
- 引きこもりやうつ状態など、周囲の対応や環境によって生じる後天的な二次障害を発症する
といったことも発達障害の特徴です。しかし、障害の特性を本人や周囲が理解する、一人ひとりに合った方法で生活を送る工夫をするなどで、社会の中でも力を発揮して生活できます。
具体例
発達障害者支援法に分類されているものから、発達障害の具体例を挙げてみると、下記の通りとなります。
- 自閉症
- アスペルガー症候群
- LD(学習障害)
- ADHD(注意欠陥多動性障害)
- チック障害
- 吃音(症)
雇用上の留意点
発達障害者を雇用している企業が雇用上で留意すべき点は、業務上の指示をする場合、具体的・視覚的かつ簡潔な指示をすること。
発達障害者には、
- 「適当」「とりあえず」といった曖昧な表現
- 会話の文脈から相手の感情を読み取る
- 目に見えないものを認識する
- 工程が定まっていないことに取り組む
- 耳で聞いたことを記憶する
- 自分で判断を行う
などが苦手という特徴があります。
そこで、
- 業務の指示を定量的に示し、固有名詞を用いて具体的に指示する
- 判断に迷った場合の「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」のルールをあらかじめ書面で伝えておく
- 「いつまでに」「何を」「どんな方法で」実施するのか、作業手順を明確に示す
などの配慮が重要になるのです。
③知的障害
知的障害とは、記憶や知覚、推理や判断といった知的機能に遅れが見られ、社会生活などへの適応が困難な状態にある障害のこと。
知的障害の発症には年齢制限があり、18歳までに生じるものに限定されています。また、医学の分野で用いられている「精神遅滞」とはほぼ同義語で使用されているのです。
知的障害と健常者との線引きは非常に難しいため、行政施策上では、知能指数(IQ)75(もしくは70)以下の場合、知的障害と判定されるといったように線引きが設けられています。
雇用上の留意点
知的障害者は、
- 言葉を用いて自分の気持ちを表現すること
- 金銭の管理
- 読み書きや計算
などが苦手です。
また個人差も大きく、一人ひとりの、
- 職務遂行能力
- 仕事への意欲
- 職場での協調性
などを採用の短時間の面接で把握することはほぼ不可能といえます。そのため、採用の段階で、保護者や行政、支援機関の担当者に面接へ同席してもらい、日頃の訓練や学習の程度、生活状況についてヒアリングするのです。
このヒアリングで得た情報を、採用だけでなく採用後の就業にも活かして、知的障害者の積極的な活用を進めていきます。
④身体障害
身体障害とは、先天的や後天的を問わず、身体機能の一部に障害が生じている状態や、そのような障害そのものを指す言葉です。
身体障害者の範囲は、身体障害者福祉法の中で定められており、身体障害者障害程度等級表に基づいて一人ひとりに等級が決定されます。
等級は、視覚や聴覚、肢体など、障害の種類ごとに設定されており、それぞれの身体障害を計7等級に区分しているのです。7等級のうち、最も重度である1級から軽度の6級に認定された身体障害者には、身体障害者手帳が交付されます。
具体例
身体障害者福祉法では、身体障害を大きく5つの種類に分類しています。
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 内臓機能などの疾患による内部障害
これらの5種類に分類された障害の種類ごとに身体障害の等級が設定されています。等級は、身体障害者障害程度等級表にまとめられており、等級ごとに障害の詳細が記載されているのです。
雇用上の留意点
身体障害者を雇用する際、当該身体障害者にとって、どのような状況が適当であるのかを確認する必要があります。
たとえば肢体不自由障害者を雇用しようとすれば、出入り口や通路、トイレ、仕事場などのバリアフリー化が必要と考えられるでしょう。現在の施設の状況を説明して、改良箇所があるかどうかを確認するのです。
聴覚障害者の場合、本人が口話や手話、筆談などどのようなコミュニケーションを取れるのかを確認します。
視覚障害者の場合、障害の程度に個人差があるだけでなく、視力や色覚、視野といった障害の種類によってもサポート方法が変わりますので、ヒアリングの際に、定期的な通院や検査といった状況も把握しておきましょう。

3.障害者雇用促進法

障害者雇用促進法とは、障害のある人の雇用を促進することを目的として、「障害者雇用に関する事業主が負うべき義務」「障害者への公的な支援措置」などが規定されている法律のこと。
障害があっても、
- 職業人としての自立を促す
- 個々の能力を発揮する機会を与えられる
といった理念の実現を目指しているのです。
障害者雇用促進法には、
- 障害のある人が就労できる機会を得やすくするために、障害者雇用に関する特別枠の設置
- 障害のある人が抱える求職に対する不安軽減のために講じる措置
などについて、具体的に定められています。
障害者雇用促進法は1960年に制定され、その後も段階的に法律改正を経てきた歴史があります。
1976年には、
- 努力義務であった障害者雇用が法的義務へ
- 法定雇用率を達成していない企業に対して、国庫に納付金を納める雇用納付金制度の創設
といった改正が行われました。この流れは現在にも引き継がれており、「割当雇用制度」として確立しているのです。
法定雇用率(障害者雇用率)とは?
法定雇用率とは、国や地方公共団体、民間企業など、すべての事業に対して「一定の数の障害のある人を雇用する」義務を数値化したもので、障害者雇用率とも呼ばれているのです。
民間企業の場合、全従業員のうち2.2%に相当する人数、障害のある人を雇用する義務がある、身体、知的、精神障害のある人を雇わなければいけないことになります。
平成28年4月の改正点
平成28年4月に行われた障害者雇用促進法の改正では、下記のようなことが盛り込まれました。
- 障害者に対する差別禁止の明文化
- 障害者が働く際、職場で生じる支障を改善するための合理的配慮の義務化
- 法定雇用率の算定基礎に、2018年4月より精神障害者も新たに追加
障害者差別の禁止
2016年4月の障害者雇用促進法の改正で、障害者に対する差別禁止が明文化されました。
すべての事業主に対して障害者の採用に関して障害のあることを理由として、
- 募集または採用の対象から排除する
- 障害者に対してのみ不利な条件を付す
- 採用の基準を満たす人の中から障害者でない人を優先して採用する
などを禁止したのです。
また、採用後についても、賃金の決定や教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇といった場面で、障害があることを理由にした不当な差別取り扱いを禁止しました。
これら差別禁止事項については、障害者雇用促進法の中で事業主が適切に対処するための指針として明文化されています。
合理的配慮
2016年4月の改正では、障害者が働く際に職場で生じる支障を改善するための合理的配慮の義務化も盛り込まれました。
これもすべての事業主が対象となっており、障害のある人と障害のない人との「均等な雇用機会の確保」「均等な待遇の確保」に支障をきたさないよう事業主に合理的配慮の提供を義務付けているのです。
また、募集や採用時には障害のある人が応募しやすいような配慮、採用後は障害のある人が、能力を有効に発揮するために支障となっている事情を改善するなども求めています。
具体的な配慮としては、
- 募集内容を音声提供する
- 面接を筆談で行う
具体的配慮は事業主と障害のある人との相互理解の上で提供されていくべきだとされています。

合理的配慮とは?【意味を簡単に】具体例、義務化、問題点
合理的配慮とは、障害を持つ人が障害を持たない人と同様に社会生活を送れるよう、社会的障壁を取り除く配慮のこと。義務化された背景、問題点、企業にできることなどを解説します。
1.合理的配慮とは?
合理的...
合理的配慮の具体例
障害者が働く際、職場で生じる支障を改善するための合理的配慮について具体例を挙げると、障害の種類ごとに次のようなケースが考えられます。
身体障害の場合では、
- 肢体不自由の障害により車椅子を利用している従業員が、通勤ラッシュを避けて出社できるように時差出勤を許可する
- 肢体不自由の障害によって通常の机での作業が困難な場合には、身体への負担を軽減させるために机や椅子の位置や高さ、作業場での動線を調整する
知的障害に関しては、
- 障害の程度や内容に応じて、作業の手順や作業内容を図や絵入りのマニュアルを作成することで、業務への理解や習得を促す
- 「それ」「あれ」「たぶん」「だいたい」といった抽象的で曖昧な表現を避け、具体的な表現で簡潔に説明する
精神障害に関しては、
- 外からは分かりにくい本人の体調や通院、服薬の状況に応じて、出退勤時刻、休暇、休憩などを調整する
- 精神障害で休職後、職場復帰した際には、復帰支援のためのリハビリ体制を構築して周囲の協力を得ながら少ない業務量から徐々に増やしていくなど、本人に過度な負担をかけないペースで復帰プランを立案、実施する
障害の程度には個人差があります。障害のある人それぞれの状況を見極め、正しい知識を持って周囲の理解とともに配慮を行うことが、合理的配慮義務を果たす上で重要でしょう。
法定雇用率の算定基礎
法定雇用率とは、企業の全従業員数に対する雇用しなければならない障害者数の割合のこと。
障害者雇用促進法の中では、国や企業などすべての事業主に対し、法定雇用率の達成が義務付けられています。また、障害者雇用促進法の改正によって、2018年の4月から新たに精神障害者の雇用も法定雇用率に組み込まれました。
改正前の法定雇用率は、民間企業の場合2.0%であったため、常勤職員が50人以上の企業においては1人以上の障害者を雇用する義務が生じるという計算でした。しかし今回の改正法の実施によって、法定雇用率が2.2%に引き上げられたのです。
現在では、1人以上を雇う義務が生じる対象は、常勤職員44.5人以上のすべての民間企業となっています。法定雇用率は、事業主区分によって若干異なり、最も高いのは、国や地方公共団体などで最も低いのは、民間企業となっています。

4.法定雇用率を満たさない企業の扱い、罰金

法定雇用率を満たさない企業は、障害者雇用納付金を納める必要があります。
障害者雇用納付金を納める
障害者雇用促進法に定められている法定雇用率を満たさない場合、不足1人につき月額5万円という障害者雇用納付金を納める必要があります。障害者雇用納付金は罰金ではないため、障害者雇用納付金を納めても、障害者雇用義務が消滅するわけではありません。
企業名が公表される
障害者雇用促進法に定められている法定雇用率を満たさない場合、厚生労働大臣によって当該企業に対し
- 「障害者雇入れ計画」の作成命令
- 「障害者雇入れ計画」の適正な実施に関する勧告
が行われます。勧告を受けた企業は、「障害者雇入れ計画」を作成し、実施しなければなりません。
万が一、厚生労働大臣による勧告に従わない場合、厚生労働大臣はその企業名を公表できます。企業名の公表という事態に陥らないためにも、企業は厚生労働大臣の勧告に対し、適切な対処を行う必要があるでしょう。

5.障害者雇用枠での就労の条件
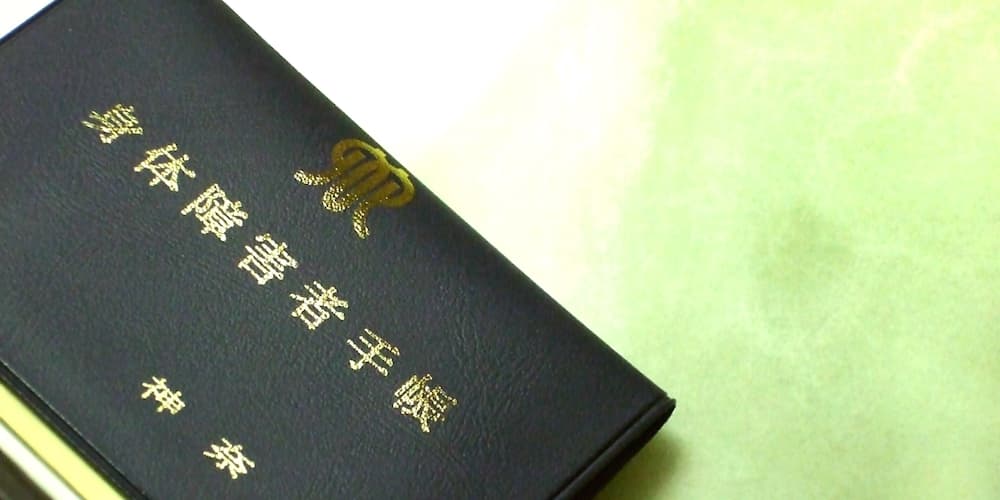
障害者雇用枠で就労するには、一定の条件を満たす必要があります。
障害者手帳の所有
障害者雇用枠で就労するための要件は、障害のある人が地方公共団体から障害者としての認定を受けた場合に取得できる障害者手帳の所有です。
一般的に障害者手帳といった場合、
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(自治体によって、名称が異なるケースもあります)
- 精神障害者保健福祉手帳
3種類の手帳を意味します。障害者雇用枠に応募し就職を希望する場合は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のどれかの障害者手帳を持っていることが必要です。
障害者雇用の対象者
障害者雇用枠の対象者には、以前から要件にあった身体障害や知的障害に加えて、2018年4月から新たに精神障害が加わりました。
- 身体障害
- 知的障害
- 精神障害
3つの障害が対象となっていることを認識しておきましょう。

6.障害者雇用に関する手続き

障害者雇用に関するさまざまな書類があります。それらの書類提出や手続き的な面で相談したい場合、ハローワークを活用しましょう。
障害者雇用状況報告書とは?
障害者雇用状況報告書とは、常時雇用する労働者数が45.5人以上の企業が、毎年6月1日現在で障害者の雇用状況を記載して提出しなければならない報告書のこと。
障害者雇用状況報告書の提出を義務付けられている企業は、
- 対象企業に送付されてくる報告書の用紙
- ハローワークのホームページにアップされているファイル
どちらかに障害者の雇用状況を記載し、本社の所在地を管轄しているハローワークへ提出します。これらの報告書は、行政が各企業に対して指導などを行う基本情報として活用されるものですので、虚偽の報告や報告書の未提出は、罰則の対象となります。
雇用人数などに関しては正確な数字を記載し、期限までに忘れないように提出しましょう。
報告の対象
障害者雇用状況報告書の報告対象となる障害は、
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
のうち、それぞれの障害に応じて付された条件に該当する者です。
身体障害者については、身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の等級が1~6級に該当する人、重度身体障害者はこのうち1~2級の人を障害者雇用状況報告書の対象人数としてカウントします。
知的障害者は、知的障害者福祉法や障害者雇用促進法などで指定された判定機関で知的障害者と判定された人、重度知的障害者は障害の程度が重いと判断された人が障害者雇用状況報告書の対象となるのです。
精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人という条件のみが付されています。
法定雇用率の達成の判断にも使われる重要な報告書なので、身体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれの障害に付されている要件をしっかりと確認しましょう。

7.障害者を雇い入れる際の社内準備

障害者を受け入れる際の、社内準備についてまとめます。
- 職場環境の見直し
- 現場の理解を促す
- 職務を設計する
①職場環境の見直し
採用された障害者が、自らの能力を最大限発揮して就労できる、苦痛を感じないで仕事ができる職場環境を整えることは、障害者を採用した企業の責任です。
職場環境の整備では事前に、当該障害者に障害の程度や必要となる職場環境についてヒアリングを行います。
- 通勤への対応
- 職場の施設や設備のバリアフリー化
- 障害者雇用に協力的な従業員の有無
- 周囲のサポートの有無
などについては最低限把握しておくべきでしょう。障害には、個人差があります。採用した障害者一人ひとりについて、どのような職場環境の整備が必要なのかを把握して、必要な準備に取り掛かりましょう。
通勤に関する確認事項
通勤に関して事前に障害者に確認しておきたい事項は、
- 通勤にかかる時間はどのくらいであるか
- 公共交通機関を使用する通勤が可能であるか
- 自動車での通勤を希望しているか
採用した障害者一人ひとりに具体的に確認していきます。
社内施設や設備に関する確認事項
社内施設や設備に関して、事前に社内で確認しておきたい事項は、
- 車椅子用のトイレはあるか
- スロープや手すり、エレベーターはあるか?
- 音声装備のエレベーターはあるか
- 移動の際に危険なスペースはないか
- 作業マニュアル、手順書は準備されているか
- 十分な休憩スペースは確保されているか
- 障害者雇用に詳しい従業員や、協力的な従業員はいるか
- 障害者が相談できる窓口や面談の機会が用意されているか
など。
- 障害者本人にどのような施設や設備が必要なのかをヒアリングする
- 社内で必要な施設や設備を検討する
といったさまざまな角度からの検討も重要です。施設や設備に関しての整備には予算の計上が必要になる場合もあります。個別の障害に対応しつつ、障害者全体から見ても使いやすい施設や設備となるように工夫が求められるのです。
②現場の理解を促す
障害者を受け入れる際には、職場の理解を促すことも重要です。そのために必要なものは、経営トップのメッセージでしょう。
障害者雇用に成功している企業の例を見てみるとその多くに、
- 経営トップが障害者雇用に対して自らリーダーシップを発揮している
- 経営トップが障害者雇用を強力に推進している
といった特徴があります。「障害者の雇用を推し進めていく」という強い決意を全社員にメッセージとして発信することが、職場理解の第一歩になるようです。
さらに、障害者に対する理解を深めるための研修も重要でしょう。身近に障害者がいない場合、障害者一人ひとりの状況だけでなく、障害者雇用の全体像すらつかみにくい状況にあるといえます。
そこで、研修によって、
- 障害の症状や特徴を学ぶ
- 障害者雇用の趣旨を含めた全体像を学ぶ
という機会を従業員に提供するのです。研修によって、障害者と健常者がお互いを正しく理解できるようになるため、職場での受け入れもスムーズになるでしょう。
③職務を設計する
障害者を受け入れる際には、既存の職務にこだわらず、新たな職務の設計も視野に入れます。そのためにはまず、そもそも会社の中にどのような種類の職務があるのかを確認しましょう。
潜在的な職務も含め現在社内にあるすべての職務の洗い出し、その内容を整理していけば、
- この職務なら任せられる
- この職務をやってもらえると助かる
- この職務は適任である
など、障害者に任せることが最適な仕事が分かってきます。
またこの作業と並行しながら、
- 社内でどんな仕事を障害者のためにつくれるか
- どの部署にどんな仕事があるか
などを事前に確認していくと、障害者を雇用した際に慌てることなく個々の障害に合わせた職務を提供できるようになります。
事務職を例にして具体的に考えると、事務という職務は、
- データ入力
- 書類や資料の作成
- 電話対応
- 伝票処理、整理、仕分け
- 備品発注、管理
などで構成されていると分かります。これが分かれば、雇用した障害者を事務職に配属する際、当該障害者に任せられる職務を選択できるのです。

8.障害者トライアル雇用とは?

障害者トライアル雇用とは、就職が困難である障害者に対して、適性や能力を見極めて継続雇用のきっかけとするという制度のこと。
- 障害者を原則3カ月(精神障害者の場合には最大12カ月雇用する
- 精神状態の安定が見られるようになる
といった場合、常用雇用に切り替えます。

評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

