業務過多とは、従業員が処理可能な仕事量を超えた業務を抱えている状態のこと。この状態が続くと、ストレスの増加や生産性の低下、さらには健康問題が発生するリスクが高まります。そのため、企業は従業員の健康と業務効率を維持するための適切な業務量の管理が必要です。
この記事では、業務過多がもたらすリスクや業務過多になる原因、その改善方法について詳しく解説します。企業ができる対策も紹介するのでぜひ参考にしてみてください。
目次
1.業務過多とは?
業務過多とは、従業員が処理可能な範囲を超える量の仕事を抱え、心身に過度な負担がかかる状態のことです。人員不足や非効率な業務プロセス、不適切な業務分配などが原因で発生します。
業務過多の状態が続くと、従業員のストレスや疲労が蓄積し、生産性の低下や健康問題につながる可能性も高いです。また、仕事の質の低下やミスの増加、離職率の上昇といった組織全体の問題にも発展する恐れもあるため、企業は適切な業務量の管理と従業員の健康維持に注意を払わなければなりません。
業務過多の言い換え方
業務過多を表現する際、状況や文脈に応じてさまざまな言い換えが可能です。以下は、業務過多と同じような状態を示す言い換え方の例です。
- 過重労働
- 労働過多
- タスク過多
- 業務過剰
- 仕事量が多すぎる
- 業務負荷が高い
- オーバーワーク
- キャパシティオーバー
2.業務過多がもたらすリスク
業務過多は従業員と企業の双方に深刻なリスクをもたらします。ここでは、業務過多によって生じるリスクについて、それぞれ詳しく見てみましょう。
従業員のリスク
業務過多が従業員におよぼすリスクとして、次の4つが考えられます。
集中力が散漫になり業務効率が低下する
業務過多の状態が続くと、従業員の集中力が低下し、業務効率が悪化します。これは、多くのタスクを同時にこなそうとすると、それぞれの作業に十分な注意を向けられなくなるためです。その結果、仕事の質が低下し、本来なら短時間で終わるはずの業務にも、より多くの時間がかかるようになります。
ミスが増える
過度な業務負担は、疲労や注意力の低下を招き、ミスの発生率を高めます。時間的プレッシャーや疲労の蓄積により、細部への注意が散漫になり、重要な情報を見落としたり、不適切な判断をしたりする可能性も高まるでしょう。
これは個人の業績評価にも悪影響をおよぼし、さらなるストレスの原因となる可能性があります。
ストレスにより体調不良に陥る
長時間労働や締め切りのプレッシャーにより、慢性的なストレスが蓄積し、頭痛や不眠といった症状が出ることがあります。また、過労や心臓病などの健康問題が引き起こされることも。
さらに、うつ病などのメンタルヘルスの問題に発展する可能性もあり、最悪の場合は過労死につながることもあるため、従業員の生活の質が大きく損なわれる恐れがあります。
ワークライフバランスが崩れる
長時間労働や休日出勤が常態化すると、家族との時間や個人の趣味・娯楽の時間が削られ、ワークライフバランスが損なわれやすくなります。その結果、プライベートの充実感が失われ、仕事への不満が増えたり、燃え尽き症候群になったりするリスクが高まるでしょう。

ワークライフバランスとは? メリット、取り組み事例などを紹介
少子高齢化に伴う労働力不足を目前とする今、ワークライフバランスの実現に多くの企業が積極的に取り組み始めています。一体、ワークライフバランスとは何でしょうか?
ワークライフバランスの意味
ワークライフ...
企業のリスク
続いて、業務過多による企業側のリスクについて見ていきましょう。
生産性が低下する
過度な業務負担やストレスは、従業員のパフォーマンスを下げ、仕事の効率を悪化させます。また、属人化や非効率な業務プロセスが蔓延すると、組織全体の生産性も落ちてしまいます。
そのため、企業は適切な業務量の管理と効率的な業務プロセスの構築に注力する必要があるでしょう。
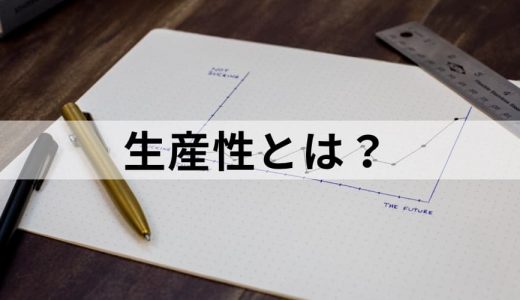
生産性とは? 意味や計算式、低い理由、向上の取り組みを簡単に
組織の生産性をあげるなら
人材情報を戦略的に活用できる「カオナビ」
⇒人事管理システム「カオナビ」の資料はこちらから
生産性を向上させるためには、単にオートメーション化するのではなく、社員の労働環境...
ミス・事故が起きやすくなる
従業員が疲労やストレスを抱えると、判断力や注意力が低下し、重大な過失や事故が発生するリスクが高まります。とくに、製造業や医療分野では、些細なミスが深刻な結果を招く恐れがあり、企業の信頼性や評判に大きな打撃を与えるでしょう。
長時間労働による法的リスクが高まる
業務過多による長時間労働は、労働基準法違反などの法的リスクを高めます。残業時間が上限を超えたり、適切な休憩が確保されなかったりすることが問題となり、労働基準監督署から是正勧告や罰金などのペナルティを科される可能性もあります。
さらに、過労死や過労自殺といった深刻な事態に発展すれば、企業としての社会的責任が問われ、重大な法的責任に直面するリスクも生じるでしょう。
退職者や休職者が増える
過度の業務負担やストレスが続くと、優秀な人材が他社へ流出したり、心身の不調により休職を余儀なくされたりする事例も出てくるでしょう。これは企業にとって人材の損失だけでなく、残された従業員の負担増加や、新たな人材の採用・育成コストの増大につながります。
3.業務過多になる原因
業務過多は従業員側と企業側の両方に原因があります。これらの要因を理解し、適切に対処することが重要です。
従業員側の原因
従業員が業務過多になる原因として、主に以下の4つが考えられます。
仕事を引き受けすぎてしまう
多くの従業員が、自分の能力以上の仕事量を引き受けてしまう傾向にあります。これは、断ることへの罪悪感や評価を上げたいという思いから生じるものでしょう。
しかし、キャパシティを超えた仕事を引き受けるのは、質の低下や締め切りの遅延につながるもの。適切な量の仕事を引き受け、必要に応じて上司や同僚に協力を求めることが重要です。
タスク管理が不足している
優先順位の設定や締め切りの管理が不十分だと、重要な業務が後回しになったり、締め切りに追われたりする事態に陥りやすくなります。タスク管理ツールの活用や、日々のTo-Doリストの作成など、自分に合った方法でタスクを整理することが大切です。

タスク管理とは? プロジェクト管理との違い、メリット、無料ツール
タスク管理とは、チーム全体ではなく、個々の担当業務を管理すること。プロジェクト管理との違いやタスク管理のメリット、どのような無料ツールがあるのか解説します。
1.タスク管理とは?
タスク管理とは、個...
ムダや非効率な業務をしている
業務には、必要性の低い作業や非効率な手順が含まれていることがあります。これらを見直し、改善することで、業務の効率化が図れます。たとえば、不要な会議の削減や報告書の簡略化、反復作業の自動化などは効果的です。定期的に自分の業務を見直し、ムダを省くよう心がけましょう。
メンタルヘルスの問題を抱えている
ストレスや不安、うつ症状などが業務効率の低下や集中力の欠如につながり、結果として業務過多を引き起こす可能性があります。自身の心の健康に注意を払い、必要に応じて専門家のサポートを受けることが重要です。
企業側の原因
会社側の要因で業務過多に陥るケースはよくみられます。典型的な例として人手不足が挙げられます。ここでは、業務過多になる企業側の原因を詳しくみていきましょう。
人手不足が続いている
人手不足は業務過多の主要な原因の一つ。たとえば、退職者が出ても新たな採用を行わず、残った従業員に業務を任せ続けると、人手不足による業務過多が生じやすくなります。
また、業績不良などを理由に人員を削減すると、一人ひとりの負担が増え、業務過多につながる原因となります。
ノルマや目標設定が高すぎる
現実的でない高いノルマや目標を設定すると、それを達成するため従業員は残業や休日出勤を余儀なくされます。また、このようなプレッシャーによって、仕事の質が落ちたり、メンタルヘルスに悪影響が出たりするリスクも高まるでしょう。
マネジメントが行き届いていない
適切なマネジメントは、業務をスムーズに進めるために欠かせません。管理者が部下の業務状況を把握できていないと、適切な指示や支援ができず、特定の従業員に仕事が集中し、過度な負担をかけることがあります。
また、管理者が適切な業務配分や進捗管理を行わないと、部署間で業務量に大きな差が出たり遅延が発生したりするなど、組織全体の効率が低下するでしょう。

マネジメントとは? 意味、役割と業務、必要なスキルを簡単に
マネジメントとは、経営管理・組織運営の手法のこと。マネジメントするうえで、なぜマネジメントが必要なのか、どういった役割やスキルを持って課題解決に取り組めばよいのかを知っていると知っていないとでは、マネ...
4.業務過多になりやすい人の特徴
業務過多は誰にでも起こり得る問題です。しかし詳しく見てみると、業務過多に陥りやすい人とそうでない人がいることがわかります。ここでは、業務過多になりやすい人の特徴を確認してみましょう。
作業スピードが遅い
作業スピードが遅いと、同じ仕事量でも他の人より時間がかかり、結果的に仕事が溜まりやすくなります。この原因には、業務の優先順位が適切でないことや、効率的な作業手順が確立されていないこと、集中力が続かないこと、または経験不足などが考えられます。
こうした課題を改善するには、業務効率化に向けたスキルの向上や時間管理の見直しが必要です。
仕事を断れない
頼まれた仕事を断れない人は、結果的に自分のキャパシティを超える業務を抱え込み、業務過多に陥りやすいです。とくに責任感が強く、他者の期待に応えたいと考える人は、無意識のうちに過剰な業務を引き受けてしまう傾向にあるもの。一度仕事を引き受けると、その後も断りづらくなり、キャパオーバーの状態が続いてしまいがちです。
期待に応えようと無理して頑張りすぎている
上司や同僚の期待に応えようと無理を重ねる人は、自分の限界を超えて業務を引き受け、結果的に業務過多に陥ることがあります。これは、体力に自信のある人や、業務を始めたばかりの新人によく見られます。
パワーハラスメントを受けている
パワーハラスメント(パワハラ)を受けている従業員は、上司や同僚との関係悪化を恐れて過剰な業務を抱え込んだり、メンタルヘルスの悪化によって集中力が低下したりする可能性があります。その結果、業務の質や量のバランスが崩れることもあるでしょう。
パワハラの具体例として、過度な叱責、机を叩くなどの威圧的な行為、不当な業務の押し付けなどが挙げられます。
このような状況を改善するには、パワハラに関する研修の実施、相談窓口の設置、管理職の意識改革など、組織全体でパワハラ防止に取り組むことが重要です。また、被害を受けている従業員自身も、一人で抱え込まずに相談するとよいでしょう。
5.業務過多の対策方法
業務過多を解消するには、従業員と企業の両方が対策を行うことが大切です。ここでは、従業員と企業がそれぞれ実践できる対策を見ていきましょう。
従業員ができる対策
業務過多を解消するために、従業員が取れる対策を解説します。
仕事を引き受けすぎない
自分のキャパシティを超えた仕事を引き受けないことが重要です。現在の業務量や締め切りを考慮し、新たな仕事を引き受ける前に慎重に検討しましょう。必要に応じて上司や同僚に相談し、業務の優先順位や分担について話し合うことが大切です。
自分の限界を認識し、適切に「ノー」と言える勇気を持つことで、無理のない働き方ができるようになります。
業務を可視化して整理する
業務を可視化すると、タスクの優先順位をつけやすくなり、効率化に役立ちます。ToDoリストやガントチャートなどのツールを使って、全体の流れを把握しましょう。これにより、重要な業務に集中しやすくなり、マニュアル作成による効率化も進みます。
また、定期的に業務を見直して不要な作業を削減すると、さらなる効率化が期待できます。
仕事の早い人を参考にする
効率的に仕事をしている同僚の時間管理やツールの使い方、タスクの優先順位のつけ方を参考にするのも効果的です。そのなかから自分に合う方法を取り入れると、業務効率の向上が期待できます。
ただし、そのまま真似するのではなく、自分に合う方法を見つけることが大切です。
上司に相談する
業務過多に陥った場合、一人で抱え込まずに上司に相談することが大切です。現在の業務状況や課題を具体的に説明し、解決策を一緒に考えてもらいましょう。上司は業務の再分配や優先順位の調整、必要に応じて人員の増強などの対策を講じていけます。早めの相談が、問題の拡大を防ぎます。
プライベートな予定を入れる
ワークライフバランスを保つには、プライベートの予定を意識的に入れることが大切です。趣味を楽しんだり、家族と過ごしたり、自己啓発の時間を確保すると、心の健康を保ち、やる気を高める効果があります。さらにオフの時間を大切にすれば、仕事に集中できるようになり、仕事の効率も上がるでしょう。
企業ができる対策
続いて、企業が業務過多を改善する方法を見ていきましょう。
無駄な業務をカットする
定期的に業務内容を見直して、不要な作業や非効率なタスクを減らすことが必要です。例えば、会議を減らしたり、報告書を簡略化したり、重複している作業をまとめたりすることが考えられます。
業務プロセスの見直しにより、従業員の負担を軽減し、本質的な業務に集中できる環境を整えられます。
業務の標準化を進め仕事量の偏りをなくす
業務の標準化は、効率性の向上と業務量の偏りを解消するために重要です。標準的な業務フローやマニュアルを整備すると、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようになります。これにより、特定の従業員への業務集中を防ぎ、チーム全体で均等に業務を分担することが可能です。

業務標準化とは? 目的、メリット、進め方をわかりやすく解説
業務標準化とは、明確な業務プロセスを確立・統一することです。標準化によって特定の担当者に依存する状況を解消でき、誰が担当しても一定の品質・成果が出せるようになります。
今回は業務標準化について、目的や...
マネジメントを見直す
管理者のマネジメント力に問題があると、業務や人材が適切に分配されないかもしれません。従業員から不満が出ている場合は、別のポジションや他部署への異動が可能か、検討してみましょう。各部署にふさわしい管理者を配置すると、業務の流れがスムーズになり、業務過多の解消にもつながりやすくなります。
業務委託・アウトソーシングを活用する
企業内で処理しきれない業務や、専門性の高い業務については、外部への委託やアウトソーシングを活用することも有効です。外注は一時的にコストが増えるものの、長期的にはコスト削減につながる場合も多いです。
外注により社内リソースを核となる業務に集中させられるため、業務の質と効率も向上するでしょう。ただし、委託先の選定や管理には十分な注意を払う必要があります。
ITツールを活用する
適切なITツールの導入は、業務効率の大幅な向上につながります。たとえば、プロジェクト管理ツール、ナレッジ共有ツール、コミュニケーションツール、会計・契約の電子化ツールなどを活用すると、情報共有の円滑化や作業の効率化が図れます。
ただし、ツールの導入にあたっては、従業員のスキルレベルや業務の特性を考慮し、適切な選択と運用が必要です。
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

