ヒューリスティックには代表性、利用可能性、固着性、シミュレーション、感情など、複数の種類が存在します。意思決定においては直感的に判断することが多く、認知バイアスが影響を与えることもあります。ビジネスや人事、マーケティングなど多くの分野で活用されています。
目次
1.ヒューリスティックとは?
ヒューリスティックとは、ある程度、正解に近いレベルの答えを導き出す方法のことです。問題に対して簡略化した方法で、英語では、「Heuristic」「Heuristics」といいます。
ヒューリスティックは行動経済学上で、意思決定の際、「綿密に計算や分析を行わない」「簡略化した思考で結論を出す」ことを意味しているのです。
類語は「経験則」
ヒューリスティックの類語は経験則(経験的法則を略した言葉)です。
経験則は、因果関係は不明確でありながらも、
- 今までの経験から得られる事実にもとづいた法則
- 経験上、おそらくそうなるだろうと考えられる法則
の2つの側面があります。経験が根拠になるため、非論理的なものと認識しないよう注意が必要です。
2.ヒューリスティックと混同しやすい言葉
ヒューリスティックと混同しやすい言葉について、解説しましょう。
- 認知バイアス
- アルゴリズム
①認知バイアス
たとえば赤いものを見たときに、「辛そう」「熱そう」など判断を下すこと。認知バイアスの判断スピードは早く、バイアスと呼ばれる偏りを含む場合もあります。ヒューリスティックは、正解に近い答えを導き出すという点で異なるのです。

バイアスとは? ビジネスでの意味、種類と具体例、対策を簡単に
1.バイアスとは?
バイアス(bias)とは、偏りや偏見、先入観を意味し、認識の歪みや思考の偏りを表す言葉として使用されます。バイアスには様々な種類があり、どれも自身の思い込みや前例といった要因か...
②アルゴリズム
計算で問題を解決する方式のこと。コンピュータープログラミングといった世界で明確な正解を出すために活躍します。一方、ヒューリスティックは、人工知能などの分析力が必要となる正解が導きにくい分野で活躍するのです。
3.ヒューリスティックが起こるメカニズム
ヒューリスティックは、経験値にもとづいて直感的に判断する場面で多く用いられます。たとえば下記のような状況下で、ヒューリスティックが起こりやすくなるのです。
- 問題に関する情報が多すぎて、すべてを把握し処理できない
- 時間が限られており、問題に対し思慮する時間がない
- 結論を導き出すには経験や情報が不足している
二重過程理論
我々人間の意思決定はふたつのしくみで行われるという理論のことで、下記2つにわかれます。
- (A)直感的かつ素早く意思決定をするシステム
- (B)論理的思考でゆっくりと熟慮後に意思決定を行うシステム
この場合、意思決定のスピードが早い(A)のシステムで、バイアスによる思考に偏りが生じやすくなります。
4.ヒューリスティックの主な種類と具体例
ヒューリスティックには何があるのでしょう。ヒューリスティックの5種類について、解説します。
- 代表性ヒューリスティック
- 利用可能性ヒューリスティック
- 固着性ヒューリスティック
- シミュレーションヒューリスティック
- 感情ヒューリスティック
①代表性ヒューリスティック
「サイコロを3回振ってすべての数字が同じになる可能性は低い」「バスケットボールの選手は背の高い人が多い」といった無意識の判断です。典型的なヒューリスティックといえるもので、どちらも必ずしもそうであるとはいえません。
②利用可能性ヒューリスティック
利用しやすい経験に頼った判断をすること。
たとえば、慌ただしい夕方にスーパーマーケットへ行ったとき、要不要を判断する時間もなく、陳列された商品の中から思い浮かんだ商品をカートに入れるような作業です。このようなケースでは、いつも買っているという経験が優先されています。
③固着性ヒューリスティック
最初に手にした情報をもとに判断すること。
英語で「Adjustment Anchoring」といい、船を固定するアンカーを基準に判断、行動することを意味します。たとえば、テレビの今日の占いを信じたり、ひとり〇個までとあれば最も多い個数を買ったりするなどです。
④シミュレーションヒューリスティック
それまでの経験や持っている先入観を用いて結果を推定する方法のこと。
たとえば、「今まで上手にできたことがないから今回も失敗する」「どんなことがあっても、きっと最後はうまくいく」などと考えることです。
自身の失敗体験か成功体験のいずれが多いかによって、思いつく結果がネガティブかポジティブか、変わります。
⑤感情ヒューリスティック
「自分によってメリットがあるか」「自分の気分」「自分にとってリスクがあるか」など、自分自身の感情を基準に意思決定を行うこと。
たとえば、好きな人から声をかけられたら嬉しく思いますが、苦手な人からの場合、わずらわしいと思うでしょう。
またオレオレ詐欺は、「自分の子どもが困っていたら助けたい」という高齢者の気持ちを悪用した例といえます。
5.ヒューリスティックが起こしやすい認知バイアス
ヒューリスティックが起こしやすい認知バイアス6つについて、それぞれ解説します。
- 正常性バイアス
- 対応バイアス
- 内集団バイアス
- 確証バイアス
- ステレオタイプ
- アインシュテルング効果
①正常性バイアス
想定外の事態に直面したとき働くバイアスで、異常事態を正常の範囲ないと誤認識してしまうメカニズムのこと。正常性バイアスが働き過ぎると、場合によっては命の危険にさらされることもあるので注意が必要です。
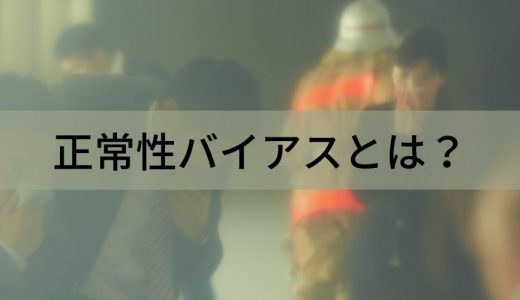
正常性バイアスとは? 具体例、強い人の特徴、同調性バイアス
1.正常性バイアスとは?
正常性バイアスとは、予期しない事態にあったとき、「そんなことはありえない」といった先入観や偏見を働かせて、「事態は正常の範囲」だと自動的に認識する心のメカニズムのこと。こ...
②対応バイアス
「外部的な要因を無視する」「自分の内面に意思決定の要因を求める」といった心理的傾向のこと。基本的帰属誤謬や根本的帰属錯誤などとも呼ばれています。たとえば電車の遅延で仕事に遅れた人を「だらしがないから遅刻した」と思い込むものです。
③内集団バイアス
外部より内輪に対して、好意的な感情を持ったり過剰な反応を示したりすること。内集団バイアスの根本には、帰属意識があるのです。たとえば、出身校が同じというだけで安心感や好印象を持ち、すぐに打ち解けるといったことが該当します。
④確証バイアス
自分を肯定する情報を無意識のうちに収集して判断材料にすること。たとえば、自分は正しいと思いたいため、「自分に都合のいい情報を採用する」「自分自身を否定する情報をシャットアウトする」といった行動です。

確証バイアスとは?【具体例でわかりやすく】正常性バイアス
確証バイアスとは、自分にとって都合のよい情報ばかりを集めてしまう認知バイアスの一種です。ここでは確証バイアスの具体例や改善方法、ビジネスシーンでの活用方法について解説します。
1.確証バイアスとは?...
⑤ステレオタイプ
広く社会に浸透している既成概念や固定概念のこと。ステレオとは、活字印刷で使用した鉛版のステロ版を指します。同じものを大量に印刷できることが言葉の由来です。
⑥アインシュテルング効果
自分になじみあるものを受け入れ、それ以外のものを無視、否定する傾向のこと。確認バイアスの基礎となるバイアスです。たとえば格下の相手に負けたり、豊富な経験があるのに失敗したりするものが該当します。
6.ヒューリスティックを効果的に活用できるシーン
ヒューリスティックを効果的に活用できるシーンを4つ、解説しましょう。
- ビジネスでの日常業務
- 人事や採用
- マーケティング
- IT
①ビジネスでの日常業務
たとえば下記のようなものです。
- 新規事業を検討する際にはヒューリスティックを理解し、期待のあまりリスクを過小評価していないかをチェックする
- 認知バイアスを利用し、SNSの更新頻度を上げたり顧客とひんぱんにコンタクトをとったりして好感度を高める
- 作業手順を決めるときは利用可能性ヒューリスティックを考慮し、目的から逆算して優先順位を決定する
②人事や採用
たとえば、利用可能性ヒューリスティックによって起こる認知バイアスである単純接触効果を活用し、内定者と頻繁に会う機会を設けて内定辞退を防止すること。内定式やその後に開催される懇親会以降、入社まで定期的にコンタクトをとるのが効果的です。
③マーケティング
たとえば、下記のようなものです。
- 選択肢を3つ用意し、そこから消費者に選択してもらう
- あえてネガティブなイメージを打ち出し、それを回避する手段を選択してもらう
- 記憶からかんたんに引き出せるようなキャッチーなイメージを消費者に植えつける
④IT
ここでは「ヒューリスティック検知」「ヒューリスティック調査・分析・評価」について、解説します。
ヒューリスティック検知
ウイルス検知で一般的に用いられるシグネチャで定義されたウイルスしか検出できない、パターンマッチング以外の検知方法のこと。ヒューリスティック検知は、設定されたアルゴリズムに従いウイルスを検知します。
シグネチャを使わないものへの精度は高いが、ある程度正しい判断にしかできず、誤認識もあります。
ヒューリスティック調査・分析・評価
- コンサルタントがwebサイトの使い勝手の良さ、アクセスのしやすさなどを調査すること。調査→分析→評価の順で進んでいきます。
- ヒューリスティック分析:経験値を活かしながら試行錯誤する
- ヒューリスティック評価:ユーザー目線で使用感を評価する
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

