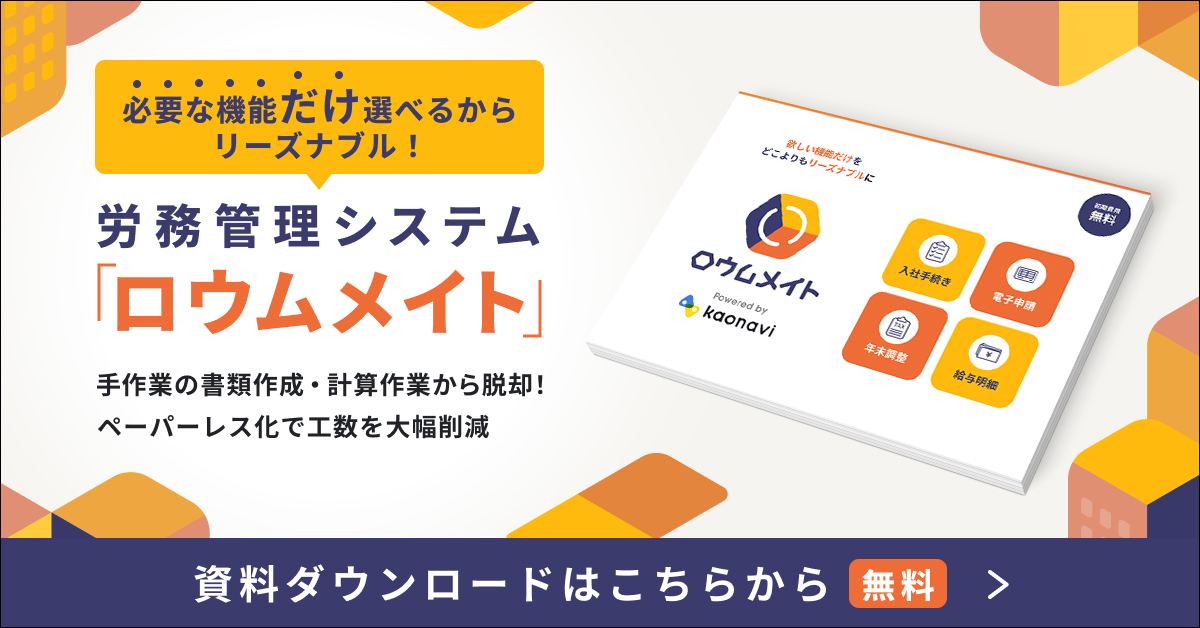人事労務業務において、被保険者整理番号の管理は避けて通れない重要な実務のひとつです。しかし、「健康保険と厚生年金保険で番号が異なるのはなぜ?」「マイナンバーとの関係性は?」など、初めて人事実務に携わる方にとっては戸惑うことも多いのではないでしょうか。
本記事では、被保険者整理番号の基礎知識から実務での活用方法まで、人事労務担当者が知っておくべき情報を分かりやすく解説します。
目次 [表示する]
被保険者整理番号の基本と重要性
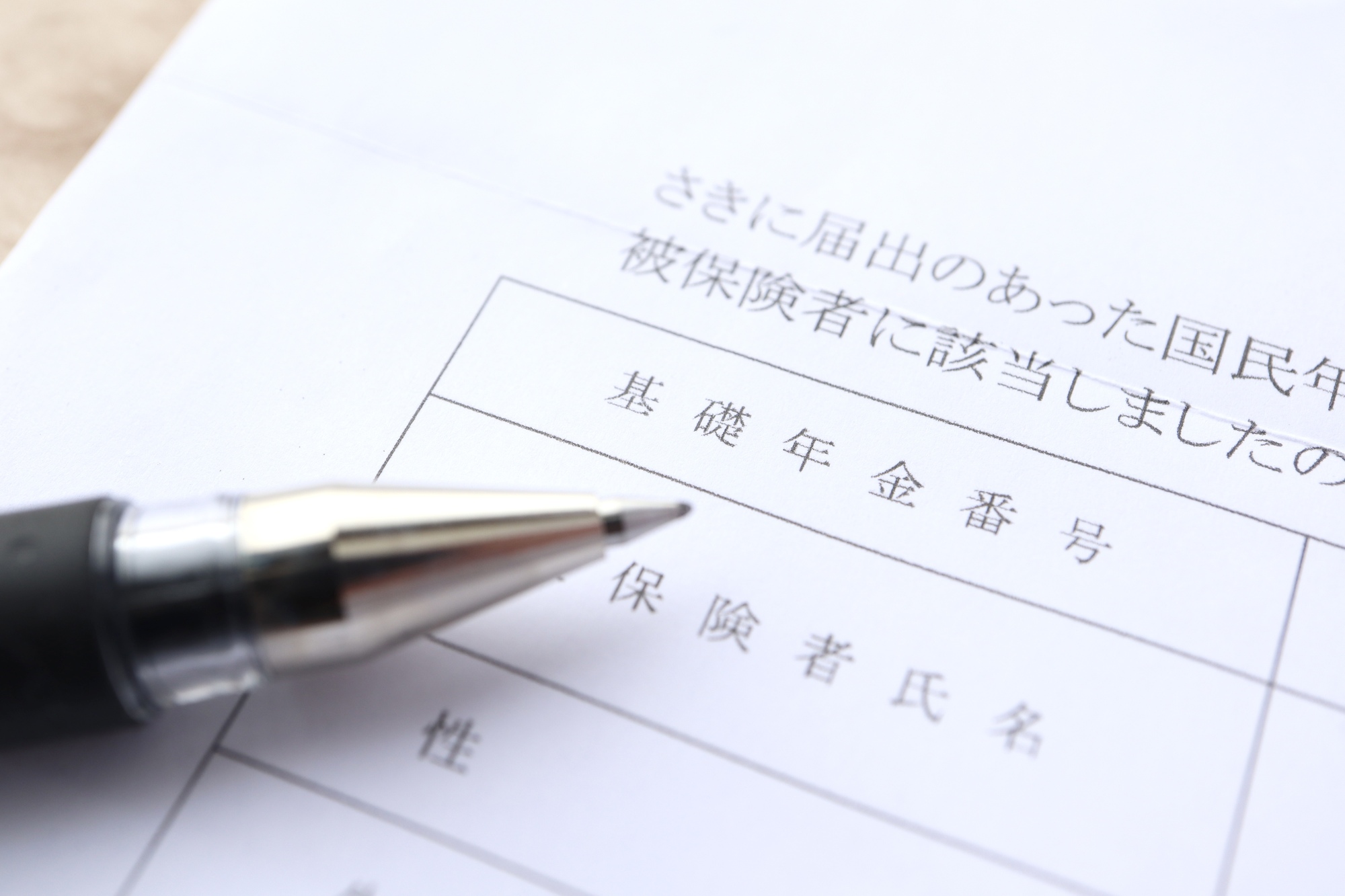
社会保険実務において、被保険者整理番号は重要な識別番号としてさまざまな場面で活用されています。この番号の基本的な定義や役割、健康保険と厚生年金保険での違い、さらにマイナンバーとの関係性まで、人事労務担当者が把握すべき基礎知識を解説します。
特に、2024年度からのマイナンバーカードの健康保険証利用開始にともなう変更点や、各種手続きでの具体的な使用方法など、実務に直結する情報を分かりやすく説明していきます。
被保険者整理番号の定義とは
被保険者整理番号は、社会保険制度において個人を特定するために使用される重要な識別番号です。健康保険や厚生年金保険の加入者に対して割り当てられ、各種の社会保険手続きで必要となります。この番号は、事業所ごとに従業員の資格取得順に付与され、一度使用された番号は再利用されません。
主な役割として、医療費の払い戻しや傷病手当金の申請、育児休業の手続きなど、さまざまな社会保険関連の手続きで本人確認の際に使用されます。また、従業員の入退社時や扶養家族の変更手続き、各種給付金の申請時にも必要となります。事業主は、この番号を適切に管理し、社会保険手続きを正確に行うことが求められます。
健康保険と厚生年金保険の番号の違い
2024年度からマイナンバーカードが健康保険証として利用可能となり、オンライン資格確認が標準となりました。マイナンバーカードの保険証利用時は、カードに記載された情報と、医療機関の顔認証付きカードリーダーで本人確認を行います。
健康保険と厚生年金保険では、被保険者整理番号の運用方法が異なります。健康保険の被保険者整理番号は、医療費の請求や出産・育児休暇の取得などの手続きで使用されます。
一方、厚生年金の被保険者整理番号は、事業主が独自に割り振る番号で、厚生年金の加入・脱退や被保険者の情報変更などの手続きに利用されます。会社を退職し新たに加入した場合は、被保険者整理番号も変更となります。
同じ被保険者でも健康保険と厚生年金で整理番号が異なる場合があります。これは、それぞれの保険制度が独立して運営されているためです。
マイナンバーとの関係性
被保険者整理番号とマイナンバーは、それぞれ異なる目的と用途を持つ重要な識別番号です。マイナンバーは、国が発行する12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野で使用される生涯不変の番号です。
一方、被保険者整理番号は、各保険制度における個人の識別に特化した番号であり、転職などで変更される可能性があります。
近年、雇用保険の被保険者資格に関する手続きや健康保険の給付申請手続きなど、さまざまな社会保険関係手続きでマイナンバーの提示が必要となっています。ただし、これは被保険者整理番号に代わるものではなく、両者は並行して使用されます。
将来的には、マイナンバーを活用した行政手続きのデジタル化が進み、社会保険手続きの効率化が期待されています。しかし、現時点では被保険者整理番号は社会保険実務において不可欠な識別番号として機能し続けています。
被保険者整理番号の確認と管理方法

被保険者整理番号の確認・管理には、マイナンバーカード時代に対応した新しい方法が必要です。従来の健康保険証での確認から、人事労務担当者による一元管理へと移行し、電子申請システムが普及したことによって、より正確な番号管理が求められています。
ここでは、被保険者整理番号の具体的な確認方法から、事業所での効率的な管理方法、さらに電子申請システムでの取り扱いまで、実務に即した重要なポイントをご説明します。
被保険者整理番号の確認方法と記載場所
被保険者整理番号の確認方法は、近年のマイナンバーカード健康保険証利用にともない大きく変わりました。従来は健康保険証の「記号・番号」欄で確認できましたが、現在は人事労務担当者への確認が主な方法となっています。
会社の人事労務担当者は、厚生年金保険資格取得届や台帳などで被保険者整理番号を管理しており、必要に応じて従業員に番号を通知します。また、管轄の年金事務所に問い合わせることで、正しい番号を確認することも可能です。
医療機関での受診時は、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーで本人確認を行うため、従来の被保険者整理番号は必要ありません。ただし、傷病手当金の申請や育児休業給付金の手続きなど、各種給付申請の際には引き続き被保険者整理番号が必要です。
なお、事業主は被保険者整理番号を適切に管理し、従業員から問い合わせがあった際に速やかに回答できる体制を整えておくことが重要です。特に電子申請システムを利用する場合は、番号の正確な把握が不可欠となります。
番号の割り振りルールと管理のポイント
被保険者整理番号の割り振り方法には、特に決まったルールはありません。多くの企業では、入社順に連番で設定する方法を採用しています。
新規入社者には、直前の手続きで使用した番号の次の番号を割り当てます。また、退職者が出て欠番が生じても、その番号を再利用することはできません。
番号管理のポイントとして、以下の2点が重要です。
- 健康保険と厚生年金で異なる番号が存在する可能性があるため、それぞれの番号を正確に記録すること
- 最後に発行された公文書(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届など)から、現在使用している最新の番号を確認できるため、これを適切に保管すること
これらの管理を効率化するため、多くの企業が労務管理システムを導入しています。システムを活用することで、被保険者整理番号の管理から各種申請手続きまでを一元的に処理できます。
電子申請システムでの番号の取り扱い
電子申請システムでは、被保険者整理番号を直接指定することはできませんが、備考欄に番号を記載することで、その番号が採番される可能性があります。
ただし、年金事務所の担当者によって、記載した番号とは異なる番号が採番される場合もあるため、事前に管轄の年金事務所や提出先の年金機構事務センターへの確認がおすすめです。
重要なのは、番号が確定した後の情報管理です。採番された番号は速やかに従業員情報に反映し、以降の手続きで混乱が生じないよう、正確な記録を保持する必要があります。
実務での活用と注意点

被保険者整理番号は、社会保険実務においてさまざまな場面で活用される重要な識別番号です。日常的な保険給付の申請から、組織変更にともなう手続きまで、その使用範囲は多岐にわたります。
以下では、実務における具体的な使用場面と、企業の合併・統合時における番号の取り扱いについて詳しく解説します。特に近年は、デジタル化の進展にともない、これらの手続きをシステムで効率的に管理する企業が増えていることにも注目が集まっています。
各種届出・申請時の使用場面
社会保険の手続きにおいて、被保険者整理番号はさまざまな場面で必要となります。健康保険の被保険者整理番号は、高額療養費支給や傷病手当金の申請時に使用します。また、海外治療費制度の利用や出産育児一時金の申請、産前産後休業の手続きなど、福利厚生に関連する手続きでも必要不可欠です。
一方、厚生年金の被保険者整理番号は、従業員の入社時における資格取得届や退職・死亡時の資格喪失届の提出時に使用します。さらに、被保険者の氏名変更や住所変更などの届出時にも使用します。
これらの管理を効率化するため、労務システムなどの管理ツールを導入する企業も増えています。デジタル化により、人事情報の一元管理が可能となり、手続きの効率化を実現できます。
会社の合併・分割時の番号の取り扱い
会社が合併・統合を行う際、事業所整理記号の変更にともない被保険者整理番号も変更が必要となります。事業所が合併・統合して事業所整理記号が変更となる場合、被保険者整理番号も新たに割り当てられます。
被保険者整理番号は、社会保険加入順に採番され、退職者による欠番があっても同じ番号は使用できません。
合併・統合後の新しい被保険者整理番号は、人事労務部門が従業員に個別に通知する必要があります。従業員は新しい番号を用いて、今後の社会保険に関する各種手続きを行うことになります。
なお、合併にともなう被保険者整理番号の変更は、管轄の年金事務所に提出する各種届出や申請書類に反映させる必要があります。
| 状況 | 必要な対応 |
| 合併・統合時 | 新規番号の割り当て |
| 番号変更後 | 従業員への通知と各種手続きへの反映 |
まとめ

被保険者整理番号は、健康保険および厚生年金保険において、加入者を個別に識別・管理するための重要な番号です。事業所ごとに付与されています。実務では各種手続きや電子申請時に必須となり、正確な管理が求められます。
近年では、マイナンバー制度との連携も進んでおり、事業所の統廃合などにも対応した柔軟な運用が行われています。今後も社会保障制度の変更に応じて、その重要性はさらに高まることが予想されます。
被保険者整理番号の管理は、人事労務担当者にとって重要な業務のひとつです。特に健康保険と厚生年金で異なる番号が存在する可能性や、マイナンバー制度との併用など、管理の複雑さは増す一方です。
従業員情報の管理課題を解決するために、多くの企業が労務管理システムを導入しています。ロウムメイトなら、従業員情報の一元管理、また各書類の電子申請まで、一連の流れで処理できます。クラウドベースで場所を選ばず利用可能で、リモートワーク環境でも効率的な労務管理を実現します。さらに、高水準のセキュリティで大切な従業員情報を守ります。