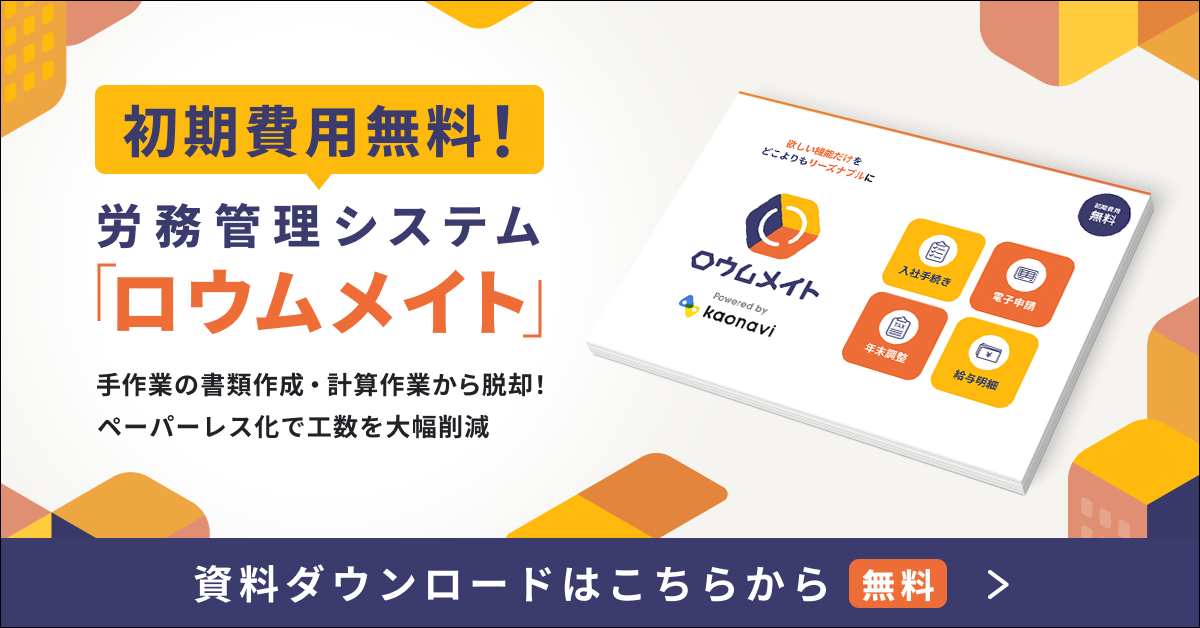人事労務担当者として法定福利費の計算・管理は避けて通れない業務ですが、複雑な計算方法や頻繁に変わる料率に頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。健康保険、厚生年金、雇用保険などさまざまな保険料が絡み合い、企業規模や業種によっても取り扱いが異なるため、正確な計算と適切な管理が求められます。
本記事では、法定福利費の基礎知識から正確な計算方法、業種別の対応まで、人事労務担当者が知っておくべき情報を完全網羅。最新の料率情報と実務のポイントを押さえた完全ガイドをお届けします。
法定福利費とは?基本知識と種類を徹底解説

法定福利費は企業運営において理解しておくべき重要な経費項目です。
この章では、法定福利費の基本的な定義から、企業が負担する意義と目的、具体的な内訳となる6つの保険料・拠出金の種類、そして一般的な福利厚生費との違いについて解説します。社会保険制度を支える基盤として、また人事労務管理の重要な要素として法定福利費を正しく理解することは、適切な人件費計算や予算策定に不可欠です。
従業員の権利保護と企業のコンプライアンス順守のために、まずは法定福利費の基礎知識をしっかりと押さえていきましょう。
法定福利費の定義と企業が負担する意義と目的
法定福利費とは、健康保険法や厚生年金保険法などの法律に基づいて企業が従業員のために負担することが義務付けられている費用です。この費用は単なる支出ではなく、従業員の健康維持や老後の生活保障、失業時の生活支援など、社会保障制度を支える重要な基盤となっています。
法定福利費には主に6つの項目があります。社会保険の加入義務は、すべての法人と常時5人以上の従業員を雇用する個人事業主に課せられています。一方、労働保険は従業員を1人でも雇用していれば加入が必要です。これらの保険制度は、労働者の権利を保護し、生活の安定を法的に担保するという重要な意義を持っています。
法定福利費に含まれる6つの保険料と拠出金の内訳
法定福利費は6種類の保険料と拠出金で構成されています。まず「健康保険料」は従業員とその家族の医療費負担を軽減するもので、保険料率は地域や加入先によって異なり、労使で折半します。「厚生年金保険料」は老後や障害、死亡に備える保険で、保険料率は18.3%で労使折半です。40歳以上の健康保険加入者には「介護保険料」が発生し、こちらも労使折半となります。
「雇用保険料」は失業時や育児・介護休業時の給付を行うもので、週20時間以上勤務する従業員が対象です。保険料率は業種により異なり、労使で負担割合が決まっています。「労災保険料」は業務上の傷病や通勤災害に対する補償制度で、保険料は事業主が全額負担します。最後に「子ども・子育て拠出金」は子育て支援サービスのための費用で、厚生年金加入の事業主が全額負担します。
法定福利費と福利厚生費の違いを明確に理解する
法定福利費と福利厚生費は、従業員の福利に関連する費用ですが、性質と義務において大きな違いがあります。
法定福利費は、健康保険料や厚生年金保険料など、法律で企業に負担が義務付けられている費用です。これらは社会保障制度を支え、従業員の健康や将来の年金などを保障するための重要な支出となります。企業は法律に基づいて必ず負担しなければならず、従業員と折半するものもあれば、企業が全額負担するものもあります。
一方、福利厚生費は、企業が従業員に対して給与・賞与とは別に提供する保障やサービスにかかる費用です。通勤手当、社宅の提供、健康診断費用、社員旅行など、従業員の満足度向上やモチベーション向上を目的としています。企業が自由に設計・提供できる性質のものです。
会計処理においても、法定福利費と福利厚生費は明確に区別され、それぞれ別の勘定科目で記帳します。企業の財務管理においては、この違いを理解し適切に処理することが重要です。
法定福利費の正確な計算方法と最新料率

法定福利費の計算には、社会保険料と労働保険料の正確な理解が必要です。この章では、具体的な計算方法と最新の料率について解説します。
まず社会保険料の計算方法と2024年度の最新料率を確認し、健康保険や厚生年金などの具体的な料率と算出方法を紹介します。続いて労働保険料の計算手順と年度更新における重要ポイントを説明します。
さらに、法定福利費の概算見積もり方法について、給与総額に対する割合や業種別の特性を踏まえた実務的なアプローチを提案します。これらの知識を活用することで、人事労務担当者として適切な法定福利費の管理が可能になります。
社会保険料の計算方法と2025年度最新料率
社会保険料の計算方法を正確に理解するには、最新の保険料率を把握することが重要です。2025年度の健康保険料率は都道府県により異なりますが、平均で約10%となっており、労使折半で企業負担は約5%です。厚生年金保険料率は18.3%で、企業負担分は9.15%となります。
これらの保険料は従業員の標準報酬月額に料率を乗じて計算します。40歳以上の従業員には介護保険料(料率1.6%、労使折半)も発生します。労災保険料は業種により料率が異なり、こちらも全額企業負担です。
保険料率は毎年改定される可能性があるため、日本年金機構や協会けんぽのホームページで最新情報を確認することが大切です。
労働保険料の正確な算出方法と年度更新のポイント
労働保険料の計算では、雇用保険と労災保険料の正確な算出が重要です。雇用保険料は給与総額に保険料率を乗じて計算し、事業主と労働者で負担します。労災保険料は事業主が全額負担し、業種により料率が異なります。
年度更新は毎年6月1日から7月10日の期間に実施する重要な手続きです。前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告・納付します。この際、電子申請の活用が推奨されています。
概算保険料が一定額以上の場合は分割納付も可能です。また、年度途中で事業規模が拡大し、賃金総額が当初見込みより2倍を超えて増加した場合は、増加概算保険料の申告が必要になります。
法定福利費の概算見積もり方法と実際の人件費比率
法定福利費を概算で見積もる場合、給与総額に対する一定の割合を使用するのが一般的です。2024年度の保険料率を合計すると、法定福利費の総額は給与総額の約17%程度となります。この数値は、健康保険料(企業負担分約5%)、厚生年金保険料(企業負担分9.15%)、雇用保険料(企業負担分1.15%)、労災保険料(平均1.7%)、児童手当拠出金(0.36%)などを加算したものです。
実際の人件費に占める法定福利費の比率は、企業の規模や業種により異なりますが、通常は人件費全体の13~17%程度を占めています。
建設業界では「労務費総額×法定保険料率」という計算式が一般的で、労務費の算出が難しい場合は「請負金額×労務費率×保険料率」という方法も活用されています。これにより、適正な法定福利費を見積書に明示し、コンプライアンスを確保することができます。
企業特性別の法定福利費対応と実務ポイント

企業の規模や業種、役職によって法定福利費の取り扱いは異なります。ここからは、企業規模による法定福利費の違いや建設業における法定福利費の内訳明示の義務化、さらに役員・個人事業主特有の法定福利費ルールについて詳しく解説します。
これらの知識は、人事労務担当者として適切な法定福利費の計算・管理を行ううえで重要なポイントです。特に企業の成長や事業拡大にともない法定福利費の構造も変化するため、自社の状況に合わせた正確な把握が求められます。それぞれの特性に応じた対応方法を見ていきましょう。
企業規模による法定福利費の違い
法定福利費は企業規模によって異なり、適切な管理が求められます。一般社団法人日本経済団体連合会の調査によると、法定福利費の全産業平均は月額約88,188円で、企業規模別では500人未満の企業で約75,734円、5,000人以上の大企業では約89,731円となっています。企業規模が大きくなるほど法定福利費も増加する傾向が見られます。
法定福利費の構成を見ると、厚生年金保険が最も大きな割合(約55%)を占め、次いで健康保険・介護保険(約35%)となっています。
人事労務担当者は、自社の規模や業種に応じた正確な保険料率を把握し、適切な法定福利費の計算・管理を行うことが重要です。
建設業における法定福利費の内訳明示と適正な見積書作成法
建設業においては、法定福利費の内訳明示が義務化されています。この背景には、建設労働者の社会保険未加入問題の解決という重要な目的があります。
建設業の見積書作成の際のポイントは主に3つあります。まず、労務費の算出では「人工数×平均日額賃金」の計算方法が一般的です。たとえば、平均日額1万5千円で0.5人工の作業を100か所で行う場合、労務費は「日額1万5千円×50人工=75万円」となります。
次に、その労務費に各社会保険料率を掛けて法定福利費を計算します。厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料、雇用保険料、子ども・子育て拠出金などの事業主負担分のみを計上します。保険料率は地域や時期によって変動するため、見積書作成時点の最新料率を確認することが重要です。
最後に見積書には、労務費と法定福利費を明確に区分して記載します。「法定福利費事業主負担額」として内訳を明示し、消費税計算の際は法定福利費も課税対象になることを忘れないようにしましょう。
役員・個人事業主の特殊な法定福利費ルールと対応策
役員報酬や個人事業主の法定福利費には特殊なルールがあります。役員についても従業員と同様に社会保険料が発生しますが、その処理方法に注意が必要です。役員報酬に対する社会保険料も、従業員と会社で折半するのが基本です。役員負担分は給与から天引きし、会社負担分は法定福利費として計上します。
実際の仕訳では、例えば役員報酬が50万円で、健康保険料の会社負担分が29,075円、厚生年金保険料の会社負担分が45,750円の場合、同額の役員負担分と合わせて「法定福利費」勘定で処理します。注意点として、厚生年金保険料には児童手当拠出金も含まれますが、これは全額が会社負担です。令和2年4月以降は0.36%の料率が適用されています。
また、役員向けの社宅や慶弔見舞金には、一般従業員とは異なる特別なルールがあります。役員の社宅費は、一定の賃貸料相当額を受け取ることで非課税となる仕組みがあります。適切な処理を行うことで、役員・個人事業主の法定福利費も効率的に管理できるでしょう。
法定福利費の実務と最新動向

法定福利費の実務に関わる重要ポイントとして、正確な会計処理の方法や最新の法改正動向について解説します。適切な仕訳処理は企業会計の基本であり、原則的方法と簡便法の違いを理解することが重要です。
また、2024年には社会保険の適用拡大など制度改正が進行したため、2025年以降も中小企業の人事担当者は注意が必要です。
以下では法定福利費の会計処理方法と具体的な仕訳例、そして最新の制度改正とその影響について説明します。企業規模に関わらず、変動する保険料率や法改正に対応するための実務知識を身につけましょう。
法定福利費の正しい会計処理と仕訳例
法定福利費の会計処理では、正確な仕訳が欠かせません。一般的な処理方法は主にふたつあります。
まず原則的な方法では、給与支給時に従業員負担分の社会保険料を「預り金」として処理します。例えば給与40万円から社会保険料4万円を天引きする場合、「(借方)給与 400,000/(貸方)普通預金 360,000、預り金 40,000」と仕訳するのです。月末には会社負担分を「(借方)法定福利費 40,000/(貸方)未払金 40,000」と計上し、実際の支払時には「(借方)預り金 40,000、未払金 40,000/(貸方)普通預金 80,000」として取り崩します。
一方、簡便法では給与支給時に社会保険料を「法定福利費」として計上し、支払時に企業負担分を含めた全額を法定福利費の借方に記入します。
2024年度の法改正と今後の法定福利費動向
社会保険制度は2024年も段階的な制度改正が進みました。注目すべき変更点として、社会保険の適用拡大があります。これまでは、従業員数101人以上の企業が対象でしたが、令和6年(2024年)10月からは従業員51人以上の企業にまで対象範囲が広がりました。
法定福利費の料率については、協会けんぽの健康保険料率が都道府県ごとに見直され、地域間格差の是正が図られています。
人事労務担当者としては、これらの制度変更をタイムリーに把握し、適切な法定福利費の計算と予算計上を行うことが重要です。特に社会保険の新規適用対象となる企業では、人件費の増加に備えた計画的な対応が求められます。
まとめ

法定福利費は事業主が負担すべき社会保険料であり、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、介護保険、子ども・子育て拠出金から構成されます。福利厚生費との違いは法的義務の有無にあり、企業規模や業種によって適用条件が異なります。
計算には最新の料率を用い、給与の一定割合で算出します。会計処理では適切な仕訳が重要で、建設業では見積書への内訳明示が必須です。
近年の法改正や料率変更にも注意が必要であり、適切な管理によって人件費の適正化を図ることができます。個人事業主や役員には特別なルールも存在するため、専門家への相談も検討しましょう。
労務管理システム「ロウムメイト」なら、e-Govを用いた行政機関への電子申請に対応し、各種社会保険帳票の作成や提出業務の効率化をすることで、社会保険の手続きの工数を削減できます。専任サポートがつくので安心して導入でき、ほかシステムとの連携もスムーズです。また、月額定額制で必要な機能だけを選べるため、コスト効率も優れています。
煩雑な法定福利費管理から解放されたい方は、ぜひロウムメイトをご検討ください。