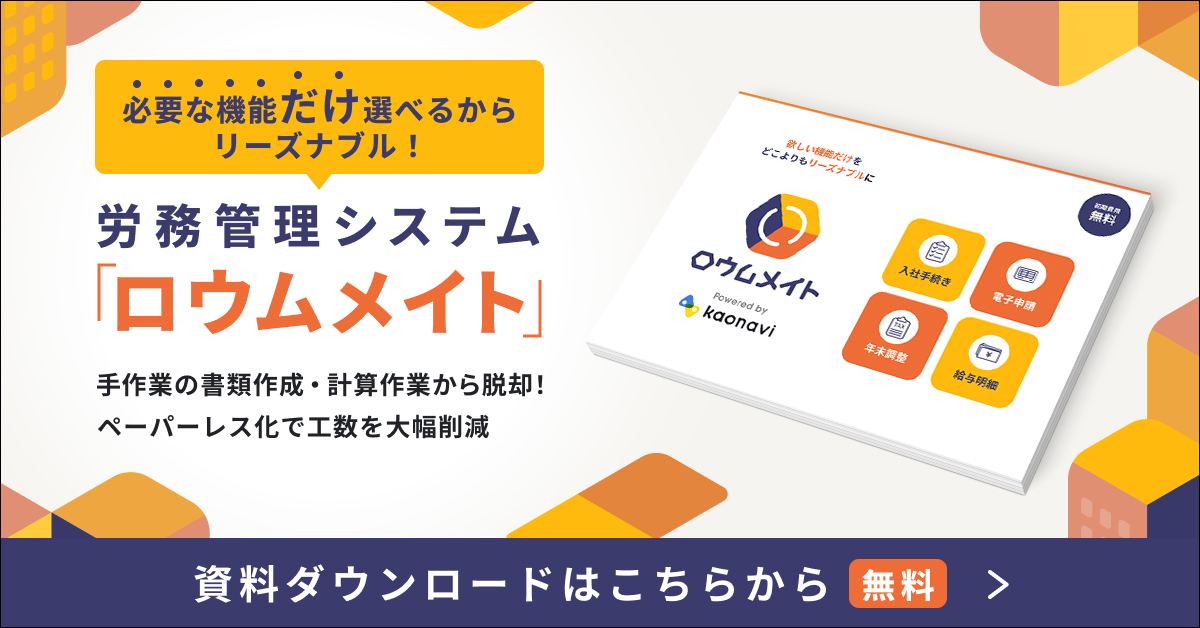政府の副業・兼業促進の流れを受け、多くの企業が副業規定の見直しを迫られています。しかし、「どんな副業を許可すべきか」「どのようなリスクに備えるべきか」と頭を悩ませる人事・労務担当者も多いのではないでしょうか。
実は、副業にはさまざまな種類があり、それぞれ特徴やリスクが異なります。適切な副業規定を作成するには、これらの違いを理解することが不可欠です。
本記事では、人事労務担当者の方々に向けて、副業の種類と特徴を体系的に解説し、実務に役立つ規定作成のポイントをご紹介します。
目次
副業とは?最新の副業事情と企業が規定を整備すべき理由
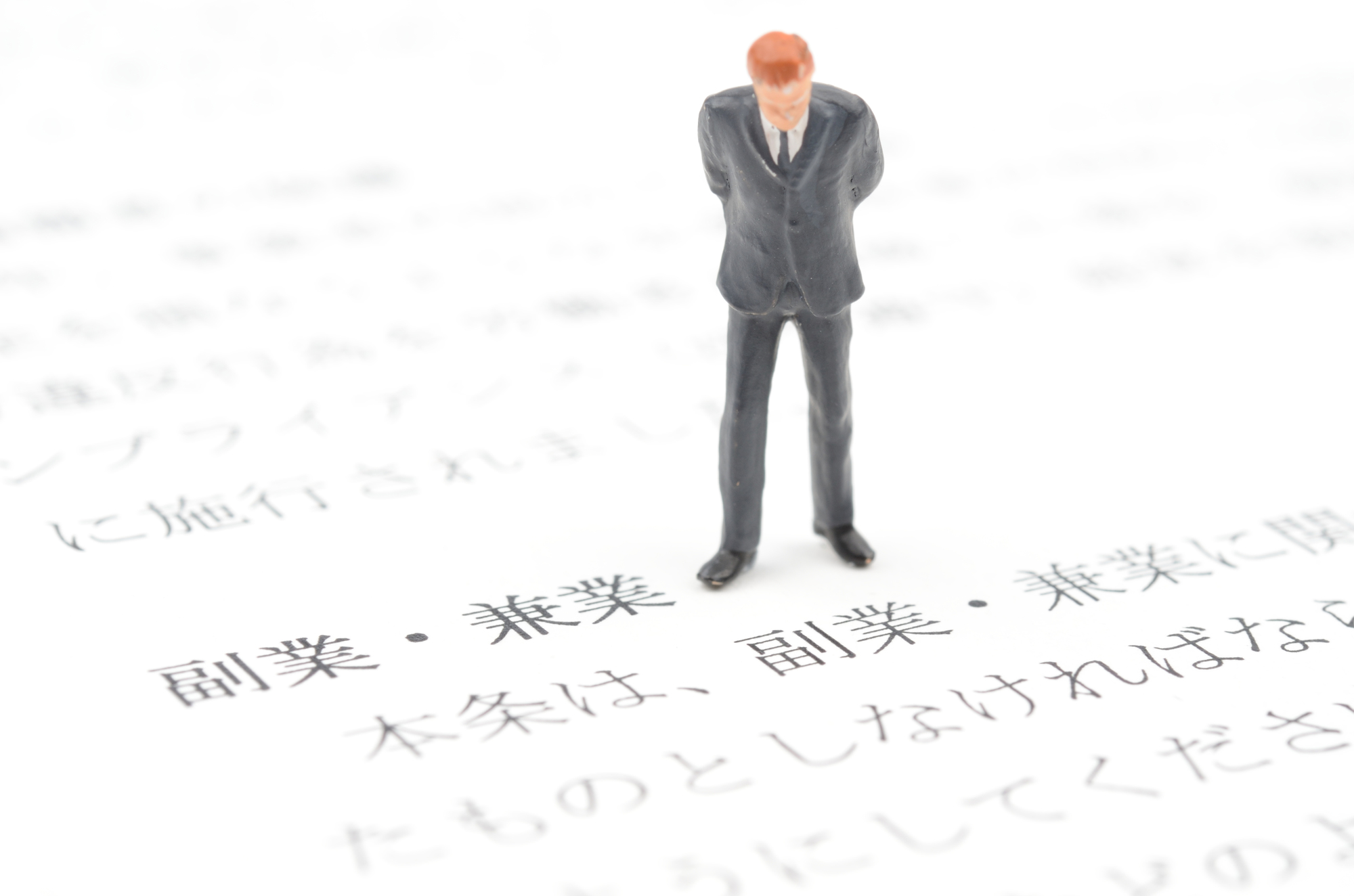
副業を取り巻く最新事情と企業が規定整備に取り組むべき理由について解説していきます。副業は近年、スキル活用型、労働提供型、投資・資産活用型、オンライン型など多様な種類が登場しており、それぞれに特徴があります。
企業が副業規定を整備する際には、これらの副業の種類や特性を理解し、自社の業種・職種に適した規定を作成することが重要です。労働時間管理や情報セキュリティなどの懸念点を解消しつつ、従業員のスキルアップや人材確保などのメリットを最大化できる規定づくりが求められています。
以下では、副業解禁の現状から規定作成の基本ステップまで段階的に説明します。
副業解禁の現状と企業に求められる対応
近年、副業を希望する労働者は増加傾向にあり、多様な働き方へのニーズが高まっています。こうした社会変化を受け、企業側でも副業を容認する動きが広がっています。
企業が副業を解禁する主な理由は「人材育成・スキル向上」と「優秀な人材の流出防止」です。自社では提供できない経験を通じて従業員の能力向上やアイデア創出を促し、イノベーションと働き方改革を推進することで生産性向上につながると考えられています。
一方で、副業を認めない企業の懸念点としては「労働時間通算の困難さ」と「長時間労働の助長」が挙げられます。企業は時間管理の煩雑化や割増賃金算定の難しさを心配しているのです。
副業規定を整備する際には、合理的な理由なく副業を制限しないこと、労働時間管理や健康管理の方法、情報漏えい防止策などを明確にすることが求められます。適切な規定作りは企業と労働者双方にとって重要です。
企業が副業を許可するメリットとリスク
企業が副業を許可する際のメリットは、主に4つに分類できます。第一に「社員のスキルアップ」です。副業を通じて自社では経験できない業務や視点に触れることで、新たな知識やノウハウを獲得し、本業にも活かせます。第二に「優秀な人材の確保・定着」です。副業を希望する労働者が増加している現在、副業を認めることで選ばれる企業となり、人材流出も防止できます。
第三に「社員の自主性向上」が挙げられます。副業は自ら考え行動する機会を提供するため、主体性やチャレンジ精神を育み、本業での意欲向上にもつながります。第四に「人材の多様化」です。副業経験を通じて様々な価値観や業界知識を持つ人材が増えることで、社内の多様性が高まり、イノベーション創出の土壌となります。
一方で、副業解禁にはリスクもあります。最も懸念されるのは「情報漏えいのリスク」です。企業機密が副業先に流出する危険があるため、競業避止義務や秘密保持誓約書の締結が必要でしょう。また「長時間労働によるパフォーマンス低下」も問題となり、従業員の健康管理が必要です。
副業解禁前には、申告義務などのルール作りや労働時間の通算管理、社員の健康状態の定期確認など、適切な制度設計が不可欠です。リスクを最小化しつつメリットを最大化する規定づくりが、企業と従業員双方にとって重要となります。
| 企業側のメリット | 企業側のリスク |
| 社員のスキルアップ | 情報漏えいのリスク |
| 優秀な人材の確保・定着 | 長時間労働によるパフォーマンス低下 |
| 社員の自主性向上 | 本業満足度の低下 |
| 人材の多様化 | 従業員の離職リスク |
副業規定作成の基本ステップと押さえるべきポイント
副業規定の作成においては、明確なステップと重要ポイントを押さえることが成功の鍵です。まず最初に、厚生労働省の「副業・兼業ガイドライン」を参照し、基本方針を定めましょう。副業規定には、副業を認める範囲や対象者、禁止する業務内容を明確に規定することが重要です。
特に注意すべきは、全面禁止ではなく「労務提供上の支障がある場合」「秘密漏えいのリスクがある場合」「競業により自社の利益が害される場合」「会社の信用を損なう場合」などの合理的な理由がある場合に限って制限する構成にすることです。
また、副業の申請・報告手続きも具体的に定め、副業先の情報、勤務形態、就業時間などを記載した許可申請書の提出を求める仕組みを構築しましょう。労働時間の適切な管理のため、副業での労働時間を自己申告させ、過重労働を防止する体制も必要です。特に月80時間を超えないように設定することが、健康管理の観点から推奨されています。
3つのカテゴリーで理解する主な副業の種類と特徴

副業にはさまざまな種類がありますが、その特徴や働き方を理解することで、企業の副業規定作成に役立てることができます。ここでは副業を「スキル活用型」「労働提供型」「投資・資産活用型」の3つのカテゴリーに分類し、それぞれの特徴や企業が注意すべきポイントを解説します。
各カテゴリーは働き方や収入獲得方法が異なるため、副業規定を作成する際には、これらの違いを踏まえた適切なルール設計が必要です。企業の実情や従業員のニーズに合わせて、バランスの取れた副業制度を構築するための基礎知識をご紹介します。
スキル活用型副業の種類と特徴
スキル活用型副業は、自分の持つ専門的なスキルや知識を活かして収入を得る働き方です。代表的なものとしては、Webライター、デザイナー、プログラマーなどが挙げられます。これらの副業の最大の魅力は、本業で培ったスキルを直接活用できる点と、場所や時間に縛られず柔軟に働ける点です。
例えばWebライターは、文章力を活かしてWebサイトの記事作成を行います。報酬体系は文字単価制(1文字○円)や記事単価制(1記事○円)が一般的で、経験を積むことで単価アップが見込めます。デザイナーやプログラマーもクラウドソーシングサイトを通じて案件を受注するなどして、自分のペースで作業できます。
また、オンライン講師やコンサルタントなども人気の高いスキル活用型副業です。特に近年はオンライン教育の需要が高まり、専門知識を持つ人にとって良い収入源となっています。
スキル活用型副業は初期投資が少なく済む点も魅力ですが、継続的な学習や自己啓発が必要であり、成功するには競争が激しい市場でいかに差別化するかが必要です。
| 副業の種類 | 特徴 | 報酬形態 |
| Webライター | 時間や場所を選ばず、文章力を活かせる | 文字単価制・記事単価制 |
| デザイナー | クリエイティブスキルを活用、ポートフォリオ構築にも役立つ | 案件単位の報酬 |
| プログラマー | 技術力を活かし、高単価案件も狙える | 時給制・案件単位 |
| オンライン講師 | 専門知識を教えることで収入を得られる | 時給制・コース単位 |
労働提供型副業の種類と特徴
労働提供型副業は、決められた時間に働くことで安定した収入を得られる副業の形態です。配達員、コンビニスタッフ、塾講師などが代表的な例として挙げられます。
この種類の副業の最大の特徴は、働いた時間に応じて確実に報酬が得られる点です。例えばコンビニでの早朝や深夜勤務では、通常より高い報酬が期待できます。
一方で、この形態の副業は時間的拘束があるため、本業との両立には体力管理や時間調整が重要です。企業が副業規定を作成する際は、社員の健康維持の観点から週あたりの労働時間上限を設けることや、本業に支障が出ないような業種制限を検討すべきでしょう。
労働提供型副業は時間に余裕があり、継続的に安定収入を得たい方に適しています。ただし、長期的なキャリア形成やスキルアップの観点では限界があることも考慮する必要があります。
投資・資産活用型副業の種類と特徴
投資・資産活用型副業は、時間をかけて資産形成を行う副業カテゴリーです。株式投資、不動産投資、FXなどが代表的で、金融リテラシーを高めながら収入を得られる点が魅力です。
株式投資は初期資金の少なさから始めやすく、長期投資により資産増加が期待できます。投資型クラウドファンディングも注目されており、融資型、ファンド型、株式投資型の3種類に分類されます。融資型は1万円程度から始められ、安定した利回りが特徴です。
不動産投資は一般的に副業禁止の企業でも認められやすい傾向があります。アパートやマンションだけでなく、空き部屋を活用した民泊、遊休地を利用したコインパーキングなど、所有資産の種類によってさまざまな方法があります。
会社員が投資型副業を行う際の注意点としては、確定申告の必要性と投資リスクの理解が重要です。特に知識不足による損失を避けるため、段階的に始めることをおすすめします。
業種・職種別に見る適切な副業とその規定例

業種や職種によって、適した副業の種類や必要な規定ポイントは大きく異なります。ここでは、オフィスワーカー、専門職、管理職・経営層の3つの職種別に、それぞれの特性に合わせた副業の特徴と規定作成のポイントを解説します。
各職種の特性を踏まえた具体的な規定例も紹介しながら、企業の人事労務担当者が押さえるべき重要事項を職種ごとに整理します。副業制度を設計する際の参考としてご活用ください。
オフィスワーカー向け副業の特徴と規定ポイント
オフィスワーカー向け副業では、本業との両立を重視した規定作りが不可欠です。最も重要なのは「労働時間管理」で、月30時間程度の上限設定や、副業と本業の時間外労働を合わせて月80時間以内にするなどの明確な条件を設定しましょう。
また「禁止業務の明確化」も必須です。顧客情報や社内リソースを利用する副業、会社の評判を損なうおそれのある業務は制限すべきでしょう。
効果的な管理方法として「誓約書の徴収」があります。本業優先の姿勢や情報管理の徹底、競業避止などを確約させることで、トラブルを未然に防げます。
専門職に適した副業の特徴と規定ポイント
専門職に従事する人材は、その専門知識やスキルを活かした副業が理想的です。エンジニアやデザイナー、医療従事者などの専門職は、本業で培った高度な技術を副業でも発揮できます。これらの職種に適した副業として、専門知識を活かしたコンサルティングやフリーランス業務、オンライン講師などが挙げられます。
企業が専門職の副業規定を作成する際には、3つのポイントを押さえることが重要です。まず「スキル維持・向上につながる活動の推奨」です。本業のスキル向上に寄与する副業は積極的に認めるべきでしょう。
次に「機密情報管理の徹底」が必須です。専門職は業務上重要な情報に触れる機会が多いため、情報漏えい防止策を明確にする必要があります。
最後に「労働時間の適切な管理」です。専門職は仕事に没頭しがちなため、健康管理の観点から総労働時間に上限を設けることが大切です。
管理職・経営層向け副業の特徴と規定ポイント
管理職や経営層の副業規定では、一般社員よりも厳格な基準が必要です。彼らは企業の中核として重要な機密情報や経営戦略に接する機会が多いため、情報漏えいリスクへの配慮が特に重要となります。
具体的な規定ポイントとしては、まず「情報管理の徹底」が挙げられます。企業秘密の守秘義務違反は損害賠償責任に発展する可能性があるため、特に注意が必要です。
次に「競業避止義務の明確化」です。管理職が同業他社で副業を行えば、自社のノウハウが流出するリスクがあります。また「労働時間の自己申告制度」の導入も重要で、過労防止のために総労働時間を把握する仕組みが必要です。
さらに、副業がしやすい社内風土づくりも欠かせません。制度があっても管理職が理解を示さないと、部下は申請しづらくなります。副業に対する前向きな理解を促す社内対話の場を設けることが、円滑な制度運用の鍵となるでしょう。
副業規定作成時の法的注意点と実務対応のポイント
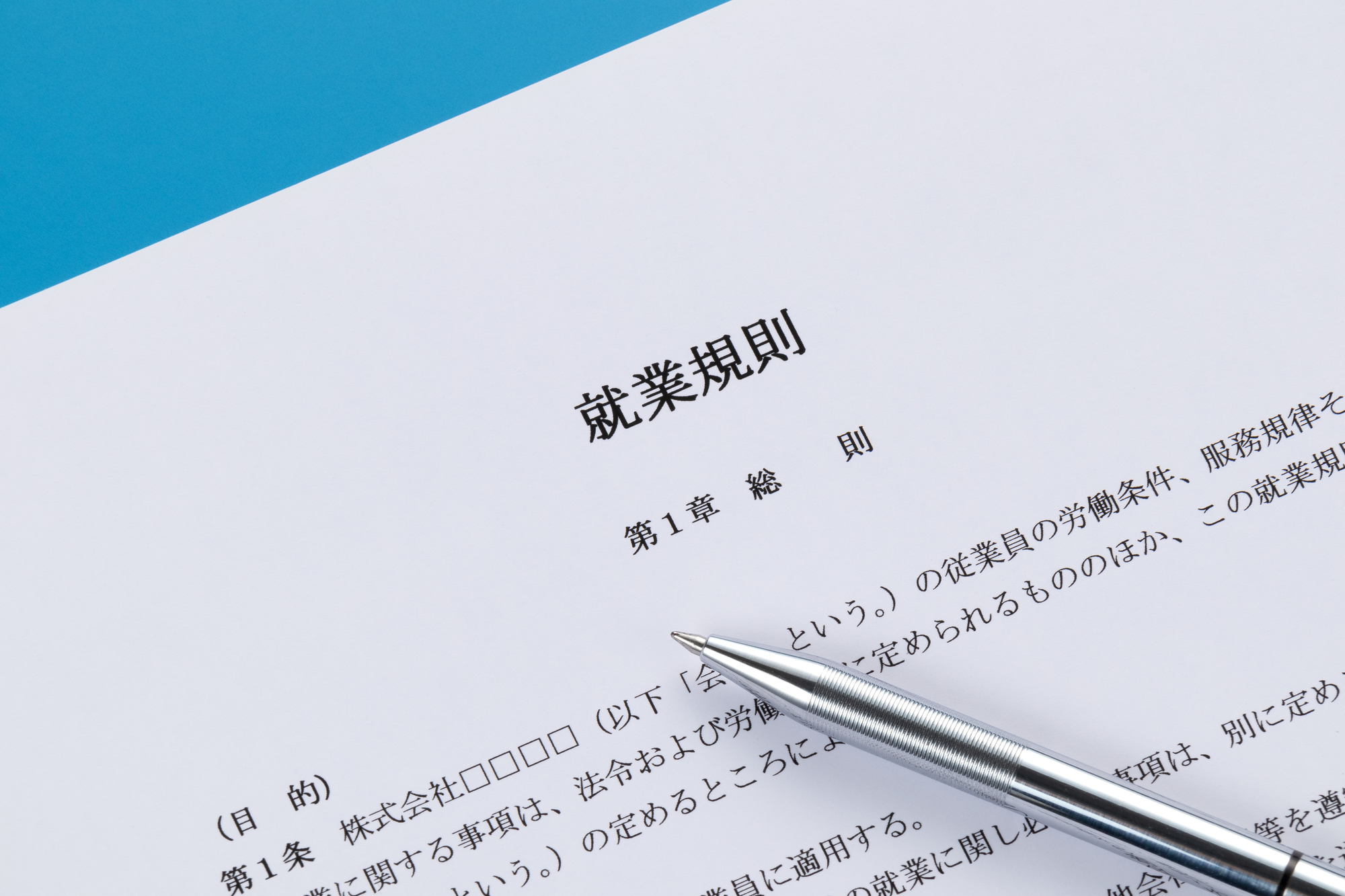
副業に関する法的な側面を理解することは、適切な副業規定の作成において非常に重要です。労働基準法の労働時間通算規定や上限規制、適用除外となる副業の種類など、企業が把握すべき法的ポイントは多岐にわたります。また、副業申請・報告制度の適切な設計は、企業と従業員双方の権利を守るために不可欠です。
ここでは、副業規定を作成する際に企業が留意すべき法的な注意点と、実務レベルでの対応ポイントについて解説します。特に副業の種類によって異なる法律の適用や、効果的な申請制度の設計方法に焦点を当て、実務担当者が活用できる具体的なガイドラインを提供します。
副業に関連する法律と順守すべき事項
副業に関する法律面では、企業が押さえるべき重要なポイントがいくつかあります。まず、労働基準法38条では複数の事業場で働く場合の労働時間は通算すると規定されています。これは従業員の健康を守るための重要な規定です。
ただし、すべての副業形態に適用されるわけではありません。フリーランスや起業家として独立した形態の副業では、労働基準法の適用外となります。また、農林水産業や管理職、高度プロフェッショナル制度該当者なども労働時間規制の適用外です。
時間外・休日労働には上限規制があり、原則として月45時間・年360時間が上限となっています。この上限を超えると罰則の対象となるため注意が必要です。
企業は副業制度導入に際して、就業規則の整備、残業制度の見直し、源泉徴収・社会保険制度の整備、機密情報漏えいリスクの検討などを行うことが重要です。副業規定設計の際はこれらの法的事項を踏まえた制度設計が求められます。
| 法律・規定 | 内容 | 留意点 |
| 労働基準法38条 | 複数事業場の労働時間通算 | 健康確保のための規定 |
| 労働時間上限規制 | 月45時間・年360時間 | 超過すると罰則対象 |
| 適用外の副業形態 | フリーランス、起業家など | 労働基準法適用外 |
| 企業側の対応 | 就業規則整備、源泉徴収など | 法令順守と従業員保護 |
副業の申請・報告制度の設計方法
副業申請・報告制度の設計では、まず「許可制」から始めるのが実践的です。副業禁止から移行する企業では、社員が副業内容を申請し、会社が審査する仕組みを整備しましょう。申請時には副業先の事業内容、業務内容、労働時間などの情報を収集します。
特に副業形態の検討は重要です。雇用契約での副業は労働時間管理が煩雑になるため、業務委託などの非雇用形態に限定する企業も多くあります。社員の成長やモチベーション向上が目的なら、自律的な働き方ができる業務委託形態が適しているでしょう。
就業規則の改定には厚労省のモデル就業規則が参考になりますが、そのまま適用せず自社の実態に合わせることが大切です。申請書様式の整備や社内通知も忘れずに行いましょう。
まとめ

副業解禁の流れが加速する中、企業には適切な規定整備が求められています。スキル活用型、労働提供型、投資型など多様な副業形態ごとに適した規定を設けることで、社員のスキルアップと企業の発展を両立できます。
しかし、労働時間管理や情報漏えい防止など、課題も少なくありません。こうした課題を解決する時間を作るためには、業務の効率化が必要です。労務管理システム「ロウムメイト」なら、従業員管理や年末調整業務がペーパーレスで完結できるほか、説明書いらずのわかりやすい操作性で従業員と企業の双方の業務効率化をサポートします。副業時代の新しい労務管理を始めてみませんか。