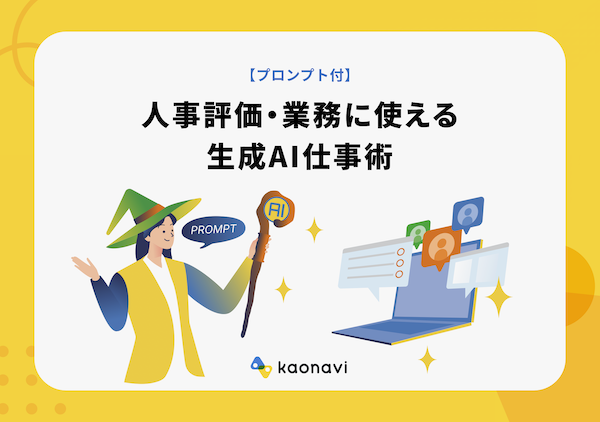部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
人事評価エラー(バイアス)とは、偏った思考により不公平な人事評価を行ってしまうこと。人事評価エラーは企業全体に悪影響を及ぼすため、早期の是正が必要です。
目次
悩む時間を減らす実務プロンプト集
1.人事評価エラーとは?
人事評価エラーとは、評価者の認識の歪みや偏りに影響され、適切な評価が行えないことです。評価バイアスと呼ばれることもあります。人事評価の原則である事実に基づいた公正な評価が実現できない場合、従業員のモチベーション低下による生産性低下や離職率上昇が懸念されます。

人事評価制度とは? 目的や仕組み、種類や手法、導入手順を解説
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...
【評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●評価シートが自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
2.7種類の人事評価エラー
人事評価エラーは、7種類あります。それぞれどのようなエラーなのか、詳しく解説しましょう。
- ハロー効果
- 中心化傾向・極端化傾向
- 寛大化傾向・厳格化傾向
- 逆算化傾向
- 期末効果
- 対比誤差
- 論理的誤謬
①ハロー効果
ハロー効果とは、特定の社員にひとつでも突出した良いポイントが見られると、その社員のすべてが良いものに見えてしまうエラーです。ハロー効果の「ハロー」は「halo」(光輪、後光)が語源で、ひとつの物事から認識を広げてしまい誤った評価をすることを指します。
一例として、
- 一流企業の出身だから仕事ができるだろう
- 過去に大変なミスをしているから、また失敗を繰り返すだろう
などがあります。経歴や過去の出来事などから影響を受けすぎると、実態とは異なる評価につながるのです。
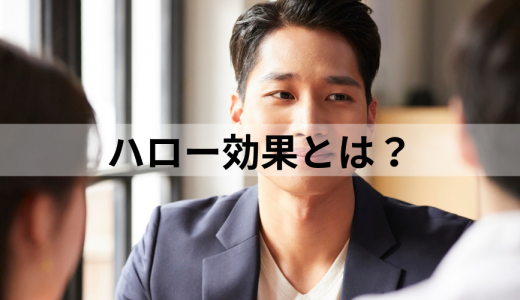
ハロー効果とは?【意味を図解でわかりやすく】具体例と対策
人事評価の実施において気になるのは、評価者による評価エラーでしょう。こうした評価エラーの中に、ハロー効果と呼ばれるものがあるのですが、一体どのようなものなのでしょう。
ハロー効果の種類や実例
ハロー...
②中心化傾向・極端化傾向
中心化傾向とは、評価基準が中心に寄りすぎてしまい、当たり障りのない評価になってしまうこと。評価者が保身するあまりに生まれる評価エラーです。
評価によって優劣をつけると、部下が反発をするなどと考えてしまい、あまり差が出ないように評価をつけていくことがあります。評価を無難に済ませるといった心理を捨てて、客観的でシンプルに判断する必要があるでしょう。
極端化傾向とは、評価が最高または最低に偏ること。評価をしないといけないという意思が強い評価者に生まれる評価エラーです。評価基準を策定し、それに則って評価をする必要があります。
③寛大化傾向・厳格化傾向
寛大化傾向とは、全体的に評価が甘くなってしまうエラーのこと。
評価者が、
- 「部下によく思われたい」「部下に頼りにされたい」などの気持ちが強い
- 部下の仕事を適切に把握できていない
といった場合に起こりやすくなります。
厳格化傾向は反対に、全体的に評価が厳しくなるエラーです。評価者自身の能力が高いと、自身の能力を基準とした評価になって厳しくなることがあります。「自分が若いころはこれくらいできた」という認識で評価すると、客観性を保てなくなるのです。
④逆算化傾向
逆参加傾向とは、先に評価を総合したときの結果を想定し、それに辻褄が合うように各評価を決めていくエラーのこと。例として、次のようなケースがあります。
- 昇給額を先に決定し、評価内容が見合うように帳尻を合わせる
- あらかじめ決められた評価基準に従うのではなく、先に平均点を決めて評価を調整する
こうしたケースは、人事評価制度が機能していないときに起こります。
⑤期末効果
期末効果とは、本来評価は期間全体をとおして判断すべきところ、期間後半の成功や失敗が評価全体に影響をおよぼすこと。
もし、期間全体で見れば同じ成果があったとしても、成果が発生した時期が期間の前後半どちらかによって評価が変わってしまう可能性もあるのです。こうした評価が続くと、評価期間の後半だけしっかり成果をあげようとする社員が出てくるおそれもあります。
⑥対比誤差
対比誤差とは、あらかじめ決められている評価基準にもとづかず、評価者が自分との対比によって評価を行ってしまうエラーのこと。対比誤差が起きる要因として、主に次の2つが考えられます。
- 評価者が評価基準を把握できていない
- 評価者が過剰な自信やコンプレックスを抱いている
たとえば、リーダーシップ能力に長けた上司が、部下のリーダーシップ能力を実態よりも低く評価してしまうケースです。
⑦論理的誤謬
論理的誤謬(ろんりてきごびゅう)とは、事実ではなく評価者の推論により評価してしまうエラーのこと。
たとえば、リーダーシップに優れている社員を評価する際、評価者の論理として「リーダーシップがあればコミュニケーション能力も高いはずだ」と考え、コミュニケーション能力を高く評価してしまうなどです。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
3.人事評価エラーが引き起こす問題
人事評価エラーが常態化すると、評価された社員だけでなく、企業全体にも悪影響をおよぼします。人事評価エラーの問題を解決せずにいると、不当な利益を得る人や不利益を被る人が出てしまい、公平かつ正確であるべき人事評価の制度を運用できなくなります。
部署内の関係性の悪化
上司にバイアスがかかって適切に評価できないと、部下は「上司からの自分への評価は本当に正確なのだろうか」と不信感を抱きます。
部下が上司に対して不信感をもつと、両者の関係性が悪化しかねません。仕事に対するモチベーションも低下し、より関係性が悪くなると上司の指示を無視するといった行動を取ることもあります。
離職率の増加
社員への評価に公平性を欠いてしまうと、その社員は評価に納得できなくなります。評価を不公平に感じたり評価者を信頼できなくなったりすると、仕事へのモチベーションが低下し、離職につながるおそれもあります。
人事評価エラーは、評価に不公平を感じた社員が「自分はこの会社に合わない」と思わせる場合もあるので、対処すべき問題だといえるでしょう。
訴訟問題に発展
評価によっては、特定の社員に対して降格や降給といった判断をする場合もあります。社員にとっては不利益な変更なので合理的な判断があるべき。よってそれに対し有効・無効を争って裁判に発展することもあるのです。
また人事評価が明らかに偏っていて運用に問題があるとされた場合、社員への降給・降格が無効となる可能性もあります。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
4.人事評価エラー発生の原因
評価エラーはなぜ起こるのでしょうか? 対策を知る前にまずは原因を確認しておきましょう。
評価制度の理解不足
評価をする上司が、評価制度や評価基準を理解していないと、人事評価エラーが起きる可能性が高まります。
部下に対する好き嫌いやそのときの気分など、評価者の感情によって評価することを是正できなくなるのです。こうした状態が続くと、寛大化・厳格化傾向や論理的誤謬など、評価者自身を基準に置いた評価エラーを引き起こします。
価値観の相違
評価をする人物と評価をされる人物の双方が同じ認識をもっているにもかかわらず、ひとつの事実に対する評価が異なるケース、それが「価値観の相違」です。
両者の認識が一致している場合に陥りやすく、人事評価エラーが発生する原因のひとつになります。評価者は、機会をつくって相互理解をさらに深めるための行動が必要です。
基準やルールに反した評価の実施
評価者の評価基準が合理的でなく、企業で作られている評価基準に則っていない評価を実施していると、人事評価エラーが起きやすくなります。
また、評価の手続きが企業で定められているにもかかわらず、それに従わない評価を実施する場合も当てはまります。現場を知らない評価者が一次評価を自分の評価基準でもって修正するようなことは、適切な評価とはいえないでしょう。
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは? 効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント⇒こちらから
5.人事評価評価エラーを防ぐ方法
人事評価エラーは無意識に起こるため、誰にでも陥る可能性があります。人事評価エラーを防止するには、意識的に注意しなければ誰でも人事評価エラーを起こす、という認識をもつことが大切です。
無意識に行ってしまうことをそのままにせず、顕在意識に引き上げて意識化していくことが重要だといえるでしょう。ここでは、具体的な防止策として、研修や面談の方法などについて紹介します。
事実にもとづいた評価
評価をする際は、何よりも具体的な事実にもとづいた評価が重要です。結果はもちろん、部下の日頃の行動や、結果に至るプロセスなども含めて評価に反映します。
行動事実をしっかり記録することで、評価が具体性を帯びて部下も納得する内容になります。また、評価者のイメージや固定観念にとらわれにくくなります。
評価基準を明確に設定
評価項目が曖昧になっていると、評価者の裁量によって決まる部分が大きくなってしまい、人事評価エラーの原因となります。評価基準を明確に設定すると、心理的なイメージに惑わされない評価ができるようになります。評価項目は、次の方法で明確にしましょう。
- 評価のルールを決める
- 数値化できない目標も評価基準を定める
- 評価項目を段階ごとに設定する

評価基準とは?【作り方をわかりやすく】目的、項目の具体例
評価基準とは評価するための水準であり、公平かつ客観的な評価を行ううえで重要な指標です。人事評価への不満は優秀人材の離職の原因ともなり、最悪のケースでは業績不調を招く恐れもあります。
今回は、評価基準と...
1on1など定期的な面談の実施
評価される社員のモチベーションを維持するためにも、定期的に面談や目標設定の見直しなどをすることが大切です。
たとえば、目標達成が明らかに難しい状況にもかかわらずそのままにしていると、社員が進路を見失ってモチベーションの低下につながります。
目標設定を柔軟に修正する場を設け、社員とのコミュニケーションを図りましょう。このとき、評価の根拠を示せるよう事実にもとづいた情報をメモに残しておくとよいでしょう。
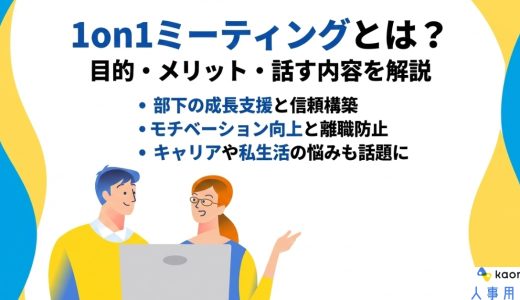
1on1とは? 目的や導入効果、面談との違いとやり方を簡単に解説
部下を育成し、目標を達成させる「1on1」とは?
効果的に行うための質問項目集付き解説資料をプレゼント
⇒ 無料ダウンロードはこちらから
ヤフーが導入したことでも注目され、現在では多くの企業が導入す...
評価者研修の実施
人事評価エラーを防止するには、評価者自身も訓練を受ける必要があります。評価者が人事評価制度の内容や基準を改めて理解できるよう、トレーニングを実施します。
また、このなかで人事評価エラーが起きやすい事例も伝えると、よくあるエラーや誤差を事前に把握できます。評価者が訓練を受けると、社員が受ける評価が是正されて不満が軽減されることが見込まれるのです。

評価者研修とは?【必要な理由】目的、具体例、実施ポイント
評価者研修とは、管理職や人事部の担当者など、人事評価の評価者を対象とした研修です。人事評価の仕組みや評価方法、評価に必要な知識・スキルを体系的かつ実践的に学べます。
評価は人材戦略の重要な要素であり、...
客観的視点を意識した評価
評価者は「部下を指導し育成している」という意識をつねにもつ必要があります。そうすることで客観的視点をもって部下へ評価できるようになっていくでしょう。評価者が客観的視点を意識するためのポイントとして、次のようなものがあげられます。
- 結果に偏りがないか
- 人事評価エラーに該当するような思考プロセスになっていないか
このようなポイントに気をつけて、評価に取り組みましょう。
【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる

⇒人事評価システム「カオナビ」の詳細を見る(https://www.kaonavi.jp/)