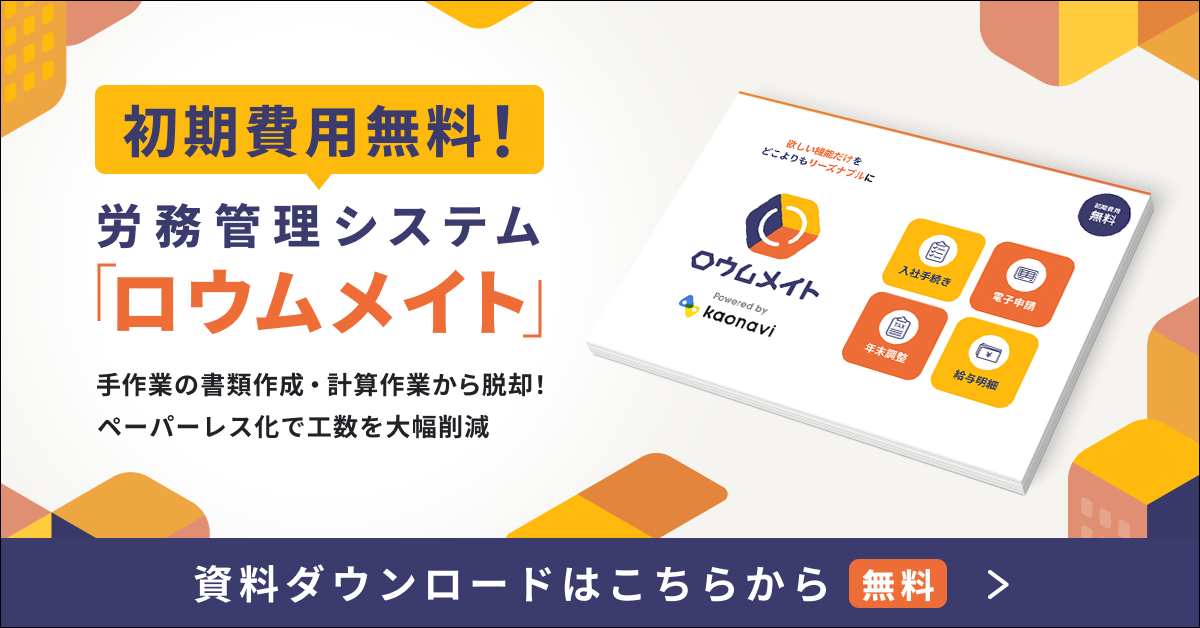社会人になると避けては通れないものに税金の支払いがあります。中でも住民税は、その支払いのタイミングが分かりにくいものです。社会人1年目と2年目では、住民税の扱いが大きく異なることをご存知でしょうか。
新卒で就職した場合、いつから住民税を支払う必要があるのか、また、その金額はどのように決まるのでしょうか。本記事では、住民税の基本的な仕組みから、社会人1年目と2年目の違いまで、詳しく解説します。
目次
住民税とは?基本的な仕組みと計算方法

住民税は、私たちの生活に密接に関わる重要な税金です。その仕組みや計算方法を理解することで、税金の納付時期や金額を把握できます。
ここでは、住民税の定義と課税対象、具体的な計算方法と税率、そして所得税との違いについて詳しく解説します。
住民税の定義と課税対象
住民税は、地方自治体が提供する行政サービスの財源となる重要な税金です。具体的には、都道府県民税と市町村民税を合わせたものを指します。この税金は、前年の1月1日から12月31日までの所得に基づいて課税されます。住民税の課税対象には、給与所得、事業所得、不動産所得などのさまざまな所得が含まれます。
住民税には、所得に応じて課税される「所得割」と、一律に課税される「均等割」があります。所得割は前年の所得金額に基づいて計算され、均等割は地域によって金額が異なりますが、一般的に数千円程度です。
また、住民税には特別徴収と普通徴収というふたつの納付方法があります。多くの会社員は特別徴収で、毎月の給与から自動的に引かれます。一方、個人事業主などは普通徴収で、自ら納付する必要があります。
住民税の計算方法と税率
住民税の計算方法は、所得割と均等割の合計で算出されます。所得割の税率は一律10%で、道府県民税・都民税4%と市区町村民税6%に分かれています。具体的な計算手順は以下のとおりです。
まず、前年の所得から所得控除を引いて課税所得金額を求めます。次に、この金額に10%の税率をかけて所得割額を算出します。最後に、均等割額を加算して、住民税の総額が決まります。
例えば、課税所得金額が300万円の場合、所得割は30万円(300万円×10%)となります。これに均等割5,000円を加えると、住民税の総額は305,000円です。
なお、2024年6月以降は、物価高騰対策として定額減税が適用されます。住民税は1万円、所得税は3万円が減税されるため、実質的な負担が軽減されます。
住民税と所得税の違い
住民税と所得税は、ともに個人の所得に課される税金ですが、いくつかの重要な違いがあります。
まず、課税主体が異なります。住民税は地方税で、都道府県と市町村が課税します。一方、所得税は国税で、国が課税します。次に、課税対象となる所得の期間が違います。住民税は前年の所得に対して課税されますが、所得税はその年の所得に対して課税されます。また、住民税には均等割があり、所得の多少に関わらず一定額が課税されます。所得税にはこの均等割がありません。
さらに、納税方法や税率、所得控除の内容なども異なります。例えば、寄附金控除は住民税では税額控除、所得税では所得控除となります。
| 項目 | 住民税 | 所得税 |
| 課税主体 | 地方自治体 | 国 |
| 課税対象 | 前年の所得 | その年の所得 |
| 均等割 | あり | なし |
| 寄附金控除 | 税額控除 | 所得控除 |
住民税の支払いが始まるタイミング

住民税の支払いが始まるタイミングは、基本的に社会人2年目です。これは、住民税が前年の所得に基づいて課税されるためです。また、年度途中の就職や転職時には、住民税の扱いが変わることもあります。
以下では、社会人1年目と2年目の住民税の違い、そして特殊なケースについて解説します。
社会人1年目の住民税
社会人1年目は、通常、住民税の納付義務はありません。なぜなら、住民税は前年の所得に基づいて課税されるためです。つまり、学生時代の所得が基準に達していなければ、1年目は納税の必要がないのです。 ただし、アルバイトなどで一定以上の収入があった場合は例外です。この場合、1年目から住民税が課税されることがあります。
社会人1年目の方の住民税納付は、通常、翌年6月から始まります。納付方法は、会社員なら給与天引き(特別徴収)、個人事業主なら自分で納付(普通徴収)です。
社会人2年目からの住民税納付
社会人2年目になると、住民税の納付が始まります。通常、6月から翌年5月までの12か月間にわたって納付することになります。これは、前年の1月から12月までの所得に基づいて課税されるためです。
会社員の場合、多くは給与から天引きされる「特別徴収」方式が適用されます。毎月の給与から少しずつ納付できるため、大きな負担感なく納税できるメリットがあります。
一方、個人事業主は自身で納付する「普通徴収」方式となります。 住民税の具体的な金額は、前年の所得によって変わります。例えば、年収300万円の場合、年間約15万円程度の住民税が課されることがあります。これは毎月およそ1万2千円ほどの負担です。
年度途中の就職や転職時の住民税
年度途中で就職や転職をした場合、住民税の扱いが変わることがあります。転職先が決まっている場合、「給与所得者異動届出書」を提出すると、新しい会社での給与からの天引き(特別徴収)が継続されます。ただし、手続きがスムーズにいかない場合は、自身で納付する普通徴収に切り替わることもあります。
退職時期によっても対応が異なります。1月1日から5月31日までに退職した場合、その年度分の残りの住民税は最後の給与から一括徴収されることが多いです。
一方、6月1日以降の退職では、退職月までは給与から天引きされ、残りは普通徴収に切り替わります。 転職と同時に引っ越しをした場合は、1月1日時点での住所地の自治体に納付します。
住民税の納付方法と注意点

住民税の納付には、いくつかの方法や注意すべき点があります。ここでは、住民税の主な納付方法である特別徴収と普通徴収の違い、減免制度や特例、そして納付が遅れた場合の対処法について解説します。
これらの知識を身につけることで、スムーズな納税と不要なトラブルの回避につながります。
特別徴収と普通徴収の違い
住民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収は、主に給与所得者に適用される方法で、毎月の給与から住民税が天引きされます。一方、普通徴収は、自営業者や特定の条件に当てはまる給与所得者が対象で、年4回に分けて自身で納付します。
特別徴収のメリットは、毎月少額ずつ納付できるため、負担感が軽減されることです。また、会社が代わりに納付するため、納税忘れのリスクもありません。一方で、普通徴収は一度に納付する金額が大きくなりますが、クレジットカード払いでポイントが貯まるなどのメリットもあります。
ただし、給与所得者の場合、原則として特別徴収が適用されます。地方税法では、所得税を源泉徴収している事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。従業員や事業主の希望で普通徴収を選択することはできません。
| 徴収方法 | 対象者 | 納付回数 | 特徴 |
| 特別徴収 | 給与所得者 | 毎月(12回) | 給与天引き、負担感軽減 |
| 普通徴収 | 自営業者 | 年4回 | 自身で納付、一回の金額大 |
住民税の減免制度と特例
住民税の減免制度は、生活困窮者や災害被災者などを救済するための重要な仕組みです。減免の対象となるのは、生活保護受給者、失業者、傷病者、災害被災者などで、前年の所得や資産状況に応じて適用されます。例えば、失業や休業で収入が著しく減少した場合、前年の所得が一定額以下であれば減免の可能性があります。
減免申請は通常、納期限までに行う必要があります。申請には、収入・資産状況の報告書や、失業証明書、罹災証明書などの書類が必要です。申請が認められると、全額免除から一部軽減まで、状況に応じた減免が適用されます。
特に災害時の減免制度は重要で、住宅や家財に被害を受けた場合、損失の程度に応じて減免が適用されます。ただし、減免制度は自治体によって詳細が異なるため、居住地の市区町村窓口に確認しましょう。
住民税の納付が遅れた場合の対処法
住民税の納付が遅れると、まず督促状が送付されます。これに応じない場合、催告書が届きます。それでも納付されないと、財産の差し押さえなどの滞納処分が行われる可能性があります。差し押さえられた財産は、自由に処分できなくなります。
納付が遅れると、本税に加えて延滞金も発生します。延滞金は、納期限の翌日から納付日までの期間に応じて計算されます。
納税が困難な場合は、早めに市区町村の担当窓口に相談しましょう。分割納付や納付猶予などの制度を利用できる可能性があります。また、生活困窮や災害被害などの理由がある場合、減免制度の適用を検討することも可能です。
まとめ

住民税は前年の所得に基づいて課税され、社会人2年目の6月から納付が始まります。納付方法には特別徴収と普通徴収があり、6月から翌年5月までの期間で支払います。給与所得者と個人事業主で計算方法が異なるため注意が必要です。
また、減免制度や特例、納付遅延時の対処方法についても理解しておくと良いでしょう。住民税に関する疑問は、各自治体の窓口で相談できます。所得税との違いを理解し、適切に納付することが大切です。
住民税の仕組みや納付方法を理解することで、適切な税金管理が可能になります。しかし、従業員の住民税管理を含む労務業務は、企業にとって大きな負担となることがあります。そこでおすすめなのが、労務管理クラウドサービス「ロウムメイト」です。
入社手続きや年末調整など、煩雑な人事・労務業務を一元管理し、効率化できます。住民税管理の効率化に興味がある方は、ぜひ「ロウムメイト」をご検討ください。