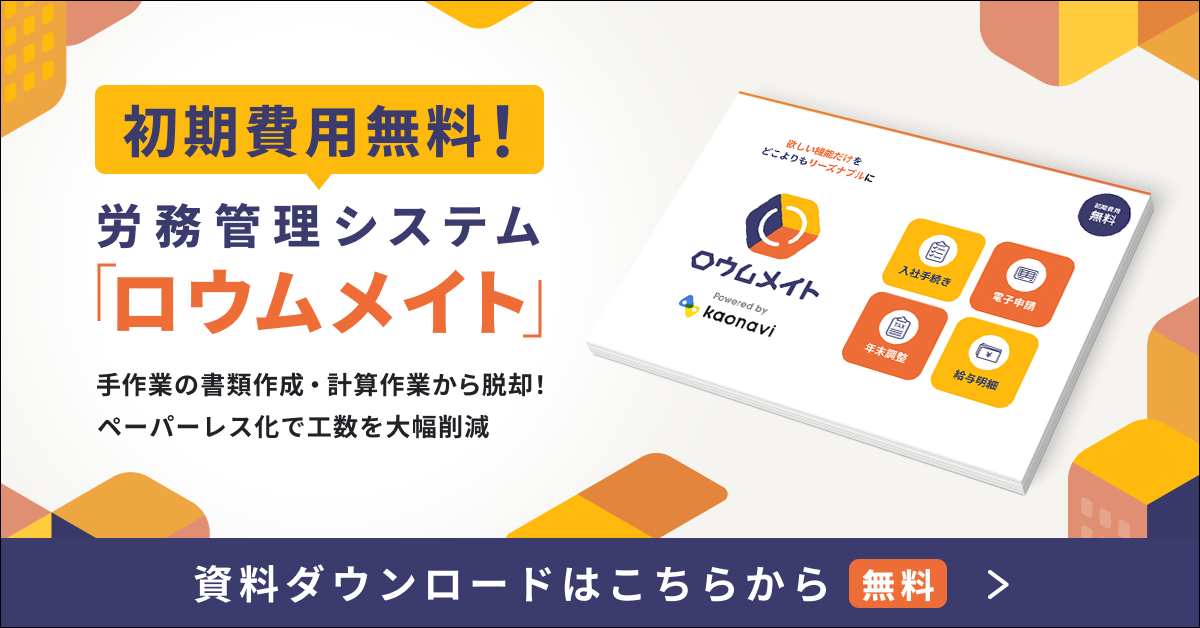高齢者雇用の促進にともない、70歳以上の従業員を抱える企業が増加している中、介護保険料に関する実務対応に頭を悩ませる人事労務担当者も多いのではないでしょうか。特に、年金受給と給与所得が併存する場合の保険料計算など、確認すべきポイントは少なくありません。
本記事では、70歳以上の従業員に関する介護保険料の実務について、人事労務担当者が押さえておくべき基礎知識から具体的な計算方法、効率的な管理方法まで解説します。
目次
人事労務担当者が押さえるべき70歳以上の介護保険制度

介護保険制度において、70歳以上の従業員は65歳以上の第1号被保険者として扱われ、独自の保険料計算方法と徴収の仕組みが適用されます。
市区町村が定める基準額をもとに、所得状況や年金受給額によって保険料が決定され、その支払い方法も年金からの天引きや口座振替など、状況に応じて変わってきます。また、2024年度からは医療費負担にも重要な変更点が加わりました。
以下では、人事労務担当者が把握すべき制度の詳細と、従業員への説明ポイントについて解説します。
70歳以上の従業員に適用される介護保険料の仕組み
70歳以上の従業員の介護保険料は、65歳以上の第1号被保険者制度の枠組みで運営されています。保険料の管理や徴収は市区町村が行い、年金受給者の場合は原則として年金から天引きされる仕組みとなっています。
保険料額は、市区町村が定める基準額をもとに、前年の所得状況や世帯の課税状況に応じて段階的に設定されます。具体的な金額は、毎年6月頃に送付される介護保険料額決定通知書で確認することができます。
| 項目 | 内容 |
| 被保険者区分 | 第1号被保険者(65歳以上) |
| 保険料決定基準 | 所得段階別の保険料率による |
| 通知時期 | 毎年6月頃 |
従業員の年金受給と介護保険料の関係
年金受給額が年間18万円以上の70歳以上の従業員については、介護保険料は原則として年金から天引きされます。ただし、年金受給開始直後、約6か月程度は口座振替や納付書による支払いとなります。
年金受給額が年間18万円未満の場合は、年金からの天引きではなく、口座振替または納付書による普通徴収方式が適用されます。また、年金の一部または全額を受給していない場合も同様の扱いです。
給与計算の実務においては、年金からの保険料徴収が開始されるまでの期間は、従業員に対して納付書による支払いや口座振替の手続きが必要である旨を説明する必要があります。市区町村から送付される介護保険料額決定通知書に基づき、適切な支払い方法を選択するようアドバイスしましょう。
70歳以上の従業員の医療費負担の変更点
70歳以上の従業員の医療費負担は、2024年度から重要な変更が実施されています。所得区分によって異なる負担割合が設定され、現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)は3割負担、一般所得者は2割負担となりました。特に、外来診療の場合、一般所得者の負担上限額は年間14.4万円に設定されています。
高額療養費制度では、所得区分に応じて自己負担限度額が定められており、外来と入院で異なる基準が適用されます。入院の場合は70歳未満と同様に世帯単位で計算され、外来は個人単位での計算となります。
医療機関での支払いを抑えるためには、マイナ保険証または限度額適用認定証を利用することが必要です。これにより、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。人事労務担当者は、これらの制度について従業員に適切な情報提供を行い、必要な手続きをサポートすることが重要です。
実務で使える70歳以上の介護保険料計算方法

70歳以上の従業員の介護保険料計算について、実務で活用できる具体的な方法を解説します。給与所得者の実例から、扶養家族がいる場合の計算方法、さらには保険料減免制度の適用条件まで、人事労務担当者が知っておくべき実践的な計算方法をご紹介します。
特に年金受給額による保険料徴収方法の違いや、所得段階に応じた計算の仕組みなど、実務で必要となる具体的なケースに焦点を当てて説明していきます。
給与所得者の介護保険料計算の実例
70歳以上の従業員の介護保険料は、第1号被保険者として市区町村が算定・管理を行います。保険料は原則として年金から特別徴収される仕組みです。
年金受給額が年間18万円以上の従業員の場合、保険料は偶数月に年6回の年金天引きとなり、1回あたり1万円が徴収されます。一方、年金受給額が年間18万円未満の従業員は、口座振替や納付書による普通徴収となります。
保険料の所得段階は、従業員本人の合計所得金額や世帯の課税状況によって決定されます。例えば、合計所得金額が200万円を超える場合、基準額の1.2倍以上の保険料となることがあります。
| 項目 | 内容 |
| 保険料の算定主体 | 市区町村 |
| 徴収方法(年金18万円以上) | 年金からの特別徴収(年6回) |
| 徴収方法(年金18万円未満) | 口座振替・納付書による普通徴収 |
| 保険料決定要因 | 所得段階・世帯課税状況 |
扶養家族がいる場合の保険料計算
扶養家族がいる場合の介護保険料計算では、世帯構成や加入している健康保険の種類により負担額が異なります。40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合でも、その家族の個別の介護保険料負担は不要です。これは、被扶養者の介護納付金を被保険者全体で負担する仕組みとなっているためです。
ただし、健康保険組合によっては「特定被保険者制度」を採用しているケースがあります。この制度下では、40歳未満または65歳以上の被保険者が、40歳以上65歳未満の家族を扶養している場合、介護保険料を負担する必要があります。約4割の健康保険組合がこの制度を採用しています。
保険料減免制度の適用条件と手続き
人事労務担当者として、70歳以上の従業員の介護保険料減免制度への理解は重要です。主な減免対象は、災害による住宅被害、世帯主の死亡や重度障害、事業廃止による収入激減などの場合で、状況に応じて保険料の全額または一部が減免されます。
申請手続きには、市区町村が定める申請書のほか、罹災証明書、所得証明書、医師の診断書など、減免理由を証明する書類の提出が必要です。なお、申請期限は原則として保険料の納期限までとなっています。
労務担当者は、従業員が減免制度を利用できる可能性がある場合、速やかに制度の概要を説明し、市区町村の介護保険窓口への申請手続きをサポートすることが求められます。
介護保険料実務の効率化と従業員サポート

介護保険料に関する実務を効率的に進めるため、相談対応から制度説明まで、人事労務担当者が実践すべき具体的なポイントをご紹介します。70歳以上の従業員からの問い合わせに的確に対応するためには、専門的な知識に加え、わかりやすい説明方法の習得が重要です。また、最新の労務管理システムを活用して作業の自動化を図ることで、業務効率を大幅に向上させることができます。
ここでは、従業員からの相談への対応方法、労務管理システムの活用法、そして70歳以上の従業員への効果的な情報提供方法について、実践的なアプローチを解説していきます。
介護保険料に関する従業員からの相談対応
人事労務担当者として、従業員からの介護保険料に関する相談に適切に対応することは重要な業務です。相談内容を正確に把握し、従業員のプライバシーに配慮しながら、丁寧な説明を心がけましょう。
よくある相談として、保険料の計算方法や納付方法に関する質問があります。具体的な数値を示しながら、わかりやすく説明することが大切です。また、年金からの天引きや口座振替など、支払方法の選択肢についても説明できるよう準備しておきましょう。
相談対応時には、必要に応じて市区町村の介護保険課や年金事務所などの専門機関を紹介することも検討します。特に、保険料の減免制度や支払いに関する相談は、各自治体の制度によって異なる場合があるため、適切な窓口を案内することが重要です。
従業員の不安や疑問を解消するためには、最新の制度情報を把握し、正確な情報提供ができる体制を整えることが求められます。
| 相談内容 | 対応のポイント |
| 保険料計算方法 | 具体的な数値を用いた説明 |
| 納付方法の選択 | 各支払方法のメリット・デメリット説明 |
| 減免制度の案内 | 自治体の窓口情報の提供 |
| 制度全般の質問 | 最新情報に基づく正確な説明 |
労務管理システムを活用した保険料計算の自動化
最新の労務管理システムは、従業員の介護保険料計算を自動化し、保険料の徴収有無を正確に判定します。従業員の年齢や標準報酬月額の変更を自動で検知し、保険料計算の更新を行います。
給与計算ソフトを導入すると、従業員情報の入力だけで、最新の保険料率に基づく計算が可能です。年度更新時の書類作成も自動化され、人事労務担当者の作業負担を大幅に軽減できます。
勤怠管理システムとの連携機能があるものを導入した場合、勤務時間データを自動で給与計算に反映します。これにより、複雑な保険料計算も正確に処理でき、計算ミスのリスクを最小限に抑えることができます。
70歳以上の従業員への情報提供と説明のポイント
70歳以上の従業員への介護保険料の説明には、視覚的な資料を活用することが効果的です。専門用語には注釈をつけた説明資料を作成することで、従業員の理解が深まります。
保険料の説明資料には、年金受給額と保険料の関係を示すグラフや、年間の支払いスケジュールを含めると理解が促進されます。市区町村から配布される介護保険料決定通知書のサンプルを用意し、見方を丁寧に解説することで、従業員の不安を軽減できるでしょう。
また、定期的な説明会の開催や、個別相談の機会を設けることで、従業員一人ひとりの状況に応じたきめ細かなサポートが可能となります。
まとめ

介護保険制度において、70歳以上の方は第1号被保険者として、原則年金からの特別徴収により保険料を納付します。保険料は所得に応じて段階的に設定され、年金受給額や世帯構成によって具体的な金額が決まります。
人事労務実務では、従業員の年齢や収入状況に応じた保険料計算が重要になります。特に、年金以外の収入がある場合や扶養家族がいる場合は、保険料額が変動する可能性があります。また、低所得者向けの保険料減免制度も活用できるため、従業員の状況に応じた適切なアドバイスが可能です。
これらの知識を活用することで、70歳以上の従業員に対する効果的なサポートと、スムーズな保険料徴収業務が実現できます。
しかし、介護保険料の計算や管理、特に70歳以上の従業員に関する実務は複雑で、人事労務担当者の大きな負担となっています。年金からの天引きや所得に応じた計算、さらには2024年度からの医療費負担の変更など、把握すべき項目は多岐にわたります。
労務管理システム「ロウムメイト」では、70歳以上の従業員を雇う時や70歳以上の従業員が退職するときに必要な書類の行政への電子申請が可能です。無料トライアルで、貴社の業務効率化を実感してください。