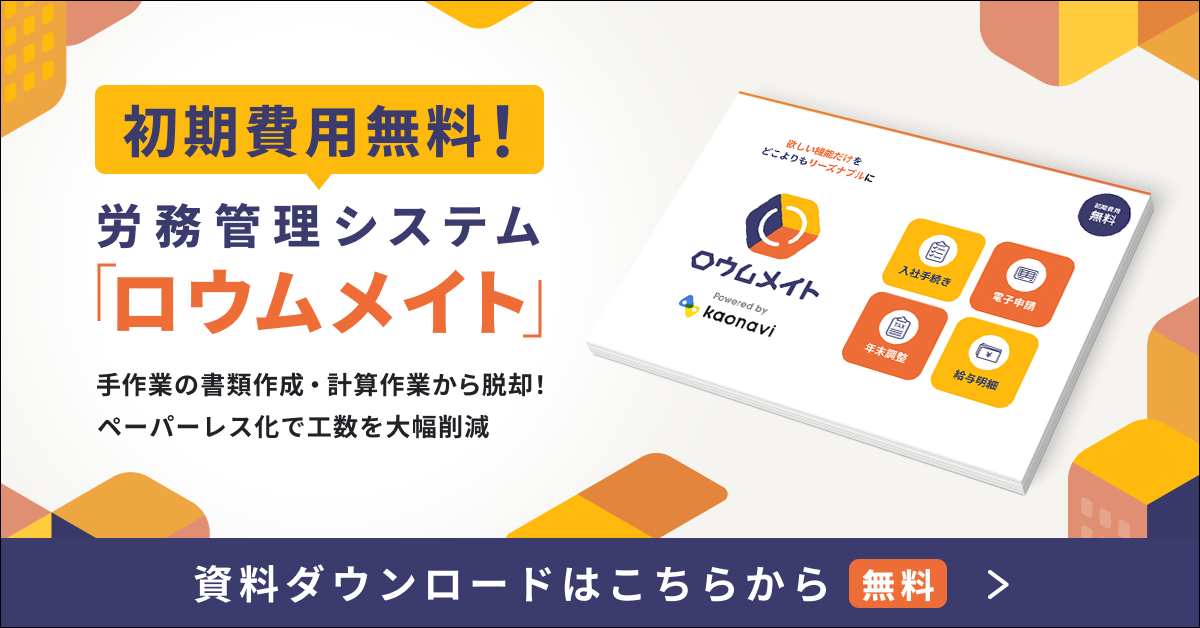企業の労務担当者にとって、従業員の介護保険料の計算は年齢や所得によって異なるため、把握すべきポイントが多岐にわたります。40歳から発生する介護保険料は、40〜64歳と65歳以上で徴収方法が大きく変わります。さらに、所得段階や自治体によっても金額が異なるため、正確な計算と控除が求められます。
この記事では、介護保険料の基本から年齢別・所得別の計算方法、減免制度まで、労務担当者が知っておくべき知識を解説します。従業員からの質問にも自信を持って対応できるよう、実務に役立つポイントをお伝えします。
目次
介護保険料の基本と年齢による違い

介護保険料の計算方法は年齢によって大きく異なります。40歳からは制度加入が義務付けられ、「第1号被保険者(65歳以上)」と「第2号被保険者(40歳~64歳)」の2段階に分かれる仕組みです。それぞれで保険料の計算方法や徴収方法が異なるため、労務担当者は正確な理解が必要です。
以下では40歳から64歳の方と65歳以上の方の介護保険料計算の違いや、医療保険の種類による計算方法の違い、年金からの天引きと納付書払いの仕組みなど、年齢別の具体的な介護保険料の計算方法について詳しく解説します。労務管理に役立つ具体的な計算例も参考にしてください。
介護保険料が発生する40歳からの2段階制度
介護保険料の徴収方法は、加入者の年齢によって「第1号被保険者(65歳以上)」と「第2号被保険者(40歳~64歳)」の2段階に分かれています。
40歳になると、法的に介護保険への加入が義務付けられ、40歳になった月から保険料の支払いが始まります。
第2号被保険者(40歳~64歳)の場合、保険料は加入している医療保険制度によって計算方法が異なります。会社員や公務員などは、給与(標準報酬月額)や賞与に保険料率をかけた金額を勤務先と折半で負担し、給与から天引きされます。
一方、国民健康保険加入者は前年の所得に応じて計算された保険料を、国民健康保険料と一体的に納付します。
この二段階制度により、40歳を境に保険料の負担方法が大きく変わります。労務担当者は従業員の年齢に応じた正確な控除処理が求められます。
40歳〜64歳の従業員の介護保険料計算の特徴
40歳から64歳の第2号被保険者の介護保険料計算は、加入している医療保険の種類によって大きく異なります。会社員や公務員など国民健康保険以外の医療保険に加入している場合、介護保険料は標準報酬月額に介護保険料率をかけて算出され、労使で折半します。
例えば、標準報酬月額30万円、介護保険料率1.82%の場合、月々の介護保険料は30万円×1.82%×1/2=2,730円となります。賞与からも同様に計算され、標準賞与額に保険料率をかけた金額の半額が控除されます。
一方、国民健康保険加入者の場合は、所得割・均等割・平等割・資産割を組み合わせて、市区町村ごとに計算方法が設定されています。特に所得に応じた計算になるため、お住まいの自治体に確認が必要です。
また、介護保険料を滞納すると、介護サービス利用時に不利益が生じる可能性があるため、納め忘れには十分注意しましょう。
65歳以上の従業員の介護保険料の仕組み
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料は、所得に応じた段階制で計算されます。各自治体が設定した「基準額」に所得段階に応じた割合をかけて算出する仕組みです。
例えば、基準額が年間80,000円の自治体では、生活保護受給者や住民税非課税世帯で所得が低い方(第1段階)は基準額の0.3倍程度の24,000円、標準的な所得の方(第5段階)は基準額と同額の80,000円、高所得者(第9段階)は基準額の1.7倍の136,000円となります。
自治体によって段階区分は9段階から最大19段階まで細分化されていることがあります。所得段階の判定基準は「本人の住民税課税状況」「世帯の住民税課税状況」「前年の合計所得金額」の3要素で決まります。
保険料の徴収方法は、年金が年額18万円以上の方は年金からの天引き(特別徴収)、それ以外の方は納付書や口座振替による納付(普通徴収)となります。年度途中で65歳になった方は、誕生日の前日に資格を取得し、その月から月割りで保険料が発生します。
給与計算における介護保険料の控除方法

介護保険料の計算方法は労務担当者として正確に理解しておきたい重要な知識です。ここでは給与からの控除に必要な3つの基本事項について解説します。まず標準報酬月額を基準とした計算式の仕組み、次に賞与からの控除方法と年度累計の上限管理、そして正確な給与計算に欠かせない端数処理のルールを順に見ていきましょう。
40歳以上の従業員が増える中、これらの知識を身につけることで、適切な給与計算と従業員からの質問にも的確に対応できるようになります。それぞれの項目について、具体的な計算例と合わせてご説明します。
標準報酬月額に基づく介護保険料の計算方法
介護保険料の計算方法は標準報酬月額に基づいて行われます。40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合、給与から控除される介護保険料は「標準報酬月額×介護保険料率×1/2」で算出されます。例えば、標準報酬月額が30万円で保険料率が1.82%の場合、月々の介護保険料は2,730円(30万円×1.82%×1/2)となります。
標準報酬月額は、通常4月〜6月の給与平均を基に決定され、健康保険法の標準報酬月額表に当てはめて確定します。この金額は給与明細にも記載されているので確認しやすいでしょう。
介護保険料率は加入している健康保険組合や協会けんぽによって異なり、毎年見直されるため、最新の保険料率を確認することが重要です。また、介護保険料は労使折半となるため、計算された金額の半分を従業員が負担します。
給与計算を担当する方は、従業員の年齢に注意し、40歳到達月から適切に介護保険料を控除するよう管理システムを設定しましょう。
賞与からの介護保険料控除の計算手順
賞与からの介護保険料控除も、給与と同様に標準賞与額が基準となります。計算式は「標準賞与額×介護保険料率×1/2」です。標準賞与額は賞与総額から1,000円未満を切り捨てた金額で、例えば50万500円の賞与なら50万円が標準賞与額です。
この標準賞与額には年度累計573万円という上限が設けられています。例えば、6月に300万円、12月に300万円の賞与を受け取る場合、合計600万円となり上限を超過します。そのため、12月分は273万円(573万円-300万円)が標準賞与額となります。
具体的な計算例として、標準賞与額が50万円で介護保険料率が1.60%の場合、控除額は4,000円(50万円×1.60%×1/2)となります。転職した場合も、同一保険者内であれば前職の標準賞与額を累計する必要があるため注意が必要です。
介護保険料計算時の端数処理ルール
介護保険料の計算では、端数処理が重要なポイントになります。「通貨の単位および貨幣の発行等に関する法律」に基づき、介護保険料に1円未満の端数が生じた場合は適切な処理が必要です。原則として、社員負担分の端数が50銭以下なら切り捨て、50銭超え1円未満なら切り上げとなります。
例えば、標準報酬月額190,000円、介護保険料率5.83%の場合、保険料は11,077円となりますが、実際には健康保険料と介護保険料をそれぞれ別々に計算します。この計算過程で端数処理すると、合計値が協会けんぽの発表額と1円ずれることがあります。
また、第1号被保険者(65歳以上)の場合は、月割計算の結果生じる10円未満の端数は切り捨てられます。たとえば年度途中で65歳になり被保険者になった場合、年額保険料を12か月で割った月額に10円未満の端数が出れば、その端数は切り捨てられます。
正確な端数処理は、保険料の過不足を防ぐために不可欠です。特に労務担当者は、この端数処理ルールを理解して適切な社会保険料控除を行いましょう。
所得段階別の介護保険料計算ガイド

介護保険料の計算方法は所得段階によって大きく異なります。特に65歳以上の方は所得に応じた段階制、40歳〜64歳の方は加入している医療保険によって計算方法が変わります。
以下では、所得段階別の具体的な保険料計算の仕組みを解説します。所得区分ごとの保険料率や自治体間の差異、さらに年度途中での所得変更時の再計算方法まで、労務担当者として押さえておくべき重要ポイントを順に見ていきましょう。介護保険料の正確な理解は、従業員への適切なアドバイスや給与計算の正確性につながります。
65歳以上の所得段階区分と保険料率の関係
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、所得に応じた段階制を採用しています。基本的には9段階制ですが、自治体によっては15段階以上に細分化している場合もあります。
各段階の保険料は自治体が定めた「基準額」をベースに計算されます。例えば、第1段階(生活保護受給者や世帯全員が住民税非課税で所得が低い方)では基準額の0.3倍程度、第5段階(基準額が適用される層)では1.0倍、高所得者層である第9段階では1.7倍といった具合に設定されています。
所得段階の判定には、「本人の住民税課税状況」「世帯の住民税課税状況」「課税年金収入と合計所得金額の合計」が重要な指標です。特に注目すべきは、世帯全員が住民税非課税かどうかという点です。この区分によって、保険料率が大きく変わります。
保険料の徴収方法は、年金額が年間18万円以上の方は「特別徴収」で年金からの天引き、それ以外の方は「普通徴収」で納付書や口座振替による支払いとなります。
| 所得段階 | 対象者 | 保険料率 |
| 第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で所得が低い方 | 基準額×0.3程度 |
| 第2段階~4段階 | 世帯全員または本人が住民税非課税の方(所得により細分化) | 基準額×0.5~0.9程度 |
| 第5段階 | 基準額適用層 | 基準額×1.0 |
| 第6段階~9段階 | 本人が住民税課税で所得が高い方(所得により細分化) | 基準額×1.2~1.7程度 |
自治体ごとの介護保険料の計算例と比較
介護保険料は自治体によって大きな差があります。全国で最も高い大阪市の基準額は月額9,249円(年間約11万円)ですが、最も低い東京都小笠原村では月額3,374円と、月額で約5,875円の開きがあります。
この差が生じる主な要因は、地域の高齢化率、要介護認定率、低所得者の割合などです。例えば、大阪市では要介護認定率が全国平均より8ポイント高い27.4%で、所得が低い人の割合も全国平均の1.5倍近い49.3%に達しています。これらの要素が保険料を押し上げる要因となっています。
労務担当者は、従業員の居住地によって介護保険料に違いがあることを理解し、給与計算に正確に反映させることが重要です。
年度途中での所得変更時の保険料再計算方法
年度途中で所得変更があった場合、介護保険料は自動的に再計算されます。例えば、確定申告の修正や遅れての所得申告をした場合、保険料が変わることがあります。
特に転入の場合は注意が必要です。新たな住所地の自治体は、前住所地に所得照会を行います。その結果が判明するまでの間、均等割と平等割のみで計算された保険料決定通知書が送付されることがあるのです。所得照会の結果に基づいて保険料が再計算され、変更通知書が送付されます。
保険料が増額になった場合は、増額分を納付する必要があります。口座振替の手続きをしている方は、指定口座から自動的に振替されます。逆に減額となった場合は、後日還付通知が送られてきます。
労務担当者としては、従業員から「所得に変更があった」という相談を受けた際には、保険料が再計算される可能性がある点を説明し、変更通知に注意するようアドバイスすることが大切です。
介護保険料の減免制度と労務担当者の対応

介護保険料の支払いが困難な状況に陥った方々を支援する減免制度や、滞納した場合のリスクについて解説します。災害や失業などの予期せぬ事態に備えて知っておくべき減免制度の種類や申請条件、そして滞納時の段階的なペナルティとその対処法までを詳しく紹介します。
労務担当者として従業員の介護保険料の納付に関する不安を解消し、適切なサポートができるよう、制度の仕組みと具体的な対応策について理解を深めていきましょう。従業員が40歳を迎える前の情報提供から、困難な状況での手続き支援まで、押さえておくべきポイントを網羅的に解説します。
介護保険料の減免制度と申請条件
介護保険料の減免制度は、災害や所得激減など予期せぬ事態で保険料納付が困難になった方を支援する仕組みです。主な減免制度には、①災害減免、②所得激減減免、③生活困窮者減免、④法第63条適用者減免(拘禁減免)、⑤制度的無年金者減免の5種類があります。
災害減免は、火災や風水害で住宅や財産に著しい損害を受けた場合に適用されます。一般的に損害割合が10%以上で前年所得が1,000万円以下の方が対象です。所得激減減免は、世帯の主たる生計維持者の失業・事業廃止・長期入院などにより、所得が前年の5割以下に減少した場合に適用可能です。
生活困窮者減免は、低所得世帯で一定の資産基準(単身世帯で預貯金350万円以下など)を満たす方が対象です。申請には区役所や市役所の介護保険担当窓口で、減免申請書と必要書類(り災証明書、収入証明書類など)を提出します。申請期限は自治体により異なりますが、原則として当該年度内です。
労務担当者は、従業員が減免制度を利用できる可能性がある場合、早めの情報提供と申請手続きの支援が重要です。
介護保険料滞納時のペナルティと対処法
介護保険料を滞納すると、その期間に応じて段階的にペナルティが発生します。滞納から1年以上経過すると、介護サービス利用時に費用の全額をいったん自己負担する「支払方法の変更」が適用されます。その後、申請により保険給付分が後から償還されますが、一時的な経済的負担が大きくなります。
滞納期間が1年6か月を超えると、償還払いの申請をしても給付が一時差し止められ、滞納保険料に充当されることになります。さらに2年以上滞納すると、自己負担割合が通常の1割から3割(負担割合が3割の方は4割)に引き上げられ、高額介護サービス費等の支給や食費・居住費の負担軽減も受けられなくなります。
労務担当者としては、従業員が40歳になる前に介護保険料の仕組みを説明し、滞納によるペナルティの重大さを伝えることが重要です。また、収入が大幅に減少した場合などには減免制度の案内も行いましょう。滞納が発生した場合は、できるだけ早く市区町村の窓口に相談するよう促すことが適切な対応です。
まとめ
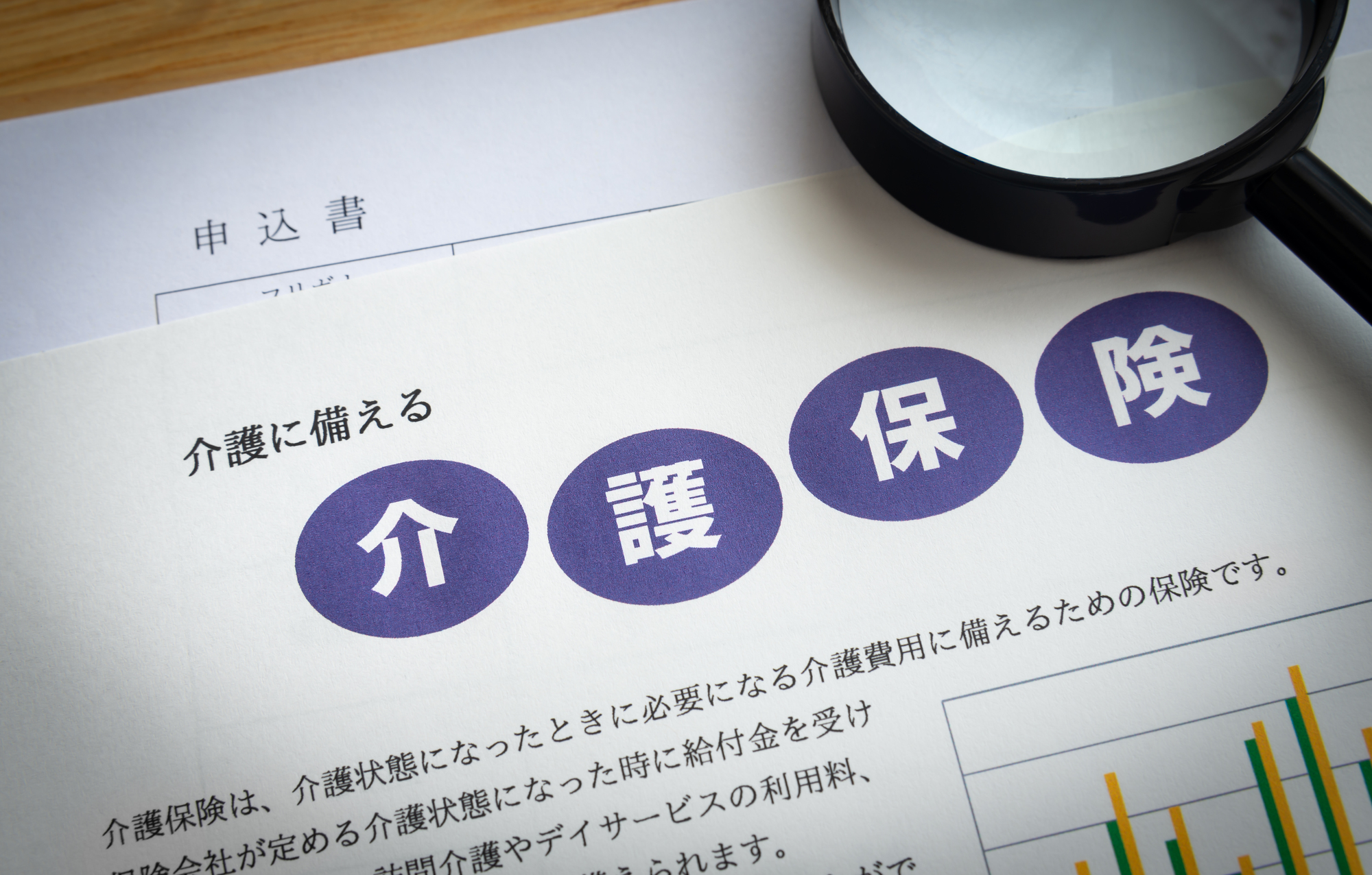
介護保険料は40歳以上65歳未満(第2号被保険者)と65歳以上(第1号被保険者)で計算方法が異なります。給与からの控除は健康保険料と一体で計算され、賞与からも標準報酬月額に応じた控除が行われます。
市区町村が設定する所得段階(通常9段階以上)によって金額が変動し、年金からの特別徴収と納付書による普通徴収の2種類の納付方法があります。また、災害や所得激減時には減免制度が適用され、労務担当者は制度内容と申請手続きを把握しておくことが重要です。
「ロウムメイト」の労務管理クラウドなら、年齢も含めて従業員情報を一元管理できます。本来の経営課題に集中するために、煩雑な労務業務を効率化しませんか。