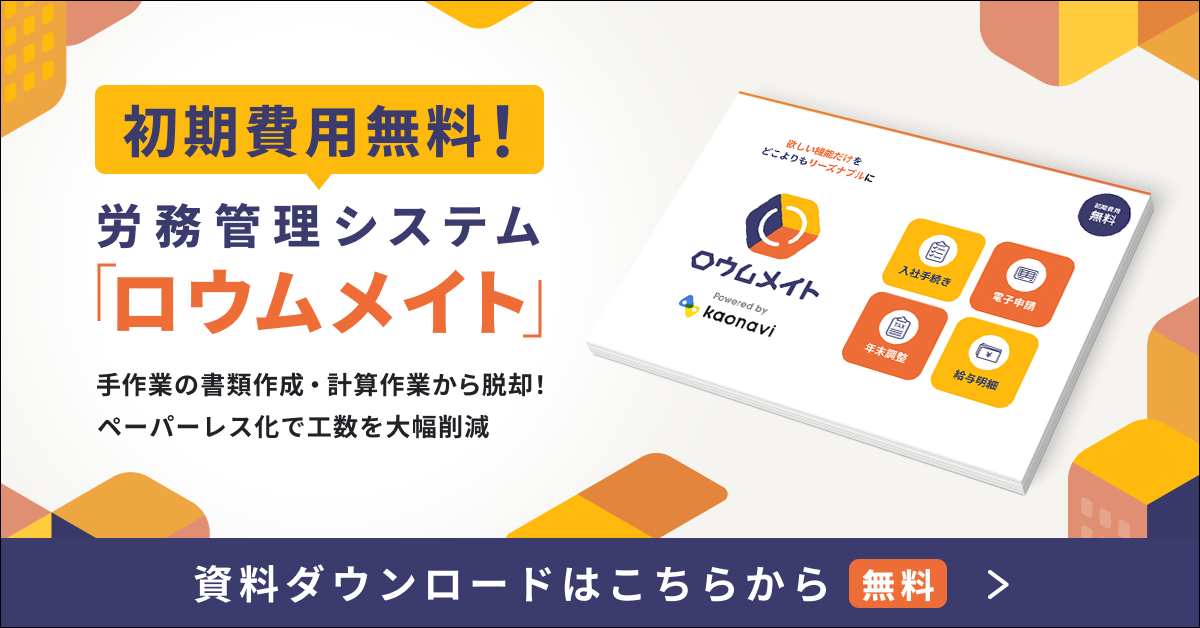メンタルヘルスとは、精神面・心の健康状態のこと。メンタルヘルスが不調な状態では仕事へのモチベーションや集中力などが低下し、生産性や業績の低下を招く恐れがあります。従業員の心身の健康のため、安定した経営のためにも従業員のメンタルヘルスケアは重要な取り組みです。
今回はメンタルヘルスについて、ケアが重要な理由やメンタルヘルスの不調のサイン、職場でできるケアや企業事例などを詳しくご紹介します。
目次
1.メンタルヘルスとは?
メンタルヘルス(Mental Health)とは、精神面、心の健康状態のことです。メンタルヘルスが良好な状態では、モチベーションや意欲が高まりやすく、仕事においてもパフォーマンスを発揮しやすくなります。一方、悪い状態では物事に集中できない、決断力が鈍ってしまうほか、うつ病や適応障害といった疾患を引き起こす恐れがあります。
厚生労働省によるメンタルヘルス不調の定義
厚生労働省によるメンタルヘルスの定義は、下記のとおりです。
精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの
うつ病や適応障害といった病名のある疾患だけでなく、ストレスや悩み、不安から日常生活に影響を及ぼしている場合は、メンタルヘルス不調といえます。
メンタルヘルスの不調は周囲から気づかれにくいだけでなく、自分からも伝えにくいことから放置されやすく、回復に時間がかかってしまうケースも多いのです。
2.メンタルヘルスケアが重要な理由
厚生労働省が実施した「令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)結果の概況」によると、現在の仕事や職業生活に関することで強い不安や悩み、ストレスといったメンタルヘルス不調を感じている労働者の割合は、82.7%でした。
メンタルヘルス不調の状態では、仕事にも悪影響をおよぼしてしまうことは明白です。あらためて、メンタルヘルスケアが重要な3つの理由をみていきます。
- 精神疾患による労災申請が増加しているため
- 生産性の低下を防ぐため
- リスクマネジメントのため
精神疾患による労災申請が増加しているため
精神疾患は、労災申請の対象です。厚生労働省の令和5年度「過労死等の労災補償状況」によると、精神疾患による労災の請求件数は前年度比892件増加の3,575件、支給決定件数は883件でした。
また、精神疾患は、『国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病』(医療法第30条の4 第2項第4号)として、5疾病の1つに位置づけられています。
2013年度の医療計画において、医療法に基づく医療計画で明示すべき疾病に追加され、がんや脳卒中、新血管疾患や糖尿病と並ぶレベルです。
「精神疾患に基づく労災請求件数」は右肩上がりにあり、生活においてストレスや不安を感じやすい職場でこそメンタルヘルスケアの重要度が高いといえます。
生産性の低下を防ぐため
メンタルヘルス不調の状態では脳機能が低下し、集中力や判断力、物事に対する意欲や生産性の低下を引き起こします。結果、業務にかかる時間が長くなる、遅刻や早退、欠勤が増えるほか、最悪のケースでは長期休業が必要となってしまうケースも出てくるでしょう。
メンタル不調により生産性が低下する人が増えれば、チーム・組織全体の生産性低下を招いてしまいます。結果的に業績低下を招き、最終的には組織の存続の危機にまで陥ってしまう恐れもある重大な問題です。ゆえに、従業員一人ひとりのメンタルヘルスケアが欠かせません。
リスクマネジメントのため
メンタル不調による生産性の低下は、業績の低下を招く恐れがある重大なものであることから、メンタルヘルスケアは経営のリスクマネジメントの一種ととらえるべきです。
そうしたことも背景に2015年より常時50人以上の労働者を使用する事業所には、ストレスチェックの実施が義務化されています。
また、メンタルヘルス不調により、集中力や判断力が低下した状態では、業務中の事故やトラブルにつながるリスクも高くなります。企業は従業員の安全を確保することも義務づけられているため、そうした観点からもリスクマネジメントとしてメンタルヘルスケアが重要です。
3.メンタルヘルスの不調がもたらす悪影響
メンタルヘルスの不調は、具体的にどのような悪影響をもたらすのでしょうか。従業員・企業の観点から、メンタルヘルスの不調がもたらす悪影響をみていきます。
従業員にもたらす悪影響
- 生産性の低下
- 仕事への意欲、モチベーションの低下
- 遅刻や欠勤の増加
- 業務上のミスやトラブル、事故や怪我の発生
- 精神疾患の発症
従業員のメンタルヘルス不調では生産性や効率性、仕事の質低下を引き起します。人事評価にも悪影響を及ぼしてしまい、本人にとってプラスになることはありません。
また、ミスが増えれば周囲の人に迷惑をかけてしまうことも増え、人間関係にも悪影響を及ぼしてしまう可能性があるでしょう。さらに、症状が重くなれば、休職や離職を余儀なくされ、今後のキャリア形成や生活にも影響が出てしまう恐れもあります。
企業にもたらす悪影響
- 業績低下
- コスト負担の増加
- 企業イメージの低下
メンタルヘルス不調の従業員が増えればそれだけ生産性が低下し、組織の活力も低下します。結果、業績にも悪影響を及ぼし、最悪のケースでは企業の将来性も危ぶまれる状況に陥る恐れがあるでしょう。
また、休職者が出たら医療費などの負担が発生し、離職が起これば人員補充のために新たに採用コストが発生します。さらに、場合によっては労災から訴訟に発展し、裁判にかかる費用や損害賠償も請求されるなど、さまざまなコスト負担が増加します。
また、メンタルヘルス不調により訴訟が起きた、自殺者が出たなどすると、企業のイメージの低下にもつながります。取引先や株主からの信頼を失うだけでなく、採用活動にも悪影響を及ぼしてしまうでしょう。
このように、従業員のメンタルヘルス不調を放置することは、結果的に企業への悪影響を増大させてしまうのです。
4.メンタルヘルスの不調を知らせるサイン
メンタルヘルスの不調は突然訪れるものではなく、蓄積していくもの。初期は本人も自覚できず、周囲も気づきにくいものの、不調が蓄積されていくとサインとして目に見えるようになってきます。
不調を知らせるサインは人によってさまざまです。ここではよくあるサインをご紹介します。
- 勤務態度や勤怠状況が悪くなる
- 仕事でミスが増える
- 身だしなみを気にしなくなる
- 態度が変わる
- 体調不良を訴えることが増える
勤務態度や勤怠状況が悪くなる
代表的なサインが、遅刻や早退、欠勤や残業が増えること。また、報連相のような基本的なコミュニケーションが減ったり、反対に無駄話が増えたりと仕事に集中できていない様子も見られます。今まで無遅刻無欠席であった人であれば、サインにも気づきやすいでしょう。
仕事でミスが増える
メンタルヘルスが不調な状態では集中力や判断力、そして仕事のパフォーマンスが低下し、ミスやトラブルが増えてしまいます。心身ともに余裕がないため、仕事の質が低下するだけでなく、仕事へのモチベーションも上がらないため、改善する姿勢もなかなか見られなくなります。
身だしなみを気にしなくなる
メンタルヘルスが不調な人によくある傾向として、身だしなみを気にしなくなり、清潔感がなくなることが挙げられます。髪を整えていない、よれたシャツばかり着ている、身の回りの整理整頓ができなくなるといった様子が見られるようになるでしょう。身だしなみは周囲の人も気づきやすいサインの一つです。
態度が変わる
挨拶をしなくなる、独り言が増える、話しかけても反応が薄い、突然怒り出すなど、通常時とは違った態度を見せるようになるのもサインの一つ。メンタルヘルス不調だと心身の余裕がなくなり、周囲と明るく接する余裕がなくなったり、誰とも話したくないといった状態に陥りやすくなります。
しかし、なかには無理して平常を保とうとする人もいるため、些細な変化に気づくことが大切です。
体調不良を訴えることが増える
メンタルヘルスの不調が影響するのは、こころだけではありません。疲労感が取れない、頭痛や肩こりが続く、食欲がない、夜に寝付けない、喫煙量や飲酒量が増えるなど、体調面での不調も著しくなります。体調不良が2週間以上続く場合、メンタルヘルスの不調にも要注意です。
5.メンタルヘルス悪化を防ぐ3つの段階
メンタルヘルスの悪化防止に取り組む際は、下記3段階を意識することがポイントです。
- 【一次予防】未然防止
- 【二次予防】早期発見
- 【三次予防】職場復帰支援
上記3段階は、ストレスに対してどの段階で予防・対処するかにもとづいた枠組みです。各段階での具体的な取り組みをみていきます。
【一次予防】未然防止
一次予防は、メンタルヘルスによる不調を未然に防ぐ段階です。ここでは、メンタルヘルスの不調の原因となるストレスを除去・減らすことを目的に対処します。
- ストレスチェック
- ストレスマネジメントやセルフケアに関する研修の実施
- ストレス緩和ケア
- 労働環境の改善
従業員自身が自分のストレス状況を把握し、休養やセルフケアなどでストレスに対処する段階です。企業側は労働環境の課題を把握し、改善してストレスが発生しにくい環境を整えることを目指しましょう。
ポイントは、従業員がメンタルヘルスに対する意識を高め、ストレスマネジメントを向上させることです。
【二次予防】早期発見
メンタルヘルスの不調を早期に発見し、適切な措置を講じる段階です。一次予防でセルフケアできなかったストレスは蓄積し、放置すれば深刻化・悪化してしまいます。そうなると回復にも時間を要してしまうため、早期発見が重要です。
- 相談窓口の設置
- 産業医との面談機会を提供
- セルフチェック
- 配置転換
具体的な措置を講じるには、メンタルヘルス不調の原因を把握することが必要です。相談窓口や産業医との面談を通じて、具体的な原因を見つけましょう。
従業員が不調を我慢し一人で抱え込まないためにも、相談できる職場風土の醸成や相談窓口・産業医面談の啓蒙、周囲が変化に気づけるようコミュニケーションを活性化させることがポイントです。
【三次予防】職場復帰支援
メンタルヘルスの不調により、回復のために休職が必要な従業員も出てきます。そうならないための一次・二次予防が重要であるものの、すべての従業員がそこで留まるとは限りません。
休職した従業員がいる場合はスムーズに職場復帰できるよう企業側が支援し、その後の再発防止に努めることが大切です。
- 医師との連携
- 職場復帰支援プログラムや支援プランの作成
- 復帰後の職場環境の整備
復帰するうえで従業員が不安に感じていることに対して、適切な措置を講じる必要があります。
また、休業の開始から復帰までの流れを明確にし、制度・ルールとして明示することも大切です。この点が曖昧だと、休職すること自体に不安を覚えてしまう恐れもあります。
厚生労働省では、休業した労働者の職場復帰支援の手引きを公開しています。手引きも参考に、職場復帰支援への理解を深め、適切な対応が取れるよう体制を整えましょう。
厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
6.メンタルヘルスケアの基本となる4つのケア
厚生労働省『労働者の心の健康の保持増進のための指針』では、メンタルヘルスケアの基本となる下記4つのケアを提示しています。
- セルフケア
- ラインケア
- 事業場内産業保健スタッフ等によるケア
- 事業場外資源によるケア
メンタルヘルスケアは、4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要です。ここでは、各ケアの内容やポイントを解説していきます。
①セルフケア
従業員自身がストレスを自覚し、自ら予防・対処すること。そのためにも、企業は従業員に対してセルフケアが行えるよう以下のような教育研修や情報提供などの支援を行うことがポイントです。
- ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
- ストレスチェックなどを活用したストレスへの気付き
- ストレスへの対処
従業員のメンタルヘルスを管理する側である管理監督者もセルフケアの対象です。ストレスに対処するには、まず本人がストレスを抱えていることを自覚する必要があります。ストレスを自覚するには、ストレスチェックの実施が有効です。
②ラインケア
管理監督者が職場のストレス要因を把握し、改善すること。具体的な取り組みには、下記が挙げられます。
- 職場環境等の把握と改善
- 労働者からの相談対応
- 職場復帰における支援
管理監督者が適切に職場のメンタルヘルスケアを行うためにも、企業は管理監督者に対して適切な教育研修や情報提供を行う必要があります。
また、従業員個々のサインを見極めるだけでなく、オフィスの照明や温湿度などの物理環境、作業レイアウトなどといった要因も含めて「職場環境」と捉え、メンタルヘルス不調の原因を把握し、適切な対応をとることが求められます。
職場環境の改善を通じたストレス対策のポイント
アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)は、職場環境等の改善を通じたストレス対策のポイントとして7つの視点を挙げています。
- 過大あるいは過小な仕事量を避け、仕事量に合わせた作業ペースの調整ができること
- 労働者の社会生活に合わせて勤務形態の配慮がなされていること
- 仕事の役割や責任が明確であること
- 仕事の将来や昇進・昇級の機会が明確であること
- 職場でよい人間関係が保たれていること
- 仕事の意義が明確にされ、やる気を刺激し、労働者の技術を活用するようにデザインされること
- 職場での意志決定への参加の機会があること
出典:厚生労働省「職場環境改善ツール」
ラインによるケアに取り組む際は、上記のポイントに着目してみましょう。
③事業場内産業保健スタッフ等によるケア
企業内の産業医や衛生管理者、保健師や人事労務管理担当者など、産業保健スタッフによるセルフケアおよびラインケアのこと。事業場内の産業保健スタッフは、従業員や管理監督者に対するメンタルヘルスケアや下記のような心の健康づくり計画の実施に伴う中心的な役割を担います。
- 具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案
- 個人の健康情報の取扱い
- 事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口
- 職場復帰における支援
個々のケースを支援するだけでなく、メンタルヘルスケアに関連する研修の企画・実施、相談できる制度や体制を整え、専門的な視点からメンタルヘルスケアを支援していきます。
④事業場外資源によるケア
メンタルヘルスの専門知識を有する外部機関やサービスの活用によるメンタルヘルスケアの実施です。事業場外資源には、以下のような機関・サービスが挙げられます。
- 都道府県産業保健総合支援センター
- 健康保険組合
- 労災病院
- 医療機関(精神科・心療内科)
- 公認心理師
- 精神保健福祉士
- 産業カウンセラー
- 臨床心理士
事業場外資源によるケアは、企業内では相談しにくい、企業が抱えるメンタルヘルスに関する課題を解決したい場合に有効です。
内部だけでは解決できない課題や問題に外部資源をうまく活用すると、内部にはない知見を活用して解決に導いてくれる可能性に期待できます。
7.企業ができるメンタルヘルスケア対策の具体例
企業は、従業員に対してメンタルヘルスケア対策を実施する義務があります。ここでは、メンタルヘルスケア対策として企業が取り組むべき対策の具体例をご紹介します。
ストレスチェックの実施
適切なメンタルヘルスケアを実施するには、まず従業員のストレス状況を把握する必要があります。ストレスチェックとは、ストレス状況を把握するだけでなく、チェック結果にもとづいた面談指導の実施や集計・分析に係る一連の取り組みのこと。
目的は、ストレスチェックによって従業員自身にストレスへの気づきを促し、セルフケアにより予防を図ることです。チェック結果を分析すると、職場環境の改善にも役立ちます。
ストレスチェックは義務化されている
2014年の労働安全衛生法の改正により、2015年12月1日からストレスチェック制度が義務化されました。労働者が50人以上いる事業所では、毎年1回のストレスチェックの実施が必要です。
ストレスチェックでは、ストレスに関する質問票を従業員に記入してもらい、医師などの実施者が回収し、ストレスの程度を評価します。
メンタルヘルスに関する社内研修の実施
メンタルヘルスケア対策を適切に実施するうえでは、従業員や管理監督者に対して正しい知識を身につけてもらうことが必要です。そのためにも下記のような研修をとおしてメンタルヘルスへの理解を深め、正しい知識を習得してもらいましょう。
- ストレスのセルフチェック促進の研修
- 部下とのかかわり方に関する研修(管理監督者向け)
- ストレスマネジメント研修
研修は、メンタルヘルスを専門とする外部機関・サービスも活用して実施すると効果が高まります。
相談窓口の設置
従業員が自発的に相談するための窓口を設けることも有効な対策です。窓口には、企業の産業医や保健師を配置しましょう。社内で相談しにくい従業員がいることも想定し、外部機関・サービスも利用できる環境も整えることがポイントです。
近年はオンラインで相談できるサービスもあるため、従業員のニーズや相談のしやすさにあわせて、適切な相談窓口を設置しましょう。相談窓口は設置するだけでなく、その存在を周知し、利用しやすい環境を整えるところまで対応することが必要です。
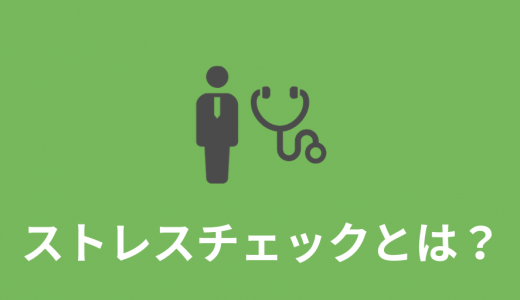
ストレスチェックとは?【実施方法を簡単に】義務化、目的
ストレスチェックは、労働安全衛生法の改正によって50人以上の労働者がいる事業場で義務付けられた検査です。
定期的に労働者のストレスをチェックすることで、労働者が心身の状態に気付き、メンタルヘルスの不調...
8.従業員自身でできるメンタルヘルスのセルフケア
メンタルヘルスケアは受動的に行うのではなく、日頃から能動的に従業員自身が取り組むことが大切です。ストレスは蓄積するため、放置すると症状は悪化の一途を辿ってしまいます。
ここでは、従業員自身でできるメンタルヘルスのセルフケアをご紹介します。
- 良質な生活を心がける
- ストレスマネジメントを身につける
- 相談する
- 医療機関を受診する
良質な生活を心がける
睡眠不足はストレスを増大させる要因となるため、体の疲れを取るためにも十分な睡眠が必要です。また、適度な運動はストレスや不安を軽減する効果のあるエンドルフィンと呼ばれる物質の分泌が促されます。
そして栄養のある食事も心がけ、規則正しい生活を送ることでメンタルも安定しやすくなります。生活習慣の改善がメンタルヘルスにも良い影響を与え、健康維持にも有効です。
ストレスマネジメントを身につける
自分自身のストレスをマネジメントすることもセルフケアの一つです。具体的な方法には、下記のようなものが挙げられます。
- ストレスの要因となっていることを書き出す
- ストレスチェックを行う
- 身近な人に相談する
またストレスマネジメントの手法としてストレスコーピング(自分が楽しくなることや問題が解決できることをリストにまとめる手法)があります。ストレスコーピングができると、ストレスの要因に対する対処法を洗い出し、そのなかから最適な方法を選べるようになるのです。

コーピングとは?【意味とやり方をわかりやすく】ストレス
1.コーピング(coping)とは?
コーピング(coping)とは、ストレス反応に対してうまく対処しようとする行動のことです。これに対して、ストレスの原因にうまく対処しようとすることをストレス...
相談する
ストレスや不安、悩みは一人で抱え込むほど増大するもの。上司や窓口、友達や家族など、相談できる人に打ち明けることで、自分の気持ちを客観的に見つめ直せるようになったり、解決に向けた方法を見つけやすくなったりします。
たとえば仕事に関する悩みを上司に相談することで、業務量を調整してもらえ、ストレス軽減につながる場合もあるでしょう。内容によっては人に相談しないと解決しないこともあるため、勇気を出して相談することも大切です。
医療機関を受診する
症状が悪化するとセルフケアでは対処できないケースもあります。そこで、医療機関を受診することもセルフケアの一つ。
専門医のカウンセリングや診療を受けることで、早期回復につながるケースも多くみられます。自分を守るためにも、医療機関を活用することもセルフケアの一つとして覚えておきましょう。
9.メンタルヘルスケアに取り組む企業事例
厚生労働省によるメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」の「職場のメンタルヘルス対策の取組事例」から、メンタルヘルスケアに取り組む企業事例をご紹介します。
三井不動産株式会社
- 人事部配下に健康管理センターを設置
- 新しく入社する人全員を対象にメンタルヘルス研修を実施
- 管理監督者を対象に年2回のラインケア研修を実施
- 年1回人事部による全員面談の実施
同社では、人事部の中に健康管理センターを設置。産業医と保健師が常駐し、精神科産業医が月2回、公認心理士が週1回くる体制を整えています。人事部を経由せず、健康管理センターに相談できる体制を整えていますが、必要な連携は密に取れるようにしている点がポイントです。
またメンタルヘルス不調による休業から職場復帰までの支援として、リハビリ出社や1年間の定期的な面談など丁寧なフォローを提供し、再休業率はほぼ0%を実現できています。さらに、年1回の人事部との全員面談では、職場に関するストレスや不安などを把握し、改善のための施策検討・実行をスピーディーに行っています。
株式会社ニチレイ
健康推進センターを主軸としたグループ横断による健康管理の実施
- メンタルヘルス関連のeラーニングの実施
- 社内セミナー「ニチレイ健康塾」を月1〜2回開催
- セルフケア研修、ラインケア研修の実施
- 「メンタルヘルスアクションチェックリスト」を活用した職場環境改善調査と改善策の検討
保健師と経営層がコミットメントすることで、保健師を中心とした社内での健康活動に取り組みやすい環境が構築されている事例です。
同社では、6名の保健師、センター長や事務職などが所属する健康推進センターを設置。グループが全国にわたることから、各エリア担当の「エリア保健師」を配置し、横断的な健康管理を実施しています。
またメンタルヘルスに関するeラーニングを社内で内製しており、受講を必須としていないものの9割以上の従業員が視聴しています。さらに、研修やセミナーへの参加者も増えており、従業員の年齢が上がる中でも高い健康水準が維持できています。
株式会社丸井グループ
- 健康保険組合との連携
- ストレスチェックの実施
- ストレスチェックの結果に基づいて、各部門でアクションプランを策定
- 産業医との全員面談
- 外部相談窓口の設置
- 全従業員を対象としたセルフケア研修の実施
同社では、健康保険組合と連携し、メンタルヘルスに留まらない幅広い取り組みを推進。具体的には、乳がんや子宮頸がんの検診率向上の取り組み、女性活躍の組織文化醸成に向けた取り組みなどを行っています。
また、ストレスチェックはただ実施するだけでなく、その結果にもとづいて各部門で改善策を検討。改善策実施後のストレスチェックも行うなどして、ストレスの原因を解消するためのPDCAを回しています。
結果2回目のストレスチェックでは、約8割の部門で結果が改善されているのです。さらに、ストレスチェックの受検率は約98%と、毎年ほぼ全員が回答しており、メンタルヘルスケアへの関心の高さがうかがえます。
そして、職場がメンタルヘルス対策に主体的に取り組めるよう、さまざまなツールの提供や仕組みの構築、社内研修のあり方を見直すなどして工夫を凝らしています。