オンボーディングとは、新入社員が職場やチームに早く馴染み、効率的に仕事を進められるようにサポートする取り組みです。効果的なオンボーディングは、早期離職を防ぎ、従業員の定着率を高める効果があります。
そのため、働き方や仕事に対する価値観が多様化している現在、オンボーディングの見直しを進めている企業も増えているでしょう。
この記事では、オンボーディングの目的やメリット、実施方法、そして企業の成功事例を取り上げています。ぜひ、自社のオンボーディング施策の参考にしてみてください。
目次
1.オンボーディングとは?
オンボーディングは、新しく組織にくわわった人材をスムーズに受け入れ、早期に戦力化するための一連のプロセスです。もともとは船や飛行機に乗り込む際の「on-board」を意味する言葉でしたが、現在は企業の人材育成分野で広く使用されています。
新卒社員だけでなく、中途採用者や幹部人材も対象となり、単なる導入研修ではなく、継続的なサポートプログラムを提供する点が特徴です。これにより、新しいメンバーの早期離職を防止し、組織への適応を促進することで、企業全体の生産性向上にも寄与します。
SaaSのカスタマーサクセスにおけるオンボーディング
オンボーディングはSaaS(Software as a Service)業界でも非常に重要な概念で、顧客にも適用されます。SaaSのカスタマーサクセスにおけるオンボーディングとは、顧客がサービスを導入し、そのサービスを効果的に使いこなせるようにサポートするプロセスです。
このプロセスによって、顧客がサービスの価値をしっかり理解し、長く使い続けるための基盤が築かれます。適切なオンボーディングが行われれば、顧客の満足度が高まり、解約率が低下し、さらに追加購入やクロスセルのチャンスが広がります。
SaaS企業にとって、オンボーディングは単なる導入支援ではなく、長期的な信頼関係を築くための非常に重要な取り組みといえるでしょう。
2.オンボーディングの目的
オンボーディングの目的は、新入社員や新しくくわわったメンバーが職場にスムーズに適応し、効率的に業務を進められるようにサポートすることです。具体的な目的には、以下のようなものがあります。
組織に馴染みやすい環境を作るため
オンボーディングの重要な目的の一つは、新入社員が組織に円滑に馴染めるような環境を整えること。新しい職場環境に適応するのは多くの人にとってストレスフルな経験であり、適切なサポートがなければ孤立感や不安を感じやすくなります。
オンボーディングは、上司や同僚を含め、職場全体で新しいメンバーを迎え入れる取り組みです。この方法により、新入社員は早期に組織の一員としての自覚を持ち、より積極的に業務に取り組むことができるようになるでしょう。
結果として、職場全体の雰囲気もよくなり、生産性の向上にもつながるのです。
早期離職を防止するため
早期離職は、人間関係のトラブルや仕事内容の不一致、価値観や職場文化のギャップが主な原因です。適切なオンボーディングを行うことで、新入社員の不安や入社前と入社後のギャップを解消し、職場への理解と意欲を高められます。
その結果、早期離職のリスクを軽減し、人材の長期的な定着を図ることが可能となります。
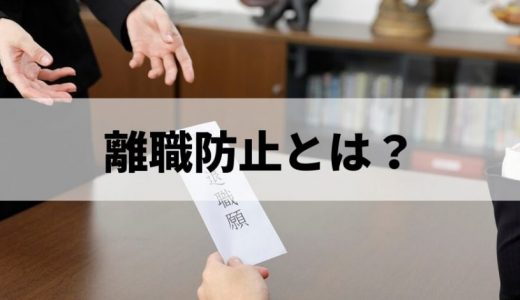
離職防止の取り組みアイデア一覧!原因と離職兆候、事例も解説
従業員の離職は企業にとって痛手であり、大きな損失です。しかし、突然の離職が発生してしまうケースも珍しくありません。従業員の離職を防ぐには、適切な方法で日々対処していくことが重要です。
今回は離職防止に...
部署による教育格差をなくすため
オンボーディングは、異なる部署間で発生しがちな教育の格差をなくす手段としても有効です。多くの企業では、新入社員の教育が各部署に任されており、内容や質に差が出やすいことが課題となっているもの。
これを解決するために、人事部が主導して統一されたオンボーディングプログラムを導入すると、新入社員全員が同じレベルでスタートを切れます。
たとえば、会社の基本方針や業務プロセス、コンプライアンスなど、全員が共有すべき知識を学ぶ期間を設けるとよいでしょう。また、部署を超えた研修やプロジェクトを通じて、幅広い視野と知識を身につける機会を提供することも重要です。
3.オンボーディングとOJTの違い
オンボーディングとOJT(On the Job Training)は、どちらも新入社員の育成を目的としているものの、ポイントが異なります。
オンボーディングは、企業文化や職場環境に早く馴染むことを重視し、組織全体での適応を促します。一方、OJTは、実際の業務を通じて必要なスキルや知識を習得し、即戦力となることを目指すもの。
つまり、オンボーディングは組織全体への適応を重視し、OJTは具体的な仕事のスキル習得に焦点を当てているという点に大きな違いがあるのです。

OJTとは? 意味、教育や研修の方法、OFF-JTとの違いを簡単に
OJTとは、実務を通してマンツーマン指導により知識・スキルを身につける育成手法です。実務を通した研修となるためスキル・知識の定着化が早く、新人や未経験者の早期戦力化に期待できます。
OJTとは何かをふ...
4.オンボーディング実施のメリット
オンボーディングを実施すると、どのようなメリットがあるでしょう。ここでは、従業員側と企業側それぞれのメリットを見ていきましょう。
従業員側のメリット
従業員にとっては、以下のようなメリットがあります。
社員同士の交流により助け合える環境を作れる
オンボーディングを通じて、社員同士が自然に交流できる場を提供することで、助け合える環境を作れます。入社時に感じる不安や戸惑いも、他の社員とのコミュニケーションを通じて解消しやすくなり、早く職場に馴染むことも可能です。
たとえば、メンター制度を導入すると、新入社員は気軽に質問や相談ができる相手ができ、職場への適応が促進されます。また、異なる部署や経験豊富な社員との交流によって、知識の共有が進み、チーム全体が成長する環境も作られるでしょう。
モチベーションが高まる
社員同士の交流や、上司・メンターからのサポートは、自分が企業に期待されていることを感じやすくし、モチベーションの向上につながります。
新しい職場で自分が認められていると感じることは、社員にとって大きな励みとなり、仕事に対して積極的に取り組む意欲が高まるもの。社員一人ひとりの意欲が高まることで、組織全体のパフォーマンス向上も期待できるでしょう。
エンゲージメントが高まる
オンボーディングを通じて、成果が正しく評価され、周囲からの承認を受けることで、社員のエンゲージメントも向上します。たとえば、成果発表の機会を定期的に設けたり、小さな成功をみんなで共有して祝う文化を育てたりすることで、新入社員は自分の貢献が組織にとって価値あるものであると実感できます。
こうした経験が、仕事に対する誇りや組織への帰属意識を強め、長期的なコミットメントを引き出すのです。
企業側のメリット
オンボーディングを実施すると、従業員のモチベーションやエンゲージ向上を期待できるとともに、企業側にも多くのメリットをもたらします。ここからは、企業側のメリットを見ていきましょう。
新入社員の早期戦力化が期待できる
オンボーディングプログラムを通じて、新入社員が短期間で職場に慣れ、迅速に業務に取り組むことができるため、早期の戦力化が期待できます。また、同僚や上司とのコミュニケーションが促進されることで、チーム内での役割分担もスムーズに進みます。
従業員の定着率を向上できる
オンボーディングのもう一つの大きなメリットは、従業員の定着率を高められる点です。新しい環境にスムーズに適応できると、社員は組織に対する安心感や帰属意識を持ちやすくなります。
とくに最初の数か月は離職率が高い時期であるものの、適切なサポートを受けることで、職場に長く定着しやすくなるでしょう。
採用や人材育成コストを削減できる
新入社員が早期に戦力となり、離職率が下がると、ひんぱんな採用や新しい教育プログラムの実施が不要になります。これにより、採用にかかる広告費や面接のための人件費、教育にかかるトレーニング費用を削減可能です。
さらに、定着した社員が長く活躍することで、企業全体の人材育成が効率的になり、長期的なコスト削減にもつながります。
チームの生産性を向上できる
新入社員が早い段階で業務に慣れ、既存メンバーと協力して仕事を進めることで、チーム内の役割分担がよりスムーズに進行します。その結果、既存のメンバーは業務負担が軽くなり、専門性の高い業務に専念できるようになるでしょう。
また、新入社員が持つ新しい視点やアイデアは、従来のプロセスや作業方法の改善を促進することもあります。このように、チーム全体の創造性と効率性が高まることで、最終的には組織全体の生産性向上にもつながります。
5.オンボーディング成功のポイント
オンボーディングを成功させるためには、ただプログラムを実施するだけではなく、戦略的なアプローチが必要です。適切なサポート体制やコミュニケーションの仕組みも欠かせません。
ここでは、オンボーディングを成功させるための5つのポイントについて詳しく説明します。
- 人事担当者が信頼関係の土台を作っておく
- キャッチアップに必要な情報を集約する
- メンター制度導入を導入するなどサポート体制を整備する
- スモールステップ法を意識する
- 上司・同僚とのコミュニケーションの場を設ける
人事担当者が信頼関係の土台を作っておく
新しい職場環境で不安を抱える社員にとって、人事担当者が安心感を与える存在となることが、早期適応に役立ちます。たとえば、入社前に面談や内定者交流会を通じて、企業文化や期待事項を伝えると同時に、新入社員の個性や強みも把握しておくとよいでしょう。
人事担当者が最初の「頼れる存在」となることで、組織との橋渡し役を担い、オンボーディングの成功をサポートします。
キャッチアップに必要な情報を集約する
新入社員が業務を円滑に進めるために、社内規則、サービスの内容、関係者リスト、業務の進め方など多くの情報が必要です。これらを整理し、かんたんにアクセスできる形で提供することで、社員が迷わずに業務に集中でき、スムーズに職場に適応できます。
また、業界の動向や会社の歴史、プロジェクトの概要など、より広い知識を段階的に提供することも重要です。社内イントラネットやナレッジシステムを活用すると、自主的な学習を促進し、新入社員の成長をサポートできるでしょう。
メンター制度導入を導入するなどサポート体制を整備する
メンター制度は、年齢や役職が近い社員が新入社員のサポート役を担う制度です。入社直後は「誰に相談すればいいか分からない」と悩むことが多いため、頼れる存在がいるだけで新入社員は安心して仕事に取り組めます。
メンターは業務指導だけでなく、職場のルールや社内の人間関係構築の手助けを行うことで、新入社員のスムーズな職場適応を支援します。こうしたサポート体制が、新入社員のスムーズな適応を促し、オンボーディングの成功に大きく貢献するのです。

メンター制度とは? メリット・デメリット、成功事例を簡単に
1.メンター制度とは?
メンター制度とは、年の近い先輩社員が新入社員や若手社員をサポート・育成する制度のこと。業務に関する支援だけでなく、人間関係やキャリアなど、幅広くサポートする点が特徴。不安や...
スモールステップ法を意識する
スモールステップ法とは、大きな目標を小さな達成可能なステップに分けて進める方法です。新入社員に大きな目標を与えると、達成のイメージがつかず、ストレスを感じてしまうことがあります。
スモールステップ法を活用して、段階的に成功体験を積み重ねることで、モチベーションを保ちながら自信をつけ、業務に取り組むことが可能になります。
上司・同僚とのコミュニケーションの場を設ける
オンボーディングの成功には、上司や同僚とのコミュニケーションが欠かせません。定期的なチームミーティングや社内イベントを通じて、新入社員が他のメンバーと交流できる機会を設けることが有効です。ランチ会や部署を超えたプロジェクトに参加することで、広い人間関係を築けます。
また、上司との1on1ミーティングを定期的に実施し、業務の進捗や課題、キャリアの展望について話し合うことで、より深いコミュニケーションが可能になるでしょう。こうした取り組みを通じて、新入社員が組織の一員としての自覚を深め、スムーズに職場に馴染むことが期待できます。
6.オンボーディングの進め方
オンボーディングを効果的に進めるには、明確な計画と段階的なアプローチが欠かせません。ここでは、オンボーディングの進め方を4つのステップに分けて解説します。
- 目標を設定する
- オンボーディングプログラムを作成する
- プログラムの実施とフォローを行う
- プログラムを見直し再実行する
①目標を設定する
まずは、新入社員に期待する成果や、習得してほしいスキル、組織への適応レベルなど、具体的な目標を設定します。たとえば、「3か月以内に基本的な業務を独力で遂行できるようになる」や「6か月以内に担当プロジェクトで自分のアイデアを提案できるようになる」など。
目標設定は、個々のスキルや経験を考慮しつつ、具体的で達成可能なものにしましょう。また、企業全体の目標と一致させることも大切です。これによって新入社員は、自分の役割が組織内でどのような位置にあるのかを理解できるようになります。
②オンボーディングプログラムを作成する
目標が決まったら、それを達成するためにオンボーディングプログラムを作成します。このプログラムには、会社の方針や社内ルール、業務の進め方にくわえ、実際の業務に必要なトレーニングや各部署の特性に応じた指導を含めることが重要です。
人事部門だけでなく、各部署の管理職や先輩社員の意見を反映させることで、より実践的で効果的なプログラムになるでしょう。
オンボーディングの期間は、新入社員が徐々に業務に慣れることを目指し、3~6か月程度を基準とします。また、入社前からの流れを考慮して、全体で1年程度を設定するのが一般的です。
さらに、プログラムには明確なタイムラインと達成目標を設定し、進捗を定期的に確認できるようにすると、プログラムの質をさらに高められます。
③プログラムの実施とフォローを行う
作成したプログラムにもとづき、オンボーディングを実施します。新入社員が実際に業務に取り組む過程で、計画されたプログラムが順調に進んでいるかを確認し、必要に応じてサポートをすることが重要です。
たとえば、メンターや上司との1on1ミーティング、週次や月次のチェックインミーティングを行い、業務面だけでなく、精神面のサポートも行います。プログラム実施中は、新入社員の反応や理解度をみながら、状況に応じてプログラムの内容や進行速度を柔軟に調整します。
④プログラムを見直し再実行する
プログラムの実施後は、その効果を評価し、見直しを行うことが大切です。評価方法としては、新入社員へのアンケート調査や、上司やメンターからのフィードバック、目標達成度の分析などが考えられます。
目標が達成されていない場合は、その原因を突き止め、次回のオンボーディングに改善策を反映させます。こうした見直しを繰り返すことで、プログラムの質が向上し、今後の新入社員がより効果的に成長できる環境が整備されるでしょう。
7.オンボーディングプログラムの具体例
オンボーディングの取り組みは、入社前から行うことが一般的です。ここでは、オンボーディングプログラムの具体例を入社前、入社直後、入社数か月後の3段階に分けて紹介します。
入社前のプログラム
入社前のオンボーディングプログラムは、新入社員の不安を和らげ、入社に対する期待感を高める上で非常に重要です。
この期間中、内定者同士が交流できる機会を設けるだけでなく、人事部が新入社員と積極的にコミュニケーションを取り、不安を解消しておくことがポイント。入社前に実施するオンボーディングプログラムの具体例を紹介します。
<入社前のオンボーディングプログラムの例>
- 内定者研修
- 内定者インターンシップ
- 内定者交流会
- オンライン交流会
- 先輩社員や上司との懇親会
- 定期面談
- 会社見学
- 社内広報資料の送付
とくに、リモートワークを取り入れる企業の増加に伴い、オンラインで交流会を開催する企業も増えています。オンライン交流会は新入社員にとって、いつでもどこでも受けられる手軽さがあり、企業側としても交流会のための交通費や宿泊費などの出費を抑えられることがメリットです。
入社直後のプログラム
入社直後は、職場に慣れず、不安を感じやすい時期です。そのため、企業の独自の文化やルールなどを早く理解してもらうことにくわえ、新入社員の不安を解消し、人間関係構築に重点を置くとよいでしょう。
入社前に実施するオンボーディングプログラムの主な内容としては、下記が挙げられます。
<入社直後のオンボーディングプログラムの例>
- 社長や経営陣による企業理念やビジョンの講義
- 企業のルールや文化を学ぶ研修
- 業界知識や自社の特徴・強みについての理解を深める研修
- 各部署や施設の見学会
- ランチ会
- 歓迎会などの交流イベント
- OJT
- 個別面談
- 目標の設定とそのサポート
- 新人発表会
新人発表会では、大学時代や前職での経験をプレゼンすることで、既存社員との会話のきっかけを作れます。また、新人のスキルや業務レベルを把握する機会にもなるため、取り入れている企業も多いといえるでしょう。
入社数か月後のプログラム
入社から数か月後は、新入社員の定着度やモチベーションを確認し、引き続きフォローを行うことが大切です。初めに設定した目標を振り返り、その達成状況に応じて新たな目標を設定し、キャリアパスを意識した育成プランを提供します。
この時期には、配属先への不満や、キャリアのズレが原因で採用ミスマッチによる離職が発生することも。これを防ぐには、キャリア面談の実施が効果的です。
配属先の上司に相談しにくいことも想定して、人事部が相談に応じる体制を整えておくとよいでしょう。入社数か月後に実施するオンボーディングプログラムの具体例として、下記が挙げられます。
<入社数か月後のオンボーディングプログラムの例>
- 業務の振り返りと評価
- スキルアップ研修
- 他部署との交流会
- 社内プロジェクトへの参加
- キャリア面談
- 人事面談
- メンター制度の継続
8.オンボーディングの成功事例
さいごに、オンボーディングの成功事例について見ていきましょう。
LINEヤフー株式会社
LINEヤフーグループでは、社員が最大限の力を発揮し、組織全体の成長を促すため、社員の成長支援を最重要課題の一つとしています。そのため、新入社員が早い段階で活躍できるように、eラーニングや社内情報を提供し、業務に必要な知識を効率よく学べる環境を整備しています。
また、一定期間後にはフォローアップアンケートを行い、入社後の定着をサポート。さらに、受け入れ部門の準備にも力を入れており、新卒社員にはOJT担当者向けのトレーニングを実施。
中途入社社員の受け入れ部門にはメンター向けガイドを配布して、サポート体制を充実させています。
さらに、「オフィシャルセンパイ」という制度も導入しており、上司やOJT担当者とは別に、新卒社員が気軽に相談できる先輩社員を配置。オフィシャルセンパイは、定期的なコミュニケーションを通じて社内の人間関係や仕事の悩みなど、相談しづらい問題にも対応し、新入社員の早期定着をサポートしています。
参照:LINEヤフー株式会社「人材成長支援〜パフォーマンス最大化のための成長促進〜」
株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、完全リモート入社に対応するため、リモートオンボーディングにさまざまな工夫を重ねてきました。その一環として「オンボーディングポータル」を導入し、新入社員に必要な情報を一元化して提供。いつでも必要な情報にかんたんにアクセスできる環境を整えています。
また、経験豊富なメンターを配置し、新入社員が迅速に実務に取り組めるようサポートしています。「メンターランチ」という、関係構築が重要なメンバーと一緒にランチを取る制度も導入しており、リモート環境ではGoogle Meetを活用。
海外からの新入社員に対しては、時差を考慮してコーヒータイムを設けるなど、柔軟な対応を行っています。
さらに、オンボーディングの進捗を確認するために、技術分野ごとに独自のKPIを設定し、サーベイを実施。リモート環境でもオンボーディングの状況を定量的に把握し、適切なサポートができる仕組みを構築しています。
参照:株式会社メルカリ「すべての新入社員に素晴らしいオンボーディング体験を」リモートオンボーディングを成功させる施策 #メルカリの日々」
サイボウズ株式会社
サイボウズ株式会社では、新卒採用者向けに1年間、キャリア採用者向けに6カ月のオンボーディング期間を設けています。
多様なバックグラウンドを持つ人材が入社するため、各自のスキルや経験に応じた柔軟な対応ができるよう、明確なコンセプトをもとにプログラムを設計。通常、キャリア採用者には即戦力としての活躍が期待されるでしょう。
サイボウズでは、新たなメンバーが前職との文化やコミュニケーションの違いに戸惑うのは当然と理解し、急がせることなく、ゆっくりと職場に慣れることを重視しています。そのため、リラックスして業務に取り組めるよう、さまざまなサポートコンテンツが用意されています。
さらに、オンボーディングに関連する情報はすべてシステム上に集約されており、プロセスを効率的に進めることが可能です。
オンボーディング終了後も、社員がスキルを引き続き向上させられる環境が整備されており、これはオンボーディングのデジタル化によって業務の円滑化を実現した好例となっています。
参照:サイボウズ株式会社「職場を知るオンボーディングと学習支援」
評価業務の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!
人事評価を効率的に行うための活用方法が満載! カオナビの資料ダウンロードはこちら
◆資料内容抜粋 (全31ページ)
・人事評価システム「カオナビ」とは?
・人事のお悩み別 活用事例9選
・専任サポートについて など

