これを適切に行うためには、評価基準の明確さと公正さが求められます。また、フィードバックや目標設定を通じて、従業員の成長を促進する役割もあります。定期的に評価を行うことで、組織全体のパフォーマンス向上にも繋がります。
目次
1.人事考課とは?
人事考課とは、企業が従業員の業績や能力、仕事に対する姿勢を総合的に評価する制度です。一定期間の業務遂行状況や成果を、企業が定めた基準にもとづいて客観的に評価します。
評価結果は、昇給や昇進、配置転換などの人事決定に活用されます。評価の公平性を保つためには、基準を明確にし、全社員に対して同一の基準で評価を行うことが大切です。適切な人事考課は、従業員のモチベーション向上や組織の活性化にもつながります。
2.人事考課と人事評価の違い
人事考課と人事評価は、ほぼ同じ意味で使われることが多いものの、厳密には目的や視点に違いがあります。人事考課は、主に従業員の能力や成果をもとに評価を行う仕組みを指し、給与や昇進といった待遇面に反映するもの。
一方、人事評価はより広範な視点で、処遇面だけでなく、従業員の能力開発や適性なども評価し、フィードバックを行うプロセスを指します。なお、企業によっては、人事考課が人事評価制度の一部として扱われたり、両者を区別せず使用したりする場合もあります。
3.人事考課の目的
人事考課の主な目的は、従業員の能力や業績を適切に評価し、公平な処遇を提供すること。具体的には、従業員の貢献度や業績を公正に判断し、その結果を昇給や昇進、異動などの人事施策に反映させます。
公平で納得感のある評価により、従業員は自身の努力が評価されていると感じ、モチベーションが向上します。また、評価を通じて従業員の能力を正確に把握することで、それぞれに適したポジションに配置しやすくなり、組織全体の生産性を高められます。
4.人事考課は人事制度の1つ
人事考課は、人事制度の重要な要素の1つです。人事制度は一般的に、評価制度、等級制度、報酬制度の3つで構成され、これらは相互に関連し、企業の人材マネジメントを支える仕組みとなります。人事考課は、この中で評価制度の一部として機能するものです。
評価制度
従業員の成果や行動を評価する制度です。評価基準にもとづき、一定期間の従業員のパフォーマンスを評価し、その結果を報酬や等級に反映させます。これにより、従業員の職務遂行能力や業績が公正に判断され、適切な人事考課が行われます。

人事評価制度とは? 必要な理由、種類と仕組み、作り方を解説
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...
等級制度
従業員を職務内容やスキルにもとづいて階層化し、その等級に応じた処遇を行う制度です。等級制度には、役割等級制度、職能資格制度、職務等級制度などがあります。各等級には求められる能力や役割が定義され、それにもとづいて昇格や降格が決定されます。

等級制度とは?【3つの制度】メリデメ、作り方をわかりやすく
等級制度とは、従業員を能力や職務、役割によってランクわけする制度のこと。人事評価制度を構成する柱のひとつで、ベースとなるものでもあります。
等級制度について、その目的や各等級制度のメリット・デメリット...
報酬制度
報酬制度は、従業員の成果や貢献度にもとづいて給与やボーナスを決定する制度です。基本給や賞与、退職金などの手当を評価に連動させ、従業員に支給します。この仕組みによって、評価と報酬が結びつくため、公平性と納得感を高めることが可能です。
評価制度、等級制度、報酬制度は、密接に関連しています。そのため、評価制度を策定・改訂する際、評価基準や項目、方法の設定だけでなく、等級制度と報酬制度も合わせて見直すことが重要です。

報酬制度とは?【制度設計の進め方】事例、目的、種類
報酬制度とは、企業が従業員に支払う報酬のルール・仕組みです。報酬制度は単に従業員の働きに対する対価を支払うだけでなく、従業員のモチベーションアップや人材定着、人件費の最適化などさまざまな目的を持ちます...
5.人事考課の評価基準
人事考課の評価基準は、一般的に業績考課、能力考課、情意考課の3つに分類されます。実際の評価では、これら3つの基準を組み合わせて、総合的に評価することが大切です。
業績考課
従業員が一定期間に達成した業績や成果を評価する基準です。主に売上やプロジェクトの達成度、目標の達成率など、具体的な数値や結果をもとに評価します。業績考課は客観的な指標を用いるため、比較的公平な評価が可能です。
ただし、総務や経理などの間接部門では、営業や開発部門とは異なり、数値で測れる目標が立てにくい傾向にあります。そのため、あらかじめ成果の定義を明確にしておくことが重要です。
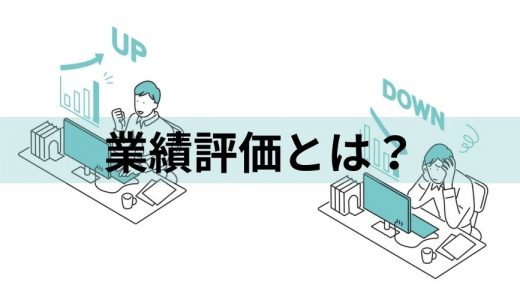
業績評価とは?【目標設定・書き方例】人事考課制度
目標管理・MBO運用の負担が大きく、通常業務が圧迫されていませんか?
カオナビならMBOに欠かせない目標設定、面談管理、評価を一気に効率化!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp ...
能力考課
従業員の能力に基づく評価基準です。この評価では、従業員が持つ「保有能力」、それを実際に活かす「発揮能力」、さらにまだ顕在化していない「潜在能力」の3つに区分して業務遂行力を判断します。
外部環境の変化や経済情勢の影響で、業績考課だけでは十分な評価が難しい場合もあります。そのため、個々の能力を評価する能力考課が重要な役割を果たすのです。
とくに、定量的な目標設定が難しい間接部門などでも適切な評価が可能となります。従業員のスキル向上やモチベーション向上にもつながる点がメリットでしょう。

能力評価とは? 項目と評価基準、目標・評価シートの書き方を解説
能力評価は人事評価項目の一つであり、職務遂行に必要なスキルや能力を評価する評価方法です。能力評価は定性的な評価項目であるため、導入する際はその性質や目的を理解し、適切な評価基準を設定して運用していくこ...
情意考課
従業員の仕事に対する姿勢や態度を評価する基準です。具体的には、協調性や責任感、積極性、チームワークといった、仕事を円滑に進めるために必要な意識や行動が評価対象となります。
この評価は、業績やスキルといった数値化しやすい要素ではなく、従業員の人柄や職場への貢献度など、見えにくい側面を判断します。考課者の主観が入りやすい傾向があるため、評価基準を明確に設定し、複数の評価者で評価を行うなどの工夫が必要です。

情意評価とは?【わかりやすく解説】項目例、評価基準
情意評価の成功に欠かせない面談管理と評価業務をまとめて効率化。
人事評価システム「カオナビ」で、評価の質を上げ、従業員エンゲージメント向上!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp ...
6.人事考課の進め方
人事考課は、一般的に以下の5つのステップで進めます。各ステップを詳しくみていきましょう。
- 目標を設定する
- 自己評価を実施する
- 上司・周囲のメンバーが評価する
- 企業内で設定された基準と照らし合わせて評価を行う
- フィードバックする
①目標を設定する
人事考課の最初のステップは、あらかじめ定められた評価基準をもとに、従業員自身が目標を設定すること。その後、上司との面談を通じて最終的な目標を決定します。目標は、具体的かつ測定可能であることが望ましく、組織の目標とも連動させることが重要です。
評価基準が1~5段階などで設定されている場合、各段階においてどの達成状況が該当するのかを明確にしておくことで、評価に対する不満や認識のズレを減らせます。
②自己評価を実施する
設定した目標に対する達成度や、業務遂行における課題などを従業員自身が評価します。この段階では、従業員自身が感じた成果や課題について正直に自己評価を行うことが重要です。自己評価は、上司との評価面談のための準備にもなります。
③上司・周囲のメンバーが評価する
自己評価の後、上司や周囲のメンバーがその従業員を評価します。日々の業務遂行状況や達成度をもとに上司が客観的に評価する際、場合によっては、チームメンバーや他の関係者からの意見も参考にするとよいでしょう。
この多面的な評価を通じて、従業員の総合的な能力や貢献度をより正確に把握することが可能です。
④企業内で設定された基準と照らし合わせて評価を行う
自己評価と、上司や同僚の評価にもとづき、企業が設定した評価基準と照合して最終的な評価を行います。バイアスの影響を避けるためには、複数の関係者で議論を重ねることが理想的です。
⑤フィードバックする
最後に、評価結果にもとづいてフィードバックを行います。具体的な事例を挙げながら、良かった点と改善が必要な点を従業員にわかりやすく伝えることが大切です。
さらに、今後の目標や期待についても話し合い、従業員が次の成長に向けて取り組むための指針を示します。フィードバックは一方的なものではなく、双方向のコミュニケーションの場として、従業員の意見や考えも積極的に聞く機会としましょう。
7.人事考課で使用される評価手法
人事考課では、さまざまな評価手法が用いられます。ここでは、代表的な4つの評価手法について説明します。
MBO(目標管理制度)
Management by Objectives and Self-controlの略で、マネジメントの創始者とされるドラッカー氏が提唱した概念です。本来は評価手法ではなく、目標管理制度を指します。
この制度では、上司が一方的に指示をして業務を遂行させるのではなく、従業員が組織の目標と結びつけながら自分の目標を設定し、上司やリーダーと話し合って調整します。
従業員が主体的に組織に貢献できる目標を考えるため、自主性が育まれるのが特徴です。また、目標達成度に基づいて評価されるため、従業員の積極的な取り組みが促進されるという利点があります。

目標管理制度とは? 意味や目的、メリット・デメリットを簡単に
マネジメントで有名な経営思想家ピーター・ドラッカーが提唱した、組織における目標管理制度(MBO)。この目標管理制度は、組織貢献と自己成長の両方が達成できる個人目標を設定させ、その達成度で評価を行う人事...
コンピテンシー評価
優れた業績を持つ人物に共通する行動特性(コンピテンシー)を基準に評価する手法です。評価項目には、リーダーシップ、コミュニケーション能力、問題解決力、リスクマネジメントなどが含まれます。
求められる行動が明確になるため、目指すべき方向性が具体的になるメリットがあります。ただし、適切な人物モデルの選定や分析、設計に時間や労力がかかるため、導入には十分な準備が必要です。
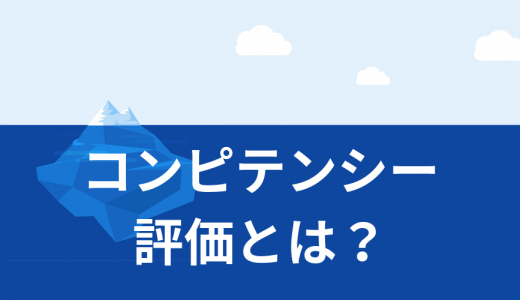
コンピテンシー評価とは? 項目例、メリット、導入手順を簡単に
コンピテンシー評価には、ハイパフォーマーの共通点の見える化が必須。
人事評価システム「カオナビ」で、コンピテンシー評価・モデル作成の問題を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.j...
バリュー評価
企業が大切にしている価値観や行動指針(バリュー)に従業員がどれだけ沿っているかを評価する手法です。この手法では、たとえ成果を出していても、バリューに沿った行動ができていなければ高評価は得られません。成績評価や能力評価とは異なる基準です。
バリュー評価は、従業員の行動を相対的に評価するので、情意考課の一環としても活用されます。従業員の行動が企業の価値観に合致しているかを評価することで、長期的に企業の成長を支える人材の育成につながるでしょう。
ただし、評価基準が抽象的になりがちなので、具体的な行動指標を設定することが重要です。

バリュー評価とは? 特徴やメリット、書き方と具体例を解説
近年、多くの企業が導入を進めている「バリュー評価」は、従業員の行動を企業の価値観やミッションに照らし合わせて評価する人事評価制度です。企業の一体感や従業員のモチベーション向上に寄与するため、注目されて...
360度評価
上司だけでなく、同僚や部下、さらには取引先など、多角的な視点から評価を行う手法です。多面的な評価により、従業員の強みや課題をより客観的に把握できます。
360度評価の特徴は、自己評価と他者評価を比較できる点で、とくに、リーダーシップやコミュニケーション能力などの対人評価に効果的です。
ただし、評価に不慣れな考課者の主観が入ったり、基準が統一されず評価のばらつきが生じたりすることがあるため、適切な教育が欠かせません。

360度評価とは? 目的やメリット・デメリットをわかりやすく
360度評価テンプレートで、Excelや紙の評価シートを楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp に...
8.人事考課で注意したい人事考課エラー
人事考課では、評価者の主観や偏見が入りやすく、それが「人事考課エラー」として現れることがあります。これらのエラーは、従業員の公正な評価を妨げる要因となるため、評価者は注意が必要です。代表的な人事評価エラーには以下のようなものがあります。
- ハロー効果
- 中央化傾向
- 寛大化傾向
- 逆算化傾向
- 論理誤差
- 対比誤差
- 期末誤差
①ハロー効果
特定の目立った特徴や業績が他の評価項目にまで影響をおよぼす現象です。たとえば、プレゼンテーション能力が高い従業員の他の能力も高く評価してしまうことがあります。
この効果を避けるには、各評価項目を独立して評価し、具体的な事実にもとづいて判断することが重要です。
②中央化傾向
評価者が極端な評価を避け、多くの従業員に平均的な評価を与えてしまうエラーです。この傾向は、評価の責任を避けたい気持ちや、従業員間の対立を避けようとする心理から生まれます。
適切な評価基準の設定や、評価者のトレーニングを行うことで、このエラーを軽減できます。
③寛大化傾向
評価者が本来よりも高い評価をつけてしまう傾向のこと。この傾向は、部下との関係を維持したい気持ちや、厳しい評価を避けたいという躊躇から生じることがあります。
しかし、過度に高い評価を与えると、評価対象者の成長を妨げたり、本当に優れた従業員のやる気を下げたりする可能性もあります。対策として考えられるのは、360度評価や匿名評価など、評価手法を工夫することです。
④逆算化傾向
昇給や昇進などの結果を先に決めてから、それに合わせて評価を調整する傾向です。この傾向は、評価の客観性や公平性を損なう可能性があるため、評価プロセスの透明性を高め、評価基準を明確にするなどの対策が求められます。
⑤論理誤差
ある特定の評価項目の結果が、論理的に関連のないほかの項目の評価に影響を与えてしまう誤りです。たとえば、勤務態度が良い従業員の業績も高く評価してしまうことがあります。
ハロー効果と同様、各評価項目の独立性を保ち、具体的な事実にもとづいた評価が重要です。
⑥対比誤差
ほかの従業員との比較によって評価が歪められる現象です。比較対象に対して優れている点や似ている点を実際以上に高く評価し、劣っている点や異なる点を過小評価してしまうエラーです。
たとえば、優秀な従業員の直後に評価すると、平均的な従業員も低く評価されてしまう可能性があります。この誤差を避けるには、絶対評価の要素を取り入れたり、評価の順序をランダム化したりすることが効果的です。
⑦期末誤差
評価期間の終盤の出来事や印象が、全体の評価に過度に影響を与えてしまう現象です。この誤差を防ぐには、評価期間全体を通じて定期的に記録を取り、それらを総合的に判断することが重要です。中間評価を導入すれば、より公平な評価が可能になるでしょう。

人事評価エラー(バイアス)とは? 種類と対策をわかりやすく
人事評価エラー(バイアス)とは、偏った思考により不公平な人事評価を行ってしまうこと。人事評価エラーは企業全体に悪影響を及ぼすため、早期の是正が必要です。
1.人事評価エラーとは?
人事評価エラーとは...
9.人事考課制度の導入の進め方
人事考課は通常、以下のステップで導入・運用します。ここでは、各ステップの内容について詳しく説明します。
- 人事考課の評価基準・項目・方法を策定する
- 考課に必要なシステムやフォーマットを整備する
- 運用方法を従業員に周知する
- 運用を開始する
①人事考課の評価基準・項目・方法を策定する
人事考課を導入する最初のステップは、評価基準、評価項目、そして評価方法を明確に策定すること。従業員の業績、能力、行動をどのように評価するか、そしてその評価をどのように処遇に反映させるかを決めます。
業績考課や能力考課、情意考課など複数の要素を組み合わせて、公平かつ透明性の高い評価制度を設計することが求められます。また、評価基準が曖昧にならないよう具体的な項目を設定することも重要です。
②考課に必要なシステムやフォーマットを整備する
評価基準が決まったら、実際に運用できるようにシステムやフォーマットを整備します。評価の頻度も重要なポイントで、半期ごとの評価が一般的です。できるだけ企業の状況に合わせて最適な頻度を検討するとよいでしょう。
人事考課シートは、かつては紙で行われていました。しかし現在ではExcelやクラウド型の評価システムを使う企業が増えています。
システムを導入する際は、操作性やほかの人事システムとの連携を考慮し、評価の記録や集計が効率的に行えるように整備します。さらに、個人情報の保護を徹底するため、セキュリティ面にも十分配慮しましょう。
③運用方法を従業員に周知する
新しい人事考課制度を導入する際は、全従業員に対して十分な説明を行うことが大切です。制度の目的や評価基準、評価方法、結果の活用方法などを明確に伝えます。
説明会の実施やマニュアルの配布、イントラネットでの情報共有など、複数の手段を活用して周知を徹底します。この段階での説明が不十分だと、従業員が制度に不安や不信感を抱く恐れにあるため、質問を受け付ける機会を設け、評価を円滑に進めるための準備を整えましょう。
とくに評価者となる管理職に対しては、評価の公平性や客観性を保つための研修を実施することが望ましいです。
④運用を開始する
全ての準備が整ったら、いよいよ制度運用を開始します。運用開始後は、制度が適切に機能しているかどうかを定期的に見直し、必要に応じて改善をしましょう。
とくに、初期段階では評価基準やシステムの不具合が見つかることもあるため、柔軟な対応が大切です。従業員のフィードバックを収集し、制度の改善に活かしていくと、長期的に信頼される評価制度を維持できます。
10.人事考課システムとは?
人事考課システムは、従業員の業績や能力を評価し、その結果を効率的に管理するデジタルツールです。従来の紙ベースの評価に比べ、データの集計や分析を自動化できるため、評価プロセス全体をスムーズに進められます。
また、評価の透明性を高めるだけでなく、管理者の負担を大幅に減らすのも可能です。
機能
人事考課システムには、主に下記の機能があります。
- 評価運用の半自動化
- 評価シートのクラウド化
- 評価結果の集計
- 評価の進捗管理
- 評価調整
また、評価プロセス全体を一元管理し、各従業員の進捗状況や過去の評価データもかんたんに確認可能です。多くのシステムでは、スマートフォンやタブレットからアクセスもでき、時間や場所を問わず評価作業を行えることもポイントです。
導入効果
人事考課システムを導入することで、下記のような効果が期待できます。
- 評価業務にかかる時間を大幅に削減
- 正確なデータの集計や分析
- 従業員に対する適切なフィードバック
評価データがデジタル化されると、正確なデータの集計や分析が可能になり、評価の透明性が向上します。従業員に対しても迅速かつ適切なフィードバックが可能となり、従業員のモチベーション向上にもつながります。
さらに、管理者の負担が軽減され、ほかの業務に集中できる時間が増えることもメリットです。
導入事例:株式会社日産クリエイティブサービス
株式会社日産クリエイティブサービスは、人事考課システムを導入し、評価業務の効率化に成功しました。従来の紙ベースでの評価シートでは、多くの時間と手間がかかっていましたが、システム導入後は評価業務にかかる時間が9割削減。
また、評価シートの忠実な再現が可能で、既存の評価シートをそのままデジタル化できたことも成功のポイントです。この導入により、管理者の負担が大幅に軽減され、評価プロセス全体の精度が向上しました。
参照: 株式会社カオナビ「評価業務にかかる時間を9割削減! ポイントは評価シートの忠実な再現」

人事評価システムとは? 比較方法、機能、メリットを解説
Excel、紙の評価シートを豊富なテンプレートで楽々クラウド化。
人事評価システム「カオナビ」で時間が掛かっていた人事業務を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセス...
【大変だった人事評価の運用が「半自動に」なってラクに】
評価システム「カオナビ」を使って評価業務の時間を1/10以下にした実績多数!!
●人事考課表が自在につくれる
●相手によって見えてはいけないところは隠せる
●誰がどこまで進んだか一覧で見れる
●一度流れをつくれば半自動で運用できる
●全体のバランスを見て甘辛調整も可能
