裁量労働制を導入する場合でも、みなし労働時間が1日8時間の法定労働時間を超える場合には、36協定を結ぶ必要があります。
また、法定労働時間を超える労働時間についても、36協定の上限時間が適用されるので、みなし労働時間もこれを超えないことが求められます。
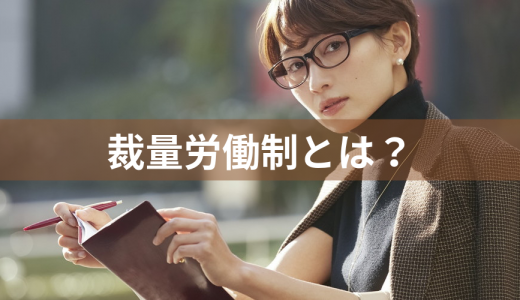
裁量労働制とは?【専門・企画業務型】残業代をわかりやすく
昨今話題になっている裁量労働制。会社員の働き方に関する非常に重要なキーワードですが、実際どういったものなのでしょうか?
ここでは、
裁量労働制の意味
裁量労働制と他の制度との違い
裁量労働制の制度詳...
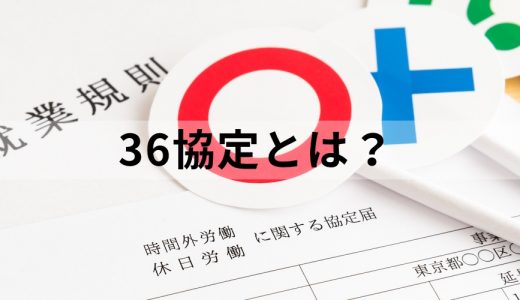
36協定とは? 残業時間の上限、特別条項などわかりやすく解説
36協定とは、従業員に時間外労働・休日労働をさせる際に締結しなければならない取り決めのこと。締結したからと無制限に時間外労働・休日労働させていいわけではなく、残業時間の上限や違反した際の罰則など、押さ...
36協定を締結する必要がある場合

裁量労働制を導入する場合には、まず会社側と労働者側とが労使協定を結び、みなし労働時間の規定などについての具体的な内容を定め労働基準監督署に届け出なくてはなりません。
その上で、みなし労働時間が法定労働時間の1日8時間を超える場合には、36協定を締結する必要があります。
みなし労働時間の算出には、実際の労働時間が反映されることが大前提となります。実際の労働時間とみなし労働時間がかけ離れたものにならないよう、十分な検討が必要です。
また、休日出勤をした場合は、裁量労働制であっても休日手当を支払わなければなりません。
36協定の上限時間にも注意

みなし労働時間を定める際には、36協定の上限時間にも注意が必要です。36協定では、一般労働者の残業時間を月間45時間まで、年間360時間までと定めています。
たとえば、1か月の平均出勤日数が20日間で、みなし労働時間を10時間とした場合、月間の残業時間は40時間となり、月間の残業上限時間はクリアしています。しかし年間の残業時間は480時間となり、36協定の残業上限時間を超えてしまいます。
みなし労働時間は限定的な期間ではなく、定常的な労働時間を定めるものですから、この場合10時間のみなし労働時間は適正でないことになります。
裁量労働制は労働基準法を遵守した上で運用する

裁量労働制は言葉のイメージから、労働時間の定めがないかのように捉えられることがありますが、労働基準法を遵守した上で運用することに変わりはありません。裁量労働者に対し、36協定を超える労働時間を強いるのは違法です。
裁量労働制の本来の目的は、専門性のある業務に就く労働者が、勤務時間にとらわれず効率的に働くことを支援することなので、長時間労働を誘発するような運用は避ける必要があります。

