予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
稟議書の書き方が分からず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。「記載内容が分からない」「上司になかなか承認してもらえない」と悩む方は少なくありません。作成方法や承認を得るためのテクニックを知っているかどうかで、仕事の進め方は大きく変わります。
そこで本記事では、稟議書の基本的な定義から具体的な作成方法、承認を得るためのポイントまで実務で使える情報を詳しく解説していきます。知識を深めて、稟議書のプロフェッショナルに一歩近づきましょう。
目次
稟議書とは?基本的な定義と役割

組織内の意思決定において重要な役割を果たす稟議書について、基本的な定義から実務での活用方法まで詳しく解説します。稟議書の定義や役割、必要となる場面、他の文書との違いといった基本的な知識を整理しながら、実務で活用できる具体的なポイントを確認してみましょう。
稟議書の定義
稟議書は、組織内での重要な意思決定を行うための公式文書です。個人の判断では決定できない事柄について、上司や経営層の承認を得るために使用されます。立案書や起案書と呼ばれることもあるでしょう。作成した稟議書は、上司および関係者に回覧してもらい承認を得ます。
稟議書が必要となる場面
稟議書が必要となる場面は、個人の判断だけでは決定できない事案が発生した際です。具体的には、以下のような場面が考えられます。
- 新規プロジェクトの立ち上げ
- 社内システムの導入
- 人材採用のための広告出稿
- 備品購入
- 出張計画 など
これらの共通点は、費用が発生する施策や人事部門が関与する企画であることです。特に予算規模が大きい案件や組織が縦割り構造の場合は、複数の決裁者による承認が必要となり、プロセスが複雑化する傾向があります。
決裁書との違い
稟議書と決裁書は、どちらも組織内で使用される文書ですが、その性質は大きく異なります。稟議書は、上司や関係者といった複数の承認を得るための文書です。複数の承認者から順次承認を得た上で、最終的に決裁の判断にいたります。
これに対し決裁書は、最終的な決裁を得るための文書として機能します。決裁書の承認者は決定権を持つ1名のみです。
【予実管理の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
予実管理システム『ヨジツティクス』を使って、経営データの収集・管理・分析が楽に!
●経営データの一元管理が簡単にできる
●属人的なエクセル業務をなくせる
●集計ミスやトラブルを防げる
●予実の差異を早期に発見し対策できる
●組織や役職別に閲覧・編集権限を制御できる
⇒ ヨジツティクスの資料を見てみたい
【例文あり】稟議書の書き方
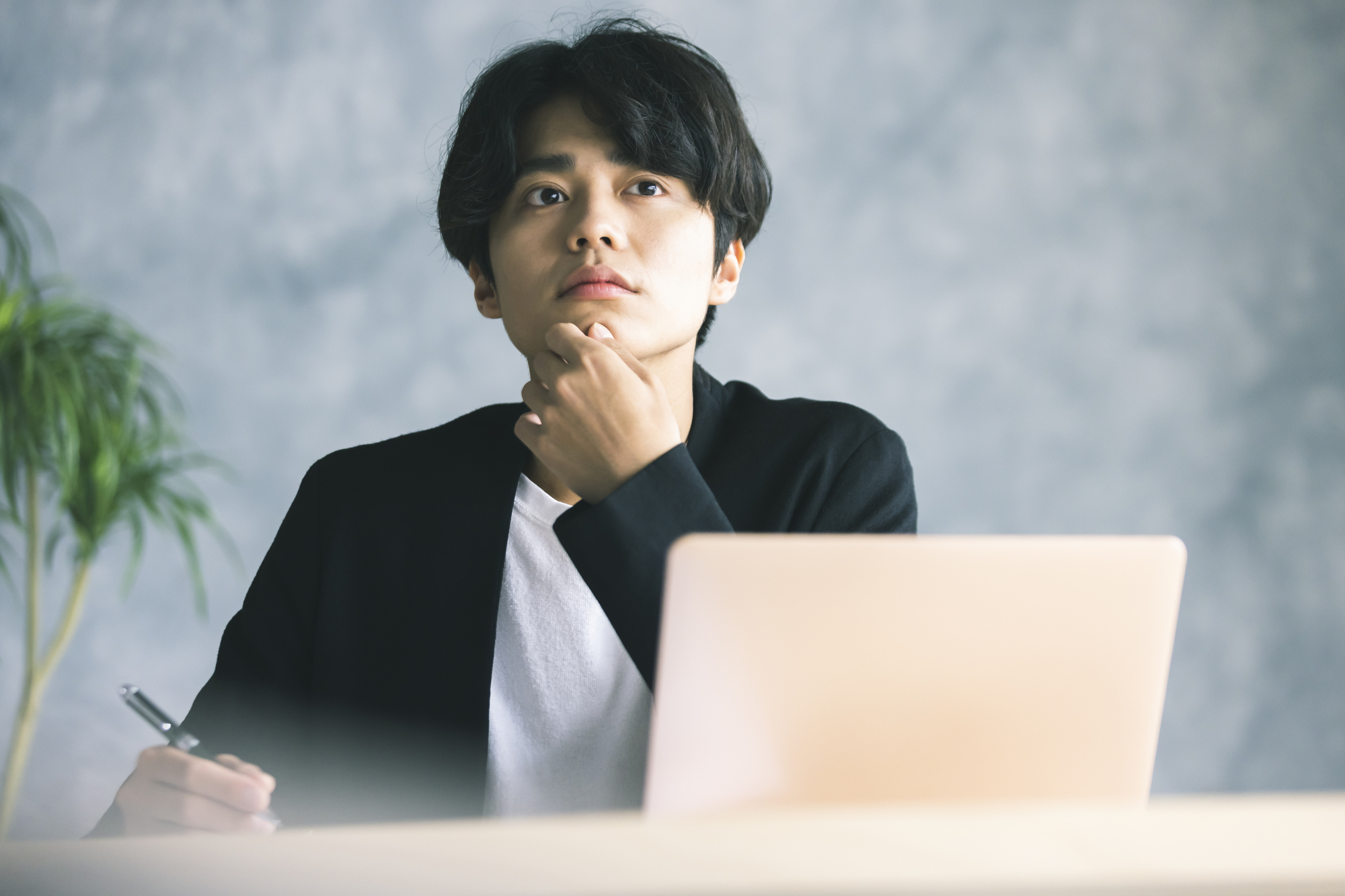
稟議書の書き方に明確な決まりはありません。しかし、承認者の理解を深め、スムーズな意思決定につなげるために必要な項目がいくつかあります。ここでは稟議書に盛り込む主要項目と具体的な記載例を確認していきましょう。
起案者名・日付・起案番号
稟議書は、「いつ」「だれが」提案したのかを明確にする必要があります。そのため、まずは起案者の部署名と氏名を記入しましょう。日付として、起案日(申請を行う日付)と決裁日(承認された日付)も記載します。
また、起案番号(決裁番号)を付与することで、稟議書の管理と特定を容易にします。企業ごとのルールを事前に確認した上で、必要に応じて記載しましょう。
件名
稟議書には、件名を付けます。稟議書の件名には、承認者が内容を一目で理解できる簡潔な表現が求められます。抽象的な表現を避けて具体的な目的や内容を明確に示すことで、承認者の理解を促し、スムーズな判断につなげられるでしょう。以下に記載例を紹介します。
- 顧客管理システム導入による業務効率化の件
- 営業担当の正社員採用の件
- ○○社との新規取引開始について など
稟議の内容
稟議書の本文では、目的や理由を明確に示す必要があります。稟議の目的は、承認者が内容を理解しやすいよう、具体的に説明すると効果的です。稟議の目的の記載例は以下のとおりです。
- 新たに顧客管理システムを導入し、業務効率化、顧客満足度の向上、営業活動の改善を目的とします
- 新規取引先「○○社」との契約締結による、販路拡大を目的とします。 など
提案の理由には、なぜその手段が必要なのかを説明します。背景や経緯を簡潔に記載しましょう。記載例は以下のとおりです。
- 現在顧客情報はExcel上で管理しておりますが、更新作業には毎月○時間かかり、他業務の進行に影響が出ています。顧客管理システムを導入し、作業の一部を自動化することで、○時間程度(人件費換算で○円程度)の削減につながります。 など
代替案との比較検討結果や、想定されるリスクとその対処方法なども併せて記載することで、判断の材料を提供できます。また、期待される効果を数値化して示すことで、説得力が増します。内容は箇条書きも活用し、専門用語を避けて誰でも理解できる表現を心掛けましょう。
金額
稟議書には購入費や必要経費なども記載します。物品購入の場合は、購入対象の商品と価格、数量、購入先なども記載しましょう。承認者が判断しやすいよう、見積書や製品カタログなどの資料を入手し、予算の内訳や支払条件を詳細に記載しておくことをおすすめします。
予算が決まっている場合は、その範囲内での提案であることを明記することで、承認を得やすくなります。予期せぬ追加費用が発生する可能性がある場合は、その旨と対応策も併せて記載しましょう。
経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード
稟議書の書き方|5つのポイント

経営層の理解を得て、スムーズな承認を実現するための稟議書を作成するには、いくつかのポイントがあります。ここでは、稟議書作成時のポイントを5つ紹介します。各ポイントを意識することで、より説得力のある文書となり、承認までの時間短縮も期待できるでしょう。
できるだけ簡潔にまとめる
稟議書は、承認者にとって読みやすい内容であることが重要です。そのため、文章は簡潔に、要点を絞って記載する必要があります。具体的には、目的や理由を冒頭で明確に示し、その後に詳細な説明を加えていく構成が効果的です。
例えば「パソコンの購入」の場合、「業務効率化のため、営業部門のパソコン10台を新たに購入したい」という結論を最初に示し、続いて現状の課題や具体的な効果を説明します。複数の承認者が確認するため、専門用語や略語は避け、誰が読んでも理解できる平易な言葉を使用することも大切です。
具体的な数値を提示する
稟議書の説得力を高めるには、具体的な数値やデータの提示が効果的です。例えば「業務効率が向上する」という抽象的な表現ではなく、「従来の作業時間が20%削減される」というように、定量的な数値で示すことで承認者の理解が深まります。
また、費用対効果を示す際も、「導入コスト300万円に対し、年間の人件費削減効果は500万円となる」など、具体的な金額で提示することで、投資の妥当性を判断しやすくなるでしょう。市場調査データや業界動向など、提案内容を裏付ける客観的な数値情報を盛り込むことでも、稟議書の信頼性が高まります。
マイナス面にも触れる
稟議書には、提案内容のメリットだけでなく、デメリットやリスクについても言及しましょう。例えば、新規システム導入の場合、初期投資コストや従業員の研修期間が必要となる点、データ移行に伴うリスクなど、想定される課題を具体的に記載します。
しかし、デメリットを示すだけでは承認を得ることは困難です。各課題に対する具体的な対処方法として、例えば段階的な導入計画や、専門家によるサポート体制の確保、バックアップ体制の整備といったリスク軽減策を併せて提示することで、実現可能性の高い提案として評価されやすくなるでしょう。
関連資料を添付する
稟議書には、承認判断の根拠となる関連資料を添付しましょう。具体的には、契約書や見積書、製品カタログ、市場調査データなどです。関連資料は、信頼性の高い情報源から得たものを選び、必要に応じて図表やグラフを活用して視覚的にまとめます。
また、複数の見積書を比較検討した資料や、導入効果を示す具体的なデータなども有用です。ただし、資料が多すぎると承認者の負担が増えるため、必要な情報に絞って添付しましょう。
事前に情報共有をしておく
稟議書の承認を円滑に進めるためには、事前の情報共有も大切なポイントです。稟議書を提出する前に、承認者に稟議の概要を口頭で説明しておくと、回覧がスムーズに進みます。事前に内容を共有することで、承認者の懸念事項を把握し、稟議書の内容を改善できる点もメリットといえるでしょう。
予実管理システム『ヨジツティクス』で、経営データの収集・管理・分析が楽に。
従量課金不要のリーズナブルな料金&専任サポート体制の安心感!
⇒
3分でわかるサービス資料ダウンロード
稟議書作成のメリット

ここでは、稟議書活用による3つのメリットについて解説します。会議を開く必要がない点、確認作業の効率化、そして多角的な視点による意思決定の質向上といった具体的なメリットを順に見ていきましょう。それぞれのメリットを理解することで、より効果的に稟議書を活用できるでしょう。
会議を開く必要がない
稟議書を作成すると、会議を開くことなく書面で承認を得られます。複数の関係者による会議を設定する場合、日程調整や会議室の確保、資料の準備など、さまざまな労力が必要です。しかし、稟議書を活用することで、これらの手間を大幅に削減できます。
確認作業を効率化できる
稟議書の大きな利点は、「いつ」「誰が」「何を提案したのか」が明確に分かることです。例えば会議での口頭説明では、複雑な内容が伝わりにくかったり、後から内容を確認する際に記憶が曖昧になったりすることがあります。
しかし、稟議書として文書化することで内容が整理され、関係者全員が共通の認識を持ちやすくなります。また、記録として残せるため、後に計画を立てる際の参考にもなるでしょう。
より内容の濃い意志決定ができる
稟議書を回覧する過程では、各部門の専門家が異なる視点から内容を精査します。例えば、営業部門からは市場性の観点、財務部門からはコスト面、法務部門からはリスク管理の視点など、多角的な検討が行われるでしょう。
その結果、当初の申請内容に対して建設的な改善提案や問題点の指摘が加わり、より実現性の高い計画へと練り上げられていきます。複数の専門家による検証を経ることで、最終的な意思決定の質が向上し、企業にとってより有益な結果をもたらすことが期待できます。
予実管理システム『ヨジツティクス』で、経営データの収集・管理・分析が楽に。
従量課金不要のリーズナブルな料金&専任サポート体制の安心感!
⇒
3分でわかるサービス資料ダウンロード
稟議書作成のデメリット

稟議書の作成・承認プロセスには、主に時間的な非効率性と責任所在の曖昧さという2つの課題があります。これらは組織の意思決定スピードや業務効率にも影響を及ぼす可能性があるため、適切な対策が必要です。以下では、稟議書作成における具体的なデメリットとその対応策について解説します。
作成や承認に時間がかかる
稟議書の作成には、調査・検討・情報収集といった多くの時間と労力が必要です。提案内容の妥当性や必要性を示すための具体的なデータ収集、関係者との事前調整、複数回の修正作業といった、さまざまな作業が発生するためです。
また、承認プロセスにおいても相応の時間を要します。複数の承認者によるチェックが必要となり、承認者が不在の場合や慎重な検討が必要な際には、さらに時間がかかることもあるでしょう。
作成から承認までの時間短縮には、フォーマットの活用や電子化された稟議システムの導入、関係者への事前の情報共有などが有効です。
責任の所在が不明確で曖昧になりやすい
稟議書は複数の承認者による合議制で意思決定が行われるため、各承認者の責任感が薄くなりがちです。また、後に何かしらのトラブルが発生した際に、責任の所在が不明確になりやすい課題もあります。
この問題を解決するためには、稟議書作成時に各承認者の役割と責任範囲を明確に定義しておくと安心です。さらに、承認者からの意見や判断根拠を記録として残すことで、後の検証や改善にも活用できます。
経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード
経営管理の効率化には予実管理がおすすめ!
企業経営において、的確な稟議書の承認判断を行うためには、リアルタイムでの経営状態の把握が欠かせません。そこで注目されているのが、予実管理システムの導入です。予実管理システムを活用することで、予算執行状況や経営指標をリアルタイムで確認でき、より的確な判断ができます。
ヨジツティクスは、部門別の予算編成から執行管理まで一元化でき、Webブラウザで随時確認できる予実管理システムです。導入によって経営状態が可視化されることで、稟議書の承認においても、予算残高や投資効果を踏まえた確かな意思決定に貢献します。
経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード
まとめ

稟議書は、組織内において個人の判断では決定できない事柄について、上司や経営層の承認を得るために使用する文書です。作成時には、簡潔にまとめたり具体的な数値を提示したりといったポイントを意識しながら、承認を得やすい稟議書を作成しましょう。
稟議書による承認プロセスをより効率的に運用するためには、予算執行状況をリアルタイムで把握できる予実管理システムの導入がおすすめです。業務の効率化や迅速な経営判断の実現を、ヨジツティクスがサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
【経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に!】
予実管理システム『ヨジツティクス』を使って、属人的なエクセル業務をなくして、経営判断を早く正確に!
●経営データの一元管理が簡単にできる
●属人的なエクセル業務をなくせる
●集計ミスやトラブルを防げる
●予実の差異を早期に発見し対策できる
●組織や役職別に閲覧・編集権限を制御できる
⇒ ヨジツティクスの資料を見てみたい

