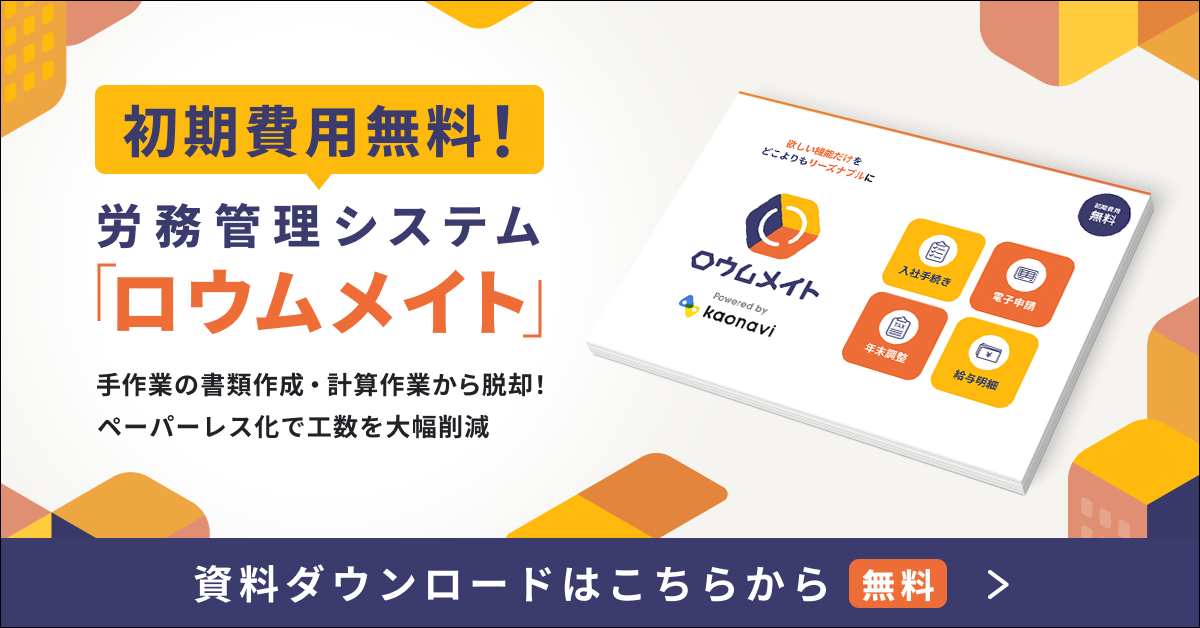労働条件とは、賃金や就業時間、就業場所などの働く上でのあらゆる取り決めのことです。労働条件は雇用する労働者に対して明示義務があり、明示する内容には定めがあります。違反した場合には罰金が科されるものもあるため、雇用契約を行う際は要注意です。
今回は労働条件について、明示義務や明示義務の一覧、労働条件の変更可否や注意点などを詳しく解説します。
目次
1.労働条件とは?
労働条件とは、賃金や就業時間、就業場所など、働く際の基本的な条件を指す言葉です。労働条件は雇用形態に関係なく、すべての労働者に対して取り決める必要があります。
パートやアルバイトは勤務時間や賃金(時給)が変更する機会が多かったり、正社員でも異動によって就業場所が変わったりすることもあるでしょう。とくに、給与や勤務時間は企業側と労働者側で認識の相違が生まれやすいため、労働条件を明確にして提示することが必要です。
2.労働条件の明示義務とは?
労働基準法第15条によって、企業が従業員を雇用する際に一定の労働条件を明示することが義務付けられています。これを労働条件の明示義務といい、従業員の雇用形態に関係なく効力を発揮します。
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければならない
出典:e-Gov法令検索「労働基準法第15条」
企業と労働者の間で結ぶ労働契約は、口約束でも成立するものです。しかし、それでは契約内容が曖昧になり、いざ入社してから聞いていた話と違うなどとトラブルを招く恐れがあるため、明示義務が課されています。
違反したらどうなる?
労働条件の明示義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科せられます。
また、パートタイマーについては、パートタイマー労働法第31条にもとづき、10万円以下の罰金の対象です。労働条件が明示されなかったことを労働者が労働基準監督署に通報することで、行政指導を受ける場合もあります。
労働条件を明示しない企業として悪いイメージがついてしまうリスクも考えられるため、労働条件の明示義務はしっかりと遵守しましょう。
3.労働条件の明示事項一覧
労働条件の明示事項には、「絶対的明示事項」と「相対的明示事項」の2つがあります。各明示事項を一覧でみていきます。
絶対的明示事項
絶対的明示事項は、必ず書面で明示しなければならない事項であり、一つも漏れることなく明示する必要があります。下記は、絶対的明示事項の一覧です。パート、アルバイトなどの短時間労働者や契約社員など期間の定めがある有期契約労働者は、絶対的明示事項の数が多くなります。
すべての労働者への絶対的明示事項
- 契約期間に関する事項
- 就業場所、従事する業務内容に関する事項とその変更範囲
- 始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩、休日、休暇に関する事項
- 賃金に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
有期労働者への絶対的明示事項
すべての労働者への絶対的明示事項に次の内容が追加されます。
- 労働契約の更新有無、その判断基準に関する事項
- 昇給、退職手当、賞与の有無に関する事項
- 雇用管理の改善などの相談窓口に関する事項
- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(更新のタイミングごと)
相対的明示事項
相対的明示事項は、企業の制度として定めがある場合に記載が必要な項目です。定めがある場合には、漏れなく記載する必要があります。下記は、相対的明示事項の一覧です。
- 退職手当に関する事項
- 賞与等臨時に支払われる賃金に関する事項
- 労働者に負担を求める食費や作業用品などに関する事項
- 安全・衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償に関する事項
- 表彰や制裁に関する事項
- 休職に関する事項
相対的明示事項は定めがある場合に明示が必要ですが、絶対的明示事項のように書面での通知が義務付けられているわけではありません。しかし、労使間のトラブルを防ぐためにも書面で明示することがおすすめです。
4.労働条件通知書と雇用契約書の違い
労働条件通知書と雇用契約書は、どちらも入社にあたって労働者に提示するものです。両者の違いは、以下2つのポイントにあります。
| 労働条件通知書 | 雇用契約書 | |
| 作成義務 | あり | なし |
| 書面の役割 | 労働条件を通知するため | 労働条件に双方が合意したことを証明するため |
労働条件通知書は法律で作成・交付が義務づけられており、企業側が労働者に対して一方的に労働条件を通知する役割を持ちます。一方的に提示できるものであることから署名や捺印箇所がなく、労働条件に合意したかを証明することはできません。
雇用契約書は作成義務がないため作成・交付は必須ではないものの、双方が労働条件に合意を得たことを証明するためにも作成し、労使間で締結しておくことがおすすめです。

労働条件通知書とは?【書き方(記入例)】テンプレ
企業が労働者の採用を決定した場合、当該労働者に労働条件通知書を交付しなければなりません。しかし、労働条件通知書とは何でしょうか。
労働条件通知書とは何か
労働条件通知書の書き方や見本
労働条件通知書...
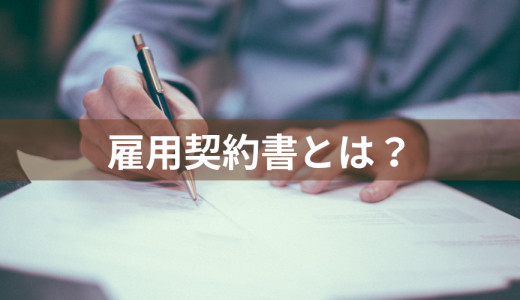
雇用契約書とは?【もらうタイミング】雛形、記入例
使用者が、労働者を雇い入れる際に交付するのが雇用契約書。類似する書面に労働条件通知書という書面もあります。
使用者と労働者間にトラブルを起こさないためにも、これらの書面について、正しく理解することは非...
労働条件通知書兼雇用契約書とは
労働条件通知書兼雇用契約書とは、労働条件通知書と雇用契約書の双方の役割を兼ねた書類です。労働条件通知書と雇用契約書が一つの書類にまとめられます。
雇用契約書は作成義務がないものの、トラブル防止のためにも作成・交付し、締結すると安心です。一つの書類にまとめられていれば、雇用契約書の作成・交付忘れの防止にも役立ちます。
5.労働条件の変更は可能?
労働条件の変更は、従業員の合意の上で可能です。労働条件の変更については、労働契約法第8条にて以下のように定められています。
労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法第8条」
合意のうえであることが必須であるため、企業側が一方的に変更できません。また、変更については合理的な理由が必要であり、就業規則に定められた内容を下回る内容に変更することは不可能です。
労働条件が変更できるケース
労働条件の変更が必要となる理由はさまざまで、なかには企業側のやむを得ない事情で変更が必要となるケースもあります。
変更内容が従業員にとって不利益となる可能性がある場合でも、労働条件の変更が妥当と認められれば労使間の合意がなくとも労働条件を変更することが可能です。
労働条件の変更が合理的であるかは、労働契約法第10条の定める下記ポイントから判断されます。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の就業規則の変更に係る事情
労働者の受ける不利益の程度については、多角的に厳しく判定されます。
とくに、労働時間や休日、休暇、昇給などに関する変更は、不利益の程度が大きくなるほど判定も厳しいです。賃金や退職金の減額などは、よほどの事情がない限り合理的と認められることはありません。
労働条件の不利益な変更に必要な手続き
従業員が不利益を被る労働条件の変更が必要な場合は、原則、従業員に個別に同意を得る必要があります。もしくは、労働組合との合意でも問題ありません。労働条件変更の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 従業員から個別に同意を得る、または労働組合との合意を行う
- 就業規則の変更方針を決める
- 同意書の作成、もしくは労働協約を締結
- 就業規則を変更し、労働基準監督署に届け出る
- 就業規則変更の旨を従業員に周知する
従業員に周知する際は、労働条件変更通知書を作成し、交付することがおすすめです。義務ではないものの、書面で通知することで後々の労使間のトラブル防止に役立ちます。
6.労働条件に関する注意点
労働条件に関する注意点をみていきます。
労働条件を明示するタイミング
労働条件を明示するタイミングは、労働契約の締結時です。労働契約の締結時と判定されるのは、一般的には採用の内定を出した時点となります。というのも、入社後の提示では、労働者が労働条件に合意したうえで入社できる状態だったとは証明できないからです。
そのため、労働条件通知書は内定通知と一緒に送付するとよいでしょう。内容を確認してもらい、後日雇用契約書に署名してもらうのも一つの方法です。
契約更新・再雇用時も労働条件の明示が必要
契約社員などの有期雇用者に対しては、契約更新ごとに労働条件の明示が必要です。また、定年後の再雇用制度などを利用して再就職する場合も再雇用後の労働条件を明示する必要があります。
同じ場所で就業するからと、労働条件を明示しないのは違反にあたります。たとえ、以前と同じ労働条件であったとしても、改めて労働条件通知書を作成して明示しましょう。
労働条件は求人票どおりの内容とは限らない
労働条件は求人票からも確認できます。しかし、求人票の内容は不特定多数に向けたものであり、個別の労働条件とは異なる場合があります。
そのため、企業側も採用時には改めて労働条件を明示する必要があり、労働者側もその内容をしっかり確認することが必要です。
求人票の労働条件を想定しており、いざ働き始めてから労働条件に違いがあったとしても、その責任は労働者にあります。
もし、求人票や面接で説明された労働条件と労働条件通知書に書かれた内容に違いがある場合には、雇用契約を締結する前にしっかりと確認しましょう。