仕事でミスした時やトラブルが発生した際には始末書を提出しなければいけません。始末書の書き方や例文、注意点などを解説します。
目次
1.始末書とは?
始末書とは、従業員が犯したミスや違反の事実関係を明らかにしつつ、反省・謝罪を促し、再発防止を誓約させる書類です。作成することで従業員の反省や再発防止の意識を高められます。また懲戒処分や処分に対する不服申し立ての裁判時に、従業員に非がある証拠として効力を発揮します。
2.始末書を作成するケース
前述の通り始末書は、従業員がミスや違反を犯すなどの不祥事を起こした際に書く書類です。始末書が作成される主な事由としては、下記のようなものが挙げられます。
- 就業規則等に違反した場合
- 業務命令に背いた場合
- 業務上のミスにより自社や取引先に損害を与えた場合
- SNSで社外秘の情報等を漏洩した場合
- 正当な理由がない遅刻や欠勤を繰り返した場合
- パワハラやセクハラなどのハラスメント行為を行った場合
3.始末書と顛末書、反省文の違い
始末書と似た文書に反省文や顛末書があります。一部企業ではほぼ区別なく使われていますが、
- 始末書はミスやトラブルの反省に重点が置かれる
- 反省文は自己の改善を促す
- 顛末書はミスやトラブルの事実関係のみを報告する
といった違いがあるのです。
始末書は事実と反省点を記入する
始末書は、仕事上のミスや過失、規程違反行為、トラブルが発生した際にその事実をすべて明らかにして、謝罪の意思を表明し、再発しないよう誓約する文書。自分の勤務する会社に提出するもので、顧客や取引先など社外の目に触れることは基本ありません。
始末書は、最初にトラブルの詳細をうそや偽りなく事実のみを説明します。次に、それらに対する自分の責任を明確にし、反省点を明記するのです。最後に今回のミスやトラブルから得た学びや再発しないよう今後の対策を明確に記載します。
顛末書との違い
顛末書とは、仕事上のミスや不始末、不祥事、トラブルが発生した際に、なぜそうなったのかを一部始終報告するための文書です。客観的な視点が必要で、ミスを犯した本人ではない立場の人による作成が最適とされています。
基本的に社内向けの報告書で、取引先や顧客など社外に向けてはほとんど用いられません。そのほか、役所や公的機関などに提出する報告書類(書類再発行の申請書など)の名称として使われています。
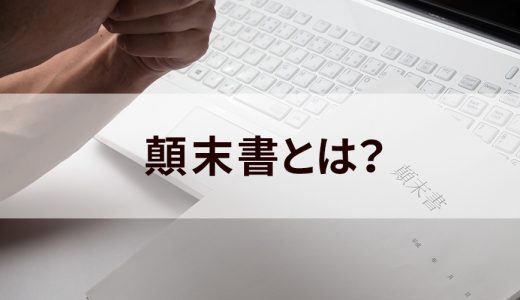
顛末書とは? 読み方、書き方と例文、始末書との違いを簡単に
顛末書とは、仕事上のミスなどトラブルが発生した際に会社にそれを報告する文書のこと。今回は顛末書の書き方や注意点、作成例について紹介します。
1.顛末書とは?
顛末書(てんまつしょ)とは、仕事において...
反省文との違い
反省文は自分の行動の改善を促すための文書、つまり個人的な報告書という趣旨があります。反省文は主に直属の上司に提出するものですが、始末書は、会社からペナルティ(懲罰)を受けることになります。
反省文とは、仕事上の失敗やミス、社内で迷惑に当たるような行為によって引き起こしたトラブルなどを振り返り、原因を考え分析し、解決策をまとめて過ちを繰り返さないよう改める気持ちを伝える文章です。

4.始末書の書き方、注意点
始末書はただ書けばよいわけではありません。謝罪の意思をうまく伝えるためにも、以下4つの注意点を押さえておきましょう。
- うそは書かない
- 年月日、日時を明確に記述
- 分かりやすく簡潔に書く
- 提出するタイミングを考える
①うそは書かない
始末書には仕事上で犯したミスや不始末、トラブルの内容を正直に書きましょう。保身のあまり言い訳がましくなり、事実を遠回しに書いてしまうのはよくありません。自分の過ちを正当化せず正直に事実のみを書くと、よい印象を与える始末書になります。
またトラブルが自分を起因としたものではなくても、同僚のせいにするなど他の人の責任にしてしまっては誠実さが伝わりません。自分の未熟さを素直に反省し謝罪の気持ちを伝えましょう。
②年月日、日時を明確に記述
始末書は何がどのように起きてしまったのか、読む人がすぐ理解できるように書きます。実際に起こったミスやトラブル、不始末の実際の内容を事の発端から整理して、全体を構成することから始めるのです。その際、時系列に順序立てて整理するとよいでしょう。
すべてを文章にまとめようとすると、言葉の選び方によっては詳細が伝わりにくくなります。年月日、日時を記入して箇条書きにすると、事実を漏らさずかつ分かりやすい文章になります。
③分かりやすく簡潔に書く
始末書は分かりやすく、簡潔により正確に書くことがポイントです。できるだけ下記のような流れで簡潔に書きましょう。
- 反省と謝罪の意を表す
- ミスやトラブルの内容を説明する
- 過失は自分にあることを認め反省の姿勢を表す
- 最後に再発を防ぐための対策を説明する
この流れで書くと、読む人がすぐ内容を理解できる簡潔な文章にまとまります。回りくどい文章やオブラートに包んだような言い回しは使わず、事実を客観的に書きましょう。
④提出するタイミングを考える
始末書を提出するよう言われたら、すぐに作成に取りかかり、なるべく早いタイミングで出しましょう。ミスやトラブルが発生し、どのように解決したのか、そして再発防止の手段が分かった時点で、速やかに提出するのです。
しかしトラブル解決に時間がかかる、原因がなかなか分からないといった際は、まず上司への報告が大切です。始末書の提出に同僚や後輩の目が気になる場合は、上司を別室に呼び、口頭で謝罪の上手渡しするのがよいでしょう。

5.始末書の例文
始末書を提出するように言われた場合、書き方に悩む人がほとんどでしょう。始末書は、ミスの発生経緯、発生原因と理由、ミスに対する反省と謝罪、再発防止策を明確にするのがポイントです。さまざまな始末書の例文を紹介しましょう。
遅刻したときの例文
遅刻したときの始末書は、遅刻の事実とその理由、今後遅刻をしないための対策を重点的に書きます。以下がその例文です。
この度は、●●年●月●日から●●年●月●日の間において、正当な理由もなく●回の遅刻をしました。これは私の自己管理能力の欠如が原因で弁解する余地もありません。
社会人として恥ずべき行為であり深く反省しております。今後は自己管理に努め、2度と遅刻することがないよう固くお誓い申し上げます。
交通事故を起こしたときの例文
仕事中に交通事故を起こしたり巻き込まれたりした場合は、事故状況と事故後の処理について正確に記載し、事故についての反省点と再発防止を誓います。以下がその例文です。
この度は、●●年●月●日午前●●時頃、●●市の●●交差点で前方不注意による追突事故を起こしてしまいました。幸い、双方共に怪我はなかったのですが、車は両方破損しましたので総務部に修理をお願いしています。
深くお詫び申し上げるとともに、今後は安全運転を心掛けて事故を起こさないよう誓います。
何かを紛失したときの例文
何かを紛失した際は、自己管理能力を問われます。事実関係をより明確に記して、反省点、再発防止対策をしっかり書きましょう。以下がその例文です。
この度、会社より貸与されている携帯電話を●●年●月●日に、帰宅途中の電車内で紛失しました件につき、多大なご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げます。
経過ですが、当日中に警察に遺失物届を提出いたしましたものの、警察からの連絡はない状況です。今後はこのようなミスを起こすことがないよう使用するとき以外は携帯電話を鞄に入れて細心の注意を払います。二度とこのようなことが起こらないよう誓います。

6.始末書による処分、クビの可能性は?
始末書を提出しないからといってクビに(解雇)されることはありません。始末書の提出枚数や、提出を拒否することも解雇の理由にはなりません。そもそも始末書の提出要求だけで、処分対応(ペナルティを与える)となるからです。
二重処分禁止の原則
社員が業務上のミスや不祥事を起こした際、始末書を提出させることで会社側は処分を下したことになります。
再度、解雇など別の処分を与えることは、「一事不再理の原則」(二重処分の禁止)に当てはまるためできません。「一事不再理の原則」とは、同一の事件について再度の審理を行うことができないという原則です。
刑事事件では一度刑罰を与えた事件について、再度刑罰を与えることはできません。これは企業でも同じです。
始末書提出後も改善が見られなかったら?
始末書を提出した後も、ミスを繰り返し行動が全く改善されなかった、もはや改善の見込みがないと認められる場合、就業規則に規定することで懲戒解雇や諭旨解雇など重い処分を与えられます。
この規定は過去に行った懲戒処分に対して重ねて処分を行うようにも見えるのですが、同じ不始末やミス行為に対して複数回にわたり処分を与える「一事不再理の原則」には反していません。
しかし、単に反省していないというだけで懲戒処分を科すことはできないのです。
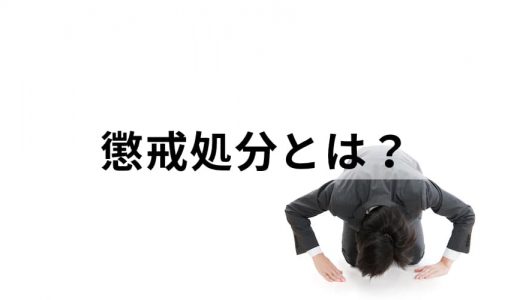
懲戒処分とは? 種類、判断基準の具体例、進め方をわかりやすく
企業は、秩序を乱した従業員に対して、問題行為に応じた懲戒処分を実施できます。万が一、従業員が懲戒処分に該当するような問題行為を行ったときに困らないためにも、
懲戒処分とは何か
懲戒処分の種類
懲戒処...

諭旨解雇/諭旨免職とは?【その他解雇との違いを解説】
いくつか種類がある解雇の中で、少し複雑な存在が諭旨解雇です。
そんな諭旨解雇の詳細について、
基本的な部分
詳細な特徴
注意点
まで幅広くまとめました。諭旨解雇を行う側、そして処分の対象となり得る...
そもそも始末書を提出しない場合は?
会社は社員に対して始末書を書くことは命じられますが、始末書の提出を強要することはできません。始末書には、ミスを起こした当人の反省や謝罪の意を記す文章だからです。
日本国憲法では「思想・良心の自由」というものが認められており、心の内は社員の自由で、始末書の提出を強要すると、この「思想・良心の自由」を侵害することになります。
しかし顛末書の提出拒否は、社員が業務命令に違反したと見なされ懲戒処分を科される場合があります。そのため始末書の提出を拒まれた場合は、顛末書の提出を命じることで、再発防止につなげることが可能です。

7.始末書提出後は誠意のある対応をしよう
業務上のミスやトラブルを起こしたことで、会社に金銭的な損失を与えてしまったり、社会的イメージを傷つけてしまったりなど、始末書を提出する理由はさまざまでしょう。いずれにせよ、自らの不始末を心から反省しお詫びする姿勢を伝えるのはとても重要です。
文章では、保身するような回りくどい説明はせず、トラブル内容の事実を簡潔に書きましょう。読む側にとって分かりやすく理解できるよう客観的に書く、つまり責任は自分にあることを認め、誠意ある対応を文章に表現することで信頼関係の回復につながります。

【人事評価運用にかかる時間を90%削減!】
評価シートの作成、配布、集約、管理を全てシステム化。
OKR、MBO、360度評価などテンプレートも用意!
●作成:ドラッグ&ドロップ評価シートを手軽に作れる
●配布:システム上で配るので、配布ミスや漏れをなくせる
●集約:評価の提出、差戻はワンクリック。進捗も一覧でわかる
●管理:過去の結果も社員ごとにデータ化し、パッと検索できる


