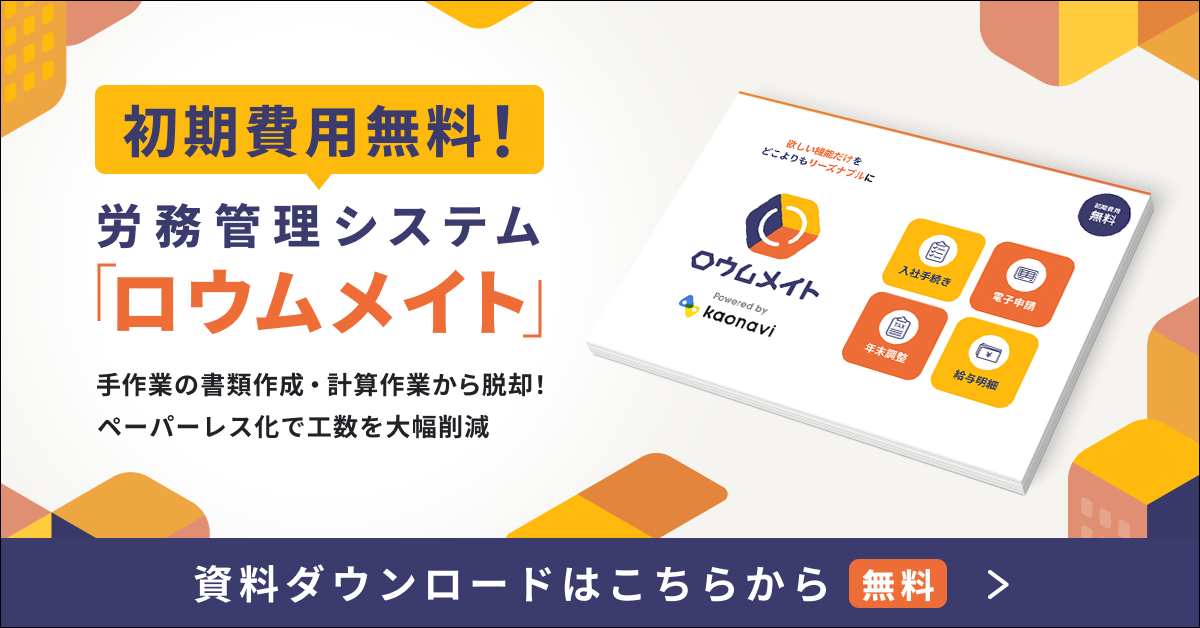「75歳以上の社員や扶養家族がいる場合、どのような社会保険手続きが必要なのか」ー企業の労務担当者の皆様は、この問題に直面したことがありませんか。75歳という年齢を迎えると、健康保険から後期高齢者医療制度への移行が自動的に行われ、会社側にはさまざまな手続きが発生します。適切な時期に正確な書類提出を怠ると、従業員や扶養家族の医療保障に空白期間が生じるリスクもあります。
本記事では、75歳以上の方々に関する社会保険手続きを期限や必要書類も含めて詳細に解説し、労務担当者の皆様の業務をサポートします。
75歳到達時の社会保険制度変更の基本知識

75歳になると社会保険制度上の扱いが大きく変わります。この節では、75歳到達時に自動的に行われる健康保険から後期高齢者医療制度への移行の仕組みと、扶養家族と社員本人それぞれに対する影響の違いについて解説します。
さらに、後期高齢者医療制度における保険料の計算方法や窓口負担の仕組み、2022年10月から導入された2割負担制度についても詳しく説明します。労務担当者として押さえておくべき75歳以上の社会保険に関する基本知識を身につけ、適切な手続きができるようにしましょう。
健康保険から後期高齢者医療制度への自動移行の仕組み
75歳の誕生日を迎えると、その日から自動的に健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行します。これは高齢者の医療の確保に関する法律に基づく仕組みで、本人の意思に関わらず自動的に行われます。
後期高齢者医療制度は、平成20年4月から開始された75歳以上の方専用の医療保険制度です。運営は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が行い、市区町村は窓口業務や保険料徴収を担当します。
この制度の財源は、公費が約5割、現役世代からの支援金が約4割、高齢者自身の保険料が約1割で構成されています。社会保険の被扶養者だった方も75歳になると独立した被保険者となり、新たに保険料負担が発生します。ただし、負担軽減措置として一定期間は均等割が軽減されるなどの配慮があります。
扶養家族と社員本人で異なる75歳到達時の影響
75歳になると、社会保険制度上の扱いが大きく変わりますが、扶養家族と社員本人では影響が異なります。
扶養家族が75歳になる場合、健康保険の被扶養者資格を自動的に喪失し、後期高齢者医療制度へ移行します。会社の労務担当者は「健康保険被扶養者異動届」を提出して、扶養から外す手続きを行う必要があります。この手続きは75歳の誕生日から5日以内に行わなければなりません。
一方、社員本人が75歳になっても会社で働き続ける場合は、健康保険の被保険者資格を喪失し後期高齢者医療制度に加入しますが、厚生年金保険は継続して加入します。会社は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出する必要があります。
また、社員本人が75歳未満で、その扶養家族が75歳以上になる場合、扶養家族は後期高齢者医療制度へ移行しますが、社員本人の健康保険には影響ありません。
| 対象者 | 75歳到達時の影響 | 必要な手続き |
| 扶養家族 | 健康保険の被扶養者から外れ、後期高齢者医療制度へ移行 | 健康保険被扶養者異動届の提出 |
| 社員本人 | 健康保険被保険者資格喪失、後期高齢者医療制度へ移行、厚生年金は継続 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の提出 |
後期高齢者医療制度の保険料と窓口負担の仕組み
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割」と所得に応じて決まる「所得割」の合計で算出されます。保険料率は2年ごとに見直され、都道府県ごとに異なります。保険料の軽減措置として、低所得者には均等割額の7割・5割・2割の軽減制度が設けられています。
医療機関での窓口負担は所得に応じて決定され、2022年10月からは現役並み所得者は3割、一般所得者でも一定以上の所得がある方は2割、それ以外の方は1割負担となりました。2割負担の基準は、課税所得28万円以上かつ年金収入とその他の合計所得が単身世帯で200万円以上(複数世帯で320万円以上)の方です。
窓口負担が2割になる方には、外来医療費の負担増を月3,000円までに抑える配慮措置があります。この措置は2022年10月から2025年9月までの3年間実施され、負担増が3,000円を超えた分は高額療養費として後日自動的に払い戻されます。
75歳到達前の事前準備と具体的な手続きフロー

75歳到達にともなう社会保険制度の切り替えは、複数の手続きが発生するため、事前準備と正確な手順の把握が欠かせません。ここでは、社員本人と扶養家族それぞれの場合における75歳到達時の手続きの流れを解説します。3か月前からの準備事項、必要書類、提出期限、さらに扶養家族への影響まで、労務担当者として押さえておくべきポイントを網羅的に説明します。
手続きの遅延は保険料の二重払いなどのトラブルにつながるため、タイムラインに沿った適切な対応方法を身につけましょう。社会保険制度における75歳以上の方への対応は、被保険者と扶養家族双方に影響するため、正確な知識と迅速な手続きが重要です。
75歳到達の3か月前から始める準備と確認事項
75歳の誕生日が近づいたら、3か月前から準備を始めましょう。まず、75歳になると健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に自動的に移行するため、手続きの確認が必要です。
準備すべき書類として、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」があります。高齢受給者証の返却準備も必要です。これらの書類提出期限は75歳の誕生日から5日以内です。
また、後期高齢者医療被保険者証は誕生月の前月頃に市町村から本人宛てに送付されるため、確実に受け取れるよう住所確認をしておきましょう。
さらに重要なのは、被保険者が75歳になると、その扶養家族(75歳未満)も同時に被扶養者資格を失うことです。扶養家族が国民健康保険に加入する必要がある場合は、14日以内に市区町村で手続きするよう案内しましょう。65歳以上75歳未満の扶養家族は保険料軽減措置が受けられるため、事前に市区町村に確認するとよいでしょう。
扶養家族が75歳になる場合の具体的な手続き手順
扶養家族が75歳の誕生日を迎えると、社会保険の被扶養者資格は自動的に喪失し、後期高齢者医療制度へ移行します。この制度変更は法律に基づく自動的なものであり、本人による加入手続きは不要です。
労務担当者は75歳の誕生日から5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を提出する必要があります。この届出書には、被保険者情報、扶養から外れる家族の情報、資格喪失日(75歳の誕生日当日)、資格喪失事由「後期高齢者医療制度該当」を明記します。
後期高齢者医療被保険者証は誕生月の前月頃に市区町村から本人宛てに直接送付されるため、住所変更がある場合は事前に届け出ておきましょう。被保険者証が届いたら記載内容を確認し、誤りがあれば速やかに市区町村窓口で訂正を依頼してください。
| 手続き項目 | 内容 | 期限 |
| 提出書類 | 健康保険被扶養者異動届 | 75歳の誕生日から5日以内 |
| 添付書類 | 健康保険証 | 同上 |
| 受け取り書類 | 後期高齢者医療被保険者証 | 誕生月の前月頃 |
| 資格喪失事由 | 後期高齢者医療制度該当 | – |
ロウムメイトでは、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届」を電子申請できます。
面倒な社会保険帳票提出業務をロウムメイトで効率化しませんか?
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
社員本人が75歳になる場合の資格喪失手続きと注意点
社員本人が75歳になると、健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。
この資格喪失手続きには「健康保険 被保険者資格喪失届」の提出が必要です。事業所を管轄する年金事務所または健康保険組合に、75歳の誕生日から5日以内に提出しなければなりません。提出時には、高齢受給者証の返却も必要です。
重要な点として、社員本人が資格喪失すると、75歳未満の被扶養者も同時に被扶養者資格を失います。この場合、被扶養者は国民健康保険への加入が必要となるため、社員に対して14日以内に市区町村での手続きが必要である点をしっかり説明しましょう。また、65歳以上75歳未満の元被扶養者は、国民健康保険料の軽減措置を受けられる可能性があります。
後期高齢者医療制度への移行手続きと保険証対応
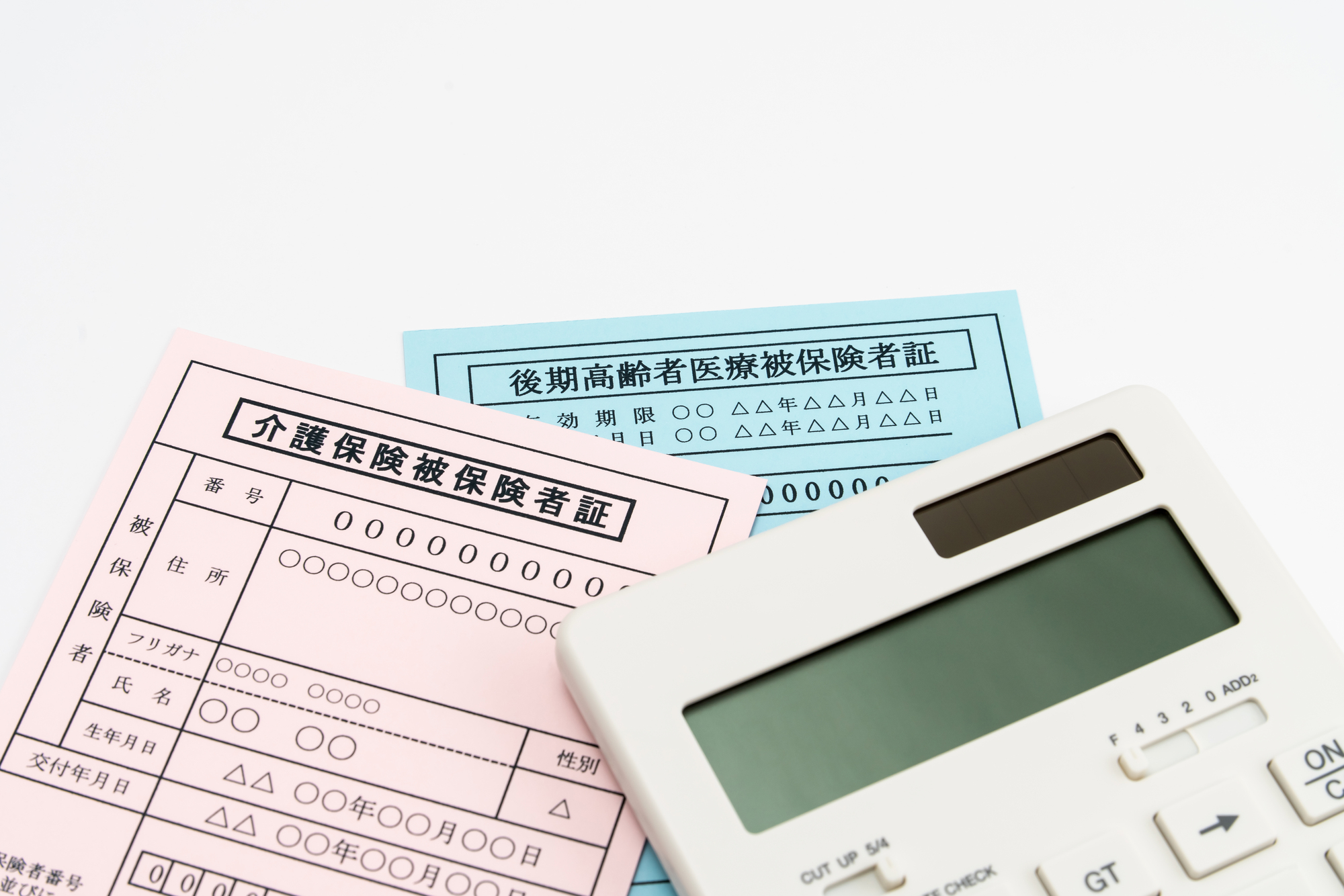
後期高齢者医療制度への移行にともなう手続きは、マイナンバーカードと保険証の一体化、資格確認書の受け取りと利用、期限超過時の対応など多岐にわたります。75歳以上の方が社会保険から後期高齢者医療制度へ移行する際には、保険証の取扱いも重要なポイントとなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットや、2024年12月以降の紙の保険証に代わる資格確認書の仕組み、窓口負担割合の決定方法など、労務担当者として押さえておくべき実務知識を以下で詳しく解説します。また、手続き期限を過ぎた場合の対処法についても触れていきます。
マイナンバーカードと保険証の一体化対応方法
マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、労務担当者が理解すべき重要な変更点です。2024年12月からは保険証の新規発行が停止され、マイナ保険証への移行が進められています。75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行する際も、このマイナ保険証の利用が推奨されています。
マイナンバーカードを保険証として利用するには、事前の登録が必要です。登録方法は主に4つあり、マイナポータルからのオンライン申し込み、区役所などの窓口での申し込み、セブン銀行ATMからの申し込み、対応医療機関に設置されているカードリーダーからの申し込みです。
マイナ保険証利用のメリットとしては、医師や薬剤師が薬剤情報や健診情報を確認できるため、より適切な診療や服薬管理が受けられる点や、高額療養費の限度額を超える支払いが免除される点などがあります。また、就職・転職・引っ越しをしても継続して利用できるため、後期高齢者医療制度への移行時もスムーズに対応できます。
なお、マイナンバーカードの紛失時には24時間対応の窓口があり、ICチップにはプライバシー性の高い情報は記録されないため、セキュリティ面でも安心です。
後期高齢者医療制度の保険証受け取りと利用開始手続き
令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行が停止され、代わりに「資格確認書」が交付されるようになりました。この資格確認書は医療機関窓口で提示することで、保険証と同様に一定の窓口負担で受診できる公的書類です。
資格確認書には申請により、「限度額情報(所得)区分」「長期入院該当日」「特定疾病情報区分」などを記載できます。これにより、高額な外来診療や入院の際に自己負担限度額までの支払いで済むほか、低所得者は食事代の減額も受けられます。
資格確認書は毎年8月1日から翌年7月31日までを1年度として更新され、7月下旬に住民票の住所地に送付されます。紛失・破損した場合は再交付申請が可能です。
なお、医療費の自己負担割合は前年の所得等によって1割、2割、3割の3区分で判定されます。世帯構成の変更や所得更正があると、年度途中でも変更される場合があるため注意が必要です。
手続き期限超過時の対処法と追加で発生する手続き
手続き期限を過ぎた場合でも、慌てずに速やかに対応することが重要です。75歳到達時の手続きが遅れた場合は、まず管轄の年金事務所や健康保険組合に連絡し、状況を説明しましょう。遅延理由を記載した理由書の提出を求められることが一般的です。
期限を過ぎても、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度への移行は自動的に行われていますが、被扶養者資格喪失手続きは早急に実施する必要があります。手続きの遅れにより保険料の過払いや二重加入の問題が発生する可能性があるためです。
特に扶養から外れる75歳以上の方の手続きが遅れた場合は、必要書類(健康保険被扶養者異動届など)を速やかにそろえ、年金事務所の指示に従って提出することでトラブルを最小限に抑えましょう。
| 手続き期限超過時の対応 | 必要な対応 |
| 年金事務所への連絡 | 状況説明と遅延理由の報告 |
| 追加書類の提出 | 遅延理由書の作成と提出 |
| 被扶養者資格喪失手続き | 速やかに「健康保険被扶養者異動届」を提出 |
| 保険料の調整 | 過払い保険料の還付手続きを確認 |
労務担当者向け高齢社員の社会保険管理とシステム活用法

高齢社員の社会保険管理は複雑で、特に75歳以上になると健康保険から後期高齢者医療制度への移行など重要な変化があります。
ここでは、厚生年金や雇用保険の取り扱いから、複数の高齢者を抱える企業向けの実務効率化まで、労務担当者が押さえておくべき社会保険管理のポイントと活用すべきシステムについて解説します。正確な手続きと効率的な管理体制の構築により、高齢社員と会社双方にとって最適な労務環境を整えましょう。
75歳以上の社員の厚生年金と雇用保険の取り扱い
75歳以上の社員を雇用する場合、厚生年金と雇用保険について正しく理解しておくことが大切です。まず、75歳以上の方は厚生年金保険の被保険者とはなりませんが、70歳以上で厚生年金適用事業所に勤務している場合は「70歳以上被用者届」を提出する必要があります。この届出に年齢上限はなく、80歳や90歳でも同様です。
雇用保険については、65歳以上の方も加入対象となります。2017年1月からは雇用保険の対象範囲が65歳以上に拡大され、年齢上限がなくなりました。つまり、75歳以上の方でも31日以上の雇用見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険に加入できます。
重要なのは、70歳以上の社員が在職中でも厚生年金を受給できますが、月額の年金と総報酬月額相当額の合計が47万円を超えると、年金が一部または全額支給停止になる可能性があることです。会社側は適切な届出と保険料計算を行い、高齢社員の処遇に配慮しましょう。
| 項目 | 75歳以上の社員の取り扱い |
| 厚生年金保険 | 被保険者とならないが「70歳以上被用者届」の提出が必要 |
| 雇用保険 | 年齢上限なし、条件を満たせば加入可能(31日以上雇用・週20時間以上勤務) |
| 年金受給と在職の関係 | 年金額と総報酬月額相当額の合計が47万円超で支給調整あり |
複数の高齢者を抱える企業の社会保険実務効率化テクニック
複数の75歳以上の社員や扶養家族を抱える企業では、社会保険手続きの効率化が重要課題となります。まず、75歳到達者を把握するための「年齢別社員・被扶養者リスト」を作成し、誕生日の3か月前にアラートが表示されるシステムを構築しましょう。
手続きの標準化も効率化の鍵です。75歳到達時の健康保険資格喪失届や70歳以上被用者届などの記入例をテンプレート化し、担当者間で共有します。資格喪失証明書の発行申請も同時に行うとよいでしょう。
電子申請システムの活用も大きな効率化につながります。労務管理クラウドサービスを導入すれば、高齢者関連の社会保険手続きを一元管理できます。75歳以上の方の後期高齢者医療制度への移行や扶養家族の手続きも漏れなく管理できるため、多くの高齢者を抱える企業にとって業務負担の軽減に役立ちます。
また、定期的な社内研修で最新の制度を共有し、手続きミスを防止することも重要です。
まとめ

75歳になると健康保険から後期高齢者医療制度へ自動的に移行します。被扶養者の資格も喪失するため、事前に手続きの準備が必要です。窓口負担割合は所得に応じて変更され、扶養条件も変わります。高齢社員を雇用する企業は、適切な社会保険管理とシステム活用が重要です。
本人と会社双方の負担を正確に把握し、保険証の切り替えなど必要な対応を行いましょう。円滑な移行には、自治体や勤務先への確認と早めの準備が鍵となります。
労務管理システム「ロウムメイト」なら従業員情報を一元管理できるため、従業員の年齢把握や被扶養者の把握が容易になります。また各種社会保険帳票の電子申請にも対応しており、提出業務を効率化できます。ぜひお試しください。