予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 【公式】https://www.kaonavi.jp にアクセスしてPDFを無料ダウンロード
消費税計算は日々の経理業務で欠かせない存在です。しかし、税率が10%と8%に分かれた軽減税率の導入により、計算方法がより複雑になりました。特に、端数処理の方法や納付税額の計算となると、「本当にこれで合っているのか」と不安になることも多いのではないでしょうか。
この記事では、消費税計算の基本から実務で役立つポイントまで、分かりやすく解説します。軽減税率制度やインボイス制度への対応についても触れていますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
消費税の基本的な仕組みと特徴
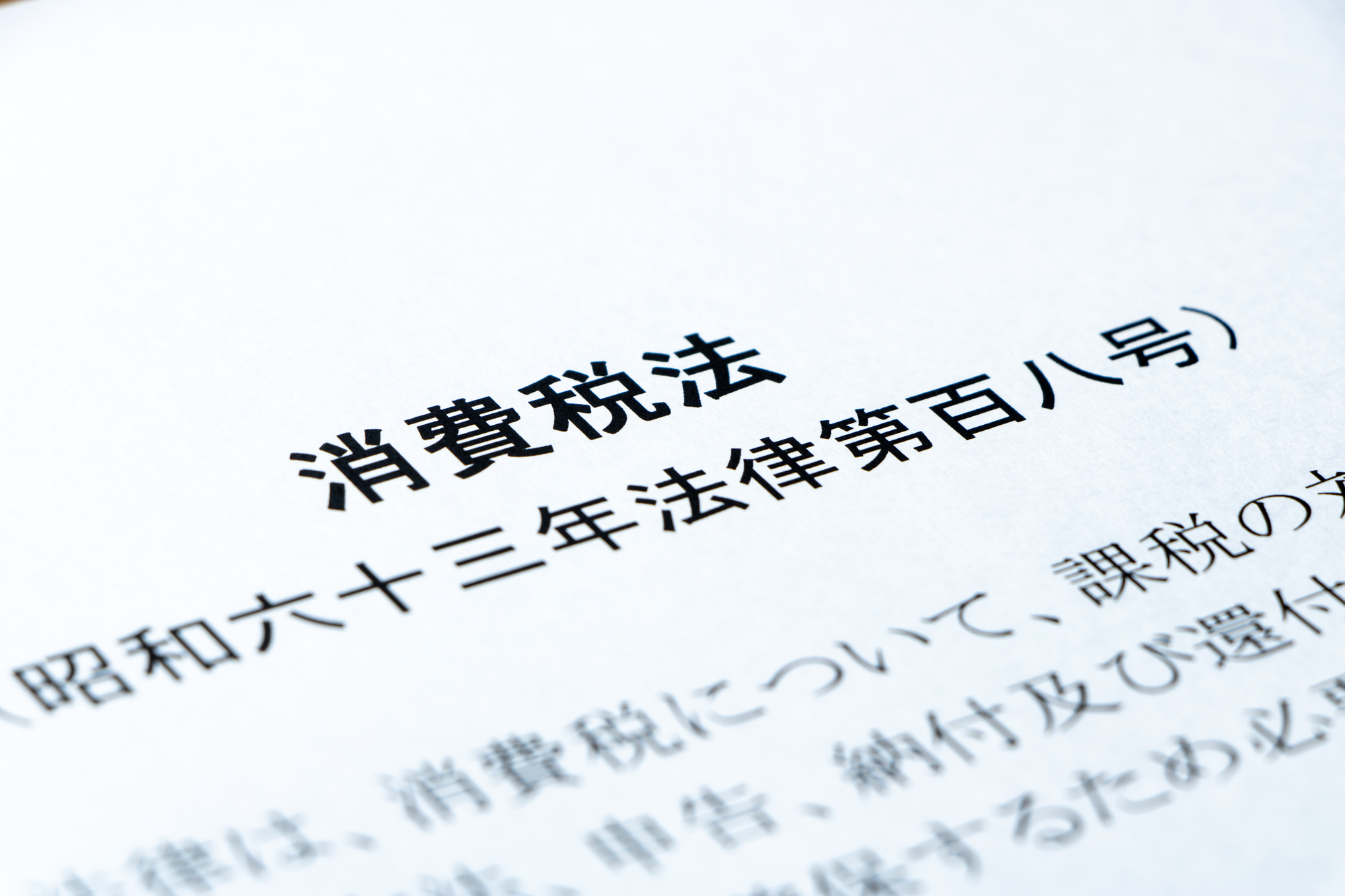
正しい消費税計算を行うために、まずは消費税の基本的な仕組みと特徴を確認しておきましょう。ここでは、商品やサービスの価格に上乗せされる消費税の仕組みから、課税取引と非課税取引の区別、さらには課税事業者と免税事業者の違いまで、消費税計算の基本となる知識を順を追って説明します。
間接税としての消費税の仕組み
税金の徴収方法には、所得税のように納税者自身が税金を納める「直接税」と、商品などの価格に上乗せして徴収される「間接税」があります。消費税は典型的な間接税で、商品やサービスの購入時に消費者が支払う税金を、事業者が預かって国に納める仕組みです。
最終的な負担者は消費者ですが、納税者は事業者という点が消費税の特徴です。事業者は取引の各段階で税を重複して納めることがないよう、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除して納付します。
消費税の対象取引と対象外取引
消費税の課税対象取引は、事業者が対価を得て行う資産の譲渡やサービスの提供が原則です。しかし、社会政策的な配慮などから、特定の取引は不課税または非課税とされています。主な不課税取引、非課税取引は以下のとおりです。
【主な不課税取引】
- 給与や賃金
- 補助金や助成金
- 保険金や共済金
- 配当金や出資分配金
- 損害賠償金
【主な非課税取引】
- 医療費
- 学費
- 土地の売買
- 住宅の賃貸料
- 火葬料や埋葬料
- 有価証券の譲渡
- 預貯金の利子
課税事業者と免税事業者の違い
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。また、特定期間(法人は前年度開始から6か月間、個人は前年1月~6月)の課税売上高が1,000万円を超える場合も課税事業者です。
一方、基準期間と特定期間の課税売上高がともに1,000万円以下の事業者は免税事業者として、消費税の納税が免除されます。ただしインボイス制度により、免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先から敬遠される可能性がある点に注意が必要です。
【予実管理の「めんどうくさい」「時間がかかる」を一気に解決!】
予実管理システム『ヨジツティクス』を使って、経営データの収集・管理・分析が楽に!
●経営データの一元管理が簡単にできる
●属人的なエクセル業務をなくせる
●集計ミスやトラブルを防げる
●予実の差異を早期に発見し対策できる
●組織や役職別に閲覧・編集権限を制御できる
⇒ ヨジツティクスの資料を見てみたい
消費税計算|基本の計算方法

消費税計算は、税抜価格からの計算、税込価格からの逆算、端数処理など、状況に応じて適切な方法の選択が必要です。以下では、経理実務で必要となる基本的な消費税の計算方法について、具体的な事例を交えながら解説します。
税抜価格から消費税額を計算する方法
消費税計算の基本は、税抜価格に消費税率を乗じる方法です。標準税率10%の場合、税抜価格に0.1を掛けることで消費税額を算出できます。例えば、税抜価格が1,000円の商品であれば、消費税額は100円です。軽減税率8%が適用される食料品などの場合は、税抜価格に0.08を掛けて計算します。
税込価格から消費税額を計算する方法
税込価格から消費税額を計算する場合は、割り戻し計算を行います。標準税率10%の場合は税込価格を1.1で割り、その差額が消費税額です。
例えば、税込価格1,100円の商品の消費税額は、1,100円から1,000円(1,100÷1.1)を引いた100円です。軽減税率8%が適用される場合は、税込価格を1.08で割って計算します。
端数処理の方法
消費税の端数処理は、事業者が適切な方法を選択できます。消費税を含む総額表示において、1円未満の端数が生じる場合、切り捨て、切り上げ、四捨五入のいずれかの方法を選択しましょう。事業者間の取引でも同様の原則が適用されます。
例えば、税抜価格が833円の商品に10%の消費税を加算する場合、消費税額は83.3円です。この場合、切り捨てなら83円(税込916円)、切り上げなら84円(税込917円)、四捨五入なら83円(税込916円)となります。
端数処理の方法は、取引の性質や事業の規模、会計システムの仕様などを考慮して決定することが望ましいでしょう。
予実管理システム『ヨジツティクス』で、経営データの収集・管理・分析が楽に。
従量課金不要のリーズナブルな料金&専任サポート体制の安心感!
⇒
3分でわかるサービス資料ダウンロード
消費税計算|軽減税率制度への対応

2019年10月の消費税率改定により導入された軽減税率制度について、その概要と実務上の重要なポイントを確認していきましょう。以下では、制度の基本的な仕組みから、消費税計算における実務上の留意点まで、段階的に説明していきます。
軽減税率制度の概要
2019年10月の消費税率10%への引き上げに伴い、軽減税率制度が導入されました。この制度は、生活必需品への税負担を軽減するため、飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読の新聞(週2回以上発行)に8%の軽減税率を適用するものです。
店舗での購入時には、商品によって税率が異なるため、イートインとテイクアウトの確認が必要です。スーパーなどで飲食料品購入時には、イートインの場合は10%、テイクアウトは8%が適用されます。
事業者は、取引を税率ごとに区分して記帳する必要があり、飲食料品を扱わない事業者でも、仕入れに軽減税率対象品目がある場合は帳簿上での区分が求められます。
軽減税率の対象品目と税率
軽減税率対象品目は、大きく2つのカテゴリーに分類されます。1つ目は、酒類・外食を除く飲食料品で、食品表示法に規定される食品が対象です。
おもちゃ付きのお菓子のような食品と食品以外が一体となった商品の場合は、「税抜価額が 1 万円以下であって、食品の価額の占める割合が 2/3 以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象」とされており、それ以外の商品は標準税率が適用されます。また、レストランでの食事やケータリング、宅配サービスは軽減税率の対象外です。
2つ目は、週2回以上発行される定期購読の新聞で、政治、経済、社会、文化などの一般社会的事実を掲載する新聞が該当します。これらの商品には8%の軽減税率(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)が適用され、それ以外の商品には10%の標準税率が適用されます。
(参考: 『消費税の軽減税意率制度が実施されます|国税庁』)
軽減税率制度における留意点
軽減税率制度では、事業者は適用税率ごとに売上・仕入れを区分して記帳する必要があります。取り扱う商品が8%と10%の両方の税率に該当する場合、それぞれの売上高を分けて管理することが求められるため注意が必要です。
帳簿やレシートには、商品の税率区分を明確に記載し、税率ごとの合計金額を表示します。請求書を発行する際は、税率ごとの明細と消費税額を記載しましょう。
予実管理システム『ヨジツティクス』で、経営データの収集・管理・分析が楽に。
従量課金不要のリーズナブルな料金&専任サポート体制の安心感!
⇒
3分でわかるサービス資料ダウンロード
消費税計算|インボイス制度への対応
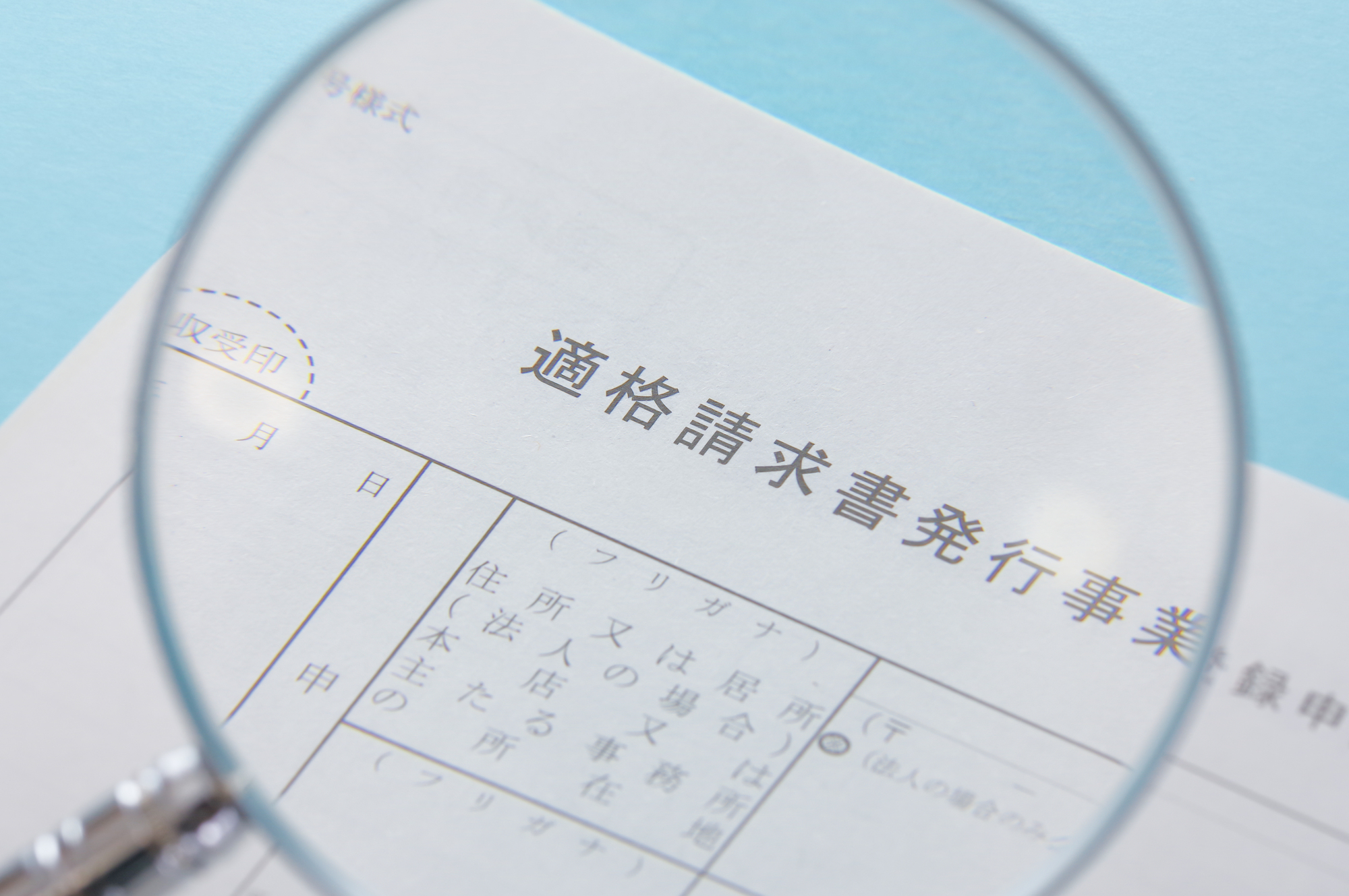
2023年10月からは、消費税の仕入税額控除を適用するためにインボイス(適格請求書)が必要になりました。これにより、消費税計算の正確性と透明性が高まり、事業者は取引先の登録番号確認や適切な記録保持が求められます。ここからは、インボイス制度の概要や注意点について見ていきましょう。
インボイス制度の概要
インボイス制度は、2023年10月1日から開始された新しい制度です。消費税の仕組みでは、最終的に消費者が負担した税額を事業者が納付します。具体的には、売上時に受け取った消費税額から、仕入れ時に支払った消費税額を差し引く「仕入税額控除」を行います。
この控除には、インボイスの保存が必要です。インボイスには、取引先の名称、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとの対価の総額、消費税額などの記載が必要ですが、小売業や飲食店などでは記載事項を一部省略した簡易インボイスの発行が認められています。
インボイス制度の注意点
インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために、取引先が適格請求書発行事業者であることの確認が必要です。取引先が免税事業者の場合、2029年9月30日までの経過措置期間中は、一定割合の仕入税額控除が認められます。
事業者は請求書の発行・保存体制を整備し、登録番号や税率ごとの消費税額などの必要事項を漏れなく記載する必要があります。特に、新規取引を開始する際は、取引先の登録番号を事前に確認し、システムに登録するフローを確立することが重要です。
小規模事業者向けには、課税売上高が1,000万円以下の場合、売上税額の2割を納税額とできる特例制度が用意されています。
経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード
消費税計算|納付税額の計算方法

消費税の納付税額を正確に計算するためには、基本的な計算方法から特例まで、幅広い知識が必要です。ここでは、一般的な納付税額の計算方法や簡易課税制度の活用方法、控除対象外消費税の取り扱いについて解説します。
消費税の納付税額計算の基本
消費税の納付税額計算は、売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除することで算出します。計算の際は、標準税率と軽減税率の複数税率に対応するため、売上と仕入れを税率ごとに区分する必要があります。売上税額の計算には、原則的な割戻し計算と特例の積上げ計算の2つの方法があります。
割戻し計算は、1年間の税込金額の合計から税抜金額を算出し、消費税を求める計算方法です。一方の積上げ計算では、インボイスに記載されている消費税の金額から消費税を求めます。
簡易課税の場合の計算方法
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択できる制度です。この制度では、売上にかかる消費税額に「みなし仕入率」を掛けることで、仕入税額を算出します。
みなし仕入率は業種によって異なる点が特徴です。卸売業は90%、小売業は80%、製造業は70%などと定められています。消費税の納付税額は、課税売上高に対する消費税額から、その金額にみなし仕入率を掛けた額を控除して算出します。
控除対象外消費税の取り扱い
税抜経理方式を採用し、課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合が95%未満の事業者は、仕入税額控除が制限されて控除対象外消費税額が発生します。資産に係る控除対象外消費税額は、原則として取得価額に算入し、償却費などとして処理します。
ただし、課税売上割合が80%以上の場合や金額が20万円未満の場合は、直接経費として処理可能です。資産以外の費用に係る控除対象外消費税額は、その事業年度の損金または必要経費として全額計上します。ただし、交際費等に係る分は、交際費等の額に加算して計算する点に注意しましょう。
経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード
消費税納付に関する確認事項

消費税の適切な納付のために、申告期限、中間申告制度、納税免除といった確認項目を覚えておくとよいでしょう。以下では、消費税納付に関する確認事項を3つ紹介します。納付の際に慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
申告・納付期限がある
法人の消費税の申告・納付は決算日の翌日から2か月以内に行う必要があります。例えば、3月31日が決算日の法人は、5月31日までに申告・納付を完了しましょう。申告は納税地を所轄する税務署に対して行い、同時に消費税の納付も必要です。
期限を過ぎて申告・納付を行った場合、期限日の翌日から納付日までの期間について延滞税が発生します。このため、決算日から逆算して消費税計算の準備を進め、期限内に確実な申告・納付ができるよう計画的に対応しましょう。
中間申告が必要なケースがある
消費税の年税額が48万円を超える場合は中間申告が必要です。中間申告の回数は、前年または前事業年度の消費税額によって異なり、48万円超400万円以下で年1回、400万円超4,800万円以下で年3回、4,800万円超で年11回と定められています。
消費税額が48万円~4,800万円の場合、申告・納付の期限は各中間申告対象期間の末日から2か月以内です。期限を過ぎると、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて計算された金額で申告があったものとみなされます。中間申告で納付した税額は、確定申告時に控除され、控除しきれない場合は還付されます。
納税が免除されるケースがある
課税売上高が1,000万円を超える事業者であっても、一定の条件を満たすと納税を免除されるケースがあります。例えば、事業開始から2年目までの法人は、原則として免税事業者です。
ただし、資本金1,000万円以上の新規設立法人や、設立1期目の前半6か月の課税売上高が2,000万円を超える法人などは設立初年度から課税事業者となることを覚えておくとよいでしょう。
経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード
予算管理の効率化にはシステム活用がおすすめ!
経理業務において、消費税計算を含む予算管理の効率化を検討しているなら、予算だけでなく実績も同時に管理できる予実管理システムの導入がおすすめです。ヨジツティクスは、予算管理を効率化するシステムで、部門別の予算編成から執行管理まで一元化できます。
導入前のデータも簡単に取り込めるため、過去のデータの確認や部門別経営データの把握などにも活用可能です。クラウドベースのシステムなので場所を選ばず利用でき、業務の効率化に大きく貢献します。
経営データの一元管理で、経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に。予実管理システム『ヨジツティクス』で、時間が掛かっていた予実管理を解決!
⇒ 3分でわかるサービス資料をダウンロード
まとめ

消費税は、課税売上に対する消費税額から課税仕入に対する消費税額を差し引いて計算します。消費税計算の際には、軽減税率制度の対応として、税率ごとの計算が求められる点に注意しましょう。
複雑化する消費税計算の負担軽減には、システム導入による効率化をおすすめします。ヨジツティクスは予算だけでなく見込みや実績も一緒に管理できる予実管理システムです。「リアルタイムで経営状況を見える化したい」といったご要望にもお応えします。
【経営判断に必要なデータの収集・管理・分析が楽に!】
予実管理システム『ヨジツティクス』を使って、属人的なエクセル業務をなくして、経営判断を早く正確に!
●経営データの一元管理が簡単にできる
●属人的なエクセル業務をなくせる
●集計ミスやトラブルを防げる
●予実の差異を早期に発見し対策できる
●組織や役職別に閲覧・編集権限を制御できる
⇒ ヨジツティクスの資料を見てみたい

