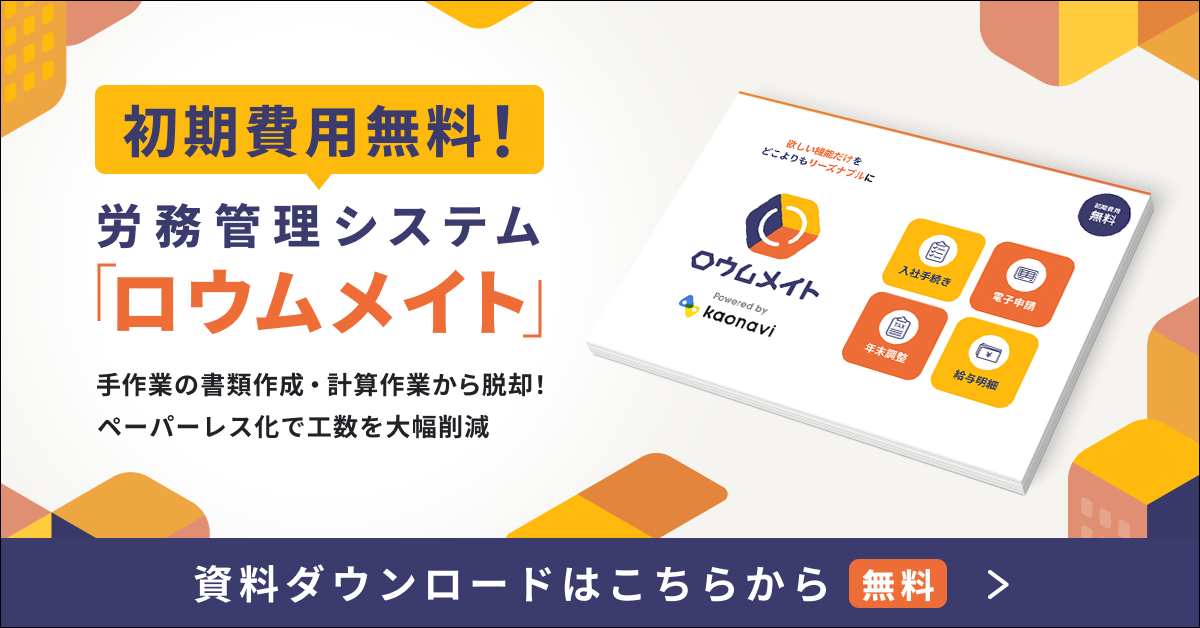企業の成長にともない、社内ルールの明文化は避けて通れない課題となります。しかし、多くの経営者や人事労務担当者は「就業規則は必要だと分かっているけれど、どう作ればいいのか分からない」というジレンマを抱えています。特に業種によって必要な規定は大きく異なるため、一般的なテンプレートをそのまま使用すると、思わぬトラブルに発展することもあります。
本記事では、あなたの会社に最適な就業規則テンプレートの選び方から、製造業・サービス業やパート・アルバイトなどさまざまな勤務体系の特性に合わせたカスタマイズのポイントまで、実務に即して解説します。
就業規則とは?基本的な役割と作成義務のある企業

就業規則は、企業経営の基盤となる重要なルールブックです。これから、就業規則の定義や経営上の重要性、作成が義務付けられる条件と届出方法、さらに小規模企業でも作成すべき理由について解説します。就業規則テンプレートを活用する際も、これらの基本的な知識を押さえておくことで、自社に最適な就業規則を効率的に作成できます。
労使間のトラブル予防や職場の秩序維持など、就業規則がもたらす具体的なメリットと、法的要件を理解することで、従業員が10人以上の企業だけでなく、小規模企業においても効果的な人事労務管理の基盤を構築できるでしょう。
就業規則の定義と企業経営における重要性
就業規則は、賃金や労働時間などの労働条件と職場の規律を定めた重要な規則です。就業規則の最大の意義は、労使間のトラブル予防にあります。労働条件や職場ルールを明確化することで、誤解や解釈の相違を未然に防ぎ、問題発生時の対応指針となるためです。また、公平な労務管理は社内モラルを向上させ、従業員の自律的な行動と組織への帰属意識を促進します。
さらに、キャリアパスや昇進基準の明確化は従業員の成長意欲を刺激し、優秀な人材の確保・定着にもつながります。法令順守の証明としても機能し、労働関連法令への適合を示すことで社会的信頼を高め、労働基準監督署の調査やトラブル時の法的根拠となります。
就業規則は単なる規則集ではなく、会社と従業員との約束事であり、企業理念や文化を定着させるための重要なツールとして、経営戦略上も欠かせない存在なのです。
就業規則作成が義務付けられる条件と届出方法
就業規則の作成と届出は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に義務付けられています。ここでの「常時10人以上」は、雇用形態を問わず、パートタイムやアルバイトも含めた従業員数で判断されます。一時的に10人を超えても、通常は10人未満に戻る場合は対象外です。
具体的な届出手続きとしては、作成した就業規則2部(会社保管用と提出用)と、従業員の過半数代表者による意見書を添えて、事業場を管轄する労働基準監督署へ提出します。複数の事業所がある場合、原則として各事業所ごとに届出が必要ですが、同一内容の就業規則を運用している場合は「本社一括届出制度」を利用できます。
この法的義務を怠ると、30万円以下の罰金が科される可能性があるほか、労働トラブル発生時に不利な立場に立たされることがあります。就業規則の作成・届出は、単なる法令順守だけでなく、円滑な組織運営のための重要な基盤です。
小規模企業でも就業規則を作成すべき3つの理由
小規模企業でも就業規則の作成は強くおすすめします。法的義務がなくても、就業規則を整備することで得られるメリットは大きいためです。
まず、労使間トラブルの予防が挙げられます。例えば、ハラスメント行為への対応や残業代の計算方法など、明確なルールを定めておくことで誤解や揉め事を未然に防止できます。曖昧な口頭での取り決めではなく、文書化された規則があれば、トラブル発生時にも迅速に対応できるでしょう。
次に、職場環境の秩序維持も重要なポイントです。統一されたルールにより、従業員間の不公平感を解消し、健全な職場環境を実現できます。これは従業員のモチベーション向上と信頼関係構築にも直結します。
さらに、将来の成長を見据えた準備としての側面もあります。従業員が増えて10人を超えると法的義務となるため、事前に整備しておくことで急な対応に追われることなく、事業拡大が円滑になります。
就業規則テンプレートの種類と基本的な選択基準

就業規則テンプレートを選ぶ際の基準と記載すべき項目について、厚生労働省が提供する無料モデルと民間テンプレートの特徴を比較しながら解説します。テンプレート選びでは、自社の規模や業種特性に適したものを選定することが重要です。
また、労働基準法で義務付けられている「絶対的記載事項」と、条件によって必要となる「相対的記載事項」の違いを理解し、就業規則に必ず含めるべき基本項目と任意で追加できる項目について詳しく見ていきましょう。適切なテンプレートをベースに、自社の実情に合わせたカスタマイズを行うことで、法令順守と効果的な労務管理の両立が可能になります。
厚生労働省のモデル就業規則と民間テンプレートの違い
厚生労働省のモデル就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場向けに無料で提供されている基本テンプレートです。労働基準法に準拠した基本項目を網羅しており、各企業は自社の実情に合わせて下線部分を修正するだけで利用できる可能性があります。定期的に法改正に対応して更新されますが、業種特有の条件への対応は限定的です。
一方、民間テンプレートには無料版と有料版の両方が存在します。有料版は特定業種向けのカスタマイズや最新法改正への迅速な対応が強みで、専門家によるサポートが付帯していることも特徴です。無料版も基本的な項目は押さえられていますが、法改正への対応スピードや詳細度は有料版に劣る場合があります。
どちらを選ぶ場合も、自社の規模・業種特性・予算を考慮して最適なものを選び、実態に合わせた修正を行うことが重要です。また、法令違反がないか確認し、労働者代表の意見聴取と労働基準監督署への届出手続きを必ず実施しましょう。
必ず含めるべき13の基本項目と任意記載事項
就業規則には法律で定められた記載事項を適切に盛り込む必要があります。まず「絶対的記載事項」として、労働時間(始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇)、賃金(決定方法、計算・支払方法、締め切り・支払時期)、昇給、退職(解雇事由を含む)に関する事項が必須です。これらは労働基準法第89条に明確に規定され、すべての就業規則に必ず含める必要があります。
一方、「相対的記載事項」は会社が制度を設ける場合のみ記載が必要となります。具体的には、退職手当、賞与、最低賃金額、食費・作業用品の負担、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁などが該当します。これらは企業の方針や事業特性に応じて記載を検討しましょう。
さらに、任意記載事項として服務規律や休職制度、副業規定なども盛り込むことで、より詳細な労働条件や職場ルールを明確にできます。就業規則テンプレートを選ぶ際は、これらの基本項目がカバーされているかを確認し、自社の実情に合わせてカスタマイズすることが重要です。
| 記載事項の種類 | 主な内容 | 記載義務 |
| 絶対的記載事項 | 労働時間、賃金、昇給、退職に関する事項 | 必須 |
| 相対的記載事項 | 退職手当、賞与、安全衛生、制裁など | 制度がある場合のみ必須 |
| 任意記載事項 | 服務規律、休職制度、教育訓練など | 任意 |
業種別に最適な就業規則テンプレートのカスタマイズ方法

業種や働き方の特性に合わせた就業規則のカスタマイズは、効果的な労務管理の鍵となります。テンプレートをそのまま使うのではなく、自社の業務実態に合わせて適切に修正することが重要です。
以下では、製造業・サービス業などの業種別の特殊条件と対応例、シフト制や変形労働時間制を導入する際の具体的な規定方法、そしてテレワークや副業といった新しい働き方に対応した最新の規定の書き方について解説します。
製造業・サービス業別の特殊条件と記載例
業種によって労働条件や就業環境は大きく異なるため、就業規則もそれぞれの特性に合わせたカスタマイズが必要です。
製造業では、交代制勤務や深夜勤務に関する規定を詳細に定め、残業や休日出勤の取り扱いを明確にすることが重要です。具体的には、「交代勤務者の休憩時間は〇時から〇時までとし、作業の都合により変更する場合は事前に通知する」といった記載が効果的です。
サービス業、特にホテル業では配膳会スタッフの勤務時間計算や、月間変形労働制の厳密な管理、夜勤対応などを規定することで労務管理が円滑になります。運輸・倉庫業界ではアルコールチェックや勤務間インターバルの明確化が重要です。
| 業種 | 特徴的な規定項目 | 記載例のポイント |
| 製造業 | 交代制勤務、安全衛生 | 機械操作の安全規則、交代シフトの休憩時間 |
| サービス業 | 変形労働時間制、深夜勤務 | 勤務間インターバル、夜勤手当規定 |
シフト制・変形労働時間制を導入する際の規定方法
シフト制や変形労働時間制を就業規則に導入する際は、法的リスクを回避するための正確な記載が不可欠です。
シフト制を採用する場合、単に「シフトによる」という記載だけでは不十分です。裁判例では、すべての勤務シフトパターンを就業規則に記載することが求められています。具体的には、①各勤務の始業・終業時刻、②シフトの組み合わせ基準、③シフト表作成の時期・手続きを明確に定める必要があります。
変形労働時間制を導入する際は、変形期間の総労働時間、各日・各週の労働時間、変形期間の起算日を明示しなければなりません。特に重要なのは、労働者の生活設計を損なわないよう配慮することです。
シフト作成・変更に関するルールは、労使双方で事前に合意しておくことが望ましく、確定したシフトの変更は労使の合意が必要です。こうした詳細な規定により、未払い残業代請求などの訴訟リスクを回避できます。
テレワーク・副業に対応した最新規定の書き方
テレワークや副業といった新しい働き方に対応した就業規則の整備は、現代の企業に不可欠です。テレワーク規定では、厚生労働省が公開しているモデル就業規則を参考に、労働時間管理の方法や情報セキュリティ対策を明確に定めることが重要です。
在宅勤務中の勤怠管理には、「始業・終業時刻は客観的な方法で記録し、管理者はシステムで確認する」といった具体的な記載が効果的です。
副業・兼業を認める場合は、原則容認の姿勢を示しつつ、労働時間の通算管理や健康状態の把握に関する規定を設けましょう。「副業・兼業を行う場合は、事前に『副業・兼業届出書』により申請し、会社の承認を得ること」などの手続きを明確にします。
また、秘密保持義務や競業避止義務に関する項目も盛り込み、「会社の正当な利益を害する恐れがある業務への従事は禁止する」といった制限事項を設けることで、企業秘密の漏えいリスクを軽減できます。
パート・アルバイト向け就業規則の作成ポイント

パート・アルバイトを雇用する場合、雇用形態に応じた就業規則の整備が不可欠です。パートタイム・有期雇用労働法に対応した内容を盛り込み、同一労働同一賃金の原則や無期転換ルールに配慮した就業規則テンプレートの選択が重要になります。
以下では、パート・アルバイト向け就業規則の必須記載事項、正社員との適切な待遇差の設定方法、複数雇用形態を一元管理する効率的な規則構成法について解説します。これらのポイントを押さえることで、法令順守と円滑な労務管理の両立が可能になるでしょう。
パート・アルバイト向け就業規則の必須記載事項
パート・アルバイト向け就業規則を作成する際は、パートタイム・有期雇用労働法に準拠した内容を盛り込むことが重要です。まず、「パートタイマー」の定義を明確にし、正社員との区別を就業規則テンプレートに明記しましょう。
パートタイマー就業規則には、労働時間、始業・終業時刻、休憩時間などの基本的な労働条件に加え、給与形態や支払方法、休日・休暇の付与基準を詳細に定める必要があります。特に注意すべきは同一労働同一賃金の原則で、正社員とパートタイマーの間に不合理な待遇差を設けると、行政指導や訴訟リスクにつながります。
また、無期転換ルールへの対応も必須です。有期雇用契約が通算5年を超えた場合、労働者からの申し込みにより無期雇用契約に転換する制度を就業規則に明記しましょう。ハラスメント防止策や個人情報保護についても、パートタイマーを含むすべての従業員に適用される規定として盛り込むことが大切です。
| 記載必須項目 | 内容・ポイント |
| パートタイマーの定義 | 適用対象者の明確化 |
| 労働条件の明確化 | 労働時間、給与、休日・休暇など |
| 均衡待遇 | 同一労働同一賃金への対応 |
| 無期転換ルール | 通算5年超えの契約転換制度 |
| ハラスメント防止 | 相談窓口と対応手順の明確化 |
正社員とパート従業員の待遇差の適切な設定方法
正社員とパート従業員の待遇差を設定する際は、同一労働同一賃金の観点から適切な基準が必要です。役付手当や資格手当は、同じ役職や資格を持つ従業員には雇用形態に関わらず同等に支給するよう就業規則に明記しましょう。精皆勤手当や時間外労働手当も、同じ業務内容であれば同一の基準で支給することが求められます。
福利厚生面では、家族手当や住宅手当、通勤手当は、転勤の有無など労働条件の違いに基づいて合理的な差を設けることが可能です。ただし、その根拠を明確に示せることが重要です。
賞与については、会社への貢献度に応じて支給するもので、パート従業員も対象とすべきです。同程度の貢献には同等の支給を行うよう規定しましょう。
また、勤続期間に基づく法定外休暇や教育訓練の機会も、正社員と同様に与えることが求められます。これらの点を踏まえ、就業規則では待遇差の根拠を明確に説明できる制度設計を心がけましょう。
正社員・パート・アルバイトを一元管理する規則の構成法
複数の雇用形態を効率的に管理するには、就業規則の一元管理が有効です。この方法では、「共通編」と「雇用形態別編」に分けて構成します。共通編には全従業員に適用される服務規律やハラスメント防止策を記載し、雇用形態別編には労働時間や給与体系など雇用形態ごとに異なる条件を規定します。
この構成法のメリットは、規則の総量削減による管理コスト低減と、全従業員への周知徹底が容易になる点です。例えば「第1章:総則(共通)」「第2章:正社員規定」「第3章:パート・アルバイト規定」といった章立てが効果的です。
ただし、「〇〇に関する規定は、アルバイトには適用しない」といった除外規定を明確にすることが重要です。このように整理することで、労働条件の違いが明確になり、同一労働同一賃金の観点からも適切な規則となります。
まとめ

就業規則は10人以上の従業員がいる企業での作成・届出が義務付けられていますが、小規模企業でも作成することでトラブル防止に役立ちます。厚生労働省のモデル就業規則を活用しつつ、自社の業種や雇用形態に合わせたカスタマイズが重要です。
特にパート・アルバイト向けには別規定を設け、テレワークや副業などの新しい働き方にも対応することが求められます。作成後は従業員への周知も忘れずに行い、定期的な見直しで法改正に対応していきましょう。
労務管理ツール「ロウムメイト」では、正社員からパート・アルバイトまで多様な雇用形態に対応し、雇用契約書などの各種誓約書類の締結を電子化できます。就業規則や雇用契約の見直しを行い、法制度に対応した働きやすい職場環境の構築を目指しませんか。