2019年4月から、すべての使用者に対して「労働者の年間5日の年次有給休暇取得」が義務付けられました。ここでは、対象者や義務化の内容や企業における対応方法などをご紹介します。
目次
1.有給休暇はどうして義務化されたのか?
年次有給休暇(有給休暇)は、賃金の支払いがある休暇のこと。一定期間勤務した労働者に付与され、原則として労働者から会社に取得請求を行います。
これまでの日本では職場への気遣いや休暇への抵抗感から、有給休暇の取得を諦めてしまう人も少なくありませんでした。しかし2019年4月に「年5日間の確実な有給休暇消化」が使用者(雇用者)に義務付けられたのです。

有給休暇とは? 付与日数や計算方法、繰越の上限をわかりやすく
有給休暇(年休)とは、従業員が心身の疲労回復やゆとりある生活を送ることを目的に取得できる休暇で、休暇でも賃金が発生します。従業員は有給休暇を取得する義務があり、企業は有給休暇を付与・取得を承認する義務...
義務化の理由とは?
有給休暇の取得が義務化された目的は、働き方改革を後押しし、ライフワークバランスの充実をはかるためです。
日本の有休消化率は平均50%と非常に低く、2017年に世界19か国対象に行われた「有給休暇国際比較調査2017」では、最下位となりました。諸外国との差は20%以上をマークし、有休消化率の底上げが火急の課題となっています。
また働き方改革を通じてワークライフバランスが求められるなか、正社員の長時間労働数はほとんど変化が見られていません。年5日間の確実な有休消化を義務付けて、有休未消化と長時間労働を代表する、仕事偏重の働き方を改善しようとしているのです。
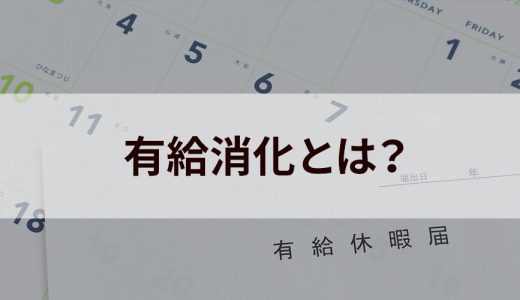
有給消化とは?【消化義務の日数・罰則】退職時の注意点
有給消化とは、従業員が保有する有給を取得すること。有給は従業員の心身のリフレッシュを目的とした制度であり、労働基準法の改正によって1年間で最低5日間の有給消化が義務化されました。
今回は有給消化につい...
2.有給休暇取得義務化の対象となる労働者とは?
有給休暇取得義務化の対象となる人は、有給休暇が10日以上与えられる労働者です。雇用形態による区別はありません。有給休暇が10日以上付与される人は年5日以上の有給取得が義務付けられ、違反した使用者には30万円以下の罰金が科されます。
フルタイム労働者
基本的にフルタイム労働者は、雇用形態にかかわらず、入社から6カ月経過すると有給取得義務の対象となります。正社員やフルタイムの契約社員は、入社から6カ月を過ぎて出勤率が8割以上の場合には有給が付与されるのです。
週5日以上または週30時間勤務のパート社員に関しても、入社して6カ月間の勤務継続実績があれば、年間10日の有休権利が発生します。
パートタイムで所定労働日数が週4日の労働者
週4日勤務の特定パートタイム労働者は、たとえば入社から3年6カ月間の継続勤務実績があって、かつ直近1年間の勤務率が8割以上であれば、年10日間の有休が付与されます。
条件を満たした特定パートタイム労働者が期限内に5日間の有休消化ができていない場合、使用者が有休取得日を指定して有給休暇を与える必要があるのです。
パートタイムで所定労働日数が3日の労働者
週3日勤務の特定パートタイム労働者は、たとえば入社から5年6カ月間の継続勤務実績があり、かつ直近1年間の勤務率が8割以上であれば、年10日間の有休が付与されます。有休の付与日数が10日以上の労働者は、有給休暇取得義務化の対象です。
対象となったパートタイム労働者が期限内に5日以上の有休消化ができるよう、使用者は管理しなければなりません。
パートタイムで所定労働日数が2日の労働者
週2日以下勤務の労働者の場合、有給休暇は最大でも年間7日の付与となります。有給休暇取得義務化の対象は年間10日以上の労働者に限られるため、日数が10日に満たない週2日以下の勤務者は義務化の対象外となるのです。

3.有給休暇義務化の規定と詳細とは?
有給休暇の取得義務が発生する時季は、有給休暇に関する社内規定の内容によって異なります。自社での運用がどのようになるか、あらかじめ確認しておきましょう。
入社6ヶ月後に10日以上の有給休暇を付与する場合
入社から6カ月が経ち、法令どおり10日以上の有給休暇を付与された場合、有給取得の権利が発生した日から1年以内に5日以上の有給消化義務が発生します。
たとえば4月1日に入社した人が出勤率8割以上で6カ月勤務した場合、10月1日の段階で10日の有休が付与されるのです。また同時に年間5日以上の有給消化をしなければなりません。さらに毎年10月1日までに、5日以上の有休消化義務が発生します。
入社と同時に有給休暇を10日以上付与する場合
入社と同時に有給休暇を付与するケースもあります。入社から6カ月を待たずに10日間の有給休暇を与える場合、付与日を基準日として基準日から1年以内に5日以上の有休を消化させなければなりません。
入社と同時に10日間の有給休暇を付与した場合、入社日から数えて1年以内に5日間の取得義務があります。その後は1年ごとに5日間の有休取得義務が発生し、労働者の希望時季に有給休暇を与えるという基本は変わりません。
期限内に5日間の取得が間に合わない場合には、使用者による取得日指定が認められます。
労働者が自分の意思で有給休暇を取得している場合
10日以上の有給休暇が付与されている労働者が、みずからの意思で期間中5日以上の有給休暇を取得している場合、使用者が有給休暇取得の指示を出す必要はありません。
しかし基準日から1年間、あるいは就業規則で定めた目安の時季までに有給消化日数が5日に満たないときは、使用者が有休取得日を指定して消化させる必要があります。
有給休暇の付与日が異なる場合
中途採用で入社日が違うなど有給休暇の発生日が異なる場合でも、原則、有休付与日を基準日とした1年以内に5日間の取得義務が発生します。
たとえば入社から6カ月後に10日間の有給休暇を付与するものの、全社で起算日を合わせたいケースについて見ていきましょう。
その後の基準日を統一する場合、それぞれの基準日をもとに年間5日の有休消化義務が生じます。重複する期間に関しては、先の期間における「初日」から後の期間における「最終日」までの月数÷12×5日で計算して、その日数を取得しても問題ありません。
時季指定の方法
有給休暇の取得時季を使用者が指定する際は、労働者に意見をヒアリングして、なるべく希望に沿った時季に取得できるよう配慮する必要があるのです。面談やメール、システムによる意見の吸い上げなど、ヒアリング方法は使用者に任されています。
機械的に5日間の有給休暇を与えるのではなく、あくまでも労働者の希望を尊重する姿勢が重要です。

4.有給休暇取得義務化への対策
企業は有給休暇取得義務化に対して、どう対策すべきでしょうか。対策には、基本的な有給休暇取得を労働者本人に任せて個別に使用者がフォローをする「個別指定方式」と、労使協定により使用者側が有給休暇を指定して与える「計画年休制度」があります。
個別指定方式を採用する
個別指定方式とは、有給休暇取得の時季を労働者本人の自由に任せる方法です。期限内に5日の取得が間に合わなさそうな労働者に対して、使用者が有休取得日を指定する形で、確実な年間5日の有給休暇取得を実現します。
個別指定方式のメリットは、「労働者の自由な有給休暇取得の権利が尊重される」「労使間での話し合いで決定や変更ができる」「柔軟な運用が可能」な点です。
しかし労働者の裁量に任せるため、有休が未消となる社員が生じるリスクもあります。また有給休暇取得期限が切れそうな時季に有休をまとめて取得されて、業務に支障が出てしまうケースも少なくはありません。
計画年休制度の導入をする
計画年休制度とは、有給休暇日数の一部を使用者が指定した日に与える制度で、制度を利用するには、就業規則の規定や労使協定の締結が必要です。
計画年休制度のメリットは、ある程度計画的に有給休暇を取得させられるため事業や業務の見通しが立てやすい点。
しかし、「労使協定の締結が前提となるため、導入まで時間がかかる」「協定を遵守するために企業の状況に応じた柔軟な変更や運用が難しい点」はデメリットでしょう。
個別指定方式と計画年休制度、どちらの導入がいいのか
個別指定方式と計画年休制度には、それぞれにメリットとデメリットが存在しています。どちらを導入するのか検討する際は、自社の状況を冷静に見極めたうえで選択しましょう。
「個別指定方式」の前提は、労働者の自由に任せる点です。そのためすでに社員が自主的に有給休暇を取得する風土がある企業に、向いています。
逆にこれまで有休取得率が低く、「有給休暇の取得に対して心理的な抵抗感を労働者が抱いている?」と感じる企業は、計画年休制度のほうが取り入れやすいかもしれません。

5.年次有給休暇の付与に関する規則
有給休暇取得は労働者の権利ですので基本、その権利を尊重しなければなりません。そのため、厚生労働省では「年次有給休暇の付与に関するルール」を定めているのです。
ここでは「年次有給休暇の付与に関するルール」をもとに、使用者が有給休暇を付与する際に気をつけるべき規則について解説します。
- 年次有給休暇を与える時季
- 年次有給休暇の繰越し
- 不利益取扱いの禁止
- 計画年休について
- 半日単位年休について
- 時間単位年休について
- 特別休暇について
①年次有給休暇を与える時季
年次有給休暇は、労働者が希望する時季に与える必要があります。労働者が具体的な月日を指定した場合も、原則はその日に付与しなければなりません。しかし希望をかなえることで事業に支障をきたす場合はその限りではないのです。
使用者には「時季変更権」が認められており、有給取得で事業が正常に運営できない場合は有休取得時季をほかの時季に変更できます。しかし時季変更権の行使を検討する際、正当な理由がない限り、使用者が労働者の有給休暇取得理由を拒否できません。
②年次有給休暇の繰り越し
年次有給休暇の時効は2年で、前年度に取得されなかった有休残日数は翌年度に繰り越されます。繰り越し分と新規付与分のどちらを先に消化すべきか、労働基準法に決まりはないため、自社の就業規則で定めるのです。
消化順序を規則で定めていない場合、有休を取得する従業員が決められます。もし新規付与分から消化させたいと考えている企業は、あらかじめ就業規則で決めておくとよいでしょう。
③不利益取扱いの禁止
使用者は、年次有給休暇を取得した労働者の利益を保護する必要があります。
たとえば、「有休取得日を欠勤扱いとして賃金や手当支給の条件から外す」「有休を使用しない人は賞与などで優遇する」といったように、年次有給休暇取得者が不利益を被る対応はなりません。
報酬ではなく人事考課に反映させる、なども不利益な取り扱いに該当するため禁止されます。
④計画年休について
計画年休は、あらかじめ年次有給休暇の取得日を定められる制度のこと。労使協定の締結が導入条件で、労働者の希望で取得できる有給休暇を最低5日以上残す必要があります。
特定の日を全社一斉に有給休暇取得日としたり、部署ごとや個人で順番を決めて有休消化したり、さまざまな形で運用可能です。
⑤半日単位年休について
年次有給休暇は原則として1日単位で取得します。ただし労働者が半日単位での有給休暇取得を望んでおり、使用者の同意が得られる場合は半日単位でも有給休暇を取得可能です。
その場合、取得1回につき0.5日として、年間5日の有給休暇消化の対象日数に含める計算となります。1日単位での有給休暇取得を妨げない範囲での取得が条件となるので、半日単位での有給休暇取得には注意が必要です。
⑥時間単位年休について
労働者が年次有給休暇を時間単位で取得したいと希望した際は、年間5日以内の範囲で取得できます。ただし時間単位で取得した有給休暇は、有給休暇取得が義務付けられている年間5日に含まないため注意が必要です。
時間単位年給の1時間あたりの賃金は、以下のいずれかをその日の所定労働時間数で割った金額になります。
- 平均賃金
- 所定労働時間の勤務で支払われる賃金
- 労使協定で定めた標準報酬日額
自社ではどの金額を基準とするか、就業規則であらかじめ決めておきましょう。
⑦特別休暇について
法律で定められている法定休暇とは別に、休暇の目的を企業独自で設定する「特別休暇」を作成できるのです。特別休暇は企業の福利厚生の一環として位置付けられるもので、リフレッシュ休暇や慶弔休暇、病気休暇などがあたります。
なお時間単位年休と同じように、年間5日を義務付けられている有給休暇取得日数には含まれません。

6.有給休暇の義務化によるメリット
年次有給休暇の年間5日取得が義務化して得られるメリットは、下記の2つです。
- 労働者にとって働きやすい会社となる
- 生活の質や労働意欲、労働能力を高める
①労働者にとって働きやすい会社となる
有給休暇取得率の高さは、「労働者の権利を正しく守っている」「労働者のプライベートや余暇を大切にしている」というメッセージになります。離職者の低下や採用候補者へのアピールにもつながるでしょう。
また対外的なイメージが良くなれば、企業価値の向上にもつながります。顧客や取引先の信頼獲得や金融機関からの資金調達の際、有利に働くケースもあるようです。
②生活の質や労働意欲、労働能力を高める
有給休暇を与えると、労働者は心身の疲れを癒し、気分をリフレッシュできるため、労働意欲や生産性の向上が期待できます。労働者個人のパフォーマンス向上やチームの成果につながれば、企業全体の業績も向上するでしょう。
労働者一人ひとりに仕事と生活、余暇のバランスをうまく取ってもらうと、労働者本人だけでなく組織全体にもメリットがあるのです。

7.有給休暇の義務化によるデメリット
有給休暇取得義務化にはデメリットも発生します。使用者にとっては費用負担が増大するほか、現場レベルでは業務の進捗管理に大きく影響をおよぼす場合があります。
仕事の進み具合が大きく変わる
有給休暇の取得が義務付けられると、「出勤しているほか労働者への負担が増加する」「業務の進行が滞る」といった恐れがあるのです。たとえば中小企業の場合、少ない人数で業務を進める場合も多い、つまり労働者ひとりの担当範囲が広い傾向にあります。
有休取得でひとりが休んだために進行状況が大幅に変わり、締め切りに間に合わなかったり、計画の遅れを補うために残業が増えたりするといった状況が考えられるのです。その結果、人件費の増大や業績悪化などにつながってしまうでしょう。
費用負担が発生する
義務化によって労働者の有給休暇取得率が高まったため、費用面にデメリットが生じるケースもあります。有給休暇は労働していない人に対して賃金を払うため、人件費が高まるのです。
これまで有休消化率が低かった企業は、義務化によってコスト増加が懸念されるでしょう。そうならないためにも、人件費高騰による利益圧迫の可能性を踏まえたうえで、事業計画を立てる必要があります。
有休義務化違反の罰則がある
有給休暇取得義務の違反による罰金があります。年間5日以上の有給休暇取得をクリアしないと、未達成1名あたり30万円以下の罰金を科されるのです。
最低限の有給休暇日数を取得できない人が多ければ多いほど、多くの罰金額を支払う状況になるでしょう。不本意な罰則やコストを回避するためにも、計画的な有給休暇取得が求められるのです。


